2020年12月23日(水)に静岡県伊豆半島の河津城に行って来ました、鎌倉公方足利持氏の七男蔭山勘解由築城とか、中世の山城です、麓に屋敷があり裏山の山頂を詰めの城としています。

河津駅の脇の城山です、駅から見えるトンネルの左上の山、右側の海側は片瀬山(多分見晴らし台)駅裏マンションの前に案内板があります。

案内板の路奥から山道へ。

この辺まではどなたさんかの屋敷跡なのでしょうね、削平されています・・・、石積もありますが。

山道に玉石が敷かれていますが・・・・・銅なのでしょうかネ?。

この辺りは麓の屋敷跡と言えばいえるかも?、見方によれば削平されていますが年代が?、何せ延徳3年(1491年)以前ですからネ。

雰囲気は非常に良いのです?。

お地蔵様は新しいのですがね、左側・右側とも人為的に削平はされていましたネ。

見てください、山道に玉石と横に石積が見られます・・・・・???。

漸く鞍部に出ました、左側城山(大日山180m)直進は片瀬山方面です、此処から左には玉石はありませんね。

少し山道を進むと木々が切れって、いよいよ河津城の虎口でしょうかネ?、でも又しばらくは竹藪等が続きます、四阿から景色が良く見えますね。

今の四阿を抜けて先に・・・しばらく竹藪が続き急坂を上れば・・・、この竹藪あたりも曲輪なのでしょうか?。

出てきました河津城本丸の虎口です、冠木門・柵が嬉しいですね雰囲気が出ますね、大きな木はオオシマサクラです。

振り返ります急坂が解りますね、山頂の独立した郭が解りますね。

虎口から城内へ・・・上段が一の郭でしょうね、此処は二の郭ですね、やはり結構狭い郭で詰めの城なのですね、説明版あり。

二の郭から見た一の郭です石積が見られます、この城は伊勢新九郎(後の北条早雲)が伊豆攻略で蔭山軍を火攻めで攻めたとの伝が伝えられているみたいですね、その後は北条に降伏。

一の郭脇から見た二の郭です、火攻めの折に水が無く米が・・説明?、焼けた米の云々は眉唾では?、水が無いので水の音を利かした話がありますが・・・・。

一の郭の上から見た二の郭、左側の冠木門から城内へ、この一の郭・二の郭の周りは切り立っていますね。

二の郭から見た河津の町方面です、河津桜はこの下の川沿いで見られますね。

同じく河津の海側を。

二の郭から見た一の郭。

虎口の冠木門です、この郭の下あたりの郭(竹藪)は見ることが出来ませんでしたが、中世城郭の山城の遺跡が充分残っていましたね、うれしかったですよ、今日はまた下田へ帰り明日は下田城(二度目ですが)です・・・下田城模擬天守も見ました。


















































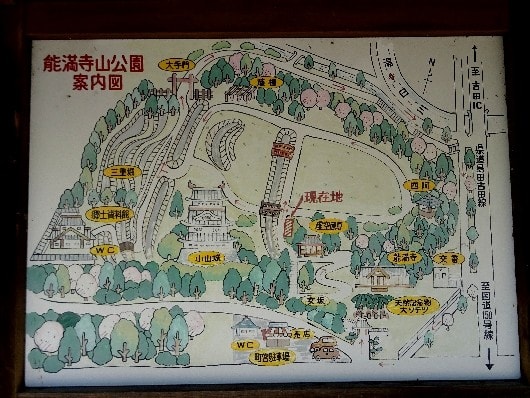


























































 駅裏側に回り込み田んぼ道から城跡が見えます、左側が本城で右側の高いのが天ケ岳砦です。
駅裏側に回り込み田んぼ道から城跡が見えます、左側が本城で右側の高いのが天ケ岳砦です。 県立韮崎高校のグランド脇から山に入ります、少しの上りで権現曲輪にでます。
県立韮崎高校のグランド脇から山に入ります、少しの上りで権現曲輪にでます。 左側は三の丸方面ですが、そこを下ると学校に出れます=>昔の御座敷(お殿様の住居です)、右側が二の丸への虎口です。
左側は三の丸方面ですが、そこを下ると学校に出れます=>昔の御座敷(お殿様の住居です)、右側が二の丸への虎口です。 山沿いを回り込むように上がると二の丸の虎口です、上り路は二の丸脇からの横矢掛かりなのでしょう。
山沿いを回り込むように上がると二の丸の虎口です、上り路は二の丸脇からの横矢掛かりなのでしょう。 二の丸の先に本丸への登り口があります、小高い山の尾根を利用した細長い縄張りです。
二の丸の先に本丸への登り口があります、小高い山の尾根を利用した細長い縄張りです。 前の写真とほぼ同じで二の丸から本丸へ回り込む道です、景色が良く、北側に富士山が見えますね。
前の写真とほぼ同じで二の丸から本丸へ回り込む道です、景色が良く、北側に富士山が見えますね。 振り返り二の丸の全景です、一番奥左側が虎口のある場所です右側は急斜面でその下側は城池です。
振り返り二の丸の全景です、一番奥左側が虎口のある場所です右側は急斜面でその下側は城池です。 回り込んで本丸の虎口です、回り込ます(横矢掛かり)の防御システムが見えますネ。
回り込んで本丸の虎口です、回り込ます(横矢掛かり)の防御システムが見えますネ。 本丸広場です、奥に細長く続いています、伝塩蔵跡の土塁があります。
本丸広場です、奥に細長く続いています、伝塩蔵跡の土塁があります。 本丸から今来た帯曲輪を上から見た所です、やはり打ちやすいですね、グランドはお座敷跡の学校です、富士山はこの方角です、今は雲がかかりスッキリしていませんでした。
本丸から今来た帯曲輪を上から見た所です、やはり打ちやすいですね、グランドはお座敷跡の学校です、富士山はこの方角です、今は雲がかかりスッキリしていませんでした。 此れが奥の伝塩蔵の跡です。
此れが奥の伝塩蔵の跡です。 細い尾根筋の奥が本丸です・・・・そう広くないですね、良くこの規模で3ケ月の籠城に耐えたのでしょうか?、この城の前も湿地帯で後は大きな池と天ケ岳の砦で大軍が一度に攻撃しずらかったのでしょうかネ?。
細い尾根筋の奥が本丸です・・・・そう広くないですね、良くこの規模で3ケ月の籠城に耐えたのでしょうか?、この城の前も湿地帯で後は大きな池と天ケ岳の砦で大軍が一度に攻撃しずらかったのでしょうかネ?。 権現曲輪を回り込むように下ります、左側が三の丸川ですね堀切ですね。
権現曲輪を回り込むように下ります、左側が三の丸川ですね堀切ですね。 城池です、昔は此処も湿地でしょうね、左側の山は秀吉軍が陣地を張ったところで、右奥が天ケ岳砦側ですね。
城池です、昔は此処も湿地でしょうね、左側の山は秀吉軍が陣地を張ったところで、右奥が天ケ岳砦側ですね。
 此れはクスノキの巨木です、向こう側がありませんが結構なものです。
此れはクスノキの巨木です、向こう側がありませんが結構なものです。 樹齢1200年の巨木です、キンモクセイです、根元から二つに分かれ痛々しいですが枝は大きく広げていますね。
樹齢1200年の巨木です、キンモクセイです、根元から二つに分かれ痛々しいですが枝は大きく広げていますね。 三嶋大社の本殿です、本殿は流れ造りで千木・鰹木をつけています、拝殿は権現造りです(入母屋造で千鳥破風・軒唐破風)、今日は段々熱くなり汗をかきながらの各所を見て歩きました、帰りの電車が疲れて長く感じましたね。
三嶋大社の本殿です、本殿は流れ造りで千木・鰹木をつけています、拝殿は権現造りです(入母屋造で千鳥破風・軒唐破風)、今日は段々熱くなり汗をかきながらの各所を見て歩きました、帰りの電車が疲れて長く感じましたね。 山中城跡は日本100名城で後北条の城で三代氏康が築いたのです、秀吉に対抗するため防御態勢を固めたのですが、1590年(天正18年)3月29日秀吉軍4万の大軍の前に北条氏則・松田康長4千は半日で落城、小田原北条の滅亡の先駆けとなったのです。縄張り図です、旧東海道を真ん中に挟み(三の丸)左側が出丸、右側が本城となります、右上が西の丸・二の丸・本丸・北の丸となります。
山中城跡は日本100名城で後北条の城で三代氏康が築いたのです、秀吉に対抗するため防御態勢を固めたのですが、1590年(天正18年)3月29日秀吉軍4万の大軍の前に北条氏則・松田康長4千は半日で落城、小田原北条の滅亡の先駆けとなったのです。縄張り図です、旧東海道を真ん中に挟み(三の丸)左側が出丸、右側が本城となります、右上が西の丸・二の丸・本丸・北の丸となります。 田尻の池です・その先に箱井戸があります井戸は飲料水で池は馬・洗濯等に利用したものです。
田尻の池です・その先に箱井戸があります井戸は飲料水で池は馬・洗濯等に利用したものです。 西の丸の空堀畝堀です、山中城は石垣が無く、すべて堀と土塁での防御システムです、畝堀・障子堀は後北条の城壁の特徴です、当時は急勾配で堀も深く関東ローム層で滑り一度落ちると登れないものだ数です。
西の丸の空堀畝堀です、山中城は石垣が無く、すべて堀と土塁での防御システムです、畝堀・障子堀は後北条の城壁の特徴です、当時は急勾配で堀も深く関東ローム層で滑り一度落ちると登れないものだ数です。 帯曲輪の先端からの見た富士山です畝堀があり右側が西櫓の馬出です。
帯曲輪の先端からの見た富士山です畝堀があり右側が西櫓の馬出です。 富士山をアップで、お城の北北西側ですね、この後雲に隠れました。
富士山をアップで、お城の北北西側ですね、この後雲に隠れました。 帯曲輪を回り込みました、右が西櫓で左側が西の丸中が障子堀の空堀で西櫓と西の丸は木橋で連携しました。
帯曲輪を回り込みました、右が西櫓で左側が西の丸中が障子堀の空堀で西櫓と西の丸は木橋で連携しました。 左側西櫓で畝堀が続きますね、右側気に下側が三の丸方面で、左側が二の丸・本丸方面です。
左側西櫓で畝堀が続きますね、右側気に下側が三の丸方面で、左側が二の丸・本丸方面です。 西櫓に上がりました、中は土塁で盛り上げてあります、富士山が見えますね、櫓台もあります、右側は西の丸方面なので土塁がありませんね。
西櫓に上がりました、中は土塁で盛り上げてあります、富士山が見えますね、櫓台もあります、右側は西の丸方面なので土塁がありませんね。 西の丸虎口から見た西の丸物見台です、向こう側に西櫓があり木橋があったそうです。
西の丸虎口から見た西の丸物見台です、向こう側に西櫓があり木橋があったそうです。 物見台から見た西の丸全景と向こうに見えるのが元西の丸です、広場が斜面上になっていますね、水を集めるための考慮と在りました。
物見台から見た西の丸全景と向こうに見えるのが元西の丸です、広場が斜面上になっていますね、水を集めるための考慮と在りました。 やはり物見台から見た西櫓と障子堀です。
やはり物見台から見た西櫓と障子堀です。 西の丸の虎口で元西の丸への通路です、ここは堀切状態でですね。
西の丸の虎口で元西の丸への通路です、ここは堀切状態でですね。 元西の丸から西の丸虎口を見た所です。
元西の丸から西の丸虎口を見た所です。 元西の丸から二の丸(北条丸)へは木橋となります。
元西の丸から二の丸(北条丸)へは木橋となります。 二の丸の橋横の土塁の上から見た元西の丸です、元西の丸は小さな広場です。
二の丸の橋横の土塁の上から見た元西の丸です、元西の丸は小さな広場です。 二の丸と本丸は土橋と木橋で繋がっています、木橋はいざの時壊せばよいのです。
二の丸と本丸は土橋と木橋で繋がっています、木橋はいざの時壊せばよいのです。 二の丸の広場です、ここは結構広いですね。
二の丸の広場です、ここは結構広いですね。 本丸広場です、天守台から見ました、正面奥が二の丸、左側したが弾薬庫・兵量庫の広場です。
本丸広場です、天守台から見ました、正面奥が二の丸、左側したが弾薬庫・兵量庫の広場です。 天守台から見た北の丸ですやはり空堀があり木橋で連結されています。
天守台から見た北の丸ですやはり空堀があり木橋で連結されています。 本丸下の駒形諏訪神社境内にある大カシの巨木です樹齢650年根回り9・6mと在りました。
本丸下の駒形諏訪神社境内にある大カシの巨木です樹齢650年根回り9・6mと在りました。 最後に出丸側の最先端であるすり鉢曲輪です、ここにも畝堀が見られました、大軍によるもう攻撃の前にこれだけの防御もわずか半日で落城するとは考えもしなかったのでしょうね!
最後に出丸側の最先端であるすり鉢曲輪です、ここにも畝堀が見られました、大軍によるもう攻撃の前にこれだけの防御もわずか半日で落城するとは考えもしなかったのでしょうね!





































