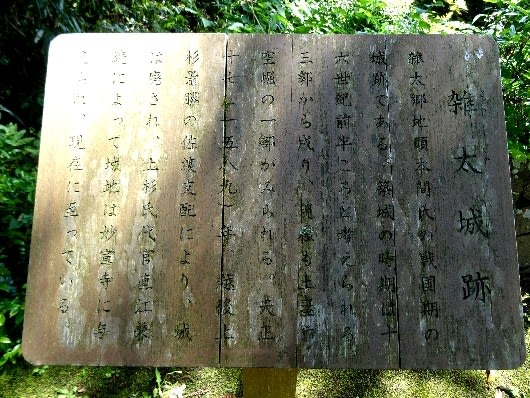2025年6月17日(火)越後の荒戸城に行って来ました、今回は本丸・三の丸について。
荒戸城の縄張り図・・・大手から二の丸へ・・・二の丸から本丸へ入りますね。
荒戸城本丸・・・・前回は此処まで・
荒戸城本丸から二の丸からの虎口を振り返りますね・・・本丸東側は土塁が奇麗に残っていますネ。
荒戸城二の丸虎口周辺から本丸北側からぐるりと・・・右側のブナが二の丸から見えた木ですね、北・西側には土塁がありませんね。
少しずらし、西南方面・・・西側は土塁無・・・南側は土塁で三の丸(西)への虎口脇から土塁が始まっていますネ。
荒戸城本丸東南の隅・・・東側は土塁、南側奥は高台ですね。
南側の高台へ・・・。
登と小さな削平地が・・・・狼煙台か隅櫓?なのでしょうね・・・今は周りに木々が・・。
高台の奥から本丸を・・・・右側が土塁・・・土塁右下は二の丸と坂虎口、左側が本丸。
土塁上から二の丸と越後湯沢方面・・・狼煙台・櫓からの連絡が出来ますね・・・見晴らしが良いのです。
本丸からの虎口、その先が二の丸からの虎口と城内は小さい境目の城です、北条軍により落城しましたね。
荒戸城本丸・・・北側です・・・この下側に当時の三国街道(上杉軍道)があり関東・越後の境目を抑えていたのですネ。
ブナの木に目がいきますネ・・・奥が虎口と東側の土塁。
左側が二の丸の北側、前回二の丸からこのブナを見上げていましたね・・・こちら側は土塁でなく木での城壁なのでしょうかネ?。
二の丸と三の丸の間の谷間ですね、水の手があるみたいですが・・・私は未確認。
荒戸城本丸西側から見た三の丸・・・左側の木々がある一段低い所が三の丸搦め手筋の虎口。
三の丸脇の一段低い曲輪・・・搦め手の虎口へ。
荒戸城本丸西側から見た所・・・正面左二の丸へのの虎口・・・右側が三の丸への虎口・・・本丸からは虎口は2か所。
三の丸への虎口。
本丸脇を回り込むように三の丸手前の一段低い曲輪へ
荒戸城三の丸・・・・虎口手前に竪堀があり虎口に殺到しづらく細めてありますね。
荒戸城三の丸・・・右側は本丸の城壁。
荒戸城搦め手の虎口・・・右側が三の丸。
三の丸端から見た本丸。
三の丸北側から見た東方面の二の丸・・・二の丸・三の丸の間には谷(堀が)により隔たれています(この下に水の手)。
二の丸側の堀が下へ続きますね・・・・二の丸からの堀底道へは降りませんでした、そこから見上げれば違う景色も・・・上杉方の城ですが北条軍も改修したのでしょうからね。