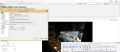NASからの音楽再生が再び可能となった。この三週間ほど不可能になっていた。切っ掛けはNASからの転送速度が落ちたことだ。だからケーブルもクラス7へとグレードアップしたが根本的な解決とはならなかった。それどころかファイル転送が一時停止するようになった。通常はサインカーヴのようなものを描くのだが、少なくともMINTの音楽再生PCではゼロ停止してしまっていた。
勿論PC内のファイルを再生するのは全く問題が無い。またPCの方ではNASをHDDのように使っているので画像などを開けるのにぐずぐずしているとストレスがたまって来ていた。理由はNASの方にあるのだが、それ以前はそれほど問題が無く、テストプログラムも問題なく回っていた。
兎に角、時間が無かったので、放っておいてSACDや問題の無いファイルで音を鳴らしていた。それ以前に問題があったのは大きな動画ファイルの再生だった。中断までいかなくとも音が途切れる症状があった。明らかにNASからの転送が上手く行っていなかった。
しかしどこにネックがあるのかが分からなかった。そこで十日ほど前に新しい方のルーターにNASを接続することにした。理由は速度が表示もされて、監視しやすいからで、実際には転送速度はそれほど変わらないと思われた。しかし結果は変わらず何よりも不都合だったのは録音をそのまま保存しているAudacityのファイルが中断でステレオの左右チャンネルがズレてしまって、するとさらに再生出来なくなった事である。中断ならばさらに続行されるのだが、左右がズレた音源は再生不可能である。
調べた結果、NASで指定しているバケット通信に相当するジャムボフレームが災いしていると分かった。これは有線のイーサネットの企画で大容量の転送をスピードアップさせるものだ。そもそもイーサネットなどはWIFIに切り替えてから長く使っていなかったのでケーブルのクラス分けがあることすらも知らなかった。だからジャムボフレームに合わせてPCの方でも調整しなければいけないことも忘れていた。しかしである、PCの方はルーターからWIFIで飛ばしているので関係ない。そしてルーターの設定に見つからない。どうも知らぬ間によさげなジャムボフレームの値を最大にしたようで、転送が難しくなったようである。
そこで、ジャムボフレームを外して、通常の音楽ファイルを再生すると最後まで問題なく流れた。そしていよいよ懸案のAudacityである。流れる、これで解決である。実際にPCのネットを量的に見るとサインカーヴの上側に近くなってきた。間隔は4sから10sぐらいである。
具体的には外すことで1500バイトとなるようだ。また転送速度を自動としたので2MiBsほどの受信が可能となっているようである。実測1MiBsぐらいは出るようになった。プレーヤーのキャッシュも二倍三倍にしてみたが、大型映像再生の音飛びは完全には解消しない。古いPCの方のCPUの稼働が上に振れているので仕方がないだろう。そもそも映像はそんなに観ないからアーカイヴ扱いである。
なによりも助かったのは、通常にPCを遥かに使いやすくなったことで、ケーブルを購入して数週間ほど経過してようやくその効果を発揮した。これで以前よりも早くなったのを確認した。一体この間何をしていたことだろう。
そして今大変なことに気が付いた。全く同じことをクリスマス前に書いていて、その記事が「健忘症のミスタービーン」となっている。アルツハイマーではないかと恐ろしくなるようなことを繰り返している。そして解決まで今回の方が時間が掛かっている。
参照:
NAS回転音の審査 2018-11-30 | 生活
健忘症のミスタービーン 2018-12-22 | 暦
カテゴリー7ケーブル導入 2019-04-06 | テクニック
勿論PC内のファイルを再生するのは全く問題が無い。またPCの方ではNASをHDDのように使っているので画像などを開けるのにぐずぐずしているとストレスがたまって来ていた。理由はNASの方にあるのだが、それ以前はそれほど問題が無く、テストプログラムも問題なく回っていた。
兎に角、時間が無かったので、放っておいてSACDや問題の無いファイルで音を鳴らしていた。それ以前に問題があったのは大きな動画ファイルの再生だった。中断までいかなくとも音が途切れる症状があった。明らかにNASからの転送が上手く行っていなかった。
しかしどこにネックがあるのかが分からなかった。そこで十日ほど前に新しい方のルーターにNASを接続することにした。理由は速度が表示もされて、監視しやすいからで、実際には転送速度はそれほど変わらないと思われた。しかし結果は変わらず何よりも不都合だったのは録音をそのまま保存しているAudacityのファイルが中断でステレオの左右チャンネルがズレてしまって、するとさらに再生出来なくなった事である。中断ならばさらに続行されるのだが、左右がズレた音源は再生不可能である。
調べた結果、NASで指定しているバケット通信に相当するジャムボフレームが災いしていると分かった。これは有線のイーサネットの企画で大容量の転送をスピードアップさせるものだ。そもそもイーサネットなどはWIFIに切り替えてから長く使っていなかったのでケーブルのクラス分けがあることすらも知らなかった。だからジャムボフレームに合わせてPCの方でも調整しなければいけないことも忘れていた。しかしである、PCの方はルーターからWIFIで飛ばしているので関係ない。そしてルーターの設定に見つからない。どうも知らぬ間によさげなジャムボフレームの値を最大にしたようで、転送が難しくなったようである。
そこで、ジャムボフレームを外して、通常の音楽ファイルを再生すると最後まで問題なく流れた。そしていよいよ懸案のAudacityである。流れる、これで解決である。実際にPCのネットを量的に見るとサインカーヴの上側に近くなってきた。間隔は4sから10sぐらいである。
具体的には外すことで1500バイトとなるようだ。また転送速度を自動としたので2MiBsほどの受信が可能となっているようである。実測1MiBsぐらいは出るようになった。プレーヤーのキャッシュも二倍三倍にしてみたが、大型映像再生の音飛びは完全には解消しない。古いPCの方のCPUの稼働が上に振れているので仕方がないだろう。そもそも映像はそんなに観ないからアーカイヴ扱いである。
なによりも助かったのは、通常にPCを遥かに使いやすくなったことで、ケーブルを購入して数週間ほど経過してようやくその効果を発揮した。これで以前よりも早くなったのを確認した。一体この間何をしていたことだろう。
そして今大変なことに気が付いた。全く同じことをクリスマス前に書いていて、その記事が「健忘症のミスタービーン」となっている。アルツハイマーではないかと恐ろしくなるようなことを繰り返している。そして解決まで今回の方が時間が掛かっている。
参照:
NAS回転音の審査 2018-11-30 | 生活
健忘症のミスタービーン 2018-12-22 | 暦
カテゴリー7ケーブル導入 2019-04-06 | テクニック