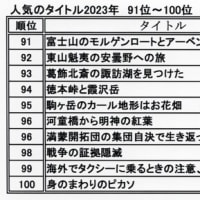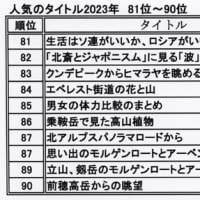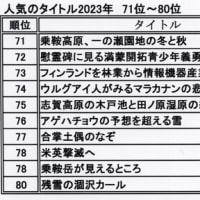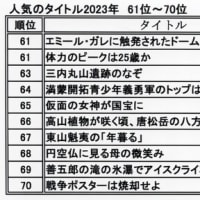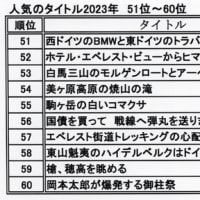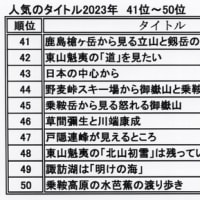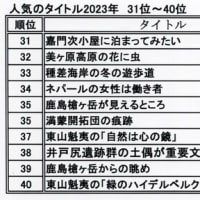「私の作品を育ててくれた故郷とも言える信州」に、
東山魁夷は作品を寄贈された。そして、
「東山魁夷館」が建設された。

「東山魁夷館」は、東山魁夷の作品を950点所蔵する。長野市。
「東山魁夷館」へ行くと、
東山魁夷と信州の「絆」を示すパネルがある。
「私が初めて信州を旅したのは、
東京美術学校、日本画科1年生のときだった」
「8日間のテント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」
(1926年)。
冬の「御嶽山」。霧ヶ峰から望む。

「横浜生まれで、神戸で少年期を過ごした私は、
初めて接した山国の自然の厳しさに、
強い感動を受けるとともに、
そこに住む素朴な人々の心の温かさに、
触れることができたのです」
「それ以来、山国へよく旅をするようになり、
信濃路の自然を描くことが多くなりました。
そして、風景画家として一筋の道を歩いてきました」
「北アルプス」を望む。

長峰山、安曇野市から。2012年4月。
東山魁夷、川端康成、井上 靖の3巨頭は長峰山を訪れている(1970年)。
「いつの間にか、私も年を重ね、
子どもがいませんので今の内に、
自家所有の作品などの処置について、
真剣に考えねばならない時期になりました」
「いろいろ考えた末に、
私の作品を育ててくれた故郷とも言える、
長野県にお願いしたいと決心したのです」
「はなはだ唐突のようなことですが、それは、
私の心の中で長い間に結ばれてきた、
信州の豊かな自然との強い絆が、
今日の結果となったわけです」
「長野県では私の身勝手な願いを快くお聞き届けになり、
このような立派な館を建てて戴き、
誠に御礼の申し上げようもないことと、
心から感謝しているしだいです」
1990年4月 東山魁夷
東山魁夷と信州の「絆」から、
「東山魁夷館」ができた。
信州には、もう一つ東山魁夷の美術館がある。
その美術館も、東山魁夷と信州の「絆」から生まれた。
「東山魁夷 心の旅路館」である。木曽郡、山口村。

東山魁夷は、東京美術学校、日本画科1年生のときに、
「テント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」。
木曽郡、山口村の「賤母」(しずも)の山中で雷雨にあい、
麻生(あそう)の村はずれの農家に駆け込んで、
「一夜の宿を求めました」
「そこで、私は思いがけないほどの、
温かいもてなしを受けたのです」
「東山魁夷 心の旅路館」のリーフレットから。
「それまで知らなかった木曽の人たちの素朴な生活と、
山岳をめぐる雄大な自然に心を打たれ、
やがて風景画家への道を歩む決意をしました」
これがきっかけで、のちに東山魁夷は、
「青春時代の思い出の地」、木曽郡の山口村に、
リトグラフや木版画、500点を寄贈された。
山口村では、東山魁夷の青春の所縁(ゆかり)の地に、
「東山魁夷 心の旅路館」を建設した(1995年)。
国道19号の道の駅「賤母」(しずも)にある。
松本は、北の「東山魁夷館」と、
南の「東山魁夷 心の旅路館」の、
中間にあって、90キロほどである。
上の写真で、左右の白樺と、右のユキツバキは(街灯の左)は、
「東山魁夷 心の旅路館」竣工記念の植樹である。
左の白樺は、「長野県の木」として、
吉村午良(ごろう)長野県知事が植樹され、
右の白樺は、「画伯の好まれる木」として、
東山魁夷画伯夫人が植樹されている。
さらに右にあるユキツバキは、「山口村の木」として、
加藤出 山口村長と大脇芳朗 山口村議会議長が、
植樹されている。
左右の白樺の間には、東山魁夷の書による「碑」がある。

「歩み入る者に やすらぎを
去り行く人に しあわせを」
魁夷
これは、ドイツの古都、ローテンブルクの入り口の城門、
シュピタール門に刻まれた言葉である。
“Pax intrantibus,
Salus exeuntibus”
ローテンブルク。市庁舎の塔から。

ハイデルベルクの東100キロのロマンチック街道にある。
東山魁夷はつぎのように言っている。
「緑濃い賤母(しずも)の森陰に、『心の旅路館』と名付けた、
私の版画による展示館が設立されたのも、
木曽路と私を結ぶ縁の糸が、
だんだん大きく太くなった結果かもしれません」
「この地を過ぎる旅の人たちにとって、
しばしの安らぎと憩いになれば、
誠に幸いに思います」
「東山魁夷 心の旅路館」のリーフレットから。
「東山魁夷 心の旅路館」建設10年後の2005年に、
越県合併で、山口村は岐阜県中津川市になっている。
東山魁夷は、東京美術学校、日本画科1年生のときに、
「テント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」様子を、
日記に書いている。「東山魁夷画文集 私の窓」、1978年から。
7月3日(1926年)。
「山路を麻生(あそう)に向う」
「木曽川沿いの中仙道を通った」
「いたるところに清水があり、眺めも美しい」
「麻生(あそう)に着いた」
「キャンプ地を探しているうちに、大粒の雨が降ってきた。
日はすっかり暮れて、雨はますます烈しく、
電光雷鳴がものすごくなった」
「山路は滝のようになり、
杉木立の下で雨宿りしていると、
バリバリと頭の真上で容赦なく鳴り響く」
「麻生に引き返して、
とある農家へ入ってわけを話すと、
老婆が快く迎え入れてくれた。
頑丈な木組み、黒光りしている柱」
「麻生」。2012年4月。

道の駅「賤母」(しずも)から南へ1.5キロ。
麻生で、人を見かけると、
「東山魁夷を、温かくもてなした老婆かな?」
と、重なってしまう。
「老婆はお茶やお菓子を出してくれて、
話などしているうちに雷も遠くなり、
やがて雨も止んだ」
「この辺には名所もないが、
公園ができたからといいながら、
老婆は私たちを誘って外へ出た」
賤母(しずも)発電所の取水ダムと水圧路管。2012年4月。

3本の水圧路管は、国道19号の下を通ってから、
木曽川沿いにある発電所に向かって急降下する。
「美しい月夜になっていた。
公園というのは、近くの水力電気の発電所のそばに、
すこしばかり桜の樹らしいものが植わっているだけの、
お粗末なものだが、老婆はまんざらでもなさそうな様子である」
発電所のそばの公園とは、これだろうか? 2012年4月。

右に水圧路管が走り、水圧路管の先は木曽川に向かって落ちていく。
水圧路管の右には、さらに広い公園が続いていた。
「私も、この月明りの山峡の眺めは、
都会のどの公園よりも素晴らしいと感じた」
「人を疑うことを知らぬこの老婆の心がうれしかった」
賤母(しずも)発電所(右)と木曽川。2012年4月。

7月4日。
「馬鈴薯ときゅうりもみのご馳走になって、
この家に別れを告げる」
須原の鎮守の森にある祠(ほこら)のそばの小屋に泊まる。
7月5日。
「小野の滝」、「寝覚めの床」を見て、
上松(あげまつ)に着く。森林鉄道に沿いに進む。
夜、土地の人に、集会所を案内され、
薪とむしろをもらって泊まる。
7月6日。
「朝起きてみると、断崖絶壁の上だった」
「さらに、森林鉄道に沿って登る」
「御嶽山がはじめて眼の前に姿をあらわす。
頂上は雲に蔽われて見えないが、雄大な山容である」
「断崖から断崖にかかる鞍馬橋を渡り、王滝の宿屋へ泊まる」
7月7日。
朝7時半、宿を出て、御嶽山に登る。
「八合目あたりで、雪渓を渡る頃から寒くなってきた」
「御嶽山」。

夏でも雪が残る。2011年8月。
「風が出て霧が舞い上がってきたと思う間もなく、
何も見えなくなってしまった。
ただ上へ上へと登る。
12時半、石室へ着く。
風は雨を交えて吹きつのってきた」
「石室で一休みして剣ヶ峰へ行こうとしたが、
風雨がますます強くなってくるのでやめにした」
「寒い夜を迎える」
「風の音が烈しい」
九合目「石室山荘」と「剣ヶ峰」(右奥)。2011年8月。

7月8日。
「石室を出て剣ヶ峰へ登る。標高3067メートル。
晴れていれば素晴らしい眺望が得られるだろうが、
今は風雨の上に霧が渦巻く混沌とした灰色の世界である」
「道を黒沢口にとって下山する。
登りの時より難路である」
御嶽山の登山コース。九合目に「石室山荘」がある。

木曽町観光協会の「御嶽山に登ろう」の「登山コース」(黒沢口)から。
木曽路のテント旅行を振り返って、
東山魁夷は、つぎのように言っている。
「この旅行は、その時は気がつかなかったが、
私に大きな影響を与えたものであることが、
あとになってわかった。
神戸で少年時代を送った私は、
生まれてはじめて山国の姿を見たのである」
「それは、私の少年時代を育ててくれた環境とは、
まったく違ったもので、
素朴で、厳しく、たくましいものだった」
「感覚的な自然環境に恵まれていた私が、
この山国の旅行で意志的なものを知ったのは、
芸術の世界という峻厳な道に踏み入る、
最初の時期であっただけに、
なにか私の人生に、
一つの眼を開いてくれたといってよい。
また、あの山国の人々の人情も忘れ得ないものである」
「私は自然の深さにひかれ、風景画家としての道をたどったが、
自然と私を強く結びつけてくれた、この青春の日の木曽路の旅は、
長い年月を経た今でも、鮮やかに浮かんでくるのである」
東山魁夷と信州との「絆」のわけが、
わかっていただけたと思う。
「山国の自然の厳しさ」に感動し、
「そこに住む素朴な人々の心の温かさ」に触れ、
「風景画家への道をたどった」ことである。
あわせて、
東山魁夷が「風景画家」になったわけも、
「山国の自然の厳しさ」に感動し、
「そこに住む素朴な人々の心の温かさ」に触れたことに、
あったことも、ご理解いただければ幸いである。
東山魁夷は作品を寄贈された。そして、
「東山魁夷館」が建設された。

「東山魁夷館」は、東山魁夷の作品を950点所蔵する。長野市。
「東山魁夷館」へ行くと、
東山魁夷と信州の「絆」を示すパネルがある。
「私が初めて信州を旅したのは、
東京美術学校、日本画科1年生のときだった」
「8日間のテント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」
(1926年)。
冬の「御嶽山」。霧ヶ峰から望む。

「横浜生まれで、神戸で少年期を過ごした私は、
初めて接した山国の自然の厳しさに、
強い感動を受けるとともに、
そこに住む素朴な人々の心の温かさに、
触れることができたのです」
「それ以来、山国へよく旅をするようになり、
信濃路の自然を描くことが多くなりました。
そして、風景画家として一筋の道を歩いてきました」
「北アルプス」を望む。

長峰山、安曇野市から。2012年4月。
東山魁夷、川端康成、井上 靖の3巨頭は長峰山を訪れている(1970年)。
「いつの間にか、私も年を重ね、
子どもがいませんので今の内に、
自家所有の作品などの処置について、
真剣に考えねばならない時期になりました」
「いろいろ考えた末に、
私の作品を育ててくれた故郷とも言える、
長野県にお願いしたいと決心したのです」
「はなはだ唐突のようなことですが、それは、
私の心の中で長い間に結ばれてきた、
信州の豊かな自然との強い絆が、
今日の結果となったわけです」
「長野県では私の身勝手な願いを快くお聞き届けになり、
このような立派な館を建てて戴き、
誠に御礼の申し上げようもないことと、
心から感謝しているしだいです」
1990年4月 東山魁夷
東山魁夷と信州の「絆」から、
「東山魁夷館」ができた。
信州には、もう一つ東山魁夷の美術館がある。
その美術館も、東山魁夷と信州の「絆」から生まれた。
「東山魁夷 心の旅路館」である。木曽郡、山口村。

東山魁夷は、東京美術学校、日本画科1年生のときに、
「テント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」。
木曽郡、山口村の「賤母」(しずも)の山中で雷雨にあい、
麻生(あそう)の村はずれの農家に駆け込んで、
「一夜の宿を求めました」
「そこで、私は思いがけないほどの、
温かいもてなしを受けたのです」
「東山魁夷 心の旅路館」のリーフレットから。
「それまで知らなかった木曽の人たちの素朴な生活と、
山岳をめぐる雄大な自然に心を打たれ、
やがて風景画家への道を歩む決意をしました」
これがきっかけで、のちに東山魁夷は、
「青春時代の思い出の地」、木曽郡の山口村に、
リトグラフや木版画、500点を寄贈された。
山口村では、東山魁夷の青春の所縁(ゆかり)の地に、
「東山魁夷 心の旅路館」を建設した(1995年)。
国道19号の道の駅「賤母」(しずも)にある。
松本は、北の「東山魁夷館」と、
南の「東山魁夷 心の旅路館」の、
中間にあって、90キロほどである。
上の写真で、左右の白樺と、右のユキツバキは(街灯の左)は、
「東山魁夷 心の旅路館」竣工記念の植樹である。
左の白樺は、「長野県の木」として、
吉村午良(ごろう)長野県知事が植樹され、
右の白樺は、「画伯の好まれる木」として、
東山魁夷画伯夫人が植樹されている。
さらに右にあるユキツバキは、「山口村の木」として、
加藤出 山口村長と大脇芳朗 山口村議会議長が、
植樹されている。
左右の白樺の間には、東山魁夷の書による「碑」がある。

「歩み入る者に やすらぎを
去り行く人に しあわせを」
魁夷
これは、ドイツの古都、ローテンブルクの入り口の城門、
シュピタール門に刻まれた言葉である。
“Pax intrantibus,
Salus exeuntibus”
ローテンブルク。市庁舎の塔から。

ハイデルベルクの東100キロのロマンチック街道にある。
東山魁夷はつぎのように言っている。
「緑濃い賤母(しずも)の森陰に、『心の旅路館』と名付けた、
私の版画による展示館が設立されたのも、
木曽路と私を結ぶ縁の糸が、
だんだん大きく太くなった結果かもしれません」
「この地を過ぎる旅の人たちにとって、
しばしの安らぎと憩いになれば、
誠に幸いに思います」
「東山魁夷 心の旅路館」のリーフレットから。
「東山魁夷 心の旅路館」建設10年後の2005年に、
越県合併で、山口村は岐阜県中津川市になっている。
東山魁夷は、東京美術学校、日本画科1年生のときに、
「テント旅行で木曽路を旅し、御嶽山に登った」様子を、
日記に書いている。「東山魁夷画文集 私の窓」、1978年から。
7月3日(1926年)。
「山路を麻生(あそう)に向う」
「木曽川沿いの中仙道を通った」
「いたるところに清水があり、眺めも美しい」
「麻生(あそう)に着いた」
「キャンプ地を探しているうちに、大粒の雨が降ってきた。
日はすっかり暮れて、雨はますます烈しく、
電光雷鳴がものすごくなった」
「山路は滝のようになり、
杉木立の下で雨宿りしていると、
バリバリと頭の真上で容赦なく鳴り響く」
「麻生に引き返して、
とある農家へ入ってわけを話すと、
老婆が快く迎え入れてくれた。
頑丈な木組み、黒光りしている柱」
「麻生」。2012年4月。

道の駅「賤母」(しずも)から南へ1.5キロ。
麻生で、人を見かけると、
「東山魁夷を、温かくもてなした老婆かな?」
と、重なってしまう。
「老婆はお茶やお菓子を出してくれて、
話などしているうちに雷も遠くなり、
やがて雨も止んだ」
「この辺には名所もないが、
公園ができたからといいながら、
老婆は私たちを誘って外へ出た」
賤母(しずも)発電所の取水ダムと水圧路管。2012年4月。

3本の水圧路管は、国道19号の下を通ってから、
木曽川沿いにある発電所に向かって急降下する。
「美しい月夜になっていた。
公園というのは、近くの水力電気の発電所のそばに、
すこしばかり桜の樹らしいものが植わっているだけの、
お粗末なものだが、老婆はまんざらでもなさそうな様子である」
発電所のそばの公園とは、これだろうか? 2012年4月。

右に水圧路管が走り、水圧路管の先は木曽川に向かって落ちていく。
水圧路管の右には、さらに広い公園が続いていた。
「私も、この月明りの山峡の眺めは、
都会のどの公園よりも素晴らしいと感じた」
「人を疑うことを知らぬこの老婆の心がうれしかった」
賤母(しずも)発電所(右)と木曽川。2012年4月。

7月4日。
「馬鈴薯ときゅうりもみのご馳走になって、
この家に別れを告げる」
須原の鎮守の森にある祠(ほこら)のそばの小屋に泊まる。
7月5日。
「小野の滝」、「寝覚めの床」を見て、
上松(あげまつ)に着く。森林鉄道に沿いに進む。
夜、土地の人に、集会所を案内され、
薪とむしろをもらって泊まる。
7月6日。
「朝起きてみると、断崖絶壁の上だった」
「さらに、森林鉄道に沿って登る」
「御嶽山がはじめて眼の前に姿をあらわす。
頂上は雲に蔽われて見えないが、雄大な山容である」
「断崖から断崖にかかる鞍馬橋を渡り、王滝の宿屋へ泊まる」
7月7日。
朝7時半、宿を出て、御嶽山に登る。
「八合目あたりで、雪渓を渡る頃から寒くなってきた」
「御嶽山」。

夏でも雪が残る。2011年8月。
「風が出て霧が舞い上がってきたと思う間もなく、
何も見えなくなってしまった。
ただ上へ上へと登る。
12時半、石室へ着く。
風は雨を交えて吹きつのってきた」
「石室で一休みして剣ヶ峰へ行こうとしたが、
風雨がますます強くなってくるのでやめにした」
「寒い夜を迎える」
「風の音が烈しい」
九合目「石室山荘」と「剣ヶ峰」(右奥)。2011年8月。

7月8日。
「石室を出て剣ヶ峰へ登る。標高3067メートル。
晴れていれば素晴らしい眺望が得られるだろうが、
今は風雨の上に霧が渦巻く混沌とした灰色の世界である」
「道を黒沢口にとって下山する。
登りの時より難路である」
御嶽山の登山コース。九合目に「石室山荘」がある。

木曽町観光協会の「御嶽山に登ろう」の「登山コース」(黒沢口)から。
木曽路のテント旅行を振り返って、
東山魁夷は、つぎのように言っている。
「この旅行は、その時は気がつかなかったが、
私に大きな影響を与えたものであることが、
あとになってわかった。
神戸で少年時代を送った私は、
生まれてはじめて山国の姿を見たのである」
「それは、私の少年時代を育ててくれた環境とは、
まったく違ったもので、
素朴で、厳しく、たくましいものだった」
「感覚的な自然環境に恵まれていた私が、
この山国の旅行で意志的なものを知ったのは、
芸術の世界という峻厳な道に踏み入る、
最初の時期であっただけに、
なにか私の人生に、
一つの眼を開いてくれたといってよい。
また、あの山国の人々の人情も忘れ得ないものである」
「私は自然の深さにひかれ、風景画家としての道をたどったが、
自然と私を強く結びつけてくれた、この青春の日の木曽路の旅は、
長い年月を経た今でも、鮮やかに浮かんでくるのである」
東山魁夷と信州との「絆」のわけが、
わかっていただけたと思う。
「山国の自然の厳しさ」に感動し、
「そこに住む素朴な人々の心の温かさ」に触れ、
「風景画家への道をたどった」ことである。
あわせて、
東山魁夷が「風景画家」になったわけも、
「山国の自然の厳しさ」に感動し、
「そこに住む素朴な人々の心の温かさ」に触れたことに、
あったことも、ご理解いただければ幸いである。