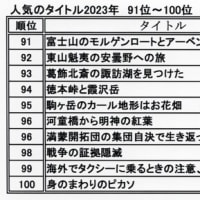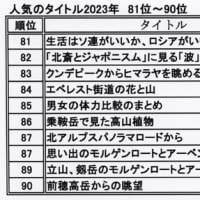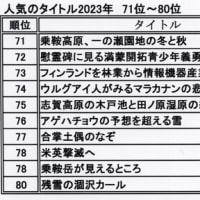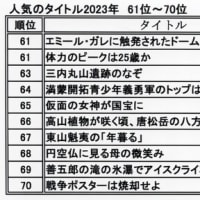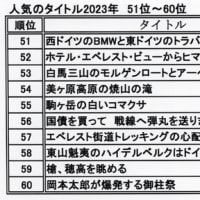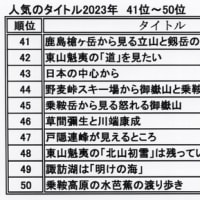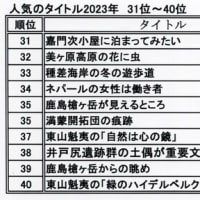「函館の景観」2011年1月23日で、
「日本では、函館が先駆けとなって、先進国の都市と同じように、
電線の『埋設率』(地中下率)100%が実現すれば、快挙だ」
「日本のほかの街でも、電線は『埋設率』で管理することになり、
埋設率100%を実現してほしい」
と書いた。
日本では、電柱が街中に林立し、
電線がクモの巣のように空をおおっていて、
街の景観を醜くしているが、
先進国の都市の電線の「埋設率」はどうであろうか?
電線の埋設率の国際比較をしてみる。
電線の埋設率の国際比較。

電気事業連合会、国土交通省の資料から作成。
海外は、電気事業連合会の調べで、「ケーブル延長ベース」。
日本は、国土交通省の調べで、「道路延長ベース」。
電線の埋設率の国際比較のグラフ。
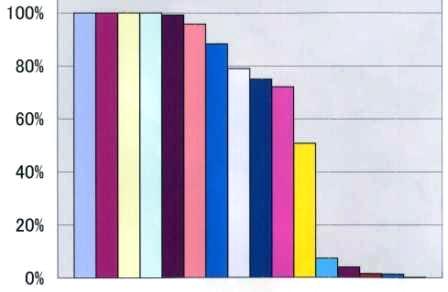
ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ボン(ドイツ)、香港の電線の埋設率は100%である。
ドイツのベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンも埋設率が高い。
コペンハーゲン(デンマーク)、クアラルンプール(マレーシア)、ニューヨーク(アメリカ)が続く。
先進国の都市は、電線の埋設率100%を目指している。
これに対して、日本の電線の埋設率は、
先進国から、大きく立ち遅れている。
たとえば、東京の電線の埋設率は7.3%である(2008年)。
だが、東京の電線の埋設率は23区に限定し、
しかも、「市街地の道路」に限定している。
つまり、市街で、しかも国道や都道(県道)沿いである。
市街を離れたり、市道を含めれば、極端に悪くなる。
京都の4%も大阪の1.4%も同じで、「市街地の道路」に限定している。
限定しても、先進国の街からは、大きく立ち遅れている。
残念なのは、電線の埋設率について、
きちんとした国際比較の資料がないことである。
世界は、電気事業連合会の調査で、1977年であり、
日本は、国土交通省の調査で、2008年である。
それに、海外は「ケーブル延長ベース」で、
日本は「道路延長ベース」である。
「ケーブル延長ベース」と「道路延長ベース」のちがいは何だろう?
日本では、電柱と電線が屋敷や田園、農地を走る。
それに、道路を横切る電柱と電線があるから、
日本の「ケーブル延長ベース」での埋設率は、
もっと悪くなりそうだ、と推察したが。
電気事業連合会の「ケーブル延長ベース」の調査は1977年と古い。
「ケーブル延長ベース」で調べた最近の結果がほしい。
でも、どうしてないんだろう?
敷設したケーブルの長さは、すぐにわかりそうだが?
日本の街は、世田谷区の0.2%(1998年)という数字が、
実感する電線の埋設率ではないだろうか?
「アメリカ、イギリス、日本の住環境」2010年10月3日で、
アメリカ、イギリス、日本で住んだ家で住環境を比較した。
「電線の埋設率の国際比較」で示した数字と、
実際にアメリカ、イギリス、日本で住んだ家の電柱、電線の状況を比較してみる。
ニューヨーク(アメリカ)の電線の埋設率は72.1%である(1977年)。
ロス・アンジェルスの家。2000年。

電柱が家の左に見える。
それと、丘の上にも点々とならぶ。
しかし、ごみごみと醜いほどではなかった。
目の前に電柱や電線があって、景色をさえぎったり、
空をおおったりはしていなかった。
ロンドン(イギリス)の電線の埋設率は100%である(1977年)。
ロンドンの家。1988年。

家は半世紀前の石造りと古い。
テレビのアンテナはあるが、電柱、電線はまったく見当たらない。
ロンドンの家の近くの並木道。1990年。

街灯はあっても、電柱、電線はまったく見当たらない。
ロンドンで、2軒目の家。2000年。

電話線が、右上から煙突の方向に走っている。
ごみごみと醜い、というほどではなかった。
世田谷区の電線の埋設率は0.2%である(1998年)。
松本。家の窓から。2007年。

電柱と電線が空をおおう。
ごみごみと醜いではないか!
みなさんの家の周りは、どうだろうか?
山(左下)や空、景色は、電線の間から見る。
こうゆうことは、アメリカでも、イギリスでも、なかった。
実際に住んだ家の電柱、電線の状況から、
ニューヨークの電線の埋設率が72.1%(1977年)であり、
ロンドンの電線の埋設率が100%(1977年)、
世田谷区の電線の埋設率が0.2%(1998年)、
というのが、うなずける。
具体的には、窓から景色や空を見ればわかる。
日本の街では、電柱が林立し、
電線がクモの巣のように空をおおっている。
しかし、先進国の街では、電線を埋設していた。
日本で、道路の拡幅にともなう電柱の工事をみる。

田んぼを区画整理して、東西南北に道路ができた。松本市。2010年。
その道路に沿って、電柱を建てているから、電線も縦横に走る。
その道路には歩道がなかったために、拡幅工事をしていた。
道路沿いの電柱はどうするのかな?
道路には、排水用の側溝を造っているから、
電線も埋設するチャンスだと思ってみていた。
歩道の幅は、電線の共同溝を埋めるのに十分な幅であるから。
すると、道路沿いの電柱、10数本を一斉に、数メートル移動した。
つまり、白い車の前あたりに並んでいた電柱の列を、
車の後方まで一斉に移動するという大工事をした。
しかも、工期は、田んぼが稲刈りを終えてから、
工事をするから、2年以上かけている。
道路を拡幅するという計画も、あらかじめわかっていて、
電線を埋設するための工期もあったが、
電線は埋設しなかった。
日本では、このように電線を埋めずに、
工事費を大幅に倹約しているから、
電気料金は、安くなるのかな? と思うが、
日本の電気料金は、アメリカやイギリスの2倍だった。
とりわけ安くなかった。とりわけ高かった。
日本は、
景観が悪く、
電気料金が高く、
歩行者や自転車、車いすの利用者にとっては危険であり、
地震や台風の災害では、ライフラインの確保がむずかしい、
ということになる。
日本でも、先進国と同じように、
電線は「埋設率」(地中下率)で管理することになり、
埋設率100%を目指してほしい、実現してほしい。
国土交通省が提唱するように、
(http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chichuka/index.htmlから)

1)「安全で快適な通行空間の確保」のために、
2)「都市景観の向上」のために、
3)「都市災害の防止」のために、
4)「情報通信ネットワークの信頼性向上」のために。
「日本では、函館が先駆けとなって、先進国の都市と同じように、
電線の『埋設率』(地中下率)100%が実現すれば、快挙だ」
「日本のほかの街でも、電線は『埋設率』で管理することになり、
埋設率100%を実現してほしい」
と書いた。
日本では、電柱が街中に林立し、
電線がクモの巣のように空をおおっていて、
街の景観を醜くしているが、
先進国の都市の電線の「埋設率」はどうであろうか?
電線の埋設率の国際比較をしてみる。
電線の埋設率の国際比較。

電気事業連合会、国土交通省の資料から作成。
海外は、電気事業連合会の調べで、「ケーブル延長ベース」。
日本は、国土交通省の調べで、「道路延長ベース」。
電線の埋設率の国際比較のグラフ。
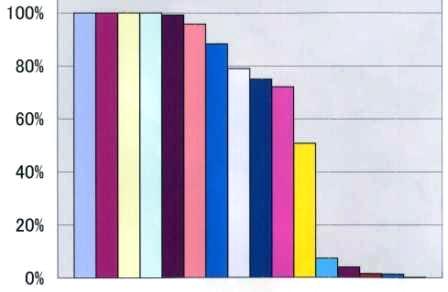
ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ボン(ドイツ)、香港の電線の埋設率は100%である。
ドイツのベルリン、ハンブルグ、ミュンヘンも埋設率が高い。
コペンハーゲン(デンマーク)、クアラルンプール(マレーシア)、ニューヨーク(アメリカ)が続く。
先進国の都市は、電線の埋設率100%を目指している。
これに対して、日本の電線の埋設率は、
先進国から、大きく立ち遅れている。
たとえば、東京の電線の埋設率は7.3%である(2008年)。
だが、東京の電線の埋設率は23区に限定し、
しかも、「市街地の道路」に限定している。
つまり、市街で、しかも国道や都道(県道)沿いである。
市街を離れたり、市道を含めれば、極端に悪くなる。
京都の4%も大阪の1.4%も同じで、「市街地の道路」に限定している。
限定しても、先進国の街からは、大きく立ち遅れている。
残念なのは、電線の埋設率について、
きちんとした国際比較の資料がないことである。
世界は、電気事業連合会の調査で、1977年であり、
日本は、国土交通省の調査で、2008年である。
それに、海外は「ケーブル延長ベース」で、
日本は「道路延長ベース」である。
「ケーブル延長ベース」と「道路延長ベース」のちがいは何だろう?
日本では、電柱と電線が屋敷や田園、農地を走る。
それに、道路を横切る電柱と電線があるから、
日本の「ケーブル延長ベース」での埋設率は、
もっと悪くなりそうだ、と推察したが。
電気事業連合会の「ケーブル延長ベース」の調査は1977年と古い。
「ケーブル延長ベース」で調べた最近の結果がほしい。
でも、どうしてないんだろう?
敷設したケーブルの長さは、すぐにわかりそうだが?
日本の街は、世田谷区の0.2%(1998年)という数字が、
実感する電線の埋設率ではないだろうか?
「アメリカ、イギリス、日本の住環境」2010年10月3日で、
アメリカ、イギリス、日本で住んだ家で住環境を比較した。
「電線の埋設率の国際比較」で示した数字と、
実際にアメリカ、イギリス、日本で住んだ家の電柱、電線の状況を比較してみる。
ニューヨーク(アメリカ)の電線の埋設率は72.1%である(1977年)。
ロス・アンジェルスの家。2000年。

電柱が家の左に見える。
それと、丘の上にも点々とならぶ。
しかし、ごみごみと醜いほどではなかった。
目の前に電柱や電線があって、景色をさえぎったり、
空をおおったりはしていなかった。
ロンドン(イギリス)の電線の埋設率は100%である(1977年)。
ロンドンの家。1988年。

家は半世紀前の石造りと古い。
テレビのアンテナはあるが、電柱、電線はまったく見当たらない。
ロンドンの家の近くの並木道。1990年。

街灯はあっても、電柱、電線はまったく見当たらない。
ロンドンで、2軒目の家。2000年。

電話線が、右上から煙突の方向に走っている。
ごみごみと醜い、というほどではなかった。
世田谷区の電線の埋設率は0.2%である(1998年)。
松本。家の窓から。2007年。

電柱と電線が空をおおう。
ごみごみと醜いではないか!
みなさんの家の周りは、どうだろうか?
山(左下)や空、景色は、電線の間から見る。
こうゆうことは、アメリカでも、イギリスでも、なかった。
実際に住んだ家の電柱、電線の状況から、
ニューヨークの電線の埋設率が72.1%(1977年)であり、
ロンドンの電線の埋設率が100%(1977年)、
世田谷区の電線の埋設率が0.2%(1998年)、
というのが、うなずける。
具体的には、窓から景色や空を見ればわかる。
日本の街では、電柱が林立し、
電線がクモの巣のように空をおおっている。
しかし、先進国の街では、電線を埋設していた。
日本で、道路の拡幅にともなう電柱の工事をみる。

田んぼを区画整理して、東西南北に道路ができた。松本市。2010年。
その道路に沿って、電柱を建てているから、電線も縦横に走る。
その道路には歩道がなかったために、拡幅工事をしていた。
道路沿いの電柱はどうするのかな?
道路には、排水用の側溝を造っているから、
電線も埋設するチャンスだと思ってみていた。
歩道の幅は、電線の共同溝を埋めるのに十分な幅であるから。
すると、道路沿いの電柱、10数本を一斉に、数メートル移動した。
つまり、白い車の前あたりに並んでいた電柱の列を、
車の後方まで一斉に移動するという大工事をした。
しかも、工期は、田んぼが稲刈りを終えてから、
工事をするから、2年以上かけている。
道路を拡幅するという計画も、あらかじめわかっていて、
電線を埋設するための工期もあったが、
電線は埋設しなかった。
日本では、このように電線を埋めずに、
工事費を大幅に倹約しているから、
電気料金は、安くなるのかな? と思うが、
日本の電気料金は、アメリカやイギリスの2倍だった。
とりわけ安くなかった。とりわけ高かった。
日本は、
景観が悪く、
電気料金が高く、
歩行者や自転車、車いすの利用者にとっては危険であり、
地震や台風の災害では、ライフラインの確保がむずかしい、
ということになる。
日本でも、先進国と同じように、
電線は「埋設率」(地中下率)で管理することになり、
埋設率100%を目指してほしい、実現してほしい。
国土交通省が提唱するように、
(http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chichuka/index.htmlから)

1)「安全で快適な通行空間の確保」のために、
2)「都市景観の向上」のために、
3)「都市災害の防止」のために、
4)「情報通信ネットワークの信頼性向上」のために。