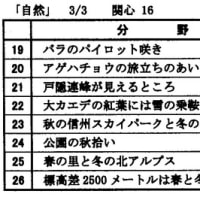春の「乗鞍岳」に登る。

乗鞍岳は3,000メートル級の山。
目指すは最高峰の「剣ヶ峰」3,026メートル。
左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
牛留池(うしどめいけ)、乗鞍高原から撮影。2014年6月15日。
剣ヶ峰には、夏に登ったことがある。2008年9月。

「乗鞍エコーライン」の終点、「畳平」から1時間半で登ることができる。
3,000メートル級の山としては楽である。それに、眺めがいい。
バス停の「肩の小屋口」から眺める「剣ヶ峰」。2013年9月。

剣ヶ峰K、蚕玉岳(こだまだけ)D、朝日岳A。
白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。
このバス停「肩の小屋口」から、さらに5分ほど走ると、
終点の「畳平」になる。
春の乗鞍岳に登りたいが、朝起きると、天気がいい。
「今日は登れそうだ」。2014年6月15日。
昨日の2014年6月14日に、乗鞍岳に登るつもりでいた。
乗鞍高原の観光センター前、始発の7時半のバスに乗ったのだが、
「大雪渓・肩の小屋口」に着くとガスがかかっていた。

剣ヶ峰は全く見えない。それに強風。
猛獣が叫んでいるような「うなり」がした。
「これでは登れない」。登山は断念した。
天気が期待できる翌日(2014年6月15日)、
乗鞍高原の観光センター前、9時40分のバスに乗った。
乗鞍エコーラインは、「大雪渓・肩の小屋口」に近づくと、
「雪の壁」が現れる。2014年6月15日。

高さ7メートルの「雪の壁」の左奥に「剣ヶ峰」が見える。
これが目指す乗鞍岳の最高峰だ。天気はいい。
「大雪渓・肩の小屋口」には、10時半ころに着いた。

バスは3台。乗客はスキーヤー、ボーダー、散策する人。
登山客はいない。始発の7時半に乗った。
バス停の名前が、「肩の小屋口」から、「大雪渓・肩の小屋口」に、
代わっている(2014年から)。
「大雪渓・肩の小屋口」は、にぎわっていた。

それに、剣ヶ峰K、蚕玉岳(こだまだけ)D、朝日岳Aが、ちゃんと見える。
ガスから晴れへと、1日で天気がガラリと変わった。
乗鞍高原の観光センター前を始発の7時半のバスで登ってきた人たちが、
すでにスキーを楽しんでいる。
蚕玉岳Dの右下が大雪渓Sだが、一面の雪で見分けがつかない。
スキーヤー、ボーダーは、大雪渓Sにこだわることなく、
好みのスロープを選んで、滑走している。
乗鞍エコーラインは、6月まで「大雪渓・肩の小屋口」が終点。
ここから先の畳平(たたみだいら)までは、雪のために閉鎖中。
乗鞍エコーラインが全線開通するのは7月1日の予定。
剣ヶ峰に登るが、ルートはどうしようか?
剣ヶ峰Kに登る人の列が、朝日岳Aの下↑に見える。
始発の7時半で上がってきた人たちだ。
写真の右の雪山を登り、蚕玉岳Dに向かっている。
ほかにも上がっている人が、蚕玉岳Dの左↑にいる。
写真の左下のバス停「大雪渓・肩の小屋口」から、
剣ヶ峰の直登ルートを取った。
帰りのバスは、限られている。
「大雪渓・肩の小屋口」発、13時24分か、15時26分になる。
最終の15時26分に乗れば、4時間で剣ヶ峰を往復して、余裕がある。
雪山の登りに2時間、頂上に1時間、下りに1時間とすれば4時間になる。
剣ヶ峰の直登ルートを選んだ。
スパッツを着け、アイゼンを着けた。
10時40分に登り始めた。雪山をあえぎながら、
滑り落ちないように、剣ヶ峰Kと蚕玉岳Dの間の鞍部▽に出た。
12時だった。1時間20分の登り。

鞍部の高さは2,988メートル。EPSONのWritable GPSで。
「大雪渓・肩の小屋口」は2,616メートルだから、標高差372メートル。
この直登ルートは、鞍部に近づくにつれて急斜面になる。

それに、雪の状態が変化した。
スキーヤーで踏み固めた下から、
スキーヤーが入らずに、ズボリと埋まる中ほど、
そして、高度が上がるにつれて、固く締まってきた上部。
先人のアイゼンの跡を、踏みしめるようにして登った。
踏み外したり、バランスを崩すと滑落する。
強風だったら、登ることはできない。
鞍部の手前は急坂、30歩ずつ休んだ。
水泳で鍛えているようでも急坂はキツイ。
1回1,000メートル、年間10万メートル泳ぐが。
滑ったことを考えると、最初に制動しなければ加速する。
下を見ると、どこまでも落ちていきそうだ。
滑落を防ぐことを考えながら登った。
前のめり状態で上がった。
帰りには使えない。危険だ!
しかし、直登コースは、槍ヶ岳Y、穂高連峰Hを見るごほうびがあった。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。
右端に常念岳Jが見え、手前には焼岳Vが見える。
そして、鞍部に出た。

アイゼンを外して、右の岩場を歩いて剣ヶ峰Kを目指す。
この鞍部からは10分ほど。頂上小屋Pのそばを登る。
岩場で休んでいる2人は、直登ルートをスキーをかついで登ってきた。
スキーが雪に刺さっている。アイゼンをスキーに履き替えて、
乗鞍岳を滑り降りる。技術も体力も備えている人たちだ。
剣ヶ峰Kの頂上に立つと、「御嶽山」3,067メートルが南に見える。

右手前は「大日岳」。
剣ヶ峰Kの頂上から北側に槍ヶ岳Y、穂高連峰Hが見える。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、
右から白馬鎗ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。
剣ヶ峰Kの頂上から南東には「南アルプス」。

富士山は、仙丈ケ岳Sと北岳Nの間に顔を出すが、
曇で覆われていた。右は間ノ岳(あいのだけ)I。
剣ヶ峰で1時間ほど休んで、13時に下りた。

奥には槍ヶ岳Y、穂高連峰H、常念岳J。手前には焼岳V。
コロナ観測所C、右下には乗鞍エコーラインEが見える。
下山のルートは、
屋根に石が乗っている頂上小屋Pの左を通って、
鞍部を通り、蚕玉岳(こだまだけ)Dに登り、
肩の小屋Nから、右に広がる雪山を下りて、
「大雪渓・肩の小屋口」Bにもどった。
13時45分だったから、最終バスの15時26分までは、
1時間50分ほどある。下のバス停の「位ヶ原山荘前」まで、

乗鞍エコーラインを下りることにした。写真を撮りながら。
そして、最終バス15時34分に乗った。
剣ヶ峰の下山から、乗鞍エコーラインを下りて位ヶ原山荘前まで、
春の乗鞍岳の写真を掲載する。
「権現池」。噴火口。蚕玉岳(こだまだけ)Dから。

雪の間から、青い池が2つ顔を出している。
「雪の壁」がある。乗鞍エコーライン。

雪の壁の間から槍ヶ岳、穂高連峰。

乗鞍エコーラインから振り返った「剣ヶ峰」。

右が蚕玉岳。鞍部が、直登ルートで登ったところ。
「乗鞍エコーライン」。

乗鞍観光センター前発、午後2時半の最終バスが2台上がって行く。
雪の渦。位ヶ原山荘前から。

除雪して明らかになった乗鞍エコーラインが左右に走る。その上に、雪の渦がある。
位ヶ原山荘から乗鞍岳を眺めていると、
ボーダーやスキーヤーが下りてくる。

「滑ってきた」という。
それで、目を凝らした。
スキーヤー○が急斜面を滑り降りてくる。右端は富士見岳。

ボーダーやスキーヤーの技術と度胸は大したもんだ。
前日はガスと強風で、あきらめた乗鞍岳の登山。
翌日は、朝の晴れを見て、思い立った乗鞍岳の登山。
ガスも強風もなく、春の乗鞍岳に登ることができた。
槍ヶ岳、穂高連峰、雪の壁を見ることができた。

乗鞍岳は3,000メートル級の山。
目指すは最高峰の「剣ヶ峰」3,026メートル。
左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
牛留池(うしどめいけ)、乗鞍高原から撮影。2014年6月15日。
剣ヶ峰には、夏に登ったことがある。2008年9月。

「乗鞍エコーライン」の終点、「畳平」から1時間半で登ることができる。
3,000メートル級の山としては楽である。それに、眺めがいい。
バス停の「肩の小屋口」から眺める「剣ヶ峰」。2013年9月。

剣ヶ峰K、蚕玉岳(こだまだけ)D、朝日岳A。
白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。
このバス停「肩の小屋口」から、さらに5分ほど走ると、
終点の「畳平」になる。
春の乗鞍岳に登りたいが、朝起きると、天気がいい。
「今日は登れそうだ」。2014年6月15日。
昨日の2014年6月14日に、乗鞍岳に登るつもりでいた。
乗鞍高原の観光センター前、始発の7時半のバスに乗ったのだが、
「大雪渓・肩の小屋口」に着くとガスがかかっていた。

剣ヶ峰は全く見えない。それに強風。
猛獣が叫んでいるような「うなり」がした。
「これでは登れない」。登山は断念した。
天気が期待できる翌日(2014年6月15日)、
乗鞍高原の観光センター前、9時40分のバスに乗った。
乗鞍エコーラインは、「大雪渓・肩の小屋口」に近づくと、
「雪の壁」が現れる。2014年6月15日。

高さ7メートルの「雪の壁」の左奥に「剣ヶ峰」が見える。
これが目指す乗鞍岳の最高峰だ。天気はいい。
「大雪渓・肩の小屋口」には、10時半ころに着いた。

バスは3台。乗客はスキーヤー、ボーダー、散策する人。
登山客はいない。始発の7時半に乗った。
バス停の名前が、「肩の小屋口」から、「大雪渓・肩の小屋口」に、
代わっている(2014年から)。
「大雪渓・肩の小屋口」は、にぎわっていた。

それに、剣ヶ峰K、蚕玉岳(こだまだけ)D、朝日岳Aが、ちゃんと見える。
ガスから晴れへと、1日で天気がガラリと変わった。
乗鞍高原の観光センター前を始発の7時半のバスで登ってきた人たちが、
すでにスキーを楽しんでいる。
蚕玉岳Dの右下が大雪渓Sだが、一面の雪で見分けがつかない。
スキーヤー、ボーダーは、大雪渓Sにこだわることなく、
好みのスロープを選んで、滑走している。
乗鞍エコーラインは、6月まで「大雪渓・肩の小屋口」が終点。
ここから先の畳平(たたみだいら)までは、雪のために閉鎖中。
乗鞍エコーラインが全線開通するのは7月1日の予定。
剣ヶ峰に登るが、ルートはどうしようか?
剣ヶ峰Kに登る人の列が、朝日岳Aの下↑に見える。
始発の7時半で上がってきた人たちだ。
写真の右の雪山を登り、蚕玉岳Dに向かっている。
ほかにも上がっている人が、蚕玉岳Dの左↑にいる。
写真の左下のバス停「大雪渓・肩の小屋口」から、
剣ヶ峰の直登ルートを取った。
帰りのバスは、限られている。
「大雪渓・肩の小屋口」発、13時24分か、15時26分になる。
最終の15時26分に乗れば、4時間で剣ヶ峰を往復して、余裕がある。
雪山の登りに2時間、頂上に1時間、下りに1時間とすれば4時間になる。
剣ヶ峰の直登ルートを選んだ。
スパッツを着け、アイゼンを着けた。
10時40分に登り始めた。雪山をあえぎながら、
滑り落ちないように、剣ヶ峰Kと蚕玉岳Dの間の鞍部▽に出た。
12時だった。1時間20分の登り。

鞍部の高さは2,988メートル。EPSONのWritable GPSで。
「大雪渓・肩の小屋口」は2,616メートルだから、標高差372メートル。
この直登ルートは、鞍部に近づくにつれて急斜面になる。

それに、雪の状態が変化した。
スキーヤーで踏み固めた下から、
スキーヤーが入らずに、ズボリと埋まる中ほど、
そして、高度が上がるにつれて、固く締まってきた上部。
先人のアイゼンの跡を、踏みしめるようにして登った。
踏み外したり、バランスを崩すと滑落する。
強風だったら、登ることはできない。
鞍部の手前は急坂、30歩ずつ休んだ。
水泳で鍛えているようでも急坂はキツイ。
1回1,000メートル、年間10万メートル泳ぐが。
滑ったことを考えると、最初に制動しなければ加速する。
下を見ると、どこまでも落ちていきそうだ。
滑落を防ぐことを考えながら登った。
前のめり状態で上がった。
帰りには使えない。危険だ!
しかし、直登コースは、槍ヶ岳Y、穂高連峰Hを見るごほうびがあった。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。
右端に常念岳Jが見え、手前には焼岳Vが見える。
そして、鞍部に出た。

アイゼンを外して、右の岩場を歩いて剣ヶ峰Kを目指す。
この鞍部からは10分ほど。頂上小屋Pのそばを登る。
岩場で休んでいる2人は、直登ルートをスキーをかついで登ってきた。
スキーが雪に刺さっている。アイゼンをスキーに履き替えて、
乗鞍岳を滑り降りる。技術も体力も備えている人たちだ。
剣ヶ峰Kの頂上に立つと、「御嶽山」3,067メートルが南に見える。

右手前は「大日岳」。
剣ヶ峰Kの頂上から北側に槍ヶ岳Y、穂高連峰Hが見える。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、
右から白馬鎗ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。
剣ヶ峰Kの頂上から南東には「南アルプス」。

富士山は、仙丈ケ岳Sと北岳Nの間に顔を出すが、
曇で覆われていた。右は間ノ岳(あいのだけ)I。
剣ヶ峰で1時間ほど休んで、13時に下りた。

奥には槍ヶ岳Y、穂高連峰H、常念岳J。手前には焼岳V。
コロナ観測所C、右下には乗鞍エコーラインEが見える。
下山のルートは、
屋根に石が乗っている頂上小屋Pの左を通って、
鞍部を通り、蚕玉岳(こだまだけ)Dに登り、
肩の小屋Nから、右に広がる雪山を下りて、
「大雪渓・肩の小屋口」Bにもどった。
13時45分だったから、最終バスの15時26分までは、
1時間50分ほどある。下のバス停の「位ヶ原山荘前」まで、

乗鞍エコーラインを下りることにした。写真を撮りながら。
そして、最終バス15時34分に乗った。
剣ヶ峰の下山から、乗鞍エコーラインを下りて位ヶ原山荘前まで、
春の乗鞍岳の写真を掲載する。
「権現池」。噴火口。蚕玉岳(こだまだけ)Dから。

雪の間から、青い池が2つ顔を出している。
「雪の壁」がある。乗鞍エコーライン。

雪の壁の間から槍ヶ岳、穂高連峰。

乗鞍エコーラインから振り返った「剣ヶ峰」。

右が蚕玉岳。鞍部が、直登ルートで登ったところ。
「乗鞍エコーライン」。

乗鞍観光センター前発、午後2時半の最終バスが2台上がって行く。
雪の渦。位ヶ原山荘前から。

除雪して明らかになった乗鞍エコーラインが左右に走る。その上に、雪の渦がある。
位ヶ原山荘から乗鞍岳を眺めていると、
ボーダーやスキーヤーが下りてくる。

「滑ってきた」という。
それで、目を凝らした。
スキーヤー○が急斜面を滑り降りてくる。右端は富士見岳。

ボーダーやスキーヤーの技術と度胸は大したもんだ。
前日はガスと強風で、あきらめた乗鞍岳の登山。
翌日は、朝の晴れを見て、思い立った乗鞍岳の登山。
ガスも強風もなく、春の乗鞍岳に登ることができた。
槍ヶ岳、穂高連峰、雪の壁を見ることができた。