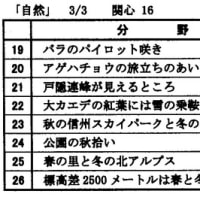「乗鞍岳」は3,000メートル級の山。

最高峰は剣ヶ峰3,026メートル。
左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
乗鞍高原スキー場の駐車場から。2013年12月。
「乗鞍岳」は松本城からも見ることができる。2014年2月。

高天ヶ原T、剣ヶ峰K、朝日岳A、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
松本市街から見ることができる乗鞍岳だから、眺望は期待できる。
右端にある「大黒岳」2,771メートルに登ると、四方を見渡すことができる。
大黒岳の北には「槍ヶ岳」Y、「穂高連峰」Hが見える。2013年9月。

大黒岳から「畳平」(たたみだいら)を見下ろす。

この畳平までバスで上がってきた。2、702メートル。
「乗鞍高原」からの「乗鞍エコーライン」の終点であり、
岐阜県側から上がる「乗鞍スカイライン」の終点でもある。
奥は里見岳2,824メートル、手前は鶴ヶ池。
松本から乗鞍高原へは、乗鞍観光センター前まで車で上がる。
電車とバスでは、松本から新島々線で新島々へ行き、
バスに乗り換えて乗鞍観光センター前へ。
低公害バスは、乗鞍観光センター前を毎時に出て、
乗鞍エコーラインを走り、50分で終点の畳平へ。
「乗鞍エコーライン」。2013年10月。

秋は、紅葉狩りや登山、スキー客を乗せて、低公害バスが上がって行く。
乗鞍観光センター前を午後2時発のバスが6台も上がる。
シーズン中は多くのお客さんでにぎわう。
冬季は大雪のためにクローズ。
除雪して5月中旬に、「肩の小屋口」まで開通する。

雪の壁は、所により5メートルはある。2014年6月14日。
乗鞍エコーラインが、畳平まで全線開通するのは7月から。
大黒岳から南には、乗鞍岳の最高峰、剣ヶ峰Kが見える。

剣ヶ峰Kへ登るルートがわかる。
写真の右下にある畳平から、
手前の富士見岳Fに一旦登ってから、先を下りる。
それか、右を迂回して、コロナ観測所Cの左下に行く。
そして、朝日岳Aの横を回って、蚕玉岳(こだまだけ)Dから、
剣ヶ峰Kに登る。2013年9月撮影。
乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」3,026メートルに登る。2008年9月。

畳平2、702メートルから、剣ヶ峰までは、1時間半ほどの登り。
3,000メートル級にしては、夏場は登りやすい山。
ただ、3,000メートル級の山だから、
夏でも寒さ対策が必要、それに、
くるぶしを覆う靴が望ましい。
剣ヶ峰からの眺めは素晴らしい。
北には「槍ヶ岳」、「穂高連峰」と北アルプス、
南東には「八ヶ岳」、「南アルプス」、「富士山」、「中央アルプス」、
南には「御嶽山」を望むことができる。
北には「槍ヶ岳」と「穂高連峰」が見える。2008年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。手前には焼岳V。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。
北側は、登ってきた方向を振り返ることになるが、
コロナ観測所Cの右下に見える平坦な道を、肩の小屋Nに向う。

夏でも雪が残る「大雪渓」Sが見える。

奥はコロナ観測所Cで摩利支天岳Mにある。その左は不動岳。
左の赤い屋根は東大宇宙線研究所T。
肩の小屋Nからは、平坦な道に分かれて、
手前の山道を上がり、蚕玉岳(こだまだけ)Dを目指す。
ここからは、くるぶしを覆う靴が望ましい。
屋根に石が乗っている頂上小屋Pのわきを通って、剣ヶ峰に登る。
右下には乗鞍エコーラインEとバス停の「肩の小屋口」Bが見える。

バス停の肩の小屋口から、終点の畳平までは、さらに5分ほど上がる。
白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。
肩の小屋口には「剣ヶ峰登山口」の標識があって、
剣ヶ峰へのルートは、大雪渓Sの右を上がり、
肩の小屋Nに出る。
肩の小屋口からは、スキーヤーも大雪渓Sに登る。2013年9月。

剣ヶ峰Kには、摩利支天岳Mのコロナ観測所Cを見ながら登ると、肩の小屋Nに出る。
肩の小屋Nで、右からの畳平からのコースと合流する。
そして、蚕玉岳(こだまだけ)Dを経て、剣ヶ峰Kへ。
「大雪渓」。

1年中、雪が消えることがないから、スキーヤーにはたまらない。2013年9月。
北側方面は槍ヶ岳Y、穂高連峰H。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、
右から白馬鑓ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。
大黒岳から。2013年9月。
剣ヶ峰からは、南東に「南アルプス」が見える。2008年9月。

⇒富士山が北岳の左に顔を出す。北岳は3,193メートルで、日本で第2位の高さ。
左端の三角は、南アルプスの甲斐駒ヶ岳(2,967メートル)。
富士山を拡大すると、

右の北岳と左の仙丈ヶ岳(3,033メートル)の間にぼんやりとある。
剣ヶ峰の南には「御嶽山」(3,067メートル)が見える。

右手前は「大日岳」。
乗鞍岳からの眺めはいい。
槍ヶ岳、穂高連峰、北アルプス、
浅間山、八ヶ岳、南アルプス、富士山、
中央アルプス、御嶽山を望むことができた。
最後に、槍ヶ岳、穂高連峰の「朝焼け」。肩の小屋口から、2013年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。右には常念岳J。
乗鞍観光センター前を、朝4時10分の「ご来光バス」に乗り、
「乗鞍エコーライン」を上がって、肩の小屋口から、
燃ゆる北アルプスを見ることができる。

最高峰は剣ヶ峰3,026メートル。
左から高天ヶ原T、剣ヶ峰K、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
乗鞍高原スキー場の駐車場から。2013年12月。
「乗鞍岳」は松本城からも見ることができる。2014年2月。

高天ヶ原T、剣ヶ峰K、朝日岳A、摩利支天岳M、富士見岳F、大黒岳I。
松本市街から見ることができる乗鞍岳だから、眺望は期待できる。
右端にある「大黒岳」2,771メートルに登ると、四方を見渡すことができる。
大黒岳の北には「槍ヶ岳」Y、「穂高連峰」Hが見える。2013年9月。

大黒岳から「畳平」(たたみだいら)を見下ろす。

この畳平までバスで上がってきた。2、702メートル。
「乗鞍高原」からの「乗鞍エコーライン」の終点であり、
岐阜県側から上がる「乗鞍スカイライン」の終点でもある。
奥は里見岳2,824メートル、手前は鶴ヶ池。
松本から乗鞍高原へは、乗鞍観光センター前まで車で上がる。
電車とバスでは、松本から新島々線で新島々へ行き、
バスに乗り換えて乗鞍観光センター前へ。
低公害バスは、乗鞍観光センター前を毎時に出て、
乗鞍エコーラインを走り、50分で終点の畳平へ。
「乗鞍エコーライン」。2013年10月。

秋は、紅葉狩りや登山、スキー客を乗せて、低公害バスが上がって行く。
乗鞍観光センター前を午後2時発のバスが6台も上がる。
シーズン中は多くのお客さんでにぎわう。
冬季は大雪のためにクローズ。
除雪して5月中旬に、「肩の小屋口」まで開通する。

雪の壁は、所により5メートルはある。2014年6月14日。
乗鞍エコーラインが、畳平まで全線開通するのは7月から。
大黒岳から南には、乗鞍岳の最高峰、剣ヶ峰Kが見える。

剣ヶ峰Kへ登るルートがわかる。
写真の右下にある畳平から、
手前の富士見岳Fに一旦登ってから、先を下りる。
それか、右を迂回して、コロナ観測所Cの左下に行く。
そして、朝日岳Aの横を回って、蚕玉岳(こだまだけ)Dから、
剣ヶ峰Kに登る。2013年9月撮影。
乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」3,026メートルに登る。2008年9月。

畳平2、702メートルから、剣ヶ峰までは、1時間半ほどの登り。
3,000メートル級にしては、夏場は登りやすい山。
ただ、3,000メートル級の山だから、
夏でも寒さ対策が必要、それに、
くるぶしを覆う靴が望ましい。
剣ヶ峰からの眺めは素晴らしい。
北には「槍ヶ岳」、「穂高連峰」と北アルプス、
南東には「八ヶ岳」、「南アルプス」、「富士山」、「中央アルプス」、
南には「御嶽山」を望むことができる。
北には「槍ヶ岳」と「穂高連峰」が見える。2008年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。手前には焼岳V。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。
北側は、登ってきた方向を振り返ることになるが、
コロナ観測所Cの右下に見える平坦な道を、肩の小屋Nに向う。

夏でも雪が残る「大雪渓」Sが見える。

奥はコロナ観測所Cで摩利支天岳Mにある。その左は不動岳。
左の赤い屋根は東大宇宙線研究所T。
肩の小屋Nからは、平坦な道に分かれて、
手前の山道を上がり、蚕玉岳(こだまだけ)Dを目指す。
ここからは、くるぶしを覆う靴が望ましい。
屋根に石が乗っている頂上小屋Pのわきを通って、剣ヶ峰に登る。
右下には乗鞍エコーラインEとバス停の「肩の小屋口」Bが見える。

バス停の肩の小屋口から、終点の畳平までは、さらに5分ほど上がる。
白は大雪渓Sで、1年中、雪が消えることがない。
肩の小屋口には「剣ヶ峰登山口」の標識があって、
剣ヶ峰へのルートは、大雪渓Sの右を上がり、
肩の小屋Nに出る。
肩の小屋口からは、スキーヤーも大雪渓Sに登る。2013年9月。

剣ヶ峰Kには、摩利支天岳Mのコロナ観測所Cを見ながら登ると、肩の小屋Nに出る。
肩の小屋Nで、右からの畳平からのコースと合流する。
そして、蚕玉岳(こだまだけ)Dを経て、剣ヶ峰Kへ。
「大雪渓」。

1年中、雪が消えることがないから、スキーヤーにはたまらない。2013年9月。
北側方面は槍ヶ岳Y、穂高連峰H。

穂高連峰Hは、左が奥穂高岳と右が前穂高岳。手前には焼岳Vがある。
槍ヶ岳Yの左には北アルプスが連なる。野口五郎岳Nとの間には、
右から白馬鑓ヶ岳、白馬岳、針ノ木岳などが見える。
大黒岳から。2013年9月。
剣ヶ峰からは、南東に「南アルプス」が見える。2008年9月。

⇒富士山が北岳の左に顔を出す。北岳は3,193メートルで、日本で第2位の高さ。
左端の三角は、南アルプスの甲斐駒ヶ岳(2,967メートル)。
富士山を拡大すると、

右の北岳と左の仙丈ヶ岳(3,033メートル)の間にぼんやりとある。
剣ヶ峰の南には「御嶽山」(3,067メートル)が見える。

右手前は「大日岳」。
乗鞍岳からの眺めはいい。
槍ヶ岳、穂高連峰、北アルプス、
浅間山、八ヶ岳、南アルプス、富士山、
中央アルプス、御嶽山を望むことができた。
最後に、槍ヶ岳、穂高連峰の「朝焼け」。肩の小屋口から、2013年9月。

槍ヶ岳Y。穂高連峰Hは、左が奥穂高岳、右が前穂高岳。右には常念岳J。
乗鞍観光センター前を、朝4時10分の「ご来光バス」に乗り、
「乗鞍エコーライン」を上がって、肩の小屋口から、
燃ゆる北アルプスを見ることができる。