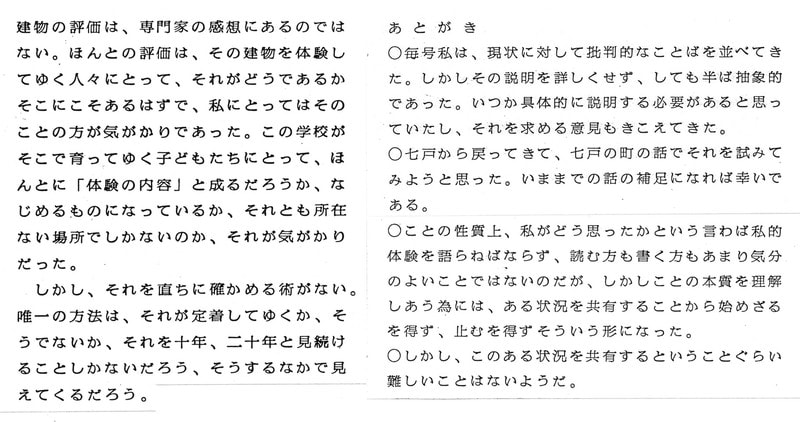
(「筑波通信№7 前半」より続く)
学校建築については、当時既に、学校において行なわれる教育の形態(授業形態)が実地に観察され、細かく分折・検討が行なわれ、いろいろな室や運動場などの(教育の場としての)備えるべき条件だとか、それらの並べかたの方法などについて、学校建築の専門家たちが研究を重ね、またそれに拠る各種の提案やモデル建築が提示されていたのであるが、しかし現実に建っている模範的と言われた実例は、正直言って合点がゆかず、私の通った古い木造の学校の方が、私には数等なじめるとひそかに思ったものである。私の疎開先の学校は、木造平家建の教室がハモニカ様に並んだ校舎が三本平行し、それを「王の字」型に廊下がつないでいる、昔よくあった型であったけれども、うす暗い教室のすみっこなどは結構楽しかったし、とりわけ二列の校舎の間の幅2メートル(もっとあったかとも思う)ぐらいの小川(用水路)がきれいな水をたたえて流れていた、その細長い空間は、もたれかかってなにかをした校舎の木の外壁とともに、別にこれといった細工など何も施されていなかったけれども、最もなじんだ場所であって、いまではもっと美化された形で思い出として浮んでくる。
そういった学校建築の専門家たちの研究成果のとりこまれた学校がなじめない、いったいそれはなぜなのか。
私の行きついた結論は、この人たちの学校建築について考えていることには、子どもたちの生活が欠落している、そこにあるのは、子どもたちの教育(授業)との係わりという局面での諸行為としての意味の生活だけなのだ、そういう結論であった。そして、学校建築というのは、そういう単なる「教育の場」として限定して考えてしまう前に、ほんとの意味での「生活の場」として先ず考えるべきだと考えるようになったのである。
子どものころを思いだしていただければ直ちに分ることなのだが、たとえば学校の建物や校庭のほんのちょっとした一偶や、校庭にあった木、草むら、あるいは往復の二十分もあれば行きつくのに小一時間もかかった道すがら(いま私は、あの疎開先の学校を思い出しながら書いている)、そういった光景とそこでの私の姿が次々と、月なみの表現でいえば走馬燈の如くに、思い出される一方で、たとえばどんな具合にしてかけ算やわり算を習ったか、その授業形態その場面としての教室の光景というのは、けろりと忘れていることに気がつくはずだ。授業がらみで思いだすことがあるとすれば、廊下に立たされたとか、指されたけれど答えられなくて弱ったことだとか、私の場合そういうえらく情けない話だけだ(これについては、ことあるたびに大人の人に尋ねてきたのだけれども、思い出すのが授業外のことである点は全く同様であった)。
すなわち、大人が必死になって考えている「教育」の局面は、子どもの私たちによって、こういった生活のほんの一部に押しやられ、あるいは一部としてくるまれてしまっていたということなのだ。
唐木順三の「途中の喪失」という随筆のなかに、次のような一節がある。
「私たちの子どものころは途中で友だちを誘い合いさんざんに道草を食って学校へいった。学校へついても授業の始まるまでに三十分も一時間もあるという具合であった。学校までの道草、ふざけたり、けんかをしたり、空想を語り合ったり、かけたり、ころんだりした道草、この一見無駄な途中によって、ほのぼのとしたものではあるが、さまざまな人生経験がつまれていったように思う。途中は目的地への最短距離ではなくて、少年たちの共通の広場であり、空想の花園でもあり、遊びの場所でもあった。ときには上級生の下級生への制裁の揚所にもなり、教室から開放された悪意の腕のふるい場所でもあったが、それはそれなりの秩序をもっていた。教室で学びえないものを、おのづからにして学びとる場所でもあったわけである。」
これは、子どもにとっての学校(生活)を十分に語って余りある文章だと私は思う。余談だが、私がこの随筆を初めて読んだのは、設計した小学校の工事監理のために七戸へ赴く夜行列車のなかのことであった。折悪しく夏の帰省時で寝台がとれず一等指定席(いまのグリーン車)中ほどより後の通路側、そんな席のことまで覚えている。設計のときいろいろ考え悩み、自信もそれほどないまま、言ってみれば半ば強引に自分の考えを押し通してきた私にとって、私と同じような考えを述べたこの文に出会ったということが、いかにうれしいものであったか。多分想像していただけるものと思う。
ことによると、しかしこういうことは、あなたがたの世代の子どものころの話であって、たとえば通学路も指定され、また授業内容も比較にならないほどきつくなっているいまの子どもたちは、必らずしもそうではないのではないか。これは、あなたがた世代の懐古の情、歳とった証拠である、などと言われかねない、などという気もする。しかしそれは、いま子どもたちに尋ねたところで、はっきりとは分ってこない。分かるのは多分彼らの十年後二十年後だろうと思う。ただ、私事で恐縮だが、私が筑波研究学園都市に移住してしばらくたったあとで、私の子どもに、前いた東京の学校といまの学校(因果なことに、ほんとに幸か不幸か、私の設計に関係した建物だ)の違いについて尋ねてみたところ、「こんどの学校は、かくれんぼができない。」そういう答がかえってきた。それをきいて、いまだって、少しも変っていない、そう私は(勝手に〉確信をもったのである。
それと同時に、この学校について、雨が漏る、暑い、‥といったいろいろな批判をうけていたのだが、そのどれにもまして、この「かくれんぼができない」という一言ほどぐさりときたものはなかった。えらそうなこと言って、既にして観念的になって、考えだけが上すべりしている、お前が七戸で考えたことは何だったのだ、どこへ行ったのだ、そういう詰問にきこえたのだ。いまでもこの学校のそばは、しょっちゅう通らざるを得ないのだが、その度に「かくれんぼのできない学校」という苦い思いがよぎるのである。
なるほど確かに、学校での子供たちの「生活」時間を、時間数で計るならば、その7・8割は教育:授業に費されているはずなのであるが、子どもの私たちにとってそれは、いま書いてきたように、むしろ逆転した比率、あるいはそれ以下にしか記憶されないのだという事実、これは十分に考えられなければならない。
考えてみれば、あるいは考えるまでもなく、学校の教育・授業(特に義務教育の)というのは大人の勝手、大人の論理なのであって、子どもの都合ではないし、子どもの都合が考えられているわけでもない。そして子どもは、そういう大人の思惑にも拘らず、それとは関係なく、そういった大人のつくった制度やわく組のなかで、それでもなおしたたかに子どもの論理を展開しているのである。
子どもにとって、彼らの生活の(ほんの)一部に「教育」がある、先ずこのことを認めることから始めよう。これが私の考えたこと:「教育の場」である前に先ず「生活の場」であるこの基本である。
ふと省みてもらえば分ることなのだが、これほど感受性豊かなときは他にないと思われる子ども時代の六年間という長い年月を、子どもたちは(彼らの意志によってではなく)学校ですごすのだ。そういう(彼らにとっていや応なく与えられる)場所での体験を経て、子どもは大人になる。これは何人も否定し得ない真実である。それが「生活の場」でなくして、いったい何だろう。
だから私には、学校建築の専門家たちの考えていることは、ただ大人の論理に従順な子どもたちをつくる教育のための鋳型だけを考えているようにしか見えなかった。そこにも、(子どもたちの)主体性というものは、つめのあかほども考えられてはいないのだ。
私は別に、ここで、子どもの論理を抽出して、言わばそれに迎合すればよい、などと言っているのではない。そうではなく、子どもたちでさえ(あるいは子どもたちだからこそかもしれない)主体的に生活をしている、そのことを知るべきだと言っているのである。この点については、最近車を走らせながらきいた、灰谷健次郎の語っていた言葉(正確ではないかも知れない)が印象に残っている。「私は教師であったとき、決して子どもに迎合しなかった。大人の論理をぶつけていった。しかしそれは、子どもの論理をないがしろにすることではなかった。」
だから、私がこの七戸町の小学校の設計に際し考えたことを、いままとめれば(というのはそんなに理路整然と、その当時まとまっていたわけではなかったから)この町の子どもたちが、教育制度という他動的なわく組に括られつつも、そこで子どもたちが主体的に生活し、言ってみれば子どもたちの社会が展開する、歳を重ね成長してゆく、そういう彼らの「体験の内容と成り得る」場所として耐え得る場所を用意すること、こういうことになるだろう。そしていわゆる「教育」は、言ってみれば、その一郭で行なわれる。そしてこれは、当然のことながら、先に説明してきた私たちと場所との関係についての話に収束する。
そして、七戸町立城南小学校は建った。そしてそれが、学校建築の専門家のなかで物議をかもしたのをうすうす知っていた。それが、少なくとも一見したところ、昔ながらの学校はもとより、当時学校建築の専門家によって推拳されていた模範的学校に比べて、どう見ても風変りであったから、専門家の間にさえ、その評価・位置づけをめぐって、少なからず途惑いが見られたのも、それは当然だったかもしれない。もちろん私には、風変りにすることが目標としてあったわけではない。
私はこの学校の設計にからんで、かなり当時の私の立場にしては過激な表現で文章をものし、建築の研究や専門家のやっていることに対し批判を重ねていたから、そういうことへの言わば感情的反発も微妙に混じったかたちで物議をかもしたのである。私が一番気にくわなかったのは(いまでもそうなのだが)こういう研究者、専門家を自称する人たちが、決して根源にさかのぼろうとはせずに(問題の本質が何であったかと自ら問うことを忘れ)ただいたずらに、一次グラフ的に進む、進めると思っていることだった。そういうのが研究者だというならば、私は潔く研究者であること、そうなること、そう呼ばれること、それを拒否しよう、そう思ったし、いまもそう思っている(だから私は建築学会の会員ではない)。
そして、いろいろな声やコメントが、直にではなく人や文章を介して私の目や耳に入ってきた。しかし、私にとってそれらはみなとんちんかんなことを言ってるようにしか見えなかった。
そうは言っても、そういう声やコメントを知っているわけだから、私が彼らの評判を全く気にしていなかったと言ったら、それはうそになる。けれどもつまるところ、彼らは一介の見学者であり観察者にすぎず視線がただその表面をなでてゆくだけだ。建物の評価は、専門家の感想にあるのではない。ほんとの評価は、その建物を体験してゆく人々にとって、それがどうであるかそこにこそあるはずで、私にとってはそのことの方が気がかりであった。この学校がそこで育ってゆく子どもたちにとって、ほんとに「体験の内容」と成るだろうか、なじめるものになっているか、それとも所在ない場所でしかないのか、それが気がかりだった。
しかし、それを直ちに確かめる術がない。唯一の方法は、それが定着してゆくか、そうでないか、それを十年、二十年と見続けることしかないだろう、そうするなかで見えてくるだろう。私は落成式の日、それはー段落してなんとなく気がぬけてゆくような感じになる日なのだが、これからが正念場、私が試される、びくびくせずに、しょっちゅう見に来よう、帰ってこよう、そう思ったのである。
この設計は、私が責任をまかされた、そういう意味で、私の初めての設計であった。この「初めて」という状況は、こういうある種の判断をともなうことの場合、極めて気のはりつめた一種の極限状況のようなものらしい。できあがった建物をあとになって見てみると、解決のしかたの下手さだとか、技術的対応のまずさだとか、そういった点が確かに目につくのだが、考えられる限り考えてあるという点では、その後の設計より数等ましだと思えるような感じさえ受ける。そういった「初めて」という状況が、問題の所在を明らかにして見せてくれるのだ(というと他動的にきこえてしまうけれども、そうではない。考えてる方が、言わばあとがないというような気分でいるから、かえって問題がその軽重をきれいに整理されたかたちで見えてくるのである)。実際、考えられるだけ考えた、まちがったことは考えなかった、手ぬきはなかった、そういう充実感というものがあって、できあがったものの下手さ、まずさにも拘らずやったことに悔いがないから不思議である。
むしろ、その後の設計の場合、確かに技術的な対応だとか解決の要領のよさだとかいう点では多少うまくなったとは思うが、どうしても目がそちらの方へ向いてしまって、問題の本質的な確認という点では、それをさぼる傾向があったのではないかと、いまふりかえってみると、思えてくる。
たとえば、先の「かくれんぼのできない学校」とは何か。ここには、その考えかたにおいて何か欠落があったのだ。何かをさぼったのだ。私は「かくれんぼ」という遊びをさんざん考えた。つまるところ、「かくれんぼ」とは、人の意表をつく遊びだと言ってよい。普通なら居そうなところに居ない。隠れる。それを、探す方も考え、探す。つまり、日常の裏返しを楽しんでいるわけだ。一番うまい隠れかたは、私の言いかたで言えば、「私の地図」外のところ、あるいは探し手側の「彼の地図」外のところに隠れることだ。「私の地図」外のところというのは、そこへ行くこと自体言ってみれば冒険であるから、そういうところに隠れていると、見つからぬようにと思う心と同時に、あるいはそれ以上に、なんとなく尻の落ちつかないその場所の不安さに圧倒されて、心臓がどきどきする。おそらくこういう後ろのお化けを気にしながら隠れていたというような体験は、みながもっているはずである。実は、そういう体験の積み重ねで(なにもかくれんぼだけでなく)「私の地図」は拡大していったのである。
「かくれんぼ」のできた学校、そこでは「私の地図」がいつも一枚しかないというのではなく、初めは狭い「私の地図」が、段々と拡大してゆき、ときには卒業するときになってもついに「私の地図」に載らないところが残ってしまった、そういう学校だと言ってよいだろう。「私の地図」が徐々に徐々に大きくなってゆくような、そういうつくりになっていたというわけだ。
これに対し、「かくれんぼのできない学校」では、「私の地図」の段階的発達がない、その初めから、たちまち全体が即「私の地図」に描かれてしまうのである。次の段階の「私の地図」は、すぐさま学校外へとびだしてしまうのだ。確かにこの学校は分りやすいのだが、体験に成長がないのである。
あえて言えば、この設計において私は、体験としての分り易さを追求はしたものの、体験の内容についての本質的な確認を、もうあたかも済ましてしまったかのように勝手に独り思いこみ、忘れてしまっていたのではないか。
七戸の場合、そこではかくれんぼができる。そこでは私はちゃんと、本質的な問題の確認をやってある。自分で言うのも妙なものだが、いまとかく忘れてしまいそうなことが、ちゃんと考えられている。
いま考えてみると、この学校はそれが私にとっての初めての設計であって、それが「初めて」であるが故に、私がその後考えてきた建築についての考えかたの大わく、骨組み:私にとっての問題の所在を、自ずと、垣間見せてくれたのだと思う。建築について私が考えてゆかなければならない問題が提起され(というより私に見えてきて)それに対してそのときの私なりに解答をだした、そのよし悪しはともかく、問題を考えられる限り考えた、おそらくそれが充実感とある種のさわやかさを私に味わせてくれたのだと思われる。言ってみれば、この設計は、いまの私の原点のようなものなのかもしれない。私はずっとそれを引きずってきた、あるいはそのとき浮んだ考え方の骨組みを確認し、問題により深く答えることを目標にして過ごしてきたのではなかろうか。そして、だから、ときおりこの原点自体に不安をもつことがあったのだ。しかし結局、その骨組みを根本的に変えるような事態にはぶつからなかった。
その後私は、いくつかのいろんな種類の設計をやってきた。その際私は、どの場合でも、いまここに書いてきたような考えかた(「体験の内容と成り得る」場所たり得ること)に基づいて、あるいは基づこうとする態度で、やってきたつもりではある。
けれどもときおり、怠惰になり、ことの本質を忘れ、惰性でことをすすめてきたきらいがある。いまでも多分ときおりそうやっているだろう。そして、いい気になっているとはっとするようなことにぶつかる。分っていたつもりのこと、あるいは考えたつもりのことが、実は少しも分っていなかった、考えられてもいなかった、問題のまま放ってあった。そういうことに気づかされる破目になる。先の「かくれんばのできない学校」の例もそうだし、この通信の一号で書いた「自然発生的集落」についての質問もそうだった。考えられる限り考えた上なら未だ救われるが、そうでないとき、それは救い難い。自分の考えは何だったのか、何を考えてきたのか、ほんとに考えてきたのか、そう思うと情けなくなるときがある。そういうとき、私は無性に七戸へ戻りたくなる、行きたくなるようだ。何を考えていたのか、考えようとしていたのか、あの「初めて」のとき以上に深く考えられるようになっているのか、「初めて」のとき以上に充実感を覚えて考えたことがあるのか、要するに自分を見つめに、簡単に言えば、頭を冷やしに行きたくなる。どうもそのようだ。
私はほぼ五年に一度、七戸を訪れている。それは、落成式の日に思ったこと、建物がどうなってゆくか見続けることの実行ではあった。しかし、むしろそれは、このことの裏返しとして、実は私は、私自身を見に行っていたのではないか、ふとそんな気がしてきてならない。七戸を訪ねよう、そう思いたつのに先だって、必らずふりだしに戻って考えなおしてみたい。みなければならないと思う何かが私の内にあったのではなかろうか(四年前のときは、「かくれんぼ」の一件のあとだ)。
今年、私はやはり、無性に七戸に行きたくなっていた。どうしても夏までには行くぞ、そう春さきから思っていた。思いあたるふしがある。このところ、私はまた惰性で生きている。本質を見ようと(観念的に思っても)していない。そう指摘する人もいた。何やってんだ。自分が腹立たしかった。(そしてその一つの反省が「通信」になった)。
予定は次々とくずれ、残すは八月末だけ九月になると忙しくなる、そんなことを考えているとき、七戸町のT氏から連絡が入った。もうじき20年になる。傷んできた。全面改築という話もあるがそうはしたくない。補修でゆきたい。相談したい。そういう電話であった。
T氏は、この小学校の、言わばプロデュースを担当した、当時町の教育委員会事務局にいた人で、次回書くつもりだが、この20年近く、七戸町のいわゆる町づくりに、文字どおり身を挺してきた人の一人である。 渡りに舟とはこのこと、八月末、七戸帰りは実現した。
故郷というものは見捨てたくなるものだそうである。そして、しかし、所詮見捨てることが、いかんともし難くできないものだそうである。私にとって七戸は、そしてそこでやった「初めて」の設計は、これもいかんともしがたく、いま私は何をしているか、それを量る物指しのO点になってしまっている。これから先もまた、何度も帰ってみることになるのではなかろうか。しかし、このことに気がついたのは、極く最近のことである。「初心不可忘」と言った先達のその言葉の意味が、いま、やっとなんとなく分りかけてきたように思う。
18年後、学校はどうであったか、そしてそもそも、当時東京にいた私がなぜはるか離れた青森の七戸町へ出かけるようになったのか、その話が残ってしまった。特に後者はつまるところ、なぜ七戸町にあの風変りな学校が建つことが許されたか、あり得たか、という話であり、それは、その町の町づくりにかける情熱と、それを支える考えかたが何であったかという話に他ならない。「地方の時代」などと言われだす20年も前から、ここにしたたかな「地方」が在った、そのように私は思う。
次回はそれについて書こうと思う。
あとがき 〇毎号私は、現状に対して批判的なことばを並べてきた。しかしその説明を詳しくせず、しても半ば抽象的であった。いつか具体的に説明する必要があると思っていたし、それを求める意見もきこえてきた。 〇七戸から戻ってきて、七戸の町の話でそれを試みてみようと思った。いままでの話の補足になれば幸いである。 〇ことの性質上、私がどう思ったかという言わば私的体験を語らねばならず、読む方もあまり気分のよいことではないのだが、しかしことの本質を理解しあう為には、ある状況を共有することから始めざるを得ず、止むを得ずそういう形になった。 〇しかし、このある状況を共有するということぐらい難しいことはないようだ。
〇たとえば、一つの言葉に人が思いをこめた、そのこめた思いというものを分る、分ろうとする、人が少なくなってきているのではないか。これは最近、私の同僚としょっちゅう問題にしていることだ。詩が、短歌が、そして俳句が分らなくなる時が真近かに迫っている。たとえば俳句を文字どおりに英訳したらなにがなんだかわけが分らなくなるのは目に見えているが、ところが、それ的理解、それ的解釈しかできない、つまり情景が想定できない人たちが確実に増えている。従ってそれを共有できない。というよりそれ以前である。ある精神科医が、精神科医は詩が分らなければその資格がないと書いているのを読んだが、それは建築家(ひろく私たちの住む揚所づくりに関わりをもつ人)に置き換えてもそのとおりだと思う。そして、言葉においてこういう状況であるならば「もの」に対しては推して知るべしである。
〇なぜ「かくれんぼができない」のか。その説明は、実はこの数年私の宿題であった。いまこの文を書いていて、自ずとその宿題が解けたように思っている。収穫であった。
〇それぞれなりのご活躍を祈る。
1818年.10.1 下山 眞司

























