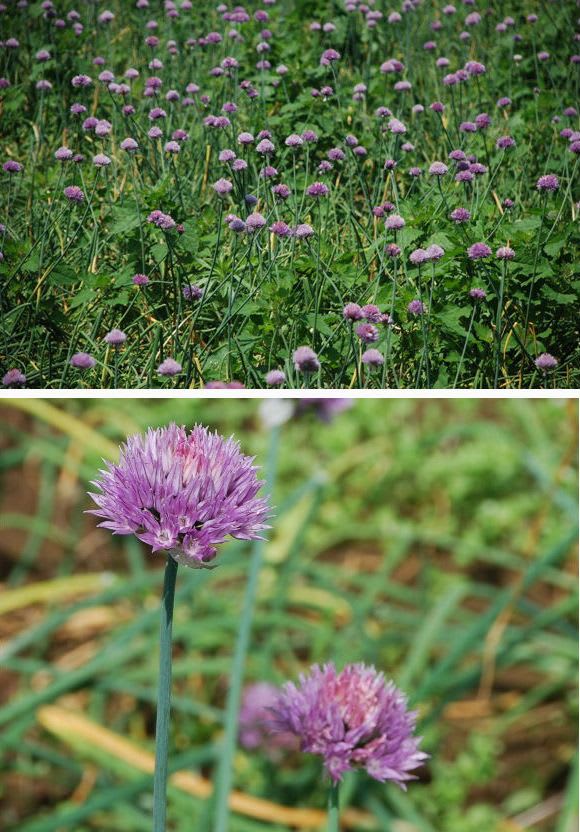8月15日になると、疎開先でのその日を思い出す。とにかく暑く、地面はからからに乾いていた。疎開前後の話は、昨年の今日、書いている(
「過渡期の体験」)。
記憶と言うのはなかなか面白い。どうでもよいような一瞬が、強烈に残っている。疎開先の8月15日の場合は、からからに乾いた地面。どういうわけかそこに落ちた水滴がつくりだした小さな窪みと土煙。
大分前に日本美術史を専門とする方々に同行させてもらって敦煌を訪ねた。8月だったと思う。まだ観光地化してない頃だったから、宿泊所も完備してなかった。
私は、かんかん照りの中、美術史の方々と別行動をとらせてもらって、近在の農村、と言っても新興の農村だが、を訪ね歩いた。ものすごく暑かったけれども、なかなか面白かった。「住まい」に対する彼我の違い、と言うより、日本で「常識」になっている「住まい」や「建物・建築」に対する考え方の「盲点」を知る機会となった(それについて書いたのが
「分解すれば、ものごとが分かるのか・・・・中国西域の住居から」である)。
延々と歩いて宿泊所に戻ったのは、たしか昼下がり。そのとき、突然のにわか雨。にわか雨と言っても、ポツポツと雨滴が落ちてきただけ。それでおしまい。それでもこの季節、珍しいことだという。なにせ年間総降雨量100mm前後という砂漠に近い場所。
雨滴が、からからに乾いた地面に落ちて、小さな窪みと土煙をあげた。そして、突然、疎開先での昭和20年8月15日の昼下がりを思い出したのである。
おそらく、日常というのは、こういうちょっとした一瞬の連続なのかもしれない。
余談だが、その日、私は、今の言葉で言えば「熱中症」にかかった。そして、中国の人たちが、常に水筒にお茶を入れて持ち歩く理由がよく分った。彼らは、水分の補給を怠らないのだ。市場に行けば、目に付くところに、かならず花模様の描かれた水筒や保温ジャーが並んでいた。