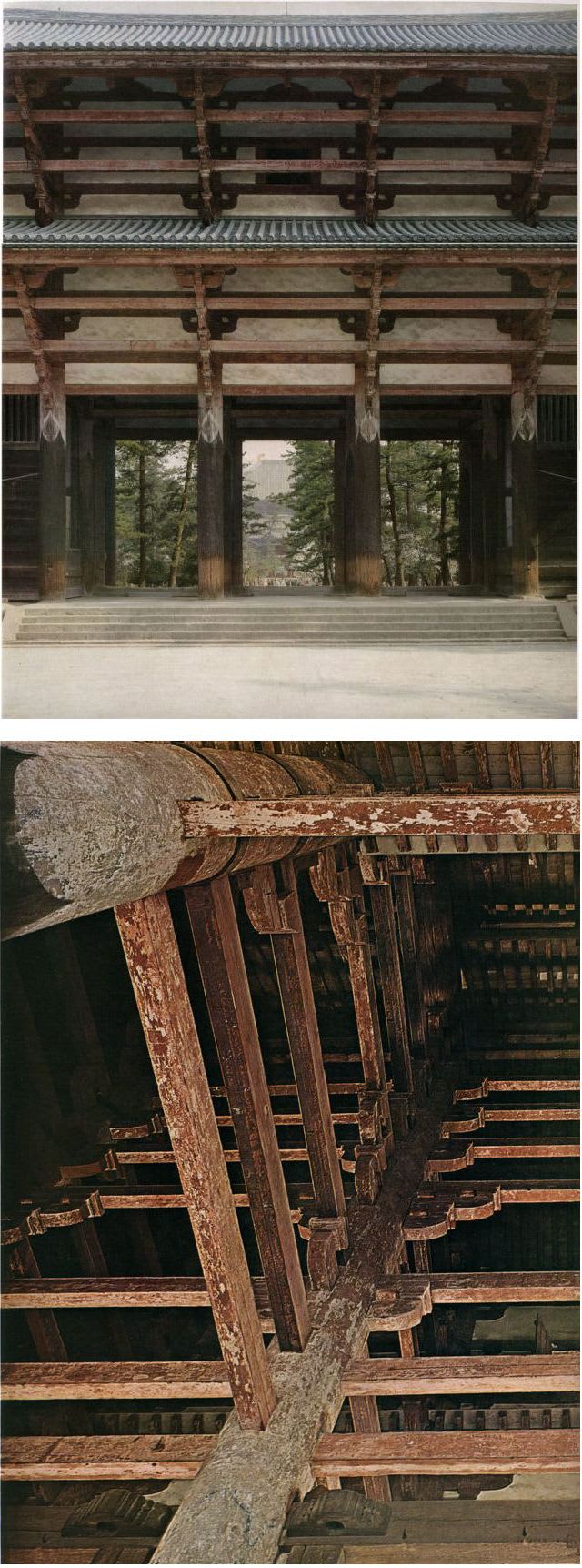[文言追加:8.36]
「会いたい」という曲で有名な沢田知加子が、「美しい国」という戦後間もない頃に書かれた詩を歌っていた。
沢田は、すべての人が、この詩、その心を知って欲しい、と思いこれをうたうのだという。
私は、その詩を、いままで知らなかった。
それは、永瀬清子(1906~1995)という方の詩。沢田がうたったのは2005年とのこと。
たしかそのころ、某国の首相が《美しい国》を掲げていなかったか?しかし、沢田の惹かれた永瀬清子の詩のなかみは、某国の元首相のとなえた《美しい国》とは、まったく異なる。
美しい国 永瀬清子 1948年(昭和23年)2月 作
はばかることなく思念(おもひ)を
私らは語ってよいのですって。
美しいものを美しいと
私らはほめてよいのですって。
失ったものへの悲しみを
心のままに涙ながしてよいのですって。
敵とよぶものはなくなりました。
醜(しう)というものも恩人でした。
私らは語りましょう語りましょう手をとりあって
そしてよい事で心をみたしましょう。
ああ長い長い凍えでした。
涙も外へは出ませんでした。
心をだんだん暖めましょう。
夕ぐれで星が一つづつみつかるやうに
感謝と云う言葉さへ
今やっとみつけました。
私をすなおにするために
貴方のやさしいほほえみが要り
貴方のためには私のが、
ああ夜ふけて空がだんだんにぎやかになるやうに
瞳はしずかにかがやきあいましょう。
よい想いで空をみたしましょう。
心のうちにきらめく星空をもちましょう。
永瀬清子は、別のところで、次のように語っている。
「・・・民主主義というのは、自分の心を自分でちゃんと知ること、それが第一で、また、それをはっきり表現できることだと思うのです。
第二には相手の心がわかること。
第三に、共に協力し進歩していくこと。
この三つが揃ってはじめて本当の民主主義なのではないかと思います。・・・」