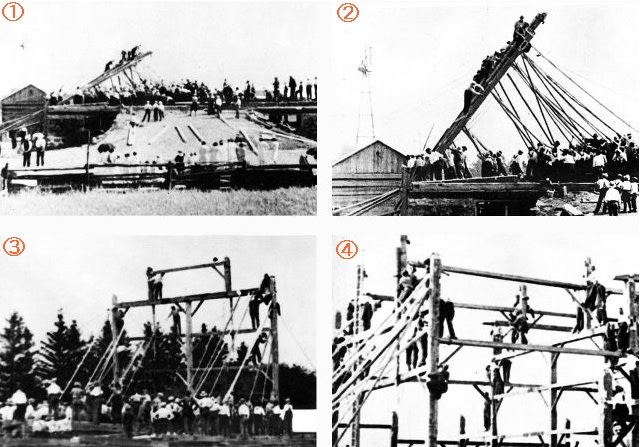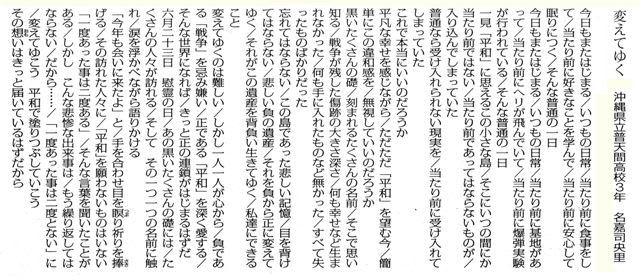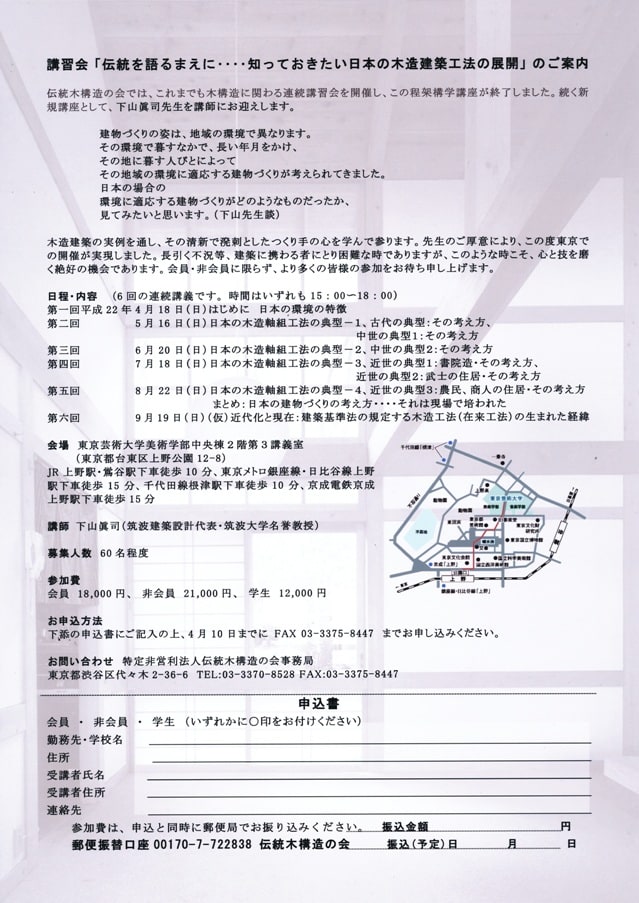CDご所望の方へ
「伝統を語るまえに」の資料を納めたCDは、明日クロネコ宅急便で発送させていただきます。
恐縮ですが、着払いとさせていただきます。ご了承ください。
******************************************************************************************
下の写真は、アメリカ・オンタリオ州での納屋(多分家畜小屋)の建て方を移したフィルムからのもの。
1918年のことです。建物の長さは134フィートあった。40メートルです。
こういう建て方があたりまえであったアメリカで、2×4工法がどのような過程で主流になっていったのか、興味が湧きます。
写真は“The Barn”(New York Graphic Society Ltd)から。
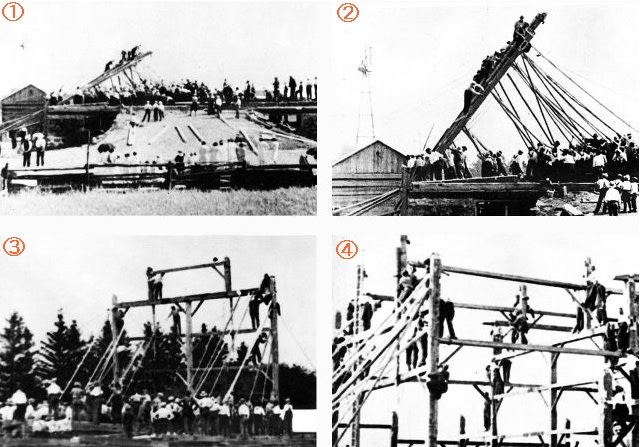
「伝統を語るまえに」の資料を納めたCDは、明日クロネコ宅急便で発送させていただきます。
恐縮ですが、着払いとさせていただきます。ご了承ください。
******************************************************************************************
下の写真は、アメリカ・オンタリオ州での納屋(多分家畜小屋)の建て方を移したフィルムからのもの。
1918年のことです。建物の長さは134フィートあった。40メートルです。
こういう建て方があたりまえであったアメリカで、2×4工法がどのような過程で主流になっていったのか、興味が湧きます。
写真は“The Barn”(New York Graphic Society Ltd)から。