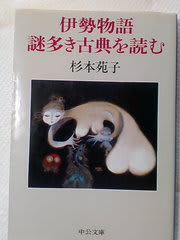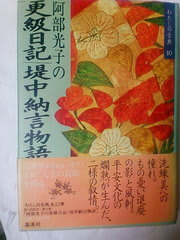今回は「伊勢物語」について解説した本を紹介します。
☆伊勢物語 謎多き古典を読む
著者=杉本苑子 発行=中央公論新社・中公文庫
本の紹介文
『伊勢物語』は在原業平の恋愛遍歴を描いた、作者不詳の歌物語である。複数と思われる作者たちは、なぜ業平を主人公に選び、どんな世界を彼に託して描こうとしたのか。物語の裏にみえかくれする、慚愧にみちた宮廷の恋物語をすかしてみて、作品成立にまつわる謎を読み解く。
目次
『伊勢物語』の、うさんくささ
軽み、そして鄙びと貧
アウトローの自覚
業平に至る血の系譜
二条ノ后と惟喬親王
物語を生んだ心理的母体
*現在では絶版のようです。興味を持たれた方、図書館か古書店を当たってみて下さい。
「伊勢物語」は、「昔 男ありけり」で始まる125編の短い歌物語集です。私は、この「伊勢物語」という古典が大好きです。なぜ好きかというと、この物語の主人公に擬せられている在原業平が好きだから、更に、彼の生きた時代に興味があるからです。そして、歌物語という物語形式が何か軽快で、読んでいてわくわくします。でも、読めば読むほどわからなくなり、ますます謎が深まっていく…、そんな不思議なところも興味をそそられます。
この、「伊勢物語 謎多き古典を読む」は、本の内容紹介文と目次から興味を引かれ、6年前に初めて読みました。ちょうど、同じ杉本苑子さんの山河寂寥 ある女官の生涯」と同じ頃に読んだのですが、「山河寂寥」の紹介でも書きましたように、その頃、家の引っ越しなどでごたごたしていて、あまり集中して読むことができませんでした。それと私の知識不足も手伝って、読み終わったあと、「伊勢物語」がますますわからなくなってしまいました。
今回、6年ぶりに再読してみたのですが、これを読んで「伊勢物語」に関する謎が解けたかどうかと尋ねられれば、残念ながらノウと答えることになりそうです。おそらく、「伊勢物語」に書かれたエピソードは史実なのか、物語がどのように成立したのか、業平とはどんな人なのかに関しては、永遠に謎のままなのかもしれません。
でも、この本に書かれている内容は6年前に比べると理解できたかなという感じがします。そこで、本の内容をかいつまんで紹介しますね。
まず冒頭の「『伊勢物語』のうさんくささ」の書き出しの部分で著者の杉本苑子さんが、『伊勢物語』はよくわからない古典である』と、私と同じことを言っていてびっくりしました。
そのあと、伊勢物語がなぜわかりにくく、うさんくさい古典であるかを述べ、その最も顕著な例として69段を紹介していました。この段は、主人公の男と伊勢の斎宮が密通する話ですが、書き加えのオンパレードとか。特に最後の、「斎宮というのは清和天皇御代の斎宮、文徳天皇皇女で惟喬親王の妹の恬子内親王である」というのは完全に後世の書き加えだそうです。つまりこの段で描かれている話はフィクションであり、しかも中国の古典を下敷きにしている話だとか。でも、真相は誰にもわからないようです。こうしてみると69段はちょっと頭が混乱してしまいそうな章段ですよね。
次の「軽み、そして鄙びと貧」と「アウトローの自覚」では、『伊勢物語』の中から著者が興味を引かれている段(東下りや筒井筒の話など)を選び出し、原文と訳を紹介しながら、『伊勢物語』の魅力や特徴を解説しています。
そしてその次の「業平に至る血の系譜」では、在原業平とはどのような人だったのかに触れ、桓武天皇→平城天皇→阿保親王と、業平の祖先たちの数奇な歴史を紹介しています。
その次の「二条ノ后と惟喬親王」では、再び伊勢物語本文に戻り、業平と関係の深かった二条ノ后藤原高子と惟喬親王が登場する章段の原文と訳を紹介し、二人の不遇の生涯にも触れています。
そして最後の「物語を生んだ心理的母体」では、再び業平やその祖先たち、特に父の阿保親王の生涯に触れ、彼らがいかに藤原氏に利用され、運命を狂わされてきたかが強調されています。
更に、「伊勢物語」のモデルがなぜ業平だったのか、著者の推論が述べられていました。つまり業平は、藤原氏が手中の玉として入内を切望していた高子と通じることによって藤原氏に挑戦した。そして、そんな業平の行為は、藤原氏に手も足も出ない廷臣たちにとっては痛快だった。そんな業平像が人々に語り伝えられていくうちに、業平は偶像化され、人々のアイドルとなり、『伊勢物語』が生まれる心理的母体が作られていったのではないか…と、著者の杉本苑子さんは述べていましたが、非常に納得がいく説だと思います。つまり、業平を偶像化した人達によって、物語の書き加えもされたのかもしれませんね。
以上、この本の内容を簡単に述べてきましたが、私のつたない説明ではすべてを伝えることはできないです…。『伊勢物語』や在原業平、平安時代前期の歴史に興味のある方はぜひ、この本を手に取って欲しいと思います。
私は、この本を再読して、『伊勢物語』の全文をもう一度読んでみたくなりましたし、在原業平や当時の歴史を調べてみたくなりました。確かに杉本さんもおっしゃっているようにわかりにくくて厄介な古典ですが、これからも私は『伊勢物語』とつき合っていきたいと思います。
☆コメントを下さる方は掲示板へお願いいたします。
☆トップページに戻る
☆伊勢物語 謎多き古典を読む
著者=杉本苑子 発行=中央公論新社・中公文庫
本の紹介文
『伊勢物語』は在原業平の恋愛遍歴を描いた、作者不詳の歌物語である。複数と思われる作者たちは、なぜ業平を主人公に選び、どんな世界を彼に託して描こうとしたのか。物語の裏にみえかくれする、慚愧にみちた宮廷の恋物語をすかしてみて、作品成立にまつわる謎を読み解く。
目次
『伊勢物語』の、うさんくささ
軽み、そして鄙びと貧
アウトローの自覚
業平に至る血の系譜
二条ノ后と惟喬親王
物語を生んだ心理的母体
*現在では絶版のようです。興味を持たれた方、図書館か古書店を当たってみて下さい。
「伊勢物語」は、「昔 男ありけり」で始まる125編の短い歌物語集です。私は、この「伊勢物語」という古典が大好きです。なぜ好きかというと、この物語の主人公に擬せられている在原業平が好きだから、更に、彼の生きた時代に興味があるからです。そして、歌物語という物語形式が何か軽快で、読んでいてわくわくします。でも、読めば読むほどわからなくなり、ますます謎が深まっていく…、そんな不思議なところも興味をそそられます。
この、「伊勢物語 謎多き古典を読む」は、本の内容紹介文と目次から興味を引かれ、6年前に初めて読みました。ちょうど、同じ杉本苑子さんの山河寂寥 ある女官の生涯」と同じ頃に読んだのですが、「山河寂寥」の紹介でも書きましたように、その頃、家の引っ越しなどでごたごたしていて、あまり集中して読むことができませんでした。それと私の知識不足も手伝って、読み終わったあと、「伊勢物語」がますますわからなくなってしまいました。
今回、6年ぶりに再読してみたのですが、これを読んで「伊勢物語」に関する謎が解けたかどうかと尋ねられれば、残念ながらノウと答えることになりそうです。おそらく、「伊勢物語」に書かれたエピソードは史実なのか、物語がどのように成立したのか、業平とはどんな人なのかに関しては、永遠に謎のままなのかもしれません。
でも、この本に書かれている内容は6年前に比べると理解できたかなという感じがします。そこで、本の内容をかいつまんで紹介しますね。
まず冒頭の「『伊勢物語』のうさんくささ」の書き出しの部分で著者の杉本苑子さんが、『伊勢物語』はよくわからない古典である』と、私と同じことを言っていてびっくりしました。
そのあと、伊勢物語がなぜわかりにくく、うさんくさい古典であるかを述べ、その最も顕著な例として69段を紹介していました。この段は、主人公の男と伊勢の斎宮が密通する話ですが、書き加えのオンパレードとか。特に最後の、「斎宮というのは清和天皇御代の斎宮、文徳天皇皇女で惟喬親王の妹の恬子内親王である」というのは完全に後世の書き加えだそうです。つまりこの段で描かれている話はフィクションであり、しかも中国の古典を下敷きにしている話だとか。でも、真相は誰にもわからないようです。こうしてみると69段はちょっと頭が混乱してしまいそうな章段ですよね。
次の「軽み、そして鄙びと貧」と「アウトローの自覚」では、『伊勢物語』の中から著者が興味を引かれている段(東下りや筒井筒の話など)を選び出し、原文と訳を紹介しながら、『伊勢物語』の魅力や特徴を解説しています。
そしてその次の「業平に至る血の系譜」では、在原業平とはどのような人だったのかに触れ、桓武天皇→平城天皇→阿保親王と、業平の祖先たちの数奇な歴史を紹介しています。
その次の「二条ノ后と惟喬親王」では、再び伊勢物語本文に戻り、業平と関係の深かった二条ノ后藤原高子と惟喬親王が登場する章段の原文と訳を紹介し、二人の不遇の生涯にも触れています。
そして最後の「物語を生んだ心理的母体」では、再び業平やその祖先たち、特に父の阿保親王の生涯に触れ、彼らがいかに藤原氏に利用され、運命を狂わされてきたかが強調されています。
更に、「伊勢物語」のモデルがなぜ業平だったのか、著者の推論が述べられていました。つまり業平は、藤原氏が手中の玉として入内を切望していた高子と通じることによって藤原氏に挑戦した。そして、そんな業平の行為は、藤原氏に手も足も出ない廷臣たちにとっては痛快だった。そんな業平像が人々に語り伝えられていくうちに、業平は偶像化され、人々のアイドルとなり、『伊勢物語』が生まれる心理的母体が作られていったのではないか…と、著者の杉本苑子さんは述べていましたが、非常に納得がいく説だと思います。つまり、業平を偶像化した人達によって、物語の書き加えもされたのかもしれませんね。
以上、この本の内容を簡単に述べてきましたが、私のつたない説明ではすべてを伝えることはできないです…。『伊勢物語』や在原業平、平安時代前期の歴史に興味のある方はぜひ、この本を手に取って欲しいと思います。
私は、この本を再読して、『伊勢物語』の全文をもう一度読んでみたくなりましたし、在原業平や当時の歴史を調べてみたくなりました。確かに杉本さんもおっしゃっているようにわかりにくくて厄介な古典ですが、これからも私は『伊勢物語』とつき合っていきたいと思います。
☆コメントを下さる方は掲示板へお願いいたします。
☆トップページに戻る