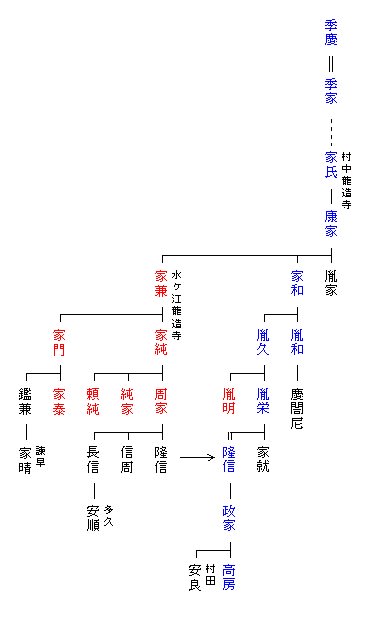二日目も朝方にちょっとだけ雨が降りましたが、雨具を引っ張り出すほどのことはありませんでした。
昼前からは晴れ空も見られましたし、ただ午後に入ったぐらいに遠くの方で雷鳴が聞こえたのでびびったのですが、何とか雷神に巡り会うこともないままの逃げ切りです。
太宰府、博多、立花と100キロを超える行程をこなせたのもお天道様の頑張りのおかげだと、感謝感激雨あられです。
まずは日本100名城の一つである大野城跡で、太宰府の近くにあります。
四王寺山のあたりが城跡となっており、飛鳥時代の朝鮮式山城とのことです。
百済を救うことを大義名分に朝鮮半島に進出をした倭でしたが、しかし白村江の戦いで唐と新羅の連合軍に敗れたとは中学生ぐらいの歴史の授業で習いました。
つまりは完全に専門外でその程度の知識しかないということで、根室のチャシ跡群と同じく日本100名城だからこそ足を運んだといったところです。
ここは百間石垣で、平均して4メートルほどの石垣が180メートルも続いていることから名付けられたそうです。
標高400メートルを超える四王寺山を囲む形で築かれた大野城ですから規模としてはかなりのものがあったようで、登るのに苦労をするわけです。
山頂というわけではありませんが駐車場などがある場所に俯瞰図が掲示をされており、先の百間石垣もしっかりと載っていました。
この他にも大石垣や小石垣、北石垣などが遺されているようでしたが、とりあえず大野城跡に行ったという手応えを手にすることが目的でしたので百間石垣で充分です。
これが中世の城であれば石にかじりついてでも巡ったのでしょうが、興味が薄かったのでここから素直に太宰府に向かったことが幸運に結びついたのはまた後の話です。

こちらは百間石垣の側を流れる四王寺川の川底から見つかった、宇美口城門の礎石です。
ただ他に発見をされた礎石は円柱なのに対してこちらは角柱であることから、研究の余地があるとは説明板からの受け売りです。
そんな貴重なものがレプリカではなく路傍の石のように置かれているのには違和感がありますが、せっかくですので写真を撮らせていただきました。
大野城跡から太宰府に向かう途中で偶然に見つけたのが、岩屋城跡と高橋紹運の墓です。
岩屋城は同じく四王寺山の中腹に築かれた城ですので実際のところは偶然でも何でもないのですが、事前の調べでは詳しい住所や場所が分からずに運を天に任せるぐらいのつもりでいたので、辛い思いをして山を登り切った甲斐がありました。
この高橋紹運の墓は脇道を逸れて数分ほど歩かなければなりませんので、看板が無かったら完全に見落としていたでしょう。
高橋紹運は大友氏の重臣である吉弘鑑理の次男で、謀反を起こした高橋氏の名跡を継いで高橋鎮種となりました。
立花宗茂の実父であり、北上する2万の島津氏を700の兵で防いだ岩屋城の戦いはあまりに有名です。
半月あまりの攻防の末に岩屋城は落城をして紹運もここで腹を切りますが、島津氏の被害も甚大で九州制圧が頓挫した理由の一つに挙げられています。
すぐ近くには岩屋城の本丸跡への登り口がありました。
難攻不落の山城のイメージがあったので登るのは大変だろうと思っていたのですが、しっかりと整備がされていましたし本丸跡までは数分です。
何があるわけではありませんが、やはりこういった史跡が遺されていることは嬉しい限りです。
本丸跡はさして広くはありません。
ざっと三十メートル四方ぐらいで、天守閣などのある近世の城郭ではありませんのでこれぐらいが一般的なのでしょう。
嗚呼壮烈岩屋城趾、とは珍しい碑ですが、それだけ激しい戦いが世に知れ渡っているからこそだと思います。
この右の写真を撮るのにはそれなりのリスクがあり、本丸跡を背に外側を向いているので張ってあるロープの内側からでは近すぎて全景が入りきらなかったために外側に出て、左手でロープを握ってできるだけ遠ざかっても広角25ミリをしてこの程度でしかありませんでした。
分かりづらいかもしれませんがロープから外側には1メートルぐらいしかなく、踏ん張っている右足は既に斜面の上でしたので、かなりがっしりとしたロープを信じて体重のほとんどを預けていたのでもし杭が外れたら崖下に転落をしていたでしょう。
その本丸跡から見た太宰府で、雨は上がっていましたが未明から降っていたことで湿気があったせいかかなりもやっていました。
左の写真の中央部を拡大して撮ったのが右の写真で、おそらくは太宰府政庁跡だろうなと思ってのことです。
これだけの標高があり、かつ登り口が狭ければ大軍で攻めても攻めきれないのは容易に想像がつきますので、一番の戦略はやはり兵糧攻めでしょう。
ただ島津氏としては豊臣秀吉が九州に向かったことは分かっていただけに、時間のかかる兵糧攻めではなく力押しをするしかなかったのだと思います。
そんなこんなで太宰府政庁跡です。
守備範囲外なので予定にはなかったのですが、岩屋城趾からの遠景を見たことでの気まぐれでしかありません。
両方の写真を見比べていただけると分かると思いますが、向きは逆になっています。
つまりは岩屋城趾からこの太宰府政庁跡に至るにはぐるっと回り込む必要があるということで、よって左の写真の背景の山が岩屋城趾ということになります。
太宰府政庁は西国の守りの要として、また外国との交渉の窓口として、往時は数千人が詰めていたと言われています。
しかしいくつかの礎石が遺されているぐらいで、ぐっとくるものはありませんでした。
寄り道ではあった太宰府政庁跡ではありましたが、実はそんなに大層なものでもありません。
すぐ隣にある太宰府展示館には大野城の日本100名城スタンプが置いてありますので、そもそも近くまでは行く予定でした。
その太宰府展示館は狙っていたわけではないただの僥倖でしかないのですが、その日から企画展としての大野城の展示がされていましたのでラッキーではあったものの、しかし朝鮮半島にある朝鮮式山城の写真がずらずらと並んでいただけで、肝心の大野城についてのものはほとんど無かったので肩すかしです。
ちなみにスタンプを押していると年配の方がいきなり話しかけてきて、日本100名城検定があるけど受けないのかなど暫しの歓談タイムに突入です。
相変わらずに地方の方はフレンドリーだなと、やはり旅は楽しいです。

太宰府展示館からほど近いところに、安養院跡があります。
安養院は観世音寺49子院の一つとされていますが、今はその面影のかけらもありません。
しかしここには開基をした少弐資頼の墓と伝えられるものがあり、その子である資能の墓とともに並んでいます。
少弐資頼は少弐氏の初代で、しかし少弐を称したのは子の資能からですので武藤資頼と書かれた資料も少なくはありません。
太宰府の次官である太宰少弐から姓を取ったのは、この武藤氏改め少弐氏が代々受け継いできたことが理由です。
資頼は西国の重鎮として鎮西奉行となり、同じく資能もその職を引き継ぎます。
しかし資能は老齢となってからの元寇の際に奮戦をしましたが子の景資とともに討ち死にをして、ここ安養院に葬られました。
写真は左が資頼、右が資能です。
太宰府では時間があれば九州国立博物館などにも行きたかったのですが、空模様が心配だったので早々に博多に戻ることにしました。
しかし雨は上がったものの曇り空だった太宰府に対して博多は青空が見えていましたので、結果的には急ぐ必要はなかったかもしれません。
そんなこんなで太宰府天満宮は素通り、よって中途半端はイヤなので香椎宮も筥崎宮も素通りをしたのですが、以前に来たときとは違って手当たり次第に何でもかんでもといったことはなくなりオプションでしかありませんでしたので、予定どおりと言えば予定どおりではあります。
そして福岡城です。
黒田長政が関ヶ原の合戦の論功行賞で中津から加増転封をされたことで築いた城で、よって時代背景からしての平城となっています。
この潮見櫓と大手門はいわゆる福岡城跡からはちょっと離れたところにあり、意識をして行かないと見落としてしまうでしょう。
潮見櫓は当時の遺構ですが大正期に移築をされたものが戦後に再移築をされましたが、しかし平成に入ってからの調査で別の櫓ではないかとの疑いが出てきたようで、よって説明板には「(伝)潮見櫓」というちょっと弱気な説明がされていました。
大手門、下之橋御門という呼び名の方が通りがよいようですが、残念なことに2000年の失火で焼失をしたために2008年の復元です。
しかしその復元方法についてはいろいろと異論があったようで、こちらもかなり微妙な言い回しの説明板となっていました。
その近くには名島門と、そして母里太兵衛邸長屋門があります。
筑前に入った黒田長政はまず小早川隆景が築いた名島城に入りましたが、しかし水軍の性格が強かった小早川氏とは違って海辺の狭隘の地にある名島城は近世の城郭としての発展の余地が無いとの判断から福岡城を築いたため、名島城はその福岡城を築く際の部材などに使われて廃城となりました。
名島門はその名島城の脇門だったもので、そのときに家臣の邸宅の門に払い下げられたものです。
また母里太兵衛邸長屋門は福島正則から名槍日本号を飲み取ったことで名高い母里友信の屋敷門で、当時の場所からここに移築をされました。
名島門は福岡市の、そして母里太兵衛邸長屋門は福岡県の文化財に指定をされています。
本丸跡に向かって最初に出くわすのが、この鴻臚館跡です。
平和台球場の改修の際に発見をされたもので、海外からの使節を迎えるためのものだと伝えられています。
鴻臚館展示館は内部に遺構を、と言いますかこの遺構を囲むように建てられており、ちょっとした別世界の雰囲気です。
福岡城むかし探訪館には福岡城の往時の模型があり、また城跡を紹介したビデオを観ることができます。
何の気なしに入って軽くスルーをするつもりが担当の方の強い薦めでそのビデオを観たのですが、これは大正解でした。
遺構が徒歩視線で紹介をされていて城内を巡るにあたっての参考になりましたので、是非とも福岡城に足を運ばれた際にはまず訪れることをお奨めします。

福岡城には多くの櫓が遺されていますが、この祈念櫓もその一つです。
本丸の東北に位置しており、東北は鬼門にあたりますのでそれを封じるために建てられました。
こちらも大正期に移築をされたものが昭和に入ってから元の場所に戻されたもので、しかし往時の写真と比べればかなり外観が変わってしまっているのは移築の際にかなりの改築がされたことが理由だろうと、そんな説明板に書いてあった悲しい物語でした。

城内には多くの井戸があり、ざっと目に付いたところでも三箇所もありました。
これは長政と言うよりは父の孝高、黒田如水の意向が働いていたのではないかとは勝手な想像です。
自身が捕虜となってしまった有岡城など多くの兵糧攻めを経験してきただけに、水の手を切られることの痛手はよく分かっていたはずです。
その答えがこの多くの井戸ではないかと、繰り返しになりますがもちろん勝手な想像でしかありません。
どうしても櫓などに目を奪われがちになりますが、もちろん福岡城にも多くの石垣がここそこに遺されています。
毎度のことながら複雑な形の石をよくぞここまで見事に積み上げるものだと感心をしてしまいますが、高い技術と多くの労働力が費やされたのでしょう。
写真は左が鉄御門跡、右が埋門跡です。
そして天守台跡と、そこから臨んだ福岡市街です。
遠くの方に見えるのはおそらくはヤフードームで、当初の計画ではビジター応援デーがあるときに訪れる予定でしたので寂しさを伴う景色です。
天守台とは言いながらも福岡城に天守閣があったかどうかは議論が分かれるところで、一度は築いたものの徳川幕府に遠慮をして破却したのではないかとの論もあるのは外様大名の悲哀なのでしょうし、しかしそういったアピールが意図的なものであれば処世術に長けていると言えなくもありません。

福岡城で国の指定文化財となっているのは、この多聞櫓とそれに連なる二の丸南隅櫓です。
多聞櫓は二層の隅櫓に挟まれた三十間ほどの平櫓で、説明板には西日本短大の学生寮として使われていたことがあったとの恐ろしい説明がありました。
16の小部屋に区切られているとのことですので、平時は蔵として使われていたのかもしれません。
多聞櫓を挟むのは左が二の丸南隅櫓、右が二の丸北隅櫓となります。
南隅櫓はとても国の指定文化財とは思えないような白壁が剥がれた状態で、再建をされた北隅櫓との差が顕著です。
あるいは南北が逆ではないかとも思ったのですが、残念ながら間違いはありませんでした。
福岡城の最後は赤坂門石垣で、土曜日の10時から17時の週一回だけの公開を狙って旅の計画を立てました。
歩道にポツンと入口があるのになかなか気がつけずに探すのに苦労をしたのですが、無事に見つけることができてよかったです。
係の人の説明によれば今は廃止となった市電の工事の際に発見をされたもので、その多くは壊されてしまいましたが一部だけを史跡として残したそうです。
海に近いために海水が浸入をするのを防ぐことが主目的だったそうで、それが理由なのか本丸の石垣などに比べると手抜きのような感じがしないでもありません。
見るからに野面積みで、なるほどと思ってしまった説明でした。

ここからは墓巡りです。
黒田氏の菩提寺は二箇所ありますが、まずはその一つである東長寺です。
両寺の宗派が違うことが二箇所に分かれている理由かもしれず、ちなみに東長寺は真言宗です。

かなり立派な五輪塔で、3メートル近い大きさです。
こちらは2代藩主の忠之の墓で、忠之は長政の長男です。
しかし黒田騒動を引き起こすなど愚昧な人物だったようで、一時は廃嫡をされそうになったことから兄弟仲も悪かったと伝えられています。
ここ東長寺には他に3代藩主の光之、8代藩主の治高の墓があります。
やはり立派な五輪塔で、花崗岩で作られています。
光之は忠之の長男で、自身の長男である綱之を廃嫡するなど第二黒田騒動を引き起こしました。
治高は京極氏の出自で7代藩主の治之の養子となりましたが、その治之も徳川氏からの養子でしたので既に如水、長政の血は絶えていたことになります。
もう一つの菩提寺は、臨済宗の崇福寺です。
一般的には黒田氏の菩提寺と言えば、この崇福寺を指すようです。
左の山門は福岡城の表御門を、右の唐門は名島城から移築をされたものです。
そして黒田氏墓所はサッカーコートが取れるぐらいの広さがありますが、これも往時に比べれば1/5ほどに縮小をされたものだそうです。
戦後に整理をされたときに墓、と言うよりは墓碑のようにも思えますが、きれいに並び替えたことで整然とした雰囲気があります。
ただあまり手入れはされていないようで草ぼうぼうの蚊がうようよには閉口をしましたが、今回はしっかりと虫よけを持っていましたのでノープロブレムでした。
入口は施錠をされていますが、記帳をすれば鍵を貸してもらえます。
境内に入る際にお寺の方に声をかける習慣がないと、隙間から覗いて諦めて帰るというパターンに陥ります。
最近はイタズラが多いのか鍵がかかっている場所が少なくはありませんので、熱意を持って当たるにしくはありません。

まずは藩祖である黒田如水の墓ですが、京都で没したことからその京都の大徳寺龍光院にあるそれが本墓で、こちらは墓碑だと思います。
自分としては黒田孝高、一般的には黒田官兵衛の名が通りやすい如水ですが、豊臣秀吉の帷幕にあって豊臣政権の成立に大きく寄与しました。
しかしその才能を忌避されて冷遇をされたとも言われており、九州平定後に早々に長政に家督を譲って隠居をします。
かなり才気走った性格だったようで、両兵衛と並び称された竹中半兵衛こと竹中重治にたしなめられたという話が伝えられています。
初代藩主の長政も京都で没しましたが、長政らしく江戸の祥雲寺に五輪塔がありますのでそちらが本墓なのでしょう。
父ほどの才は無かったものの当時としては一流の部類に入る武将で、関ヶ原の合戦における暗躍が有名です。
そして如水に次男の熊之助がいたことは、あまり知られてはいません。
朝鮮の役で軍監として渡鮮した如水の代わりに中津城の留守居役を務めましたが、父や兄を助けたい一心で密かに船出をしたものの玄界灘で遭難をして溺死をしました。
18歳とのことですので元服はしていたはずですが、その名は伝わっていません。
写真は左が長政、右が熊之助です。
その他はかなりいい加減です。
4代藩主の綱政、5代藩主の宣政、6代藩主の継高、7代藩主の治之、9代藩主の斉隆、10代藩主の斉清は、あっさりと一つの墓碑にまとめられています。
綱政は3代藩主の光之の三男で、先にご紹介をした長兄の綱之が廃嫡をされたことで家督を継ぎました。
宣政は綱政の次男で、また継高は光之の四男の長清の長男ですから、ここまでは如水、長政の男系が保たれていたことになります。
しかし治之、斉隆、斉清はいずれも徳川の出自で、これも長政の生き方を考えればらしいと言えなくもありません。
また長政は四男の高政に4万石を分知して直方藩を立藩し、その初代藩主の高政、2代藩主の之勝、4代藩主の長清が同じく一つの墓碑にまとめられています。
このあたりは人間関係がややこしいのですが、高政には子が無かったために兄で福岡藩の2代藩主である忠之の次男で甥にあたる之勝を養子に迎えて2代藩主とし、しかし之勝にも子が無かったために同じく兄で福岡藩の3代藩主である光之の三男で甥にあたる長寛を養子として3代藩主としましたが、その長寛が福岡藩に戻って綱政となり4代藩主となったために、その弟である長清が4代藩主となりました。
しかしその長清の子の継高も福岡藩を継いだために跡継ぎがいなくなり、直方藩はここで消滅をして所領は本藩に吸収をされてしまいました。
写真は左が綱政らの、右が高政らの墓碑です。

次に目指すは立花です。
立花山の山頂には立花山城があり、西の大友とも呼ばれた立花氏の居城でした。
大野城跡を自転車で巡ったことを鴻臚館展示館の係の方と話をした際に「じゃあ次は立花山城だな」と言われていたのですが、さすがにその気力も体力も勇気もありませんでした。
しかし帰ってきてから調べてみれば最初こそきつい上り坂ながらもハイキングコースが整備をされており、これまで登ってきた山城とさして変わらなかったようです。
そんな後悔も文字どおりに後の祭りですが、目的である梅岳寺には行き着けましたので気にないことにします。
それなりにアップダウンを乗り越えてきましたので、見つけたときには小さくガッツポーズです。
ここ梅岳寺は戸次鑑連、後の立花道雪の母である養孝院を埋葬したことから梅岳寺養孝院と改称し、そして道雪もここに埋葬されました。
その墓所は鍵がかかっていて中に入ることはできませんでしたが、塀が低いために写真を撮るのに不自由はありません。

立花道雪の墓です。
あまりに小さく、また土台がコンクリートで固められているように見えるのが気にはなりましたが、まさに当時ものという雰囲気でした。
道雪は大友氏の重臣としてその最盛期、また凋落期を支えた武将で、立花宗茂の養父でもあります。
大友氏の一族である戸次氏の出自ですが、立花鑑載が毛利氏の誘いに乗って謀反を起こしたことで討伐をされて道雪が名跡を継ぎました。
しかし道雪が立花氏を名乗ったことは無いらしく、便宜的に立花道雪とは書いたもののどうやら北条早雲と同じ位置づけのようです。
並んだ三基の墓の右が道雪で、左は薦野増時の、そして中央が養孝院の墓です。
薦野増時は立花氏の重臣で、鑑載から道雪、そして宗茂の三代に仕えました。
しかし宗茂にとっては老臣は小うるさい存在だったようで、関ヶ原の合戦で宗茂が改易をされたときに立花氏を離れて黒田氏に仕官をします。
そして道雪の眠る梅岳寺を守ることを自らの使命と考えたようで、それが道雪母子とともに葬られている理由なのでしょう。
左が薦野増時、右が養孝院です。

梅岳寺だけで博多に戻るのももったいないので、ちょっと遠回りをして寄り道をすることにしました。
もっとも行きはかなりのアップダウンがあったものの帰りはかなり平坦な道が続き、距離はありましたが結果的には寄り道が体には優しかったようです。
まずは浦宗勝の墓がある、その名のとおりの宗勝寺です。
浦宗勝は小早川隆景の重臣で、あるいは乃美宗勝の方が通りがよいかもしれません。
乃美氏の出自で父の賢勝が浦氏を継いだために浦宗勝が正しいのですが、父が乃美氏を名乗り続けたために宗勝も一般的には乃美宗勝のようです。
乃美水軍を率いて小早川水軍の一翼を担い、数々の戦いで活躍をしました。
ここ宗勝寺は妻の菩提を弔うために建立をしたもので、その墓は仲良く並んでいます。
勝手に右側の大きなものがそれだと思っていたのですが、左側の墓石にはしっかりと宗勝寺殿天與勝運大居士と戒名が刻まれていたために気がつくことができました。
この日の最後は泉蔵寺で、ここには大内盛見の墓があります。
盛見は大内氏の11代当主で、足利義満に反旗を翻し応永の乱を起こして滅んだ義弘の弟です。
義弘が敗死をした後は足利幕府の意向をくんだ弟の弘茂、道通を滅ぼして家督を継ぎ、しかし大友氏や少弐氏らと対立をして争った挙げ句に討ち死にをしてしまいました。
その際に家臣が戦場から首を持ち帰って葬り、そして建立をしたのが泉蔵寺です。
ちょっと分かりづらい場所にあり、お寺の方が案内をしてくれたことで助かりました。
【2012年7月 福岡の旅】
ボーダーレスな対馬
ボーダーレスな対馬 旅程篇
ボーダーレスな対馬 旅情篇
ボーダーレスな対馬 史跡巡り篇 対馬の巻
ボーダーレスな対馬 史跡巡り篇 柳川、久留米の巻
ボーダーレスな対馬 グルメ篇
ボーダーレスな対馬 スイーツ篇
ボーダーレスな対馬 おみやげ篇