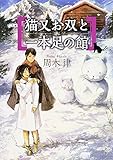蘆名氏の名将と讃えられた盛氏ではなく嫡男で酒毒により早世した盛興でもなく、盛興の未亡人を妻に迎えた二階堂氏からのかつての人質で近臣に弑逆された盛隆でもなく、盛隆の子で僅か3歳で夭折した亀王丸でもなく、佐竹氏から養子に入った実質的に戦国大名としての最後の当主となる義広の時代を描いた作品ですので珍しすぎます。
しかも豊臣秀吉に会津執権と呼ばれた金上盛備をタイトルにしているのはマイナー好きな自分としては魅力たっぷりで、ここのところは電車通勤が無くなったため読書をする時間がたまの遠出のときぐらいになりなかなか読み進めることができませんでしたが、連作短編集ですのである程度の区切りを付けられたのは助かりました。
奥羽の各氏は複雑な血縁関係のため蘆名氏と佐竹氏、そして伊達氏には薄くとも同じ血が流れており、そのため亀王丸の後継者争いに佐竹氏と伊達氏が候補に挙がり家中を二分した争いの結果、金上盛備ら佐竹派が勝利して義広が当主となるも伊達派との対立が残り、また義広に従ってきた家臣団と重臣たちとの亀裂がそれに拍車をかけます。
最後は摺上原の戦いで伊達氏に大敗して蘆名氏の滅びに繋がりますが、そこに至るまでのそれぞれの立場、思惑がメインに描かれています。
戦国末期の大きな流れからすればあまりに小さな争いではあるのですが、その中で家を思い、自らを思い、そして時代を思う姿はスケールの大小で語るものではないでしょう。
ただの兵卒が主人公になっているものもありなかなかに興味深く、しかしそれだけにもっと深掘りをして欲しかったですし肝心の金上盛備の存在感がイマイチで、また大きな鍵を握った猪苗代盛国を取り上げる編があってもよかったのではないかと、滅びに向かう一本筋のようなものが見えず散漫としていた感じがあります。
最後に小田原征伐に際しての伊達政宗を持ってきたのも中途半端でなぜに蘆名氏で押し切られなかったのか、滅び後の義広を描いてくれれば満点に近かっただけに残念至極です。
2020年6月16日 読破 ★★★★☆(4点)