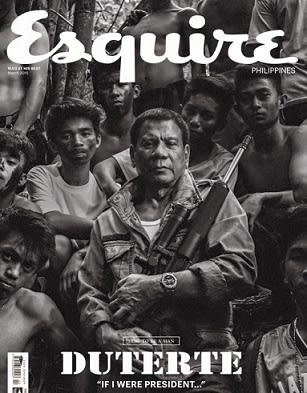(中国山西省で昨年3月、ブランコで遊ぶ子ども。両親はゴミ拾いで生計を立てている。【5月10日 ロイター】)
【内陸農村貧困層200万人超を移住させて、貧困からの脱却を】
急速な経済成長を実現した中国ですが、爆買いに走るような富裕層の一方で大きな格差も存在し、特に内陸農村部には膨大な貧困層を抱えていることは周知のところです。
そうした貧困対策として、中国政府は200万人超の大規模な移住を計画してると報じられています。
****中国は年内に200万人超の移住促す、貧困撲滅の一環で****
貧困撲滅を目指す中国は年内に、内陸部の辺ぴな地域に住む貧困層の住民200万人超を比較的発展した地域に移住させる方針だ。国務院(内閣に相当)当局者が10日に明らかにした。
国営新華社がこれまでに報じたところによると、大規模な移住計画は2020年までに1000万人を貧困から脱却させるとする目標の達成に向けた戦略の1つ。
国務院扶貧開発領導小組弁公室の劉永富主任は記者会見で、農村の住民の一部は学校や病院といったより良い公共サービスを受けられる地域に移住し、辺ぴな地域の住民の一部はより良い道路や水資源がある地域に移住すると述べた。
政府や政府系メディアによると、中国の人口約14億人のうち約5%が貧困層に当たる。大半が農村部に住んでおり、年収は2300元(362ドル)未満となっている。【5月11日 ロイター】
**********************
この計画自体は昨年末段階ですでに報じられていたものですが(http://peoplechina.xyz/migration-for-poverty-reduction/ 【2015年12月16日 「人民のつぶやき」】)、計画実行に向けて動きだした・・・ということでしょうか。
なお、【12月16日 人民のつぶやき】によれば、この移住計画にあたっては、“新しい融資メカニズムを通じて、五年で6000億人民元(約11兆2970億円)を投入”とも。
「新しい融資メカニズム」が何を指しているのかは知りません。
【必要とされる住民意思の尊重と移住後の生活保障】
広い国土に分散したインフラも未整備で就業機会ない貧困層居住地区を整備・底上げしていくよりは、“より良い公共サービスを受けられる地域に移住”するというのは、ひとつの選択でしょう。
問題は、移住に関する住民の意思が尊重されて、移住後の生活が保障された形で行われるのかどうかという点です。
中国では、地方政府が事実上強制的に住民を立ち退かせ、接収した土地を開発・売却するなどして巨額の利益を得るといったことが横行し、そうした地方役人の横暴に対する住民の暴動が全国各地で起きているとも聞きます。
今回の移住計画が、そうした発想の延長線上で行われると、膨大な悲劇と混乱を招くことにもなります。
中国では大規模公共事業でも“公益優先”の住民立ち退きがしばしば問題になります。
世界最大級の「三峡ダム」建設の事例がよく話題にされますが、今年に入っても、世界最大級の電波望遠鏡の建設に係る立ち退きが報じられています。
****宇宙人探索!?世界最大級・電波望遠鏡の建設進む 中国貴州省 周辺住民1万人立ち退き****
中国内陸部の貴州省で、世界最大級の電波望遠鏡の建設が進んでいる。地球外生命体の探索などが目的。今年9月の完成を控え、周辺住民約1万人が立ち退きを迫られることになったという。国営通信新華社が伝えた。
望遠鏡建設は、1995年にスタートした国家プロジェクト。貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州にある山中のくぼ地に建設されており、口径は500メートル。「宇宙の起源の謎」に迫る観測が期待されている。
電磁波の影響なども考慮し、移住が決まったのは周辺約5キロ圏内の住民。補償金として1人当たり1万2千元(約20万円)が支払われる。困窮する少数民族には、金額の上乗せもあるという。
中国では、長江(揚子江)流域の世界最大級の「三峡ダム」建設の際も、100万人以上が強制的に移住させられた。【2月29日 西日本】
******************
最近は中国でも物価が上昇しており、20万円の補償金というのは桁違いに少なすぎる、その後の生活はどうするのか・・・とも思われます。
前出【2015年12月16日 「人民のつぶやき」】では、国務院の大規模移住計画の情報と併せて、同時期に明らかにされた、農民工の市民化による不動産需要の拡大に関する政治局会議の方針も紹介されています。
****政治局会議:不動産の在庫解消のため、農民工の市民化を加速する****
新市民の満足をもって、住居制度改革、有効な需要の拡大、不動産市場の安定の出発点と為すことを推進する。有効な供給を拡大し、有効な投資力を保持し、発展が不足しているところを補うことに注力する。
農民工の市民化を推進するために、戸籍人口の都市化比率の引き上げを加速する。都市の居住の利便性を増強する。都市の規模の調整・制御を導く。」(財経ネット)【2015年12月16日 「人民のつぶやき」】
**********************
両方の計画・方針をつなぎ合わせると、農村部貧困層を都市部に移住させ、それによって供給過剰状態にある都市部不動産への需要を喚起する・・・・という意図ではないかという話にもなりますが、先述のように、あくまでも移住計画は住民の意思、移住後の生活保障を最重点に行われるべきものです。
【アイデンティティーと尊厳を破壊したチベット遊牧民定住化】
冒頭の内陸貧困農民の都市移住計画と同じような発想で、チベット遊牧民の都市定住化も行われていますが、チベットの場合、中央政府との軋轢が絶えないチベット民族対策という微妙な側面も加わります。
こうした、少数民族をある地域に移住させ、一定に金銭的給付は行うという施策は、アメリカ先住民でも同様のものが見られますが、生きがいの持てる新たな生活の構築、更には、アイデンティティーと尊厳の基盤となる伝統文化の維持という面で、住民の側からすればあまり成功しているようには見えません。
もっとはっきり言えば、飼い殺しのような結果にもなります。(政府側としては、それで“成功”なのかもしれませんが)
****都市移住を強いられた元チベット遊牧民らの苦悩、中国****
まだ午前中だというのに、ロブサンさんの革のカウボーイハットはくたびれ、黒いガウンは乱れ、吐く息からは酒の臭いがする。かつてチベットの高原を遊牧していた彼は今、薄いコンクリート造りの家の周りで足をふらつかせている。
ロブサンさんと妻のタシさんは数十年間、ヤクやヒツジを放牧してきた。何世紀も前から、ほとんど変わらない生活だった。──3年前、中国政府の要請を渋々受け入れ、ヤクの毛のテントから再定住先の家へ移り住むまでは。
現在夫妻は、中国四川省南西部のアバ・チベット族チャン族自治州アバ県から、曲がりくねった山道を車で1時間の場所にある再定住村に住んでいる。そこには青い屋根に灰色の壁の同じ家が、何列も立ち並んでいる。
「この町に移ってきて、何もかも変わった」と、タシさん。彼女も夫と同じ40代だが、正確な年齢は分からない。「まずお金がなくなった。そして夫は自分に見合う仕事を見つけられず、酒量がどんどん増えていった」
中国当局は、チベット自治区を都市化していけば、工業化と経済発展が促され、遊牧をしていた人たちの生活水準が上がり、環境保護にも役立つとしている。
移住に応じた人々には、中国語で「戸口」と呼ばれるいわゆる戸籍のうちでも、「城市戸口」(都市戸籍)が与えられる。これは中国国内における厳しく管理された居住許可で、これによって社会福祉サービスを利用できるようになる。政府は完全に無料か、あるいは多額の助成金を出して家や医療保険を提供し、教育も無償化する。
しかし、この政策はお仕着せの措置で、多くの元遊牧民が約束されたような豊かな生活は送っていないと、批判の声が上がっている。
オランダにあるエラスムス大学ロッテルダム社会科学大学院大学(ISS)のアンドリュー・フィッシャー准教授は、「社会が急に混乱した生まれた場合に陥りがちな、失業やアルコール依存症といったさまざまな問題が起きている」と指摘する。
■「戻りたいが手遅れ」
再定住施設でAFPの取材に応じた多くの元遊牧民は、仕事も職業訓練も不十分だと不満を漏らした。
ドルカーさん(42)は2年前に、最後まで飼っていたヤク13頭を8万5000元(現在の為替レートで約140万円)で売却したが、今になってその決断を後悔している。まだ安定した職に就けていないのだ。
ドルカーさんは「政府の職員が来て、移住しろと言われた」と当時を振り返る。「この町の物価がこんなに高いとは知らなかった」「戻りたい、だがもう手遅れだ」
都市部ですぐ手に入るのは建設作業員や清掃員の職で、賃金は低い。かつてチベット自治区で貴重な家畜を所有して裕福な暮らしを送っていた元遊牧民らの中には、こういった仕事を敬遠する人も少なくない。
■分離独立派を抑制
都市移住政策に批判的な人たちの間では、中国政府が1951年から統治しているチベットの居住者に対する監督を強化する目的もあるとの指摘もある。
AFPが取材に訪れた再定住村は、中国侵攻前のチベット東部のカム地方に当たる地域にある。ここでは地元の戦士たちが、時に米中央情報局(CIA)の支援を受けながら、1960年代後半まで中国共産党の軍事部隊と戦っていた。
チベット自治区での都市移住政策は共産党支部を各地に作ることを目的として5年前に始まった。政府の統計によると、2000年以降、チベット自治区の都市居住者は約60%も増えた。
中国共産党チベット自治区委員会のトップ、陳全国書記は、全ての再定住村は「チベット分離主義勢力の侵入を防ぎ、これと戦う」ための「とりで」にならなくてはならないと発言している。
国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ(HRW)のソフィー・リチャードソン(Sophie Richardson)中国代表は、遊牧民を都市部へ移住させる政策によって、「より監視しやすく、生活していくために国の助成への依存度がより高まる場所、つまりさらにコントロールしやすくなる地域に人々を集めている」とみている。
■環境にも悪影響
一方、環境専門家らは、この政策によって山間部の草原が保護されるどころか、雑草が増えて土壌の性質が変わってしまうと指摘する。
水道が使えるといった利便性を得る代わりに、チベットの遊牧民というアイデンティティーを喪失する。子どもたちの教育が、ほぼ全て中国語で行われていることに対する不満も多く聞かれる。
「子どもたちがチベットの歴史を知ることはないだろう、われわれチベットの伝統を理解できないだろう」と嘆くのは、6年前に再定住村に移ってきたドルジェさん。彼は今、雑用のような仕事を散発的に請け負っている。
「孫たちは、私がかつて尊敬され富裕な男だったと知ることはないだろう。彼らは貧困しか知らずに育つのだ」
【5月10日 AFP】
********************
移住によって新しい住居・生活を手にして喜んでいる者も多くいることでしょうから、総合的な判断が必要になりますが。
なお、日本でも超高齢化社会の進行とともに増加する「限界集落」への対応として、移住・再定住という選択が検討されることも多くなろうかと思われますので、他人事でもありません。