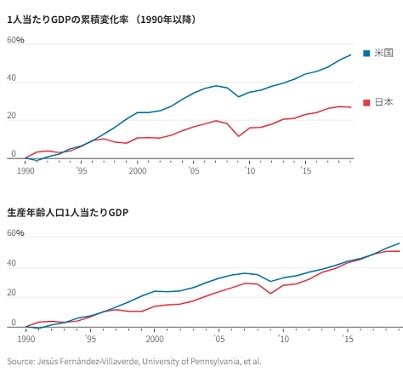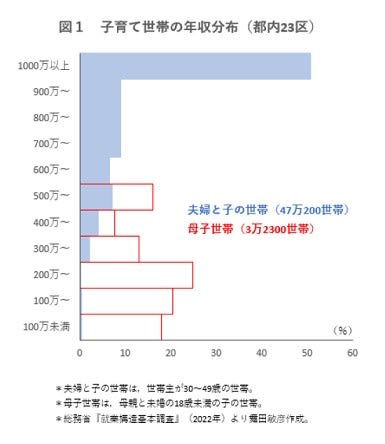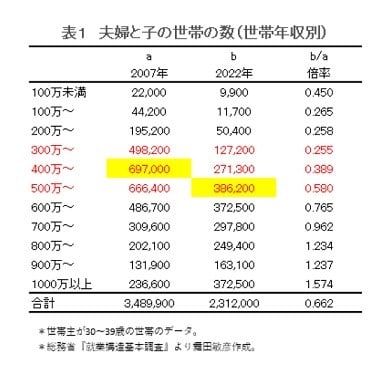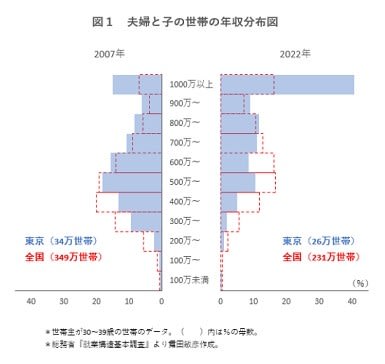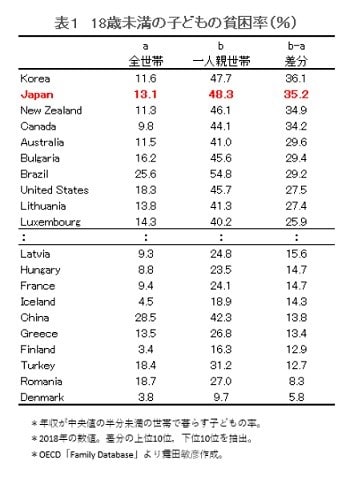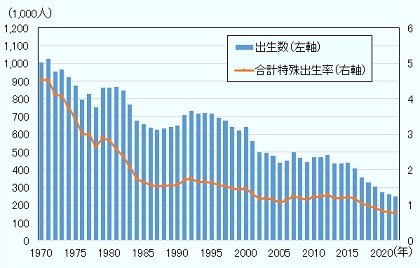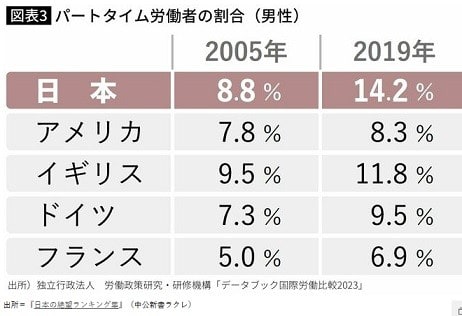(【6月29日 読売】)
【いつまでも曖昧な“コウモリ”ではいられない】
下記はアメリカと中国の対立が激化するに伴い、米中両国と“良い関係”を維持することが難しくなった韓国に関するものですが、東アジア、東南アジアなど多くの国に該当する話でしょう。
****いつまでも曖昧な“コウモリ”ではいられない…アメリカか中国か、韓国の「外交安保の座標」はどこに****
「我々も我々なりに(外交安保の座標を)定めるのが望ましい。アメリカが“3時”の方向を期待し、中国が“9時”の方向を要求するなら、韓国は基本的に“1時半”の方向で対応する国であることを認識させるべきである。すでに日本・オーストラリア・インドは“3時”から“12時”の間でそれぞれ異なる方向を取っている。してはならないのは、“3時”と“9時”の間を行ったり来たりすることだ」
李在明(イ・ジェミョン)大統領の「国益中心・実用外交」公約を設計した外交ブレーンであるウィ・ソンラク国家安保室長は、2020年に自ら出版した著書『韓国外交アップグレード提言』の中でこのように強調した。
アメリカ・中国・日本・ロシアなど主要周辺国との国際関係が複雑に絡み合う中で、韓国が独自の外交的座標を定められなければ、四方からの圧力だけを受けることになりかねないという指摘だ。
こうした主張は、韓国外交がこれまで確固たる方向性を持たず、その場しのぎでイベントに対応してきたという問題意識から出ている。代表的には「THAAD配備」や米中貿易戦争のように、主要国間で激しく対立する状況で積極的な対応をためらい、“ブレる”外交スタンスを国際社会に印象づけてしまった、ということだ。
では、現在の李在明大統領の「外交安保の座標」は、時計の何時を指しているのだろうか。
6月22日、李在明大統領がNATO(北大西洋条約機構)首脳会議への最終的な不参加を決定したことで、その座標があいまいになったとの指摘が出ている。NATO加盟32カ国という自由陣営の中核国家に対して、大統領就任初期から不明確なメッセージを発した形になったからだ。
ウィ・ソンラク国家安保室長が大統領の代わりに出席したものの、前政権では3年連続で大統領が出席していた外交的一貫性を考慮すると、加盟国の間に疑問が残る可能性もある。また、世界的に安保の重要性が増すなか、韓国の防衛産業セールス外交の好機を逃したとの惜しむ声もある。
こうした状況の中、イランとイスラエルの戦争によって国際秩序に「力の論理」が強まるほど、強国が自国の外交路線を押し付ける相反する圧力も一層激しくなるとみられる。目下、米韓関係だけでも、関税や防衛費分担といった積み残された課題についての協議や請求が控えている。
一方で、アメリカによるイラン攻撃に影響を受けた北朝鮮・中国・ロシアの結束が強まり、権威主義陣営による圧迫も本格化するとの見通しもある。
李在明大統領のNATO欠席で止まった「外交の一貫性」
6月17日(現地時間)、李大統領がカナダ・カルガリーで開催されたG7(主要7カ国)首脳会議のスケジュールをこなし、帰国した段階では、NATO首脳会議への出席が既定路線と見られていた。
前政権が3年連続で参加してきた会議を欠席すれば、外交的一貫性の観点から国際社会に誤ったメッセージを与える可能性があるからだ。しかも李在明大統領は、G7会議にて日本の石破茂首相をはじめとする9カ国の首脳と会談をこなし、実用外交の初舞台を無難に務めたことで、内外に好印象を与えるチャンスにもなっていた。
特に、G7でドナルド・トランプ米大統領が早期帰国したため、米韓首脳会談が流れたこともあり、NATO首脳会議への出席が外交的に正当化されるという声は大きかった。関税や防衛費など山積する米韓間の外交懸案を動かすためには、トランプ大統領と初対面の会談を行うことが急務だったためだ。大統領室もこうした理由で、NATO首脳会議への出席を積極的に検討していたとされる。
しかし、アメリカがイランの核施設に対する先制攻撃を行い、中東情勢の不確実性が増すと、状況は急変した。
大統領室は「国内外の複数の懸案と中東情勢の不確実性」を理由に不参加を決めたが、トランプ大統領との会談が成果を上げられるか不透明になった点も判断に大きく影響したとみられている。
トランプ大統領自身のNATO出席が不確実だったうえ、出席しても主要議題の中で通商問題の比重が下がれば、実利は乏しいと見なしたのだ。
大統領室の不参加決定をめぐって、政界では意見が分かれた。
野党「国民の力」の外交統一委員らは、「アメリカによるイラン核施設への精密攻撃とそれに伴う中東地域の緊張の高まり、そして李在明大統領のNATO首脳会議不参加決定によって、韓国は重大な外交的試練に直面している」と述べ、「今回の不参加によって、韓国がアメリカ同盟国の中で最も弱い輪と見なされ、むしろ中国やロシアからの強圧外交の対象になるのでは」と懸念を示した。
一方、与党「共に民主党」は「李在明大統領のNATO不参加は、内乱による混乱も収束しないなかで中東戦争まで重なった複合危機を考慮した苦悩の末の決定だった」とし、「韓米同盟の重要性や関税交渉など両国間の懸案の緊急性は理解しているが、NATOに行ったからといってすべてが解決するわけではないのでは」と反論した。
特に韓国・日本・オーストラリア・ニュージーランドという、NATOに招待されたインド太平洋4カ国(IP4)のうち、ニュージーランドの首脳のみが出席したという点から、「特別問題視することではない」との見方も多い。
日本の石破茂首相とオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相も、李在明大統領と同様に中東情勢の不透明さを考慮して閣僚を代理出席させた。さらに、トランプ大統領がIP4との特別会合に出席しないことを最終決定したため、仮に李大統領が出席していても、トランプ大統領と会談するのは難しかったという見方も現実的だ。
「戦略的曖昧さ」の韓国…迫る“選択の時”
ただし、これらIP4諸国は従来から韓国に比べて明確な外交方向性を持っていたという点で、単純に同列で比較するのは難しいという指摘が多い。
例えば日本は、早くから中国をけん制する日米外交戦略として「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を強く支持し、多国間安保協力体であるクアッド(QUAD)を結成するなど、新冷戦以後の明確な路線を構築してきたとの評価が支配的だ。
経済面では、中国への輸出依存を徐々に減らしつつ、アメリカとの関税問題では実利を優先し、さまざまな交渉カードを提示している。日本の外交座標は“1時半”方向、つまりアメリカ寄りの立場に位置していると言える。
オーストラリアも2021年に米英との三国安保パートナーシップ「AUKUS」を結成し、インド太平洋地域における中国の影響力拡大をけん制する基本的座標を確立している。今年4月には中国がアメリカとの関税戦争への共同対応を求めたが、オーストラリアは対中経済依存の縮小という名分を掲げ、一定の距離を置く姿勢を示した。
これに対して韓国は、政権ごとに外交路線が頻繁に変わってきたため、戦略的な曖昧さがより大きいという評価を受けている。
特に米ホワイトハウスは、李在明大統領当選直後、「米韓同盟は鉄壁のように維持される」としながらも、「中国の干渉を懸念する」と述べた。これは李在明政権が実用外交を掲げる中で提示してきた「安米経中(安保はアメリカ、経済は中国)」や「両手外交」がやや不明瞭であることを間接的に指摘した発言と解釈されている。
こうした点は、ウィ・ソンラク国家安保室長が長年懸念を表明してきた部分でもある。
彼は著書で「韓国には、周辺主要国間の対立構図の中で、韓国が進むべき道を積極的に模索しようという意識が乏しい。むしろそれを避けて現状に安住しようとする傾向が強い」とし、「米中間で困難が生じると、曖昧にふるまった。選択が避けられなくなると、その時その時の圧力の度合いに応じて便宜的に対応することが多かった」と記している。
NATO首脳会議に大統領の代理で出席したウィ・ソンラク室長自身が、その「場当たり的対応」と「戦略的曖昧さ」を最も警戒していたわけだ。
韓国の外交安保の時計において、「避けられない選択の時」は遠くないと見られる。
6月25日(現地時間)、NATO各国がトランプ大統領の圧力により、2035年までに防衛費をGDPの5%水準にまで引き上げることで合意したことで、次なる要求の矛先がアジアに向けられる可能性が高まっている。今年の韓国の防衛費はGDP比2.32%(約61兆ウォン=約6兆1000億円)水準であり、NATO並みの5%を要求された場合、年間約130兆ウォン(約13兆円)規模の国防支出が必要となる。
ジョセフ・ユン駐韓米大使代行は6月24日のあるセミナーで、防衛費分担特別協定(SMA)に関連して「建設費、人件費、軍需費の3部門から成っているが、他の費用もどのように分担するか議論する必要がある」と述べた。「他の費用」が何を意味するかは明らかにされなかったが、アメリカの戦略兵器展開費用なども韓国が分担する可能性があるという観測が出ている。
また中国・ロシアなど権威主義陣営の圧力も、一層激しくなるとの見方がある。アメリカによるイラン核施設への空爆は、アメリカがいつでも地域紛争に介入しうるという警告のメッセージとも解釈されており、中国・ロシア・北朝鮮にとっては脅威として受け止められるだろう。
そしてその余波は、地政学的要衝である朝鮮半島にも直接的に及ぶ可能性がある。
実際、習近平中国国家主席は7月に開催されるBRICS首脳会議に、2009年の発足以来、初めて欠席を決定した。これは最近、あからさまに親米路線を取っているインドなどに対する牽制メッセージだという見方も出ている。
中国・北朝鮮という微妙な関係国と同時に向き合わなければならない李在明政権にとって、外交的座標の設定にかかる負担はますます大きくなっている。
イスラエル・ライヒマン大学の中国・中東専門家ゲダリヤ・アフターマンは、ワシントン・ポストに、「トランプ大統領が実際に武力を用いてイランに介入したことは、アメリカが中国の台湾侵攻に対しても軍事的に対応する可能性がある、という懸念を植え付けたのではないか」と述べた。【6月28日 サーチコリア】
*****************
*****************
【「避けられない選択の時」は遠くないのは日本も韓国と同じ 軋みが目立つ最近の日米関係】
米中対立のはざまで、どちらに組するのか迷うアジア諸国は多く、韓国だけの話ではありませんし、これまでアメリカとの強固な同盟関係を大前提とされてきた日本についても、トランプ政権になってからはに日米関係の軋みが目立ちます。
上記記事の「韓国」「李在明大統領」を「日本」「石破首相」に読み替えても、そのまま通用するものが多いようにも思えます。
****米国「国防費GDP比5%に引き上げを」 韓国含むアジア同盟国に要求***
米国防総省のパーネル報道官は19日(米東部時間)、韓国を含むアジアの同盟国も国内総生産(GDP)の5%を目安とする国防費を支出しなければならないとする新たな基準を提示した。(中略)
米国は現在、北大西洋条約機構(NATO)加盟国に対しGDPの5%を国防費として支出するよう求める新たなガイドラインを設けているが、これを韓国や日本などアジアの同盟国にも一律に適用する立場を示したことになる。
(中略)パーネル氏は「中国の莫大な軍事力増強と北朝鮮の持続的な核・ミサイル開発を考慮すると、アジア太平洋の同盟国が欧州の防衛費の支出ペース・水準に合わせるため迅速に動くのは常識」と強調。米国が新たに要求する国防支出の増額が「アジア太平洋の同盟国の安全保障利益に符合する」と主張した。【6月20日 聯合ニュース】
米国は現在、北大西洋条約機構(NATO)加盟国に対しGDPの5%を国防費として支出するよう求める新たなガイドラインを設けているが、これを韓国や日本などアジアの同盟国にも一律に適用する立場を示したことになる。
(中略)パーネル氏は「中国の莫大な軍事力増強と北朝鮮の持続的な核・ミサイル開発を考慮すると、アジア太平洋の同盟国が欧州の防衛費の支出ペース・水準に合わせるため迅速に動くのは常識」と強調。米国が新たに要求する国防支出の増額が「アジア太平洋の同盟国の安全保障利益に符合する」と主張した。【6月20日 聯合ニュース】
*******************
****【日米亀裂】石破首相、安全保障会合を電撃キャンセル!米の防衛費「3.5%要求」に激怒か****
日本が米国と予定していた外務・防衛閣僚会合「2プラス2」を突如キャンセルしたと、フィナンシャル・タイムズ(FT)紙が21日(現地時間)報じた。日本は通常、米国の要求に忠実に従うことで知られている。米国が日本に国内総生産(GDP)の3.5%まで防衛費を増額するよう求めたことで、日本国内の反発が高まり、会合がキャンセルされた。
当初、米国はGDPの3%を防衛費として支出するよう要求していたが、今回これを3.5%に引き上げた。米国は北大西洋条約機構(NATO)加盟国にはGDPの5%を防衛費として支出するよう求めており、韓国にも最近5%の支出を迫り始めた。
FT紙は情報筋の話として、中谷元防衛相と岩屋毅外相が7月1日に米ワシントンでマルコ・ルビオ米国務長官、ピート・ヘグセス米国防長官と安全保障会合を開催する予定だった日程をキャンセルしたと伝えた。いわゆる「2プラス2」会合のキャンセルを米国側に通知したとされている。
FT紙によると、米国防総省ナンバー3のジョン・ルード次官(政策担当)が最近、日本にGDPの3%から3.5%への防衛費支出の増額を要求し、日本政府の怒りを買ったという。日本はすでに、ドナルド・トランプ米大統領が4月から日本に相互関税を課すなど、貿易交渉で強硬姿勢を取ったことに不満を抱いていた。
ある政府の高官は、7月1日の「2プラス2」会合のキャンセルは、来月20日に予定される参議院選挙とも関連があると述べた。与党自民党の苦戦が予想される中、有権者に屈辱的な姿を見せかねないことも、会合をキャンセルした背景の一つだという。
日本専門家で元米政府高官のクリストファー・ジョンストン氏は、日本が「2プラス2」会合を「非常に重視していた」と指摘し、これは「日米同盟の強固さを示す政治的に貴重な機会」だからだと説明した。ジョンストン氏は、しかし今回の会合キャンセルを選挙後に延期したことは、日本側が日米関係の現状と展望に深刻な不満を抱いていることを示唆していると分析した。【6月23日 望月博樹氏 江南タイムズ】
********************
****同盟と「法の支配」の板挟みに イラン攻撃巡り一時苦慮―日本政府****
米国によるイラン攻撃を巡り、日本政府は一時ジレンマに陥った。数日前にイランを攻撃したイスラエルを日本政府は「強く非難」。米国にも強い姿勢で臨まなければ「ダブルスタンダード」の指摘を受ける恐れの一方、批判すれば同盟関係を損なう懸念があった。
今回は米国に一定の理解を示す見解をまとめ、何とか乗り切った日本政府だが、トランプ米政権を相手に今後も対応に苦慮する場面が増えそうだ。
石破首相「早期沈静化」訴え 米攻撃の賛否示さず
国連憲章は武力攻撃を受けた国が自衛権を行使するケースなどを除いて、武力行使を原則禁じている。イスラエルが13日にイランの核施設や軍事施設を「先制攻撃」したことを受け、日本政府は「法の支配」を重視する立場から「(イスラエルの)行動を強く非難する」と直ちに表明した。
日本政府の立場は先進7カ国(G7)の他のメンバー国と比べても厳しいものだった。中国などの威圧的な動きをかねて「力による一方的な現状変更の試み」と批判してきたことも背景にあった。
しかし、米国が22日にイラン攻撃に踏み切ると、日本政府は対応に窮することになった。米国は「集団的自衛権の行使」と主張したが、「国際法的に難しい論点がある」(外務省関係者)のは否めなかった。さりとて、国際法上の根拠に乏しいと疑問を公に呈すれば、トランプ大統領を遠ざけ、関係悪化を招く可能性もあった。
23日になってようやくひねり出したのが「イランの核兵器保有を阻止する決意を示したものと承知する」(外相談話)とのライン。支持も批判もせず、理解を示す内容だった。外務省幹部は「同盟国の米国に『国際法上の懸念がある』などとは到底言えない」と苦しさをにじませた。
石破茂首相は23日の記者会見で、攻撃の法的評価を問われ、「国際法の観点から議論があることは承知している」としつつ「わが国は直接の当事者ではない。確定的な評価は困難だ」と言葉を濁した。
トランプ氏はデンマーク領グリーンランドの領有に意欲を見せるなど、国際法を重視しているとは言い難く、日本政府は今後も「法の支配」とのはざまで頭を悩ませることになりそうだ。【6月26日 時事】
********************
一方で、関税交渉は自動車を主戦場に日米の利害が相反し、トランプ大統領は日本にとって農家保護から「敏感」な政治問題である米輸入にも不満を強めています。
****トランプ氏、日本の自動車貿易「不公平」=関税25%、通告を示唆―対米交渉の打開に暗雲***
トランプ米大統領は29日放送された米FOXニュースのインタビューで、日本との自動車貿易に関し「不公平だ」と述べ、改めて不満をあらわにした。
日本に対し「自動車には25%の関税がかかるという書簡を送ることができる」と明言した。日本は米政権が課している日本車への25%の追加関税見直しを求めて交渉を続けているが、先行きに暗雲が垂れ込めている。
トランプ氏は「日本は大量の原油を受け入れることができる。他にも多くのものを買える」と主張。対日貿易赤字の削減へ、米国製品の輸入拡大を要求した。
さらに、米国車の対日輸出が少ない一方、米国は日本車を多く輸入していると指摘。「大きな(対日貿易)赤字を抱えている。そのことを日本に説明し、彼らは理解している」と語った。
トランプ氏は各国に関税率を通知する書簡を送ると明らかにしていた。インタビューでは「わたしは書簡を送る。それで貿易交渉は終わりだ」と協議打ち切りを示唆。「(各国とは)会う必要がない」と言い切った。【6月30日 時事】
***************
****トランプ大統領「われわれのコメ受け取られない」 日本の輸入に不満「手紙を送るだけ」***
トランプ米大統領は6月30日、自身の交流サイト(SNS)への投稿で「日本はわれわれのコメを受け取らない。深刻なコメ不足なのにだ」と日本のコメ輸入を巡って不満を表明した。29日に放送された米メディアで、日本の自動車貿易が不公平だと答えたばかりで、関税交渉が本格化している日本に揺さぶりをかける狙いとみられる。
トランプ氏は投稿で日本に対し「手紙を送るだけだ」とも書き込んだ。詳細には触れていないが、自動車に関しては25%の追加関税がかかるという内容の手紙を送るとしており、日本側が重視する自動車分野で譲歩しない姿勢を改めて示した可能性がある。
トランプ氏はこれまでも「日本はコメを売ってほしくないので700%の関税を課している」との持論を展開し、日本の市場が閉鎖的だと繰り返し批判している。【7月1日 産経】
********************
米鉄鋼大手USスチールと日本製鉄のパートナーシップ承認でも紆余曲折があったことも周知のところ。
そうした最近の日米間の軋み、さらに言えば、トランプ大統領の政治姿勢への日本側の不信感もあって・・・・
****米国「信頼する」22%…読売世論調査****
読売新聞社が27~29日に実施した全国世論調査で、米国を「信頼している」との回答は、「大いに」の3%と「多少は」の19%を合わせて計22%だった。「信頼している」は、トランプ氏が大統領選で返り咲きを果たした直後に実施した昨年11月の日米共同世論調査の34%から12ポイント減少した。「信頼していない」は「あまり」46%と「全く」22%の計68%(昨年日米調査55%)。
同じ質問をした日米調査で、比較できる2000年以降「信頼している」が最低だったのは、18年の第1次トランプ政権下の30%。当時もトランプ氏が自動車など対日貿易赤字の是正を強く求めていた。
今回それも下回ったのは、トランプ政権の高関税政策だけではなく、中東情勢やロシアのウクライナ侵略に対するトランプ氏の言動なども影響しているとみられる。【6月29日 読売】
******************
日中関係も問題は多い状況ですが、上記のような国際状況を受けて、中国側には一方的に日本を刺激しないようにとの配慮も垣間見えます。中国の税関総署は6月29日、東京電力福島第一原発の処理水放出を機に禁止していた日本産水産物の輸入について、「一部を再開する」と発表しました。