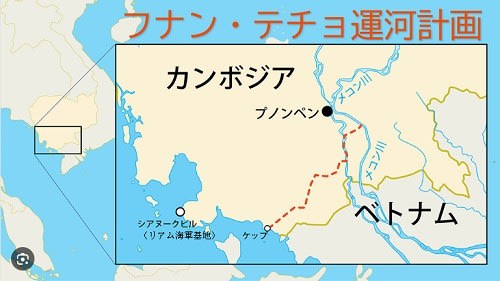(東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国の外相会議で、マレーシアのモハマド外相(中央右)と手をつなぐ中国の王毅外相(同左)=クアラルンプールで2025年7月10日【7月11日 毎日】)
【中国 ASEANに寄り添う姿勢をアピール】
東南アジア各国は、トランプ米大統領による大規模関税措置(8月1日発動予定、最大40%超)に対して、強い懸念と反発、そして緊急対応を強いられています。以下、主要国別のリアクションです。
****東南アジア各国のトランプ関税へのリアクション****
ベトナム
当初、11%程度で交渉合意と見られていたが、トランプ氏が一転して20%(再輸出品は40%)に引き上げたことが判明し、ハノイでの交渉を混乱させました。
信頼性低下を批判し、追加交渉が継続中です 。
インドネシア
農産物やエネルギーなど約190億ドル分の米輸入を提案。財務相は36%の関税に「驚きつつも前向き」と発言 。
首席交渉官がワシントンへ出向き、買いオファーや交渉努力を継続中 。
タイ
36%の関税込みの警告に直面しつつも、米財務省へ積極的に交渉を継続 。
マレーシア
関税25%(少し上昇)の見込み。アンワル首相が「これは一時的な嵐ではない」と警鐘を鳴らし、ASEAN内で協力強化を訴えました 。
中銀は利下げ対応、また交渉継続の姿勢を示しています 。
カンボジア
ガーメント・靴などに対する関税が36%→減少した模様で、一部産業にとって救いになっています 。
ミャンマー
40%の新関税警告書に対し、政権トップが「米国からの初の公式接触」と歓迎し、支持を表明。制裁緩和や関税引き下げを条件に尋常ならざる外交姿勢を見せています 。【ChatGPT】
********************
この東南アジア諸国の混乱・戸惑い・反発を利用して、寄り添うソフトな姿勢をアピールして好感度上昇・取り込みを狙うのが中国。
****トランプ関税は“好都合” ASEANに寄り添う中国の思惑****
トランプ米大統領が東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国などに対する新たな関税率を発表し、域内で動揺が広がる中、中国は「取り込み」の好機と見てASEANへの働きかけを強めている。
マレーシアの首都クアラルンプールで8日から開かれ、11日に閉幕したASEANの一連の外相会議で、中国の王毅外相兼共産党政治局員は米国の関税政策を繰り返し強く批判し、ASEAN各国に寄り添う姿勢を見せた。
「王毅だ!」。10日午前、中国とASEANの外相会議が行われる会議室前。会場入りするマレーシアのモハマド外相を報道陣が撮影していたところ、突如王氏が後方から現れ、報道陣から驚きの声が上がった。
国際会議では、主催国が招待国を出迎えるのが通例だ。しかし王氏はこの日、モハマド氏が来る前に会場入りしたうえで、カメラの前で手を上げて主催者を歓迎。満面の笑みを浮かべて親密さをアピールした。
さらに同日行われたモハマド氏との会談で王氏は、「米国は紙一枚をASEAN各国に送りつけ高関税を徴収しようとしている。典型的で一方的ないじめ行為だ。中国は自国のためだけではなく、ASEAN各国との共同利益を守るためにも立ち上がって抵抗する」と、米国を激しく非難してみせた。
米国と対立しながら経済を維持する必要がある中国にとって、ASEANとの良好な関係は不可欠だ。東南アジアに工場を移転したり、東南アジア向けの輸出品を多くしたりすれば、米国の高関税政策による打撃を緩和できるともみている。
中国税関総署によると、2025年1~5月、中国の対ASEAN輸出入額は3兆200億元(約60兆4000億円)に上り、前年同期比で9・1%増加した。トランプ政権は中国製品がASEAN各国を迂回(うかい)して米国に輸出されることを警戒している。
また中国は、フィリピンやベトナム、マレーシアなどと南シナ海の領有権を巡って対立を抱える。この問題への米国の介入をけん制するためには、トランプ政権の高関税政策は中国にとって「好都合」な面もあった。
王氏は今回、南シナ海を巡る問題について表面上は強硬な主張を控えた。10日のASEANとの会議では、南シナ海について「地域諸国の共通の故郷であり、大国同士の駆け引きの『闘技場』ではない」と指摘し、ASEAN側と「南シナ海行動規範(COC)」の協議を進めていく考えを示した。南シナ海問題で中国と激しく対立するフィリピンのラザロ外相と会場で握手する場面もあった。
一方、米国のルビオ国務長官もASEAN外相との会合で、「インド太平洋地域は米国の外交政策の中心だ」と述べ、高関税政策にかかわらず、米国はASEANを重視していると訴えた。
また南シナ海問題でのフィリピンなどとの連携も強調。日米比外相会談が終了した10日夜、報道陣の取材に応じたルビオ氏は「我々は日本、フィリピンと良好な関係を築いており、海上での安全保障や領土の一体性について緊密に協力している。今後もパートナーシップを強化しつづける」と語った。
一連の会議を終え、ASEAN外相会議は11日、トランプ政権の関税政策を念頭に「世界的な貿易摩擦や国際経済情勢の不確実性の高まり、特に関税に関する一方的な行動」に懸念を表明する共同声明を発表した。
中国とASEANの関係について青山瑠妙・早稲田大大学院教授(現代中国外交)は「中国は、領土問題で対立しながらも関係は前進できると考えている。ASEANは米中いずれにも偏らない外交を続けるが、中国がこの域内で指導力を強化する流れは今後も続いていくだろう」と語っている。【7月11日 毎日】
*****************
アメリカは対中国を今後の外交戦略の基軸とする・・・としながらも、実際にやっていることは周辺諸国を中国の側に押しやっているだけ・・・みたいな戦略性の欠如を感じます。
【英国に続き2例目。アジアでは初めてとなったベトナムの“20%合意”・・・ベトナム指導部には“寝耳に水” 今も交渉中】
個別にみると興味深いことも。
アメリカが巨額の貿易赤字を抱えるベトナムは他国に先駆けて合意し、その後の他国の交渉において「基準」となるとされています。
****トランプ氏、ベトナムとの関税交渉で合意と発表 アジアで初****
トランプ米大統領は2日、ベトナムとの関税交渉で合意したと明らかにした。自らのソーシャルメディアに投稿した。トランプ政権が大規模関税を発動した後に合意するのは、英国に続き2例目。アジアでは初めてとなる。
トランプ政権はベトナムに対し、46%の相互関税率を課していた。トランプ氏はソーシャルメディアで、ベトナム最高指導者のトー・ラム共産党書記長と会談した上で、▽ベトナムからの全ての輸入品に対し20%の関税を課す▽ベトナムは米国からの輸入品を無関税にする――ことで合意したと公表した。
トランプ氏は「相互関税」の上乗せ分の停止期限である7月9日までに多くの国との交渉をまとめたい考えを示していた。
米商務省によると、2024年の米国の対ベトナムの貿易赤字は1235億ドル(約17・7兆円)で、中国、メキシコに次ぎ3番目に大きかった。【7月3日 毎日】
******************
しかし、この「20%関税で合意」は“ベトナムの指導部にとって寝耳に水”だったようです。
****トランプ政権20%関税、ベトナムにとって寝耳に水-税率引き下げ探る****
トランプ米大統領がベトナムからの輸入品に対して20%の関税で合意したと先週発表したことは、ベトナムの指導部にとって寝耳に水だった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。ベトナム側は関税率の引き下げを目指しているという。
非公開の交渉だとして匿名を条件に話した関係者によると、ベトナムのトー・ラム共産党書記長は2日遅くにトランプ氏と電話会談を行った直後、交渉チームに対し、引き続き関税率の引き下げに向けて取り組むよう指示した。ベトナム側はより有利な関税レンジを確保したと考えていたため、20%という数字は予想外だったという。
ベトナムは電話会談前、10-15%の関税水準を求めて交渉を進めていた。
ベトナムの国営メディアでは、今回の20%関税に関する言及はほとんどない。ブルームバーグ・ニュースが確認した地元メディア宛ての政府文書では、ベトナムと米国の間でコンセンサスがない内容や、曖昧な情報あるいは臆測に関して掲載しないよう当局が地元メディアに指示した。
ベトナム外務省にコメントを求めたが、現時点で返答はなかった。
トランプ大統領が貿易合意を発表したのは英国に次いでベトナムが2例目だった。その後、トランプ氏は8月1日から最大50%の関税を課すと通知する書簡を対象の貿易相手国に次々と出している。
トランプ氏が自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」でベトナムに関して投稿した翌日、ベトナム外務省は合意の詳細を詰めるため、米側となお調整していると説明していた。
それ以降、ベトナム指導部は公式コメントでこの問題への言及を避けており、ファム・ミン・チン首相は輸出先やサプライチェーンの分散を進め、新たな関税政策への適応を図る姿勢を強調した。
トランプ氏が今回の合意を発表してから1週間以上が経過したものの、ベトナムと米国はいずれも20%関税や迂回輸出と見なされる製品に課される40%関税について、具体的な内容や適用方法などをほとんど明らかにしていない。
ホワイトハウスに通常業務時間外にコメントを求めたが、すぐには回答がなかった。【7月11日 Bloomberg】
******************
ベトナム側の合意が得られていない段階で、トランプ大統領が「合意」を発表したということでしょうか?
ベトナム政府は具体的な合意文書を出しておらず、20%関税を正式に受け入れたわけではない状況で、“トー・ラム共産党書記長は2日遅くにトランプ氏と電話会談を行った直後、交渉チームに対し、引き続き関税率の引き下げに向けて取り組むよう指示した。”と、引き下げ交渉を継続しています。
この「寝耳に水」的な展開は、トランプ政権の一連の通商政策の突発性や曖昧さを象徴する事案として、大きな注目を浴びています。
同時に、ASEAN諸国にとっても米国との通商不安要因として、今後の交渉の行方が極めて重要になっています。
【ミャンマー トランプ氏からの関税通知が米国が軍政によるミャンマー統治を認めた初の事例 ミャンマー軍政は関税40%ながらもトランプ大統領に感謝】
変わったところではミャンマー。 関税40%ながらもトランプ大統領に感謝しているとか。
****ミャンマー軍政、関税40%でもトランプ氏に感謝 通知による「承認」で****
ミャンマー軍政は11日、軍政トップのミンアウンフライン国軍総司令官がドナルド・トランプ米大統領を称賛し、制裁解除を求めたと明らかにした。トランプ氏からの関税通知を受けたもので、これは米国が軍政によるミャンマー統治を認めた初の事例とみられている。
ミンアウンフライン氏は、2020年米大統領選が「盗まれた」とするトランプ氏の虚偽の主張を支持するとともに、紛争で荒廃したミャンマーについて独立報道を行う報道機関への資金提供を停止したことに感謝の意を表した。
国軍は2021年、クーデターを実行しアウンサンスーチー氏の民主政権を転覆した。以来、ミャンマーは内戦状態にある。
米国務省は、ミャンマー国民を「暴力とテロを用いて抑圧し」「彼らが自らの指導者を自由に選ぶ権利を否定した」として、ミンアウンフライン氏らに制裁を科した。
米国は軍政と正式な外交交渉を持っていないが、トランプ氏は7日、ミンアウンフライン氏宛てに書簡を送り、ミャンマーからの輸入品に対して8月1日から40%の関税を課すと通告した。
シンクタンク「国際危機グループ」のリチャード・ホーシー氏はAFPの取材に対し、「米国がミンアウンフライン氏と軍政を認める兆候を公にしたのは、今回が初めてだ」と述べた。
それ以前の非公式なやり取りは「当然ながら、トランプ氏からのものではないことはほぼ確実だ」と語った。
ミンアウンフライン氏はこの機を逃さず、軍政の情報チームが11日、ビルマ語と英語で公開した複数ページに及ぶ書簡で返答。
トランプ氏の書簡に「心からの感謝」を表明するとともに、トランプ氏の「米国を繁栄に導く強力なリーダーシップ」を称賛した。
また、国軍による権力掌握の正当化も試み、「トランプ氏が2020年米大統領選で直面した困難と同様、ミャンマーでも大規模な選挙不正などの重大な不正行為が起きた」と述べた。
自由なメディアのない国々にニュースを届けることを使命として米国によって設立されたボイス・オブ・アメリカとラジオ・フリー・アジアは、トランプ政権による資金提供停止を受けて、ビルマ語放送を停止した。
ミンアウンフライン氏は、こうしたトランプ氏の措置に「心から感謝する」と述べた。
軍政は、経済と軍事において、同盟国である中国とロシアからの支援への依存を強めている。
ミンアウンフライン氏はトランプ氏に対し、「ミャンマーに対する経済制裁の緩和と解除について再検討」を求めるとともに、関税率についても10〜20%に引き下げるよう要求。
トランプ氏が「世界一の市場である米国の特別な経済に引き続き参加するという心強い招待」をしてくれたことにも感謝した。
トランプ氏の懲罰的関税通知を受け、来月の発動を前に多くの国が米国と土壇場での合意締結に追われている。 【7月12日 AFP】
*********************
“トランプ氏からの関税通知を受けたもので、これは米国が軍政によるミャンマー統治を認めた初の事例”
外交的にこれが的確な選択だったのか・・・それともトランプ政権側は、ミャンマー軍政のリアクションを見越して敢えてそうした対応をとったのか?