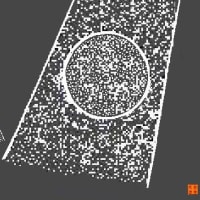代役アンドロイド 水本爽涼
(第55回)
『うん!』
彼女? は保に従順である。全てがそのようにプログラムされているからだ。保は自動補足機のプログラムが入ったフラッシュメモリーをパソコンに差し込んだ。受け持ちパーツの最終チェックだ。教授と後藤はローラー部を点検始動している。すでに仕上げて新聞を読んでいる但馬は、時折り優越感を覚えながら、三人を見回す。
『あのう…、あなたは何もしなくて、いいんですか?』
沙耶の素朴な質問が但馬を直撃した。
「えっ!? ああ、僕ですか。私はもう仕上がってるんで、いいんですよ」
但馬は予想外の質問に明らかに動揺していて、僕と私を併用した。
『そんなもんなんですか…。手助けとかは、されないんですね?』
人間の感性なら少し嫌味っぽい沙耶の言葉だが、アンドロイドの沙耶にとっては、正当な質問をした・・という機能判断で、集積データを得るための通常発言の範囲と捉えられていた。
「ええ、まあ…」
ぎこちなく、怪訝な表情を浮かべて但馬が沙耶を見た。保はその会話を聞き、少し緊張した。これ以上、荒げないで欲しい…と願う心もあった。なおも質問を続けるようなら、ふたたび釘を刺さねばならない。釘を刺すということは、サッカーでいうイエローカードではないが、台風の注意報ぐらいのところだった。警報まではいかないのだ。
最新の画像[もっと見る]












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)