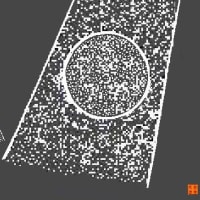堤防の土手道を小さく移動する物があった。谷岡が目を凝(こ)らすと、それは、一人の子供が懸命に自転車のペダルを漕(こ)ぐ姿だった。一瞬、谷岡は、そんなはずはない…と、目頭(めがしら)を擦(こす)った。だが、その子は疑うべくもなく、遠い自分の姿だった。いや、そんな馬鹿なことはない…と、もう一度、谷岡は子供の姿を凝視(ぎょうし)した。やはり、その子は遠い幼(おさな)い頃の自分だった。ふと、谷岡にその頃の記憶が甦(よみがえ)った。確かに、この光景に似た記憶が谷岡にはあった。
季節は丁度、青葉が芽吹く今の時節だった。そのとき俺は…と、谷岡は記憶を辿(たど)った。そうだ…、母ちゃんが倒れたと小野先生に言われたんだ。俺は学校を早退し、病院へ向かっていた。この堤防の道だった…。徐々(じょじょ)に谷岡の追憶は鮮明になっていった。あのとき…、そうだった。あと五分、早いとね…と、医師の富沢は言ったのだ。両眼を閉ざした母の顔が幼い谷岡の目に焼きついていた。それが今、甦ったのだった。
陽炎(かげろう)で堤防が揺らいで見えた。その中を幼い谷岡は、懸命にペダルを漕いでいた。見えるはずがない幻(まぼろし)の姿を、谷岡は今、見ていた。谷岡は、思わず叫んでいた。
「頑張れ~!」
一瞬、ペダルを漕ぐ子供の谷岡が谷岡を見た。いや、谷岡にはそう思えた。そして、谷岡の意識はゆらゆらと陽炎のように遠退(とおの)いた。目を開けたとき、辺りにはすでに夕闇が迫っていた。谷岡は堤防の草叢(くさむら)で眠っていたのだった。不思議なことに、違う記憶が谷岡に甦った。谷岡は、亡くなる前の母に会えたのだった。母は、二コリと幼い谷岡を見て笑っていた。
THE END












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)