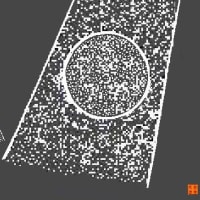残月剣 -秘抄- 水本爽涼
《旅立ち》第六回
父が座る前栽(せんざい)の廊下が、朝の陽を浴びて黒艶を浮き立たせ、輝いていた。常松は、父の隣へ、ゆったりと腰を下ろした。手に持った竹刀を地に立てて杖がわりにし、荒い息とまでは乱れていない吐息を整えた。傍(かたわ)らに座る倅(せがれ)へ、父は静かに語り始めた。
「お前は、云わずと知れた三男坊だ。孰(いず)れは、この秋月の家を出て行かねばならん。それは、源五郎だとて同じだが、これだけは肝に銘じておくのだぞ。幸い、そなたは剣の腕が立つ故、どこぞの道場の内弟子にと…儂(わし)も考えておったのだが…。まあ、十年ほどは先の話じゃが…」
と、尻切れ蜻蛉に言葉を濁して、清志郎は軽く笑った。父として、清志郎は精一杯の助言をした積もりであった。
「父上は私を買い被られているのではないのですか? 私は、兄上の竹刀を受け返すのが精一杯なのです。とても腕が立つなどとは…」
「ははは…。そう謙遜せずともよい。そなたの剣には才が見て取れる。父が申すのだから、間違いあるまいが。如何じゃ?」












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)