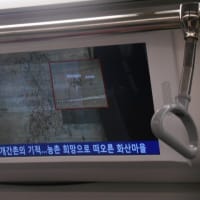娘が図書館から借りてきた「百人一首 人物大辞典」という本を手に取ってみた。百人一首のそれぞれの歌の意味と、背景となった歌人の人生を、美しいイラストとともに解説した本だ。昔から正月などによくやっており耳に馴染んだ百人一首であるが、それぞれの歌の意味や背景を知るのは初めてだった。子ども向けの本とされているが、大人でも十分以上に勉強になる良書だ。
こうして歌の意味を知ると、百人一首には本当に美しい恋を表現したものが多いと分かる。千年以上も昔の日本で、これほど美しく恋心を表現した歌(短い詩といえる)が、これほどたくさん存在したのだ。今さらになって気づいたが、これは本当にすごいことではないか。百人一首は、日本が世界に誇るべき文化遺産だ。
同じ時代(千年以上も前)の外国では、これほどの文化があっただろうか? 少なくともヨーロッパは、ここまで進んでいなかっただろう。中国には漢詩はあったが、恋の心情を細やかに歌ったものは少なかったのではないかと思う。
なお、私が特に気に入った歌は、藤原義孝の
君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな
(あなたのためなら惜しくなかったこの命 あなたに会えた今となっては 長くあってほしいと思う)
と、右大将道綱母の
嘆きつつ ひとりぬる夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る
(嘆きながら一人寝る夜 明けるまでの時間がいかに長いか あなたは知らないのでしょう)
である。