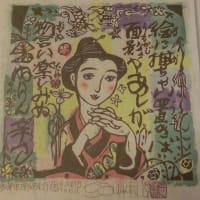昭和19年〈1944〉
◇学童疎開。
7月7日。鹿児島、沖縄両県の知事に政府命令が下された。
『奄美大島、徳之島、沖縄本島、宮古島、八重山島の5島の老幼婦女子を沖縄からは、本土へ8万人、台湾へ2万人の疎開を7月中に完了せよ』というもの。
これより先、サイパン島陥落も目前に迫った6月。政府は『一般人の疎開の促進を図るとともに、特に国民学校初等科児童の疎開を強力に推進する』ことを閣議で決議。疎開先に縁故がいない者は集団疎開。それは『保護者の申請による』としていた。
第1回疎開は8月5日。巡洋艦「長良」で無事、目的地に到着した。第2回目は8月21日夕刻、学童疎開船「対馬丸」「和浦丸」「暁空丸」の3隻が那覇港を出た。しかし、翌8月22日午後10時12分、対馬丸は鹿児島県下トカラ列島に浮かぶ悪石島沖合を航行中、米海軍の潜水艦に撃沈され、1700人の疎開者が海底に沈み、生存者は59人だけだった。この対馬丸事件で疎開業務は一時中止をみるが、10月10日の那覇空襲により情勢は一変。昭和20年までに九州、台湾へ8万人を疎開させた。学童疎開地及び員数は次の通り。
⊿宮崎県=学童2643人。関係者477人。計3120人。
⊿熊本県=学童341人。関係者48人。計389人。
⊿台湾=宮古島、八重山島の学童が疎開しているが、実数は定かでない。

写真提供:対馬丸記念館
※昭和19年。
◇10・10空襲。
米軍司令官マーク・A・ミッチャー中将率いる大型航空母艦7隻を含む85隻からなる米58機動部隊から艦載機グラマンが沖縄諸島、宮古島、八重山島、大東島などを攻撃。全県下での死者約600人、負傷者約9000人を出した。沖縄本島が主要目標にされ、5回にわたって約1時間ごとの空襲が繰り返された。特に那覇市の中心街は、まるまる2日間燃え続けて、市の90%が廃墟と化した。那覇市だけで死者255人、負傷者358人。これは沖縄全体の死傷者50%を占める多大な被害。空襲が途絶えたこの日の夕刻から那覇には、北部方面への避難命令が出され、市民は夜を徹して避難行についた。
因みにその日私は、那覇市山下町の生家にいた。年齢は6歳に満たなかった。荷馬車に最低限の衣類、食料を積み、祖父母を乗せ、少年は父親の手にしがみついて那覇を脱出。恩納村山田に向かった。そこにいたのも数日、すぐに恩納岳、石川岳を東に横断した後、現在の金武町の山中に潜んでいるところを捕虜にされた。
※【官選知事時代】
◆島田叡[しまだ あきら]明治34年~昭和20年=1901~1945=。兵庫県神戸市出身。*第22代沖縄県知事。
東京大学法学部卒業。昭和19年〈1944〉には大阪府内務部長。サイパンは玉砕し、南方での敗戦が濃厚となった時期に島田叡は、昭和20年1月12日に沖縄県知事を発令され、1月31日に着任した。前年の10・10空襲で県庁所在地の那覇市は廃墟と化し、米軍の進攻は時間の問題とされ、しかも前任の泉守紀知事が本土出張中のまま、香川県知事に転出するという最悪の状況下での赴任だった。島田叡知事は着任するや、老幼婦女子の緊急避難と県民の食糧確保という最も困難な問題に着手。2月下旬には自ら台湾に赴き、台湾米確保の折衝を行った。
3月26日、機能困難な県庁を首里に移し、さらに米軍が上陸した4月1日からは、真和志村繁多川〈現・那覇市〉の避難壕内で県業務をした。5月、首里陥落。島田知事と県職員数名は、現在の糸満市在の大城森から伊敷の通称「轟の壕」などを転々とした。6月3日ごろ、沖縄県後方指導挺身隊や警察警備隊に解散を命じた。6月14日、島田知事との同行を切望する部下に『一般地方人として投降せよ』と同行を拒否して決別した。さらに追いつめられた島田知事は、轟の壕を出て敗走、本島南端の地・摩文仁在の軍医部隊壕に移ったとされる。そして最後は、壕を出て自決とも戦死とも言われているが、詳細は今なお不明。
※昭和20年〈1945〉。
◇学徒隊の動向。
沖縄決戦体制に突入した師範学校生をはじめとする中学校及び青年学校生は、昭和18年頃〈1943〉から日本軍各部隊に協力して陣地構築、食料運搬など戦力増強に動員された。正規の学業は停止状態。軍事教育と戦闘施設建築作業に連日、従事した。そして、すべての中等科生徒は入隊に備えて待機。女子中学校看護教育を実施。3月20日から各中学校は、軍事訓練をした生徒を中心に各部隊から入隊命令を受け、職員とともに鉄血勤皇隊、通信隊、従軍看護隊に配置された。しかし、そのほとんどが戦死している。
さて、今号で明治から敗戦までの[官選県令・知事]の歴代符は終わる。県令5代、知事23代に及んだが、私は勝手に同列視して加算して記してきた。その辺りは、乞う容赦、次号から戦後の[任命主席時代]に入る。
◇学童疎開。
7月7日。鹿児島、沖縄両県の知事に政府命令が下された。
『奄美大島、徳之島、沖縄本島、宮古島、八重山島の5島の老幼婦女子を沖縄からは、本土へ8万人、台湾へ2万人の疎開を7月中に完了せよ』というもの。
これより先、サイパン島陥落も目前に迫った6月。政府は『一般人の疎開の促進を図るとともに、特に国民学校初等科児童の疎開を強力に推進する』ことを閣議で決議。疎開先に縁故がいない者は集団疎開。それは『保護者の申請による』としていた。
第1回疎開は8月5日。巡洋艦「長良」で無事、目的地に到着した。第2回目は8月21日夕刻、学童疎開船「対馬丸」「和浦丸」「暁空丸」の3隻が那覇港を出た。しかし、翌8月22日午後10時12分、対馬丸は鹿児島県下トカラ列島に浮かぶ悪石島沖合を航行中、米海軍の潜水艦に撃沈され、1700人の疎開者が海底に沈み、生存者は59人だけだった。この対馬丸事件で疎開業務は一時中止をみるが、10月10日の那覇空襲により情勢は一変。昭和20年までに九州、台湾へ8万人を疎開させた。学童疎開地及び員数は次の通り。
⊿宮崎県=学童2643人。関係者477人。計3120人。
⊿熊本県=学童341人。関係者48人。計389人。
⊿台湾=宮古島、八重山島の学童が疎開しているが、実数は定かでない。

写真提供:対馬丸記念館
※昭和19年。
◇10・10空襲。
米軍司令官マーク・A・ミッチャー中将率いる大型航空母艦7隻を含む85隻からなる米58機動部隊から艦載機グラマンが沖縄諸島、宮古島、八重山島、大東島などを攻撃。全県下での死者約600人、負傷者約9000人を出した。沖縄本島が主要目標にされ、5回にわたって約1時間ごとの空襲が繰り返された。特に那覇市の中心街は、まるまる2日間燃え続けて、市の90%が廃墟と化した。那覇市だけで死者255人、負傷者358人。これは沖縄全体の死傷者50%を占める多大な被害。空襲が途絶えたこの日の夕刻から那覇には、北部方面への避難命令が出され、市民は夜を徹して避難行についた。
因みにその日私は、那覇市山下町の生家にいた。年齢は6歳に満たなかった。荷馬車に最低限の衣類、食料を積み、祖父母を乗せ、少年は父親の手にしがみついて那覇を脱出。恩納村山田に向かった。そこにいたのも数日、すぐに恩納岳、石川岳を東に横断した後、現在の金武町の山中に潜んでいるところを捕虜にされた。
※【官選知事時代】
◆島田叡[しまだ あきら]明治34年~昭和20年=1901~1945=。兵庫県神戸市出身。*第22代沖縄県知事。
東京大学法学部卒業。昭和19年〈1944〉には大阪府内務部長。サイパンは玉砕し、南方での敗戦が濃厚となった時期に島田叡は、昭和20年1月12日に沖縄県知事を発令され、1月31日に着任した。前年の10・10空襲で県庁所在地の那覇市は廃墟と化し、米軍の進攻は時間の問題とされ、しかも前任の泉守紀知事が本土出張中のまま、香川県知事に転出するという最悪の状況下での赴任だった。島田叡知事は着任するや、老幼婦女子の緊急避難と県民の食糧確保という最も困難な問題に着手。2月下旬には自ら台湾に赴き、台湾米確保の折衝を行った。
3月26日、機能困難な県庁を首里に移し、さらに米軍が上陸した4月1日からは、真和志村繁多川〈現・那覇市〉の避難壕内で県業務をした。5月、首里陥落。島田知事と県職員数名は、現在の糸満市在の大城森から伊敷の通称「轟の壕」などを転々とした。6月3日ごろ、沖縄県後方指導挺身隊や警察警備隊に解散を命じた。6月14日、島田知事との同行を切望する部下に『一般地方人として投降せよ』と同行を拒否して決別した。さらに追いつめられた島田知事は、轟の壕を出て敗走、本島南端の地・摩文仁在の軍医部隊壕に移ったとされる。そして最後は、壕を出て自決とも戦死とも言われているが、詳細は今なお不明。
※昭和20年〈1945〉。
◇学徒隊の動向。
沖縄決戦体制に突入した師範学校生をはじめとする中学校及び青年学校生は、昭和18年頃〈1943〉から日本軍各部隊に協力して陣地構築、食料運搬など戦力増強に動員された。正規の学業は停止状態。軍事教育と戦闘施設建築作業に連日、従事した。そして、すべての中等科生徒は入隊に備えて待機。女子中学校看護教育を実施。3月20日から各中学校は、軍事訓練をした生徒を中心に各部隊から入隊命令を受け、職員とともに鉄血勤皇隊、通信隊、従軍看護隊に配置された。しかし、そのほとんどが戦死している。
さて、今号で明治から敗戦までの[官選県令・知事]の歴代符は終わる。県令5代、知事23代に及んだが、私は勝手に同列視して加算して記してきた。その辺りは、乞う容赦、次号から戦後の[任命主席時代]に入る。