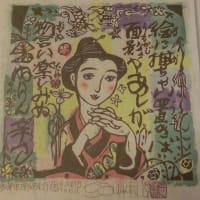日々感じたこと。共感を得たいこと。経験談、面白ばなしエトセトラ。
原稿用紙のます目を一字一字埋めていく。なめらかに筆がすすむ折りは、流行作家になったような(自己満足感)があって、誰かに読ませたくなる。
逆に思いは多々あっても、なかなか筆がすすまない折りは、イライラが昂じて、罪もない原稿用紙を破り捨てる場合がある。自分の文章力のなさを棚に上げて・・・・。
小生は職業柄、文字をあやつることが(仕事の一部)になっているが、これといった文章を仕上げたことは少ない。いつも(間に合わせ)のやっつけの(モノ書き)をしているからだろう。
もっとも小生のいう文章は(放送原稿)で、失礼ながら、放送に関わりのない方には、どうでもいい事柄を書いているに過ぎないが・・・・。けれども、それが放送の善し悪しを決める要素のひとつであってみれば、手を抜くわけにはいかないのである。
これといった文章を書いた場合、誰かに(読ませたい)と思うのは人情だろう。その手段として新聞の論壇、投稿欄は一般の人にとって重宝だろう。
八重瀬町の幸地忍さん(75歳)は、県内の新聞に意見や提言を投稿するようになってから30年余り。採用された原稿を中心に収録した3冊目の著書『新・校外の曲がり角』を自費出版した。投稿は自分を見つめ直し、視野を広げる機会になると、この数年は小・中学生の孫にも奨励。3冊目は初めて孫たちの作品も掲載して(共著)にしている。
沖縄タイムス社学芸部・粟国雄一郎記者の取材記事をもとに、そのいきさつを紹介したい。
『県退職校長会の副会長も務めた元中学校教諭・幸地忍さんの新聞投稿のきっかけは、徳島県鳴門教育大学に学んでいた40歳の折り、高校野球・甲子園大会の常連だった故・蔦文也監督の講演会だった。
思春期の高校生の精神をいかに鍛えるか、心技体の調和を説く、蔦氏の話に感銘を受け、沖縄タイムス紙に(その感動・感銘)のほどを投稿した。
以来、なにげない日常の出来ごと、少年非行、基地、米軍人の犯罪などをテーマに現役時代から臆することなく書いてきた。「輝く未来ある子どもたちへ、より良い社会を引き継ぐのは大人の債務。池に石を落とすと水面に波紋が広がっていくように、少しづつ何かが広がればと願っている」としている。
現役の教員時代も、学級・学年・学務主任、教頭、校長便りなど、立場に応じて生徒や家庭向けに文章を発信してきた。
自分の書いた原稿が新聞に掲載される時の喜びは格別だという。
投稿の不採用が続くと、さすがに「気がめいる」というが、掲載されるとあちこちから声が掛り、また元気が出る。令和元年12月5日に75歳の誕生日を迎えたばかり。地域のスポーツ大会への出席や老人会の活動などで忙しい毎日を送っているが「継続は力なり」と、また投稿への決意を新たにしている。
同署は1冊1320円。問い合わせは著者。090-9527—1003へ。
小生は幸地忍氏との面識はない。
ないけれども、自分の日常を赤裸々に吐露し、新聞投稿することは、思いのほか(勇気)が要ることである。世の中は表があれば裏もある。賛成者が居れば反対者も居る。白があれば黒もある。富者があれば貧者もある。これほどさように(両極)をもって浮世の歯車は回っているように思う。そこのところを百も承知で、原稿を書き、投稿を続ける幸地忍氏の努力と勇気に心底、共鳴して、この項を書かせてもらった。
3冊目が孫との(共著)としたところもいい。本は残る。
「祖父としての孫たちへの遺産という個人的な思いもある」とする幸地忍氏の洒脱な思いが感じられるし、また「うちの祖父は立派な人」と、リスペクトするお孫さんたちの声も聞こえてくるようだ。
小生にも6人の孫がいるが、何も遺せないこの爺を、どう評価しているのか?・・・・。恥ずかしいかやら、背中に冷たいモノが走るやら・・・・。
◇年ぬ寄てぃてぃやゐ 徒に居るな 一事どぅんすりば 為どぅなゆる
《とぅしぬ ゆてぃてぃやゐ いたじらに WUるな ちゅくとぅどぅん すりば たみどぅなゆる》
1600年代「琉球の教育振興」に尽力し、「六諭衍義」を著し、庶民向けには「琉球いろは歌」を普及した程順則・名護親方寵文が「琉球いろは歌」の(と)の部に詠んだうたである。
歌意=自分は齢を取った。もう何もできない。と諦めて徒に生きていてはならない。特別なことではなくても、いま、自分に成し得ることを誠意をもって、ちょっとでもやれば、それは自分のためにも、他人さまのためにも、何らかの役に立つ。
人生を30年区切りで考えるならば、第1期は「学びの人生」。第2期は「創造の人生」。第3期は「ゆとり奉仕の人生」。これを理想とするそうな。
小生も「何かひと事」をやりたいのだが、何をしていいやら皆目、当てがない。歳は十分持ち合わせているが、まだ第1期の「学びの人生」を歩めっ!ということか。
原稿用紙のます目を一字一字埋めていく。なめらかに筆がすすむ折りは、流行作家になったような(自己満足感)があって、誰かに読ませたくなる。
逆に思いは多々あっても、なかなか筆がすすまない折りは、イライラが昂じて、罪もない原稿用紙を破り捨てる場合がある。自分の文章力のなさを棚に上げて・・・・。
小生は職業柄、文字をあやつることが(仕事の一部)になっているが、これといった文章を仕上げたことは少ない。いつも(間に合わせ)のやっつけの(モノ書き)をしているからだろう。
もっとも小生のいう文章は(放送原稿)で、失礼ながら、放送に関わりのない方には、どうでもいい事柄を書いているに過ぎないが・・・・。けれども、それが放送の善し悪しを決める要素のひとつであってみれば、手を抜くわけにはいかないのである。
これといった文章を書いた場合、誰かに(読ませたい)と思うのは人情だろう。その手段として新聞の論壇、投稿欄は一般の人にとって重宝だろう。
八重瀬町の幸地忍さん(75歳)は、県内の新聞に意見や提言を投稿するようになってから30年余り。採用された原稿を中心に収録した3冊目の著書『新・校外の曲がり角』を自費出版した。投稿は自分を見つめ直し、視野を広げる機会になると、この数年は小・中学生の孫にも奨励。3冊目は初めて孫たちの作品も掲載して(共著)にしている。
沖縄タイムス社学芸部・粟国雄一郎記者の取材記事をもとに、そのいきさつを紹介したい。
『県退職校長会の副会長も務めた元中学校教諭・幸地忍さんの新聞投稿のきっかけは、徳島県鳴門教育大学に学んでいた40歳の折り、高校野球・甲子園大会の常連だった故・蔦文也監督の講演会だった。
思春期の高校生の精神をいかに鍛えるか、心技体の調和を説く、蔦氏の話に感銘を受け、沖縄タイムス紙に(その感動・感銘)のほどを投稿した。
以来、なにげない日常の出来ごと、少年非行、基地、米軍人の犯罪などをテーマに現役時代から臆することなく書いてきた。「輝く未来ある子どもたちへ、より良い社会を引き継ぐのは大人の債務。池に石を落とすと水面に波紋が広がっていくように、少しづつ何かが広がればと願っている」としている。
現役の教員時代も、学級・学年・学務主任、教頭、校長便りなど、立場に応じて生徒や家庭向けに文章を発信してきた。
自分の書いた原稿が新聞に掲載される時の喜びは格別だという。
投稿の不採用が続くと、さすがに「気がめいる」というが、掲載されるとあちこちから声が掛り、また元気が出る。令和元年12月5日に75歳の誕生日を迎えたばかり。地域のスポーツ大会への出席や老人会の活動などで忙しい毎日を送っているが「継続は力なり」と、また投稿への決意を新たにしている。
同署は1冊1320円。問い合わせは著者。090-9527—1003へ。
小生は幸地忍氏との面識はない。
ないけれども、自分の日常を赤裸々に吐露し、新聞投稿することは、思いのほか(勇気)が要ることである。世の中は表があれば裏もある。賛成者が居れば反対者も居る。白があれば黒もある。富者があれば貧者もある。これほどさように(両極)をもって浮世の歯車は回っているように思う。そこのところを百も承知で、原稿を書き、投稿を続ける幸地忍氏の努力と勇気に心底、共鳴して、この項を書かせてもらった。
3冊目が孫との(共著)としたところもいい。本は残る。
「祖父としての孫たちへの遺産という個人的な思いもある」とする幸地忍氏の洒脱な思いが感じられるし、また「うちの祖父は立派な人」と、リスペクトするお孫さんたちの声も聞こえてくるようだ。
小生にも6人の孫がいるが、何も遺せないこの爺を、どう評価しているのか?・・・・。恥ずかしいかやら、背中に冷たいモノが走るやら・・・・。
◇年ぬ寄てぃてぃやゐ 徒に居るな 一事どぅんすりば 為どぅなゆる
《とぅしぬ ゆてぃてぃやゐ いたじらに WUるな ちゅくとぅどぅん すりば たみどぅなゆる》
1600年代「琉球の教育振興」に尽力し、「六諭衍義」を著し、庶民向けには「琉球いろは歌」を普及した程順則・名護親方寵文が「琉球いろは歌」の(と)の部に詠んだうたである。
歌意=自分は齢を取った。もう何もできない。と諦めて徒に生きていてはならない。特別なことではなくても、いま、自分に成し得ることを誠意をもって、ちょっとでもやれば、それは自分のためにも、他人さまのためにも、何らかの役に立つ。
人生を30年区切りで考えるならば、第1期は「学びの人生」。第2期は「創造の人生」。第3期は「ゆとり奉仕の人生」。これを理想とするそうな。
小生も「何かひと事」をやりたいのだが、何をしていいやら皆目、当てがない。歳は十分持ち合わせているが、まだ第1期の「学びの人生」を歩めっ!ということか。