ブレイエンベルフWillem van Blyenburgからスピノザへの最初の書簡は書簡十八で,1664年12月12日付でドルトレヒトDordrechtから送られています。スピノザはこのときはフォールブルフVoorburgに住んでいましたが,返信となる書簡十九はスヒーダムSchiedamから出されています。スピノザが書簡を受け取ったのがフォールブルフであったのかスヒーダムであったのかは不明ですし,ブレイエンベルフがどうしてスピノザに書簡を送ることができたのかも僕には分かりません。この書簡に限らずブレイエンベルフとスピノザとの間での書簡はオランダ語で交わされ,いずれも遺稿集Opera Posthumaに掲載されました。
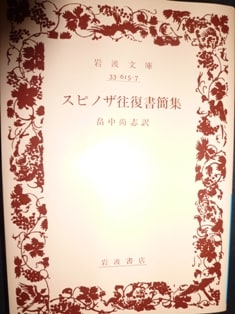
ブレイエンベルフは1663年の終りに出版された『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』を読みました。その内容についてスピノザに質問するというのがこの書簡の内容です。ブレイエンベルフは後に自説を敷衍するようになるのですが,この書簡にはそれは強く出ていません。スピノザはこの書簡を読んだときにはブレイエンベルフの意見opinioがスピノザのそれと一致していると勘違いしたわけですが,その理由のひとつはその点にあったと思われます。そしてもうひとつ,その要因がこの書簡にはみられます。
ブレイエンベルフは書簡の冒頭で自己紹介をしているのですが,そこで自身のことを,純粋な真理veritasへの愛amorに動かされ,人生において学問の中に支柱を見出そうとしている人間であるといい,さらに真理の探究にあたっては名誉gloriaや富を求めるのではなく,真理そのものを目的finisとし,その真理の果実によって心の平安を得ようとしているのだと続けています。これはスピノザが『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』で自身についていっていることとよく似ているといえるでしょう。だからスピノザはブレイエンベルフを,自分のような人間であるとみなしてしまったのです。
実際にはブレイエンベルフがいう真理というのは,聖書に書かれていることを真理とみなすという意味の真理であって,スピノザがそう理解するような真の観念idea veraの集積としての真理ではありません。スピノザがそれを理解するのは,書簡二十を受け取ってからでした。
感情の模倣affectum imitatioについて僕がいっておきたかったのはこれだけです。最後にこれと関連した事項をひとつだけ指摘しておきます。
第二部定理一三備考では,すべてのものが精神を有するといわれています。これはすでに指摘しておいたように,スピノザの哲学では精神が構造的な面から示されるのであって,機能的な側面から規定されるわけではないということと関連します。ただしそのときにいったように,スピノザは精神の機能にまったく注目していないわけではありません。なのでこの部分ではmensというラテン語を用いていないのだと思われます。そしてこの機能の差異をスピノザは明確な形で『エチカ』の中で文章として残しています。それが馬は馬らしい情欲libidoに駆られ,人間は人間らしい情欲に駆られるという形で,今回の考察では馬にも感情affectusがあるということをスピノザが認めているということを指摘した第三部定理五七備考の冒頭部分です。
「この帰結として,いわゆる非理性的動物の感情(というのは我々は精神の起源を識った以上は動物が感覚を有することを決して疑いえない)は人間の感情と,ちょうど動物の本性が人間の本性と異なるだけ異なっているということになる」。
これも感情の相違ではなく本性essentiaの相違について語っているわけですが,ここではそのことよりもいわゆる非理性的動物といわれている点に着目しましょう。スピノザはいわゆるといういい方をしていますが,このいい方は人間以外の動物には理性ratioはないといっていると解せます。理性というのはスピノザの哲学では精神の能動actio Mentisを意味しますから,動物に理性はないというのは動物は能動的ではないといっているのと同じことです。第三部定理二はあくまでも人間の身体humanum corpusと人間の精神mens humanaとの間における記述ですが,証明Demonstratioのために援用されている第二部定理六は一般的なものですから,動物にも適用されなければなりません。したがって動物の精神が能動的ではあり得ないということと動物の身体が能動的ではあり得ないということは同じ意味でなければならないのです。つまり,人間の精神は能動的であり得るが,動物の精神はそうではあり得ないという,機能の相違があるのです。
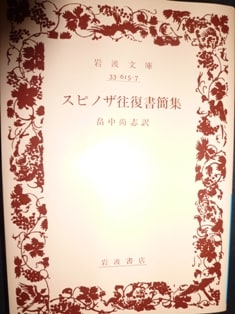
ブレイエンベルフは1663年の終りに出版された『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』を読みました。その内容についてスピノザに質問するというのがこの書簡の内容です。ブレイエンベルフは後に自説を敷衍するようになるのですが,この書簡にはそれは強く出ていません。スピノザはこの書簡を読んだときにはブレイエンベルフの意見opinioがスピノザのそれと一致していると勘違いしたわけですが,その理由のひとつはその点にあったと思われます。そしてもうひとつ,その要因がこの書簡にはみられます。
ブレイエンベルフは書簡の冒頭で自己紹介をしているのですが,そこで自身のことを,純粋な真理veritasへの愛amorに動かされ,人生において学問の中に支柱を見出そうとしている人間であるといい,さらに真理の探究にあたっては名誉gloriaや富を求めるのではなく,真理そのものを目的finisとし,その真理の果実によって心の平安を得ようとしているのだと続けています。これはスピノザが『知性改善論Tractatus de Intellectus Emendatione』で自身についていっていることとよく似ているといえるでしょう。だからスピノザはブレイエンベルフを,自分のような人間であるとみなしてしまったのです。
実際にはブレイエンベルフがいう真理というのは,聖書に書かれていることを真理とみなすという意味の真理であって,スピノザがそう理解するような真の観念idea veraの集積としての真理ではありません。スピノザがそれを理解するのは,書簡二十を受け取ってからでした。
感情の模倣affectum imitatioについて僕がいっておきたかったのはこれだけです。最後にこれと関連した事項をひとつだけ指摘しておきます。
第二部定理一三備考では,すべてのものが精神を有するといわれています。これはすでに指摘しておいたように,スピノザの哲学では精神が構造的な面から示されるのであって,機能的な側面から規定されるわけではないということと関連します。ただしそのときにいったように,スピノザは精神の機能にまったく注目していないわけではありません。なのでこの部分ではmensというラテン語を用いていないのだと思われます。そしてこの機能の差異をスピノザは明確な形で『エチカ』の中で文章として残しています。それが馬は馬らしい情欲libidoに駆られ,人間は人間らしい情欲に駆られるという形で,今回の考察では馬にも感情affectusがあるということをスピノザが認めているということを指摘した第三部定理五七備考の冒頭部分です。
「この帰結として,いわゆる非理性的動物の感情(というのは我々は精神の起源を識った以上は動物が感覚を有することを決して疑いえない)は人間の感情と,ちょうど動物の本性が人間の本性と異なるだけ異なっているということになる」。
これも感情の相違ではなく本性essentiaの相違について語っているわけですが,ここではそのことよりもいわゆる非理性的動物といわれている点に着目しましょう。スピノザはいわゆるといういい方をしていますが,このいい方は人間以外の動物には理性ratioはないといっていると解せます。理性というのはスピノザの哲学では精神の能動actio Mentisを意味しますから,動物に理性はないというのは動物は能動的ではないといっているのと同じことです。第三部定理二はあくまでも人間の身体humanum corpusと人間の精神mens humanaとの間における記述ですが,証明Demonstratioのために援用されている第二部定理六は一般的なものですから,動物にも適用されなければなりません。したがって動物の精神が能動的ではあり得ないということと動物の身体が能動的ではあり得ないということは同じ意味でなければならないのです。つまり,人間の精神は能動的であり得るが,動物の精神はそうではあり得ないという,機能の相違があるのです。










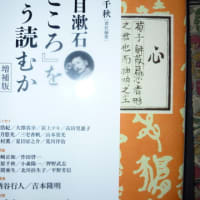

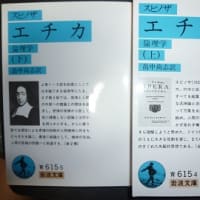

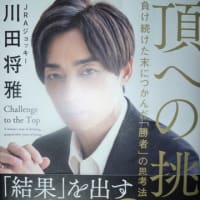



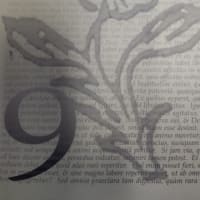





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます