書簡二十一は書簡二十への返信として書かれました。これは1665年1月16日付でドルドレヒトDordrechtのブレイエンベルフWillem van Blyenburgから出されたもので,このときはペストの流行によりスヒーダムSchiedamに避難していたスピノザに送られました。スピノザとブレイエンベルフの間のすべての書簡がそうであったように,この書簡もオランダ語で書かれ,遺稿集Opera Posthumaに掲載されました。スピノザはこの書簡をラテン語に訳しておかなかったようです。一方で原書簡はアムステルダムAmsterdamの教会の図書館に所蔵されていて,遺稿集のオランダ語版De Nagelate Schriftenに掲載されたのはその文章と同じです。なので他人の手によって訳された遺稿集のラテン語版よりも,オランダ語版に掲載されたものが正文ということになるでしょう。
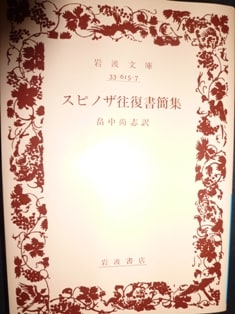
この書簡は非常に長いものなので,内容がどういったものであるのかということはここでは紹介しませんので,それを知りたいという場合は『スピノザ往復書簡集Epistolae』を読んでください。何度かいっているように,この書簡はスピノザとブレイエンベルフとの間のやり取りの中での契機となったものです。最初の書簡十八を読んだとき,スピノザはブレイエンベルフは真理veritasを獲得することだけを目的finisとしていて,その点で自身と一致すると思いました。そしてそういう立場から書簡十九を送ったのです。ところが書簡二十の内容から,スピノザはブレイエンベルフが,聖書に書かれていることが真理であると解する懐疑論者scepticiであるということを理解しました。このゆえにこの書簡の返事となる書簡二十一の冒頭で,これ以上は書簡のやり取りを続けても両者の一致点を見出すことはできないであろうという主旨のことをいったのです。
スピノザは,聖書が教えるのは真理ではなくて服従obedientiaであるということを『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』の中で示しました。これはいい換えれば聖書は真理を教えてはいないということであって,聖書をいくら研究しても真理を獲得することはできないということを意味します。スピノザはふたりの間には根本的原理そのものに相違があるといっていますが,それは具体的にはこのことです。
このことはスピノザとマイエルLodewijk Meyerとの関係にも影響するかもしれません。マイエルが著した『聖書解釈者としての哲学Philosophia S. Scripturae Interpres』は,スピノザがいうところの独断論的な視点で書かれたものであるからです。すなわちマイエルはブレイエンベルフWillem van Blyenburgのような懐疑論者scepticiであったわけではなく,デカルト主義者であるか否かという立場の相違はあったとしても,グレフィウスJohann Georg GraeviusやフェルトホイゼンLambert van Velthuysenと同様に独断論者dogmaticiであったのです。
『スピノザーナ15号』で高木久夫が指摘しているように,たぶん『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』には一種の捏造があったのであり,スピノザはそこで独断論者としてマイエルを批判したかったのであり,それが捏造の意図であったと僕はみています。そしてこの批判により,マイエルとスピノザは仲違いすることになったという説があります。しかしスピノザは懐疑論者に対しては絶縁を迫るようなこともしましたが,フェルトホイゼンやグレフィウスといった,デカルト主義者の独断論者に対してはそういう態度をとりませんでした。であれば,独断論者であってもデカルト主義よりスピノザ主義に近かったマイエルに対してそのような態度をとることはなおのこと考えられないでしょう。マイエルがスピノザの批判をどう受け止めるかということは別の観点としてみなければいけないでしょうが,少なくともスピノザの方からマイエルと交友関係を絶たなければならないような動機は,何もなかったということになります。
以前からいっているように,マイエルはスピノザの遺稿集Opera Posthumaの編集者のひとりであったのだから,マイエルとスピノザとの交友関係が断たれるというようなことはなかったとみています。そうでないと編集者になったことを説明できないからです。コレルスの伝記Levens-beschrijving van Benedictus de Spinozaで,スピノザの死を看取った医師が,それが事実であったかどうかは別としても,マイエルであったと示唆されていることもそのことを補強する材料になるでしょう。なので,僕はスピノザとマイエルが仲違いしたことはないとみていますが,それとは別に,スピノザがグレフィウスやフェルトホイゼンとの交流を拒まなかったということも,その説を補強する材料になるのではないかと思います。
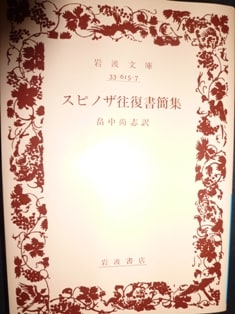
この書簡は非常に長いものなので,内容がどういったものであるのかということはここでは紹介しませんので,それを知りたいという場合は『スピノザ往復書簡集Epistolae』を読んでください。何度かいっているように,この書簡はスピノザとブレイエンベルフとの間のやり取りの中での契機となったものです。最初の書簡十八を読んだとき,スピノザはブレイエンベルフは真理veritasを獲得することだけを目的finisとしていて,その点で自身と一致すると思いました。そしてそういう立場から書簡十九を送ったのです。ところが書簡二十の内容から,スピノザはブレイエンベルフが,聖書に書かれていることが真理であると解する懐疑論者scepticiであるということを理解しました。このゆえにこの書簡の返事となる書簡二十一の冒頭で,これ以上は書簡のやり取りを続けても両者の一致点を見出すことはできないであろうという主旨のことをいったのです。
スピノザは,聖書が教えるのは真理ではなくて服従obedientiaであるということを『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』の中で示しました。これはいい換えれば聖書は真理を教えてはいないということであって,聖書をいくら研究しても真理を獲得することはできないということを意味します。スピノザはふたりの間には根本的原理そのものに相違があるといっていますが,それは具体的にはこのことです。
このことはスピノザとマイエルLodewijk Meyerとの関係にも影響するかもしれません。マイエルが著した『聖書解釈者としての哲学Philosophia S. Scripturae Interpres』は,スピノザがいうところの独断論的な視点で書かれたものであるからです。すなわちマイエルはブレイエンベルフWillem van Blyenburgのような懐疑論者scepticiであったわけではなく,デカルト主義者であるか否かという立場の相違はあったとしても,グレフィウスJohann Georg GraeviusやフェルトホイゼンLambert van Velthuysenと同様に独断論者dogmaticiであったのです。
『スピノザーナ15号』で高木久夫が指摘しているように,たぶん『神学・政治論Tractatus Theologico-Politicus』には一種の捏造があったのであり,スピノザはそこで独断論者としてマイエルを批判したかったのであり,それが捏造の意図であったと僕はみています。そしてこの批判により,マイエルとスピノザは仲違いすることになったという説があります。しかしスピノザは懐疑論者に対しては絶縁を迫るようなこともしましたが,フェルトホイゼンやグレフィウスといった,デカルト主義者の独断論者に対してはそういう態度をとりませんでした。であれば,独断論者であってもデカルト主義よりスピノザ主義に近かったマイエルに対してそのような態度をとることはなおのこと考えられないでしょう。マイエルがスピノザの批判をどう受け止めるかということは別の観点としてみなければいけないでしょうが,少なくともスピノザの方からマイエルと交友関係を絶たなければならないような動機は,何もなかったということになります。
以前からいっているように,マイエルはスピノザの遺稿集Opera Posthumaの編集者のひとりであったのだから,マイエルとスピノザとの交友関係が断たれるというようなことはなかったとみています。そうでないと編集者になったことを説明できないからです。コレルスの伝記Levens-beschrijving van Benedictus de Spinozaで,スピノザの死を看取った医師が,それが事実であったかどうかは別としても,マイエルであったと示唆されていることもそのことを補強する材料になるでしょう。なので,僕はスピノザとマイエルが仲違いしたことはないとみていますが,それとは別に,スピノザがグレフィウスやフェルトホイゼンとの交流を拒まなかったということも,その説を補強する材料になるのではないかと思います。











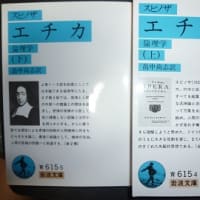
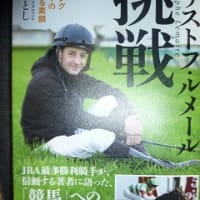




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます