エリザベス女王杯を勝ったジェラルディーナの母はジェンティルドンナです。父はディープインパクト。母はドナブリーニ。ひとつ上の全姉に2012年の京都牝馬ステークスと関屋記念を勝ったドナウブルー。Gentildonnaはイタリア語で淑女。
2歳11月のデビュー。このレースは2着に負けましたが2戦目の未勝利で初勝利。
3歳1月のシンザン記念に出走して重賞初制覇。チューリップ賞は4着に負けましたが桜花賞で大レース初制覇。オークスも勝って二冠を達成。
秋はローズステークスで復帰して重賞4勝目。秋華賞を勝って牝馬三冠を達成。ジャパンカップに進むと外のオルフェーヴルを弾き飛ばすように進路を確保し優勝。JRA賞の年度代表馬に選出されました。
4歳初戦はドバイシーマクラシックに遠征して2着。帰国して出走した宝塚記念はゴールドシップの3着。
秋は天皇賞(秋)で復帰してジャスタウェイの2着。ジャパンカップは連覇を果たして大レース5勝目。JRA賞では最優秀4歳以上牝馬に選出されました。
5歳の初戦は京都記念で6着。この年もドバイシーマクラシックに遠征。直線で進路をなくしましたが外に切り返して優勝。帰国して出走した宝塚記念はゴールドシップの9着。
この年の秋も天皇賞(秋)で復帰して2着。ジャパンカップはエピファネイアの4着に負けて三連覇を逃しました。引退を伸ばして出走した有馬記念を勝って大レース7勝目。JRA賞で年度代表馬に選出されて現役を退きました。
この馬はスピードやスタミナがあるといった競走能力だけでなく,闘争心とか根性といった面もきわめて優れた馬で,競走馬として必要なすべての要素を兼ね備えていたといえます。そして産駒が大レースを制覇したのですから,まさに名牝といえるでしょう。
特別な場合というのがどういう場合であるのかということについては例示しておきましょう。ここでは『エチカ』を実例とします。

スピノザは第一部定理一一の第三の証明をした直後の備考Scholiumの冒頭で次のようにいっています。
「この最後の証明において私は神の存在をアポステリオリに示そうとした。これは証明がいっそう容易に理解されるようにであって,同じ根底から神の存在がアプリオリに帰結しえないためではない」。
ここでいわれているアポステリオリというのは,結論から条件あるいは結果effectusから原因causaに進む論証Demonstratioをいい,アプリオリはそれとは逆に,条件から結論に,あるいは原因から結果へと進捗する論証のことをいいます。第三の証明についていえば,現実的に何かが存在するという結論から,最高の実在性realitasを有するものは存在しなければならないという条件が論証されているので,これはアポステリオリな論証であることになります。そしてスピノザは,これをアポステリオリに証明した理由を説明しているのであり,その理由とは,この証明が容易に理解できるからだとしています。確かにこの証明はとても分かりやすいものなのであって,最高の実在性を有するものが存在するかそうでなければ何も存在しないかのどちらかであるということが二者択一として示されるのであれば,何かが,たとえば僕たちが存在するという反証し得ない事実から,最高の実在性を有するもの,つまり神Deusが存在するということが理解できます。
一方,スピノザがアポステリオリに証明した理由についてなぜここで述べているのかといえば,それがアプリオリに証明することができないからではないのであって,アプリオリにも証明できるといいたかったからです。なぜそういいたかったのかといえば,これはこの定理Propositioに限らず,あらゆる定理は本来的にはアプリオリに証明されるべきだとスピノザは考えているからです。このことは第一部公理三や第一部公理四から,本来の論証は原因から結果へと進むべきものであるということになるということから明白でしょう。ただ,この第三の証明はアポステリオリな論証の方が,アプリオリな論証より理解することは容易なのです。
2歳11月のデビュー。このレースは2着に負けましたが2戦目の未勝利で初勝利。
3歳1月のシンザン記念に出走して重賞初制覇。チューリップ賞は4着に負けましたが桜花賞で大レース初制覇。オークスも勝って二冠を達成。
秋はローズステークスで復帰して重賞4勝目。秋華賞を勝って牝馬三冠を達成。ジャパンカップに進むと外のオルフェーヴルを弾き飛ばすように進路を確保し優勝。JRA賞の年度代表馬に選出されました。
4歳初戦はドバイシーマクラシックに遠征して2着。帰国して出走した宝塚記念はゴールドシップの3着。
秋は天皇賞(秋)で復帰してジャスタウェイの2着。ジャパンカップは連覇を果たして大レース5勝目。JRA賞では最優秀4歳以上牝馬に選出されました。
5歳の初戦は京都記念で6着。この年もドバイシーマクラシックに遠征。直線で進路をなくしましたが外に切り返して優勝。帰国して出走した宝塚記念はゴールドシップの9着。
この年の秋も天皇賞(秋)で復帰して2着。ジャパンカップはエピファネイアの4着に負けて三連覇を逃しました。引退を伸ばして出走した有馬記念を勝って大レース7勝目。JRA賞で年度代表馬に選出されて現役を退きました。
この馬はスピードやスタミナがあるといった競走能力だけでなく,闘争心とか根性といった面もきわめて優れた馬で,競走馬として必要なすべての要素を兼ね備えていたといえます。そして産駒が大レースを制覇したのですから,まさに名牝といえるでしょう。
特別な場合というのがどういう場合であるのかということについては例示しておきましょう。ここでは『エチカ』を実例とします。

スピノザは第一部定理一一の第三の証明をした直後の備考Scholiumの冒頭で次のようにいっています。
「この最後の証明において私は神の存在をアポステリオリに示そうとした。これは証明がいっそう容易に理解されるようにであって,同じ根底から神の存在がアプリオリに帰結しえないためではない」。
ここでいわれているアポステリオリというのは,結論から条件あるいは結果effectusから原因causaに進む論証Demonstratioをいい,アプリオリはそれとは逆に,条件から結論に,あるいは原因から結果へと進捗する論証のことをいいます。第三の証明についていえば,現実的に何かが存在するという結論から,最高の実在性realitasを有するものは存在しなければならないという条件が論証されているので,これはアポステリオリな論証であることになります。そしてスピノザは,これをアポステリオリに証明した理由を説明しているのであり,その理由とは,この証明が容易に理解できるからだとしています。確かにこの証明はとても分かりやすいものなのであって,最高の実在性を有するものが存在するかそうでなければ何も存在しないかのどちらかであるということが二者択一として示されるのであれば,何かが,たとえば僕たちが存在するという反証し得ない事実から,最高の実在性を有するもの,つまり神Deusが存在するということが理解できます。
一方,スピノザがアポステリオリに証明した理由についてなぜここで述べているのかといえば,それがアプリオリに証明することができないからではないのであって,アプリオリにも証明できるといいたかったからです。なぜそういいたかったのかといえば,これはこの定理Propositioに限らず,あらゆる定理は本来的にはアプリオリに証明されるべきだとスピノザは考えているからです。このことは第一部公理三や第一部公理四から,本来の論証は原因から結果へと進むべきものであるということになるということから明白でしょう。ただ,この第三の証明はアポステリオリな論証の方が,アプリオリな論証より理解することは容易なのです。













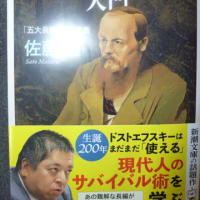
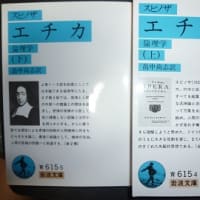






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます