試合後のマイクによるパフォーマンスの効果だったとはいえないのかもしれませんが,ラッシャー・木村は馬場とのシングルマッチをまた実現させるに至りました。1988年8月29日の日本武道館大会。7月16日に殺されてしまった超獣のメモリアル大会と銘打って開催された興行です。
馬場と木村はそれまでにも何度かシングルで対戦していました。まだ木村が国際プロレスに在籍していた頃のものは僕のプロレスキャリアより以前ですから,後にビデオで視ただけ。それは対抗戦につきもののような殺伐としたムードが感じられるものでした。しかし木村が国際血盟軍を結成して以後のものは,木村が実直に馬場に立ち向かうといった趣で,どちらかといえばのんびりとしたムードさえ感じられるような試合になっていました。この日もそんな内容で,馬場が勝利しました。馬場も木村も全盛期の力はなかった筈ですが,プロレスラーの力として,木村には馬場に勝つだけのものはなかったというのが妥当で,試合の結果はごく順当なものでしょう。
そして試合後のマイク。このときのパフォーマンスは日本プロレス史上に残すべきものと僕は思っています。
ふたりは毎日のようにタッグマッチで対戦していました。この大会の前のシリーズは23戦ありましたが,そのすべてで馬場&X対木村&鶴見五郎の試合が組まれています。それだけ対戦していると,馬場を他人と思えなくなってきたから,兄貴と呼ばせてほしいというのがこのときのマイクパフォーマンスの主旨でした。プロレスとしてはおおよそあり得ないような内容ですが,木村が発すると,単に笑いがあるだけでなく,真実味も含まれているように感じられました。それは木村の人柄のなせる業だったといえるでしょう。
これを機に,ふたりの関係はまた新しい段階に入っていくのです。
スチュアートは,ヘーゲルのライプニッツ批判が,スピノザ主義寄りの立場からなされていることに気付いていたようです。そこで,ヘーゲルが取りあげている批判を,別の問題として置き換えています。それは,神とモナドとの関係を,ライプニッツはどう主張するべきかという問題です。
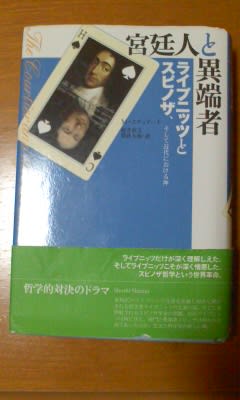
スチュアートが示しているように,ライプニッツにはふたつの選択肢があるように僕には思えます。ひとつは神とは純然たる実体であって,モナドとは異なるという選択です。もうひとつは神は実体であるけれども,同時にモナドでもあるという選択です。スチュアートは,ライプニッツはきっと後者を選択するであろうと予想しています。僕もその予想に賛同します。ただし,その後でスチュアートが示している事柄は,またスピノザ主義寄りの立場から展開されていると僕は考えます。なので,スチュアートの予想がなぜ正しいかということに関しては,僕が独自の方法で説明していくことにします。
まず,ライプニッツにとって重要だったのは,神学的観点からスピノザと対決することでした。そしてヤコービとライプニッツとの違いを示したことから明らかなように,ヤコービは論理的にスピノザと対決するのは不可能であると考えていたのに対し,ライプニッツは論理的にスピノザ主義を崩壊させることが可能であると判断していました。この点が大前提になります。
次に,第一部定理五に対するライプニッツの疑問は,第一部定義三を射程に入れたものでした。いい換えればライプニッツは,実体はそれ自身のうちにあるけれども,それ自身によって考えられることはないと認識していたのです。モナドとは,その条件を満たすような実体でなければなりません。実体と実体との区別が実在的区別であるなら,あるモナドと別のモナドは実在的に区別されなければなりません。スピノザ主義に依拠すると,ヘーゲルがいっている通り,モナドとモナドの区別は様態的区別であるということになります。しかしライプニッツは,区別のあり方について,スピノザとは違って考えていたと僕は理解します。いい換えればこの部分でスピノザ主義的にこれを解決することは僕はしません。
馬場と木村はそれまでにも何度かシングルで対戦していました。まだ木村が国際プロレスに在籍していた頃のものは僕のプロレスキャリアより以前ですから,後にビデオで視ただけ。それは対抗戦につきもののような殺伐としたムードが感じられるものでした。しかし木村が国際血盟軍を結成して以後のものは,木村が実直に馬場に立ち向かうといった趣で,どちらかといえばのんびりとしたムードさえ感じられるような試合になっていました。この日もそんな内容で,馬場が勝利しました。馬場も木村も全盛期の力はなかった筈ですが,プロレスラーの力として,木村には馬場に勝つだけのものはなかったというのが妥当で,試合の結果はごく順当なものでしょう。
そして試合後のマイク。このときのパフォーマンスは日本プロレス史上に残すべきものと僕は思っています。
ふたりは毎日のようにタッグマッチで対戦していました。この大会の前のシリーズは23戦ありましたが,そのすべてで馬場&X対木村&鶴見五郎の試合が組まれています。それだけ対戦していると,馬場を他人と思えなくなってきたから,兄貴と呼ばせてほしいというのがこのときのマイクパフォーマンスの主旨でした。プロレスとしてはおおよそあり得ないような内容ですが,木村が発すると,単に笑いがあるだけでなく,真実味も含まれているように感じられました。それは木村の人柄のなせる業だったといえるでしょう。
これを機に,ふたりの関係はまた新しい段階に入っていくのです。
スチュアートは,ヘーゲルのライプニッツ批判が,スピノザ主義寄りの立場からなされていることに気付いていたようです。そこで,ヘーゲルが取りあげている批判を,別の問題として置き換えています。それは,神とモナドとの関係を,ライプニッツはどう主張するべきかという問題です。
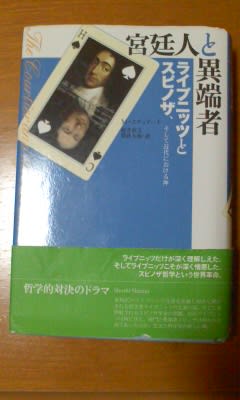
スチュアートが示しているように,ライプニッツにはふたつの選択肢があるように僕には思えます。ひとつは神とは純然たる実体であって,モナドとは異なるという選択です。もうひとつは神は実体であるけれども,同時にモナドでもあるという選択です。スチュアートは,ライプニッツはきっと後者を選択するであろうと予想しています。僕もその予想に賛同します。ただし,その後でスチュアートが示している事柄は,またスピノザ主義寄りの立場から展開されていると僕は考えます。なので,スチュアートの予想がなぜ正しいかということに関しては,僕が独自の方法で説明していくことにします。
まず,ライプニッツにとって重要だったのは,神学的観点からスピノザと対決することでした。そしてヤコービとライプニッツとの違いを示したことから明らかなように,ヤコービは論理的にスピノザと対決するのは不可能であると考えていたのに対し,ライプニッツは論理的にスピノザ主義を崩壊させることが可能であると判断していました。この点が大前提になります。
次に,第一部定理五に対するライプニッツの疑問は,第一部定義三を射程に入れたものでした。いい換えればライプニッツは,実体はそれ自身のうちにあるけれども,それ自身によって考えられることはないと認識していたのです。モナドとは,その条件を満たすような実体でなければなりません。実体と実体との区別が実在的区別であるなら,あるモナドと別のモナドは実在的に区別されなければなりません。スピノザ主義に依拠すると,ヘーゲルがいっている通り,モナドとモナドの区別は様態的区別であるということになります。しかしライプニッツは,区別のあり方について,スピノザとは違って考えていたと僕は理解します。いい換えればこの部分でスピノザ主義的にこれを解決することは僕はしません。













