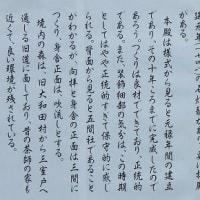飛鳥には妙な石造物が数多く残されていて,非情に興味深いところです。
現在流に考えるから謎なのであって、当時、この石造物が作られた頃にはどうしても必要な物で、其処には無くてはならなかったものだと考えるのが極自然なことだと思う。
この猿石にしても一見猿に似ていることから「猿石」と呼ばれていますが、背中にまで曰くありそうな面相を彫りつけていたりしていてどうも、これが何なのかは良くわかりませんが、何かの呪物のようにも思えてきます。

江戸時代・元禄15年に欽明天皇陵(きんめいてんのうりょう)の南の田んぼから掘り出され、うち4体は現在の吉備姫王墓に、もう1体は高取城(たかとりじょう)へ運ばれ、今でも高取城跡に置かれています。


『今昔物語』に「軽寺南方の天皇陵の堤にあった石の鬼形」として載っており、猿石はもともと欽明天皇陵の堤に置かれていて、この陵墓の守りの役目をになわされていたのかもしれません???

吉備姫王墓(きびつひめのおほきみのはか)は、欽明天皇稜直ぐ脇の小高い森で奥に回りこむと鉄柵のはまった鳥居越しに、この四体の奇妙な姿に出逢うことが出来る。
鉄柵にレンズを入れての撮影、まずいところはお許しあれ。

正面左の二体、左端はまるでオオトカゲのような顔をした「女」と呼ばれている石像、これが女だったら、蝶蝶トンボも鳥のうち??

しかしこの「女」、男のイチモツがついて、 高さ100cm、幅65cm、奥行き100cmの大きさです。

後ろ姿は稜内に入ることが出来ないので、飛鳥資料館のレプリカですが何がなにやらさっぱり解りません。

「女」の右側は、ここの主人公のようにも見える「山王権現」戸呼ばれる石像。
サルだと言えばサルのような、僕は昔絵本で見た河童のイメージがダブるけど???、絵本のカラス天狗にも似ているような??
しかし立派な一物に手を添えているようにも見え、 高さ128cm、幅101cm、奥行き84cm。

こちらの後ろ姿は、よくわかる具体的な顔です。
なぜ後ろにも顔があるのか、こちらが前だと言えばそのまま,そうなんだと思ってしまうかもです??。
しかしここ飛鳥ではどうしてこれほどおおらかに、男のシンボルが目立って多いのだろうか。

正面右側には「僧」と「男」の二体が並んでいる。
手前側が「僧」と呼ばれる石像でもっとも人間らしい顔をしているように思えます。
高さ106cm、幅79cm、奥行き74cm、やっぱりちゃんとシンボルつけてます。

最後は「男」と呼ばれている石像。
これが男なら、最初の女もあんなものかと妙に納得、高さ99cm、幅90cm、奥行き58cm。
しかし妙な、笑顔で揉み手までして、まるで関西の商売人。
それでもしっかりシンボルつけてます。

高取城跡の、登城道にある猿石も吉備媛王の墓前の4体と同じもので、どうしたことかこの1体だけが、この高取城跡におかれている。



これはまさしく猿の顔、高さ85cm、幅73cm、奥行き68cm、ここでもしっかり男のシンボルはつけています。
当時このシンボルはどうしても、こうしてしっかり誇示させておかなければならなかった理由は何だろう??。
撮影2006.12.13 :2007.2.3