
写真は、マツタケのシロの一部である.マツタケの菌糸に覆われた菌根が見えている(白いところ).
全山のシロ化とシロの崩壊
アカマツの樹齢の進行とともにシロ数が増え、また、シロ直径が大きくなる.マツタケの発生量が増加する.時には、一つのシロに400本のマツタケが生えることもある.壮齢林では100kg/ha以上の生産量が望める.
マツタケと他の土壌微生物とのインタラクション(攻撃,協調、無関心など)は場所や時間によってその質は異なるが、マツタケのシロは痩地であり乾燥ぎみのマツタケが優占しうる諸条件が整っている場所へ広がっていく.
シロ数が増え、また、シロの先端が年々外側に10-15cmほど広がり大きくなると、マツタケのシロは重合する.重合すると瓢箪状、線状あるいは弧状にマツタケ子実体が発生するようになる.しかし、マツタケは土壌微生物との競争に弱いため、手を入れてない林では、途中で消滅するシロも多い.
ドーナツ状のシロの内部は、土壌がパサパサになり、細根が脱落した主根だけが残り、菌糸の残骸や死んだ細根由来のキチンとセルロースやヘミセルロースまたリグニン、タンニンが多い.それらは難分解物質のため、シロ内部の微生物社会はマツタケの発生してない土壌やシロ周辺部土壌のそれとも違っている.シロの内部には、アカマツの根も侵入せず、マツタケも生えない忌地 (sick soil)となる.
マツタケ発生後40年もすると、アカマツ林内にはマツタケの忌地面積が増える.また、アカマツの生長が鈍り根の発達が悪くなるため、マツタケの発生量は落ちてくる.アカマツの生長を促したり,林の更新を考える時である.アカマツが常に生長するように、枝払いや芯止めを施して、100年生のアカマツ林でも、マツタケ発生量が落ちない手入れもある.
更新は、薪炭生産林をモデルとすると良い.マツタケ感染アカマツ樹(シロ)を一部残し伐採する.地かき後、アカマツ異齢林をつくる.あるいは、帯状に伐採区と非伐採区を設け、伐採区は地かきし、新たなアカマツ林を造成することを考える.このような作業では、マツタケが非常に早く発生することが見られる.(続く)










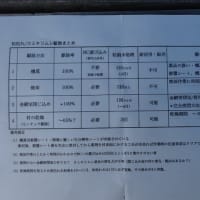















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます