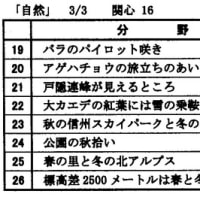「ノキアNokiaという名前から、
最初は日本の企業と思われました。これは名誉なことです。
日本製品は、先端技術と高品質の代名詞ですから」
と、ティモはうれしいことを言ってくれる。
フィンランドを代表する企業にノキアがある。
携帯電話で世界一のシェア(30%以上)だ。
ノキアによって、フィンランドの主産業は、
これまでの製紙や林業から、IT(情報機器) 産業へと、
産業構造を転換することに成功した。
「ノキアは、世界の9か国に製造工場があり、
研究所が11か国にあり、5万人以上の社員がいます。
フィンランドのノキアから、世界のノキアになりました」
ガラス張りの本社ビル(ノキア・ハウス)は、
首都ヘルシンキのとなり町エスポーの林の中に、
建設して、これまでのヘルシンンキから移転した。

会議室からは、森と湖が広がり、
まさに、フィンランドそのものである。
――どうして、ノキアは急成長したのだろうか?
フィンランドの産業を、林業からITへと、
みごとに、産業構造を転換してしまったが。
ティモは、ノキア成長の秘密を話す。
「ノキアは、1865年の製紙業がスタートでした。
一時、ゴム長靴や電線も手がけたが、経営危機になった」
「携帯電話の開発に着手したが、
用途が、災害や救助の緊急用と限定的で、しかも、
基地局を数キロごとに造らなければならないから、
インフラストラクチャー社会基盤への投資が大変で、
既存の電話よりも大きなビジネスになるとは、
世界のだれもが考えませんでした」
「ニッチ(すき間)産業のままだろう、と思われていた。
まして、IT産業の主役に躍り出ようとは、
思いもよりませんでした」
「それでも、地道に開発を続けたことが幸運をもたらした。
1990年代にGSMというディジタル携帯電話の世界標準規格が、
定められた。そして、通信サービスの規制緩和によって、
市場が開放された」
「これまで開発を進めてきたノキアが、
最初に携帯電話の市場に入ることができました。
それで、急速に世界に進出できたのです。
環境の変化に、勇気をもって技術開発をしていたことが、
成功につながりました」
「しかし、携帯電話は最初、企業に1台でした。
緊急連絡が必要な経営者や役員が持ちました。
そして、災害や救助の連絡にも、使われ始めました。
つぎに、屋外で仕事をする営業やドライバーが持つようになり、
今では一般の人から学童まで、なくてはならないものになりました」
――ビジネスの用途からスタートしているが、
既存の電話を超えてしまった。一般の商品になって、
ニッチ(すき間)産業から、IT産業の主役に成長させている。
「それに、電話としての機能ばかりではなく、
パーソナルな情報機器として、その用途は無限に広がっています。
eメール、インターネット、ショッピング、銀行の取引、
自販機から商品の購入、家のセキュリティの管理、位置の管理、
サウナ・バスの電源、音楽やゲーム、映画のエンターテイメント……」
「全部をノキアやフィンランドだけで開発するのは、限界があります。
それで、世界の企業が参加して、プロジェクトを達成する、
“コンソーシアム”を作って、国際的な協調で進めています」
ノキアのパーティが開催されたヘルシンキ大学の学生会館。

舞踏室、レストラン、ミュージック・ルームなどがある。
繁華街にあって、デパートメント・ストア、ストックマンに近い。
140年の歴史があり、当時のヘルシンキ大学の学長、
ロシア皇帝アレクサンドル3世が訪れている。
「大学との“産学連携”も積極的に進めています。
先端技術から品質管理まで、幅広く共同研究し、
連携する大学も、フィンランドの大学のほかに、
アイルランド大学をはじめ、世界に広げています」
「産学連携は、ノキアにとっては知恵袋であるとともに、
優秀な人材の確保になります。共同研究に参画した学生が、
ノキアを知り、就職する効果につながるからです」
環境の変化を見越した開発、コンソーシアムや産学連携などの
世界との協調によって、ノキアはよみがえり、世界企業に成長した。
そして、フィンランドを林業からIT(情報機器)産業へ転換させて、
ドイツ資本に侵略されるという杞憂を乗り切った。
フィンランドは、これまで、
歴史から消滅する“国存亡”の危機、
“国際化か死か”の危機があった。
“国存亡”の危機とは、
スウェーデンとロシアに分割された統治700年間、
帝政ロシアのニコライ2世による抑圧(1917年まで)、
第2次世界大戦の敗戦、ソ連への賠償支払い、
ソ連が崩壊する1991年までの脅威。
“国際化か死か”の危機とは、
人口も資源もないフィンランドは、
先端技術でヨーロッパと競争するのか?
それとも北欧の中立国として埋没するのか?
の選択を迫られていた。
国の復興をかけて、
教育の改革、IT産業への転換、国際協調に、
取り組んできた。
そして、“国存亡”の危機、“国際化か死か”の危機を乗り切った。
フィンランドは危機を乗り超え、知的な中立国を実現しているが、
ノキアは、その中心的な役割を果たしている。
最初は日本の企業と思われました。これは名誉なことです。
日本製品は、先端技術と高品質の代名詞ですから」
と、ティモはうれしいことを言ってくれる。
フィンランドを代表する企業にノキアがある。
携帯電話で世界一のシェア(30%以上)だ。
ノキアによって、フィンランドの主産業は、
これまでの製紙や林業から、IT(情報機器) 産業へと、
産業構造を転換することに成功した。
「ノキアは、世界の9か国に製造工場があり、
研究所が11か国にあり、5万人以上の社員がいます。
フィンランドのノキアから、世界のノキアになりました」
ガラス張りの本社ビル(ノキア・ハウス)は、
首都ヘルシンキのとなり町エスポーの林の中に、
建設して、これまでのヘルシンンキから移転した。

会議室からは、森と湖が広がり、
まさに、フィンランドそのものである。
――どうして、ノキアは急成長したのだろうか?
フィンランドの産業を、林業からITへと、
みごとに、産業構造を転換してしまったが。
ティモは、ノキア成長の秘密を話す。
「ノキアは、1865年の製紙業がスタートでした。
一時、ゴム長靴や電線も手がけたが、経営危機になった」
「携帯電話の開発に着手したが、
用途が、災害や救助の緊急用と限定的で、しかも、
基地局を数キロごとに造らなければならないから、
インフラストラクチャー社会基盤への投資が大変で、
既存の電話よりも大きなビジネスになるとは、
世界のだれもが考えませんでした」
「ニッチ(すき間)産業のままだろう、と思われていた。
まして、IT産業の主役に躍り出ようとは、
思いもよりませんでした」
「それでも、地道に開発を続けたことが幸運をもたらした。
1990年代にGSMというディジタル携帯電話の世界標準規格が、
定められた。そして、通信サービスの規制緩和によって、
市場が開放された」
「これまで開発を進めてきたノキアが、
最初に携帯電話の市場に入ることができました。
それで、急速に世界に進出できたのです。
環境の変化に、勇気をもって技術開発をしていたことが、
成功につながりました」
「しかし、携帯電話は最初、企業に1台でした。
緊急連絡が必要な経営者や役員が持ちました。
そして、災害や救助の連絡にも、使われ始めました。
つぎに、屋外で仕事をする営業やドライバーが持つようになり、
今では一般の人から学童まで、なくてはならないものになりました」
――ビジネスの用途からスタートしているが、
既存の電話を超えてしまった。一般の商品になって、
ニッチ(すき間)産業から、IT産業の主役に成長させている。
「それに、電話としての機能ばかりではなく、
パーソナルな情報機器として、その用途は無限に広がっています。
eメール、インターネット、ショッピング、銀行の取引、
自販機から商品の購入、家のセキュリティの管理、位置の管理、
サウナ・バスの電源、音楽やゲーム、映画のエンターテイメント……」
「全部をノキアやフィンランドだけで開発するのは、限界があります。
それで、世界の企業が参加して、プロジェクトを達成する、
“コンソーシアム”を作って、国際的な協調で進めています」
ノキアのパーティが開催されたヘルシンキ大学の学生会館。

舞踏室、レストラン、ミュージック・ルームなどがある。
繁華街にあって、デパートメント・ストア、ストックマンに近い。
140年の歴史があり、当時のヘルシンキ大学の学長、
ロシア皇帝アレクサンドル3世が訪れている。
「大学との“産学連携”も積極的に進めています。
先端技術から品質管理まで、幅広く共同研究し、
連携する大学も、フィンランドの大学のほかに、
アイルランド大学をはじめ、世界に広げています」
「産学連携は、ノキアにとっては知恵袋であるとともに、
優秀な人材の確保になります。共同研究に参画した学生が、
ノキアを知り、就職する効果につながるからです」
環境の変化を見越した開発、コンソーシアムや産学連携などの
世界との協調によって、ノキアはよみがえり、世界企業に成長した。
そして、フィンランドを林業からIT(情報機器)産業へ転換させて、
ドイツ資本に侵略されるという杞憂を乗り切った。
フィンランドは、これまで、
歴史から消滅する“国存亡”の危機、
“国際化か死か”の危機があった。
“国存亡”の危機とは、
スウェーデンとロシアに分割された統治700年間、
帝政ロシアのニコライ2世による抑圧(1917年まで)、
第2次世界大戦の敗戦、ソ連への賠償支払い、
ソ連が崩壊する1991年までの脅威。
“国際化か死か”の危機とは、
人口も資源もないフィンランドは、
先端技術でヨーロッパと競争するのか?
それとも北欧の中立国として埋没するのか?
の選択を迫られていた。
国の復興をかけて、
教育の改革、IT産業への転換、国際協調に、
取り組んできた。
そして、“国存亡”の危機、“国際化か死か”の危機を乗り切った。
フィンランドは危機を乗り超え、知的な中立国を実現しているが、
ノキアは、その中心的な役割を果たしている。