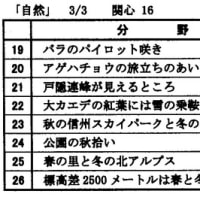東山魁夷は、
「ネッカー河畔のハイデルベルクは、
ドイツの京都とも言うべき山紫水明の古都である」
と言っている。
東山魁夷の「緑のハイデルベルク」を北澤美術館で見た。2012年。

絵はがきから。
「ハイデルベルクは、第二次世界大戦では、
少しの損傷も受けなかった町である。
京都のように爆撃の目標から外す、
という考慮があったのだろうか」
と、東山魁夷は言っている。
「ハイデルベルク」の写真がある(1989年)。

ネッカー川にかかるカール・テオドール橋を渡って、
対岸からハイデルベルク城や旧市街を眺めた。
ハイデルベルクのランドマーク、
「ハイデルベルク城」が山すそにあり、
その下に、ハイデルベルクの旧市街が広がる。
奥の2つの白い塔は、橋門ブリュッケン・トーア。
「緑のハイデルベルク」の実物を見たい!
それに、東山魁夷は、
なぜ「緑のハイデルベルク」を描いたのだろうか?
また、どうしてドイツなのか?
東山魁夷とドイツとのかかわりはつぎである。
東山魁夷は、25歳のときにドイツに渡り(1933年)、
ベルリン大学に留学している。しかし、
父の病状が悪化し、残り1年の留学を断念して帰国した(1935年)。
ふたたび、ドイツを訪れるのは、34年後である(1969年)。
そして、「緑のハイデルベルク」を描いた(1971)。
東山魁夷とドイツとのかかわりを簡単に書くと、たった5行。
しかし、「東山魁夷画文集」1979年、新潮社を、
松本の古本屋「青翰堂」で、手に入れたから、
あちこちをめくって、ドイツとのかかわりを、
もう少し詳しく書くので、おつき合いください。
東山魁夷は、東京美術学校(現在の東京藝術大学)の、
研究科を修了すると、貨物船でドイツに渡った(1933年)。
在学中から、挿絵を描いて渡航費用を貯めながら、
ドイツ語を学ぶ生活を2年間続けて、遊学の準備をした。
遊学の動機を、日記に書いている。
「若い間に欧州を見ておく」
「日本画家としても将来自分の進路を判断する上に、
日本でない生活、日本でない芸術を見ておく必要がある」
ドイツを選んだわけも書いている。
「フランスはエレガントで、イタリアは明るいが、
ドイツの持つあの暗さ、荘重なものに私は牽(ひ)かれる」
「ドイツへ向かったのは、感覚的な世界に傾きがちの私の性質に、
しっかりした支柱を入れたい意味もあった」
ベルリンでは、語学教室に通い、
翌年の1934年には、4ヶ月のヨーロッパ一周旅行をする。
イタリアのフィレンツェでは、衝撃を受けている。
「ルネッサンスの作品を眼の前にして、
私は身体が熱くなる程、昂奮したり、
打ちのめされたり、鼓舞されたり、
まるで熱病の発作のような状態でした」
「画家になろうとしたのは間違いだったと、
このフィレンツェに来てつくづく感じる」
「努力も勤勉も築き上げ得ないものがある。
自分には画家になる素質がないことを、
こんど程痛切に感じたことはない」
「しかし、自分を見失ってしまって何になるだろう」
「東洋の片隅で、不自由な日本画の絵具を使ってでも、
表現し得る世界がある。こう考えて来た時、
思わず眼の中が熱くなってきました」
と、気を取り直している。
マネするつもりは、サラサラない。
東山魁夷を生むことになる。重要なことだ! と思う。
ヨーロッパ一周の旅行からベルリンにもどると、
日独交換学生の制度ができたことを知り、
第一回の交換学生に選ばれた。
ベルリン大学の哲学科、美術史部に入学し(1934年)、
2年間の留学費がドイツから与えられることになった。
ところが、1935年に父の病状が悪化して、
残り1年の留学を断念して、帰国している。
帰国して、結婚。
「これまでは、私の遍歴の日々は順調だったといえるでしょう。
しかし、これから先は、暗い谷間を辿ることになるのです」
借財でどうにもならなくなっていた家の商売(船具商) の整理。
父の死。第二次世界大戦へ突入。召集されて熊本の部隊に配属。
戦局は悪化する一方である。
そして、ソ連との開戦になり、
「東山二等兵。再び絵筆をとる時は来ないぞ」
と、同僚から言われている。
「自分ももとより承知の上だ。
自分のことより、日本の文化が風前の灯だと思う」
そして、敗戦を迎える。
母が亡くなり、弟も病死した。
兄は、以前に亡くなっているから。
これで、肉親を失ったことになる。
「すべてが無くなってしまった私は、
また、今生まれ出たのに等しい。
これからは、清澄な目で自然を見ることができるだろう。
腰を落ち着けて制作に全力を注ぐことできるだろう。
また、そうあらねばならない」
第一回の日展に出品するが、落選する。
「友達は次々と展覧会で華々しい成績を挙げ、
一躍画壇の寵児となって活躍して行くのですが、
私はたいして良い成績も挙がらず、
生活もアルバイトに子供の絵本を描くのが、
主なものですから、ようやく暮らせる程度です」
そして、「第三回日展に出品した『残照』は、
特選となり、政府買上げとなって、ようやく、
私の仕事が世に認められるきっかけとなったのである」
東山魁夷39歳である(1947年)。
苦難だった、長い道のりだった!
「残照」、1947年。

「東山魁夷画文集」、1979年、新潮社から。
それから、東山魁夷は、
日本の古都を「京洛四季」として描いた。
「その後、私の中に、当然、起こってくるのは、
残り半分であるドイツの古都を描くことであり、
それによって戦後における『古き町にて』を、
完成させることに他ならない」
こうして、東山魁夷は、
「京洛四季」を描き終わると、
ドイツ、オーストリアの旅にでた(1969年)。
36年ぶりのドイツである。こんどは、ご夫妻で。
「ネッカー河畔のハイデルベルクは、
ドイツの京都とも言うべき山紫水明の古都である」
そして、「緑のハイデルベルク」が生まれた(1971年)。
やっと、「緑のハイデルベルク」にたどりつきました。
長いおつき合い、ありがとうございました。
あとは、「緑のハイデルベルク」の実物を見たい!
「緑のハイデルベルク」は、北澤美術館が所蔵している。
「春になると展示します」と、電話で聞いていた。
その3月になった。雪は降ったが、
諏訪湖のほとりにある北澤美術館へ行った。2012年。

北澤美術館のチケットは、エミール・ガレの「ひとよ茸」。

「ひとよ茸」は、北澤美術館の目玉である。
ボランティア・ガイドの説明もあり、
お目当てのお客さんが多い。
1階の常設展示室にある。
今回は、展示替えをした2階である。
さっそく上がった。そして、ついに、
「緑のハイデルベルク」に逢えた!
「緑のハイデルベルク」は、やはり緑だった。
「青春時代に見たままだった!」
という、東山魁夷の安堵感が伝わってくる緑だ。
「ドイツ・オーストリア」、新潮文庫で、
東山魁夷はつぎのように言っている。
「ハイデルベルクを私は緑の色調で描いた。
緑は青春の色である」
ふたたびドイツを訪れる動機、
そして、再会した感想を、
東山魁夷はつぎのように書いている。
「遠くの方からドイツの古都が、私を呼んでいるのを感じた。
老い疲れようとする心身に、少しでも若い日の鼓動を、
甦(よみがえ)らせたい願いもあって、
私は36年振りに再遊の旅に出た」
「私には懐しい期待と、同時に不安もあった。
戦争を経て、古い町々の面影が今も残っているだろうか。
もし失われていたならば、私の心の青春の残影も、
消え去ってしまうことになるだろう」
「幸いなことにドイツの北から南へ、
そしてオーストリアへの旅を通じて、
小さな町は昔日の姿をよく残していた。
私の夢の情景そのままでさえあったと言える」
「自然と古都、そのどちらをも、
美しく保とうとする『人間』の心が籠(こも)っていた」
「東山魁夷画文集」では、
つぎのようにも言っている。
ハイデルベルクは、
「私のような遠くの国からの旅人にさえ、
あたかも故郷ででもあるかのような、
親しい感情を起こさせるのである」
ハイデルベルク城から眺めた「ハイデルベルク」の街並み(1989年)。

右の白い塔は、カール・テオドール橋の橋門ブリュッケン・トーア。
ネッカー川の手前は旧市街で、
ネッカー川の対岸は新市街である。
「哲学者の道」は、対岸の丘の中にある。
旧市街の左の教会は、ハイリッヒ・ガスト教会Heiliggeistkirche。
教会は市庁舎と向かい合って、その間はマルクト広場。
マルクト広場一帯は、旧市街の中心地である。
ハイデルベルクで一番高い建物は、教会の尖塔。
ネッカー川の対岸の新市街は、
1978年に訪れたときと比べて、

建物が増えている。
しかし、まわりとの調和を保っている。
ごちゃごちゃと醜いことはなかった。
「旧市街と新市街と分けて開発している」
と、東山魁夷は言っている。
つぎののような予想がつくと思います。
旧市街で、一番高い建物は、教会の尖塔だった。
開発する新市街は、まわりとの調和を保っていた。
そして、
「一番、大切なことは、
そこに住んでいる人々が誇りと、
愛着を持っていることであろう」
「ハイデルベルクの大学は、ドイツ最古の歴史を持っている。
1386年に創立されたもので、その図書館は、
古文書、写本の類の世界的な蒐集で知られている」
「ハイデルベルク大学」(1978年)。

「大学は、ちょっとした広場があるだけで、何もなく、
校舎の建物が町の家々と溶け合って存在している感じである」
東山魁夷が青春の一時期を過ごしたドイツ。
そして、古都「ハイデルベルク」に、
愛着を持っていることが伝わってくる。
そのドイツからご褒美があった。
「思いがけなく西ドイツ大統領から、
功労大十字勲章を贈られた」1976年。
「私はドイツに功労があったわけではないが、
戦前、若いときに留学した国が、その後、
現在までの私の日本における仕事を見守っていてくれて、
その意義を認めてくれたことをありがたく思った」
ドイツもありがたく思う「緑のハイデルブルク」である。
「ネッカー河畔のハイデルベルクは、
ドイツの京都とも言うべき山紫水明の古都である」
と言っている。
東山魁夷の「緑のハイデルベルク」を北澤美術館で見た。2012年。

絵はがきから。
「ハイデルベルクは、第二次世界大戦では、
少しの損傷も受けなかった町である。
京都のように爆撃の目標から外す、
という考慮があったのだろうか」
と、東山魁夷は言っている。
「ハイデルベルク」の写真がある(1989年)。

ネッカー川にかかるカール・テオドール橋を渡って、
対岸からハイデルベルク城や旧市街を眺めた。
ハイデルベルクのランドマーク、
「ハイデルベルク城」が山すそにあり、
その下に、ハイデルベルクの旧市街が広がる。
奥の2つの白い塔は、橋門ブリュッケン・トーア。
「緑のハイデルベルク」の実物を見たい!
それに、東山魁夷は、
なぜ「緑のハイデルベルク」を描いたのだろうか?
また、どうしてドイツなのか?
東山魁夷とドイツとのかかわりはつぎである。
東山魁夷は、25歳のときにドイツに渡り(1933年)、
ベルリン大学に留学している。しかし、
父の病状が悪化し、残り1年の留学を断念して帰国した(1935年)。
ふたたび、ドイツを訪れるのは、34年後である(1969年)。
そして、「緑のハイデルベルク」を描いた(1971)。
東山魁夷とドイツとのかかわりを簡単に書くと、たった5行。
しかし、「東山魁夷画文集」1979年、新潮社を、
松本の古本屋「青翰堂」で、手に入れたから、
あちこちをめくって、ドイツとのかかわりを、
もう少し詳しく書くので、おつき合いください。
東山魁夷は、東京美術学校(現在の東京藝術大学)の、
研究科を修了すると、貨物船でドイツに渡った(1933年)。
在学中から、挿絵を描いて渡航費用を貯めながら、
ドイツ語を学ぶ生活を2年間続けて、遊学の準備をした。
遊学の動機を、日記に書いている。
「若い間に欧州を見ておく」
「日本画家としても将来自分の進路を判断する上に、
日本でない生活、日本でない芸術を見ておく必要がある」
ドイツを選んだわけも書いている。
「フランスはエレガントで、イタリアは明るいが、
ドイツの持つあの暗さ、荘重なものに私は牽(ひ)かれる」
「ドイツへ向かったのは、感覚的な世界に傾きがちの私の性質に、
しっかりした支柱を入れたい意味もあった」
ベルリンでは、語学教室に通い、
翌年の1934年には、4ヶ月のヨーロッパ一周旅行をする。
イタリアのフィレンツェでは、衝撃を受けている。
「ルネッサンスの作品を眼の前にして、
私は身体が熱くなる程、昂奮したり、
打ちのめされたり、鼓舞されたり、
まるで熱病の発作のような状態でした」
「画家になろうとしたのは間違いだったと、
このフィレンツェに来てつくづく感じる」
「努力も勤勉も築き上げ得ないものがある。
自分には画家になる素質がないことを、
こんど程痛切に感じたことはない」
「しかし、自分を見失ってしまって何になるだろう」
「東洋の片隅で、不自由な日本画の絵具を使ってでも、
表現し得る世界がある。こう考えて来た時、
思わず眼の中が熱くなってきました」
と、気を取り直している。
マネするつもりは、サラサラない。
東山魁夷を生むことになる。重要なことだ! と思う。
ヨーロッパ一周の旅行からベルリンにもどると、
日独交換学生の制度ができたことを知り、
第一回の交換学生に選ばれた。
ベルリン大学の哲学科、美術史部に入学し(1934年)、
2年間の留学費がドイツから与えられることになった。
ところが、1935年に父の病状が悪化して、
残り1年の留学を断念して、帰国している。
帰国して、結婚。
「これまでは、私の遍歴の日々は順調だったといえるでしょう。
しかし、これから先は、暗い谷間を辿ることになるのです」
借財でどうにもならなくなっていた家の商売(船具商) の整理。
父の死。第二次世界大戦へ突入。召集されて熊本の部隊に配属。
戦局は悪化する一方である。
そして、ソ連との開戦になり、
「東山二等兵。再び絵筆をとる時は来ないぞ」
と、同僚から言われている。
「自分ももとより承知の上だ。
自分のことより、日本の文化が風前の灯だと思う」
そして、敗戦を迎える。
母が亡くなり、弟も病死した。
兄は、以前に亡くなっているから。
これで、肉親を失ったことになる。
「すべてが無くなってしまった私は、
また、今生まれ出たのに等しい。
これからは、清澄な目で自然を見ることができるだろう。
腰を落ち着けて制作に全力を注ぐことできるだろう。
また、そうあらねばならない」
第一回の日展に出品するが、落選する。
「友達は次々と展覧会で華々しい成績を挙げ、
一躍画壇の寵児となって活躍して行くのですが、
私はたいして良い成績も挙がらず、
生活もアルバイトに子供の絵本を描くのが、
主なものですから、ようやく暮らせる程度です」
そして、「第三回日展に出品した『残照』は、
特選となり、政府買上げとなって、ようやく、
私の仕事が世に認められるきっかけとなったのである」
東山魁夷39歳である(1947年)。
苦難だった、長い道のりだった!
「残照」、1947年。

「東山魁夷画文集」、1979年、新潮社から。
それから、東山魁夷は、
日本の古都を「京洛四季」として描いた。
「その後、私の中に、当然、起こってくるのは、
残り半分であるドイツの古都を描くことであり、
それによって戦後における『古き町にて』を、
完成させることに他ならない」
こうして、東山魁夷は、
「京洛四季」を描き終わると、
ドイツ、オーストリアの旅にでた(1969年)。
36年ぶりのドイツである。こんどは、ご夫妻で。
「ネッカー河畔のハイデルベルクは、
ドイツの京都とも言うべき山紫水明の古都である」
そして、「緑のハイデルベルク」が生まれた(1971年)。
やっと、「緑のハイデルベルク」にたどりつきました。
長いおつき合い、ありがとうございました。
あとは、「緑のハイデルベルク」の実物を見たい!
「緑のハイデルベルク」は、北澤美術館が所蔵している。
「春になると展示します」と、電話で聞いていた。
その3月になった。雪は降ったが、
諏訪湖のほとりにある北澤美術館へ行った。2012年。

北澤美術館のチケットは、エミール・ガレの「ひとよ茸」。

「ひとよ茸」は、北澤美術館の目玉である。
ボランティア・ガイドの説明もあり、
お目当てのお客さんが多い。
1階の常設展示室にある。
今回は、展示替えをした2階である。
さっそく上がった。そして、ついに、
「緑のハイデルベルク」に逢えた!
「緑のハイデルベルク」は、やはり緑だった。
「青春時代に見たままだった!」
という、東山魁夷の安堵感が伝わってくる緑だ。
「ドイツ・オーストリア」、新潮文庫で、
東山魁夷はつぎのように言っている。
「ハイデルベルクを私は緑の色調で描いた。
緑は青春の色である」
ふたたびドイツを訪れる動機、
そして、再会した感想を、
東山魁夷はつぎのように書いている。
「遠くの方からドイツの古都が、私を呼んでいるのを感じた。
老い疲れようとする心身に、少しでも若い日の鼓動を、
甦(よみがえ)らせたい願いもあって、
私は36年振りに再遊の旅に出た」
「私には懐しい期待と、同時に不安もあった。
戦争を経て、古い町々の面影が今も残っているだろうか。
もし失われていたならば、私の心の青春の残影も、
消え去ってしまうことになるだろう」
「幸いなことにドイツの北から南へ、
そしてオーストリアへの旅を通じて、
小さな町は昔日の姿をよく残していた。
私の夢の情景そのままでさえあったと言える」
「自然と古都、そのどちらをも、
美しく保とうとする『人間』の心が籠(こも)っていた」
「東山魁夷画文集」では、
つぎのようにも言っている。
ハイデルベルクは、
「私のような遠くの国からの旅人にさえ、
あたかも故郷ででもあるかのような、
親しい感情を起こさせるのである」
ハイデルベルク城から眺めた「ハイデルベルク」の街並み(1989年)。

右の白い塔は、カール・テオドール橋の橋門ブリュッケン・トーア。
ネッカー川の手前は旧市街で、
ネッカー川の対岸は新市街である。
「哲学者の道」は、対岸の丘の中にある。
旧市街の左の教会は、ハイリッヒ・ガスト教会Heiliggeistkirche。
教会は市庁舎と向かい合って、その間はマルクト広場。
マルクト広場一帯は、旧市街の中心地である。
ハイデルベルクで一番高い建物は、教会の尖塔。
ネッカー川の対岸の新市街は、
1978年に訪れたときと比べて、

建物が増えている。
しかし、まわりとの調和を保っている。
ごちゃごちゃと醜いことはなかった。
「旧市街と新市街と分けて開発している」
と、東山魁夷は言っている。
つぎののような予想がつくと思います。
旧市街で、一番高い建物は、教会の尖塔だった。
開発する新市街は、まわりとの調和を保っていた。
そして、
「一番、大切なことは、
そこに住んでいる人々が誇りと、
愛着を持っていることであろう」
「ハイデルベルクの大学は、ドイツ最古の歴史を持っている。
1386年に創立されたもので、その図書館は、
古文書、写本の類の世界的な蒐集で知られている」
「ハイデルベルク大学」(1978年)。

「大学は、ちょっとした広場があるだけで、何もなく、
校舎の建物が町の家々と溶け合って存在している感じである」
東山魁夷が青春の一時期を過ごしたドイツ。
そして、古都「ハイデルベルク」に、
愛着を持っていることが伝わってくる。
そのドイツからご褒美があった。
「思いがけなく西ドイツ大統領から、
功労大十字勲章を贈られた」1976年。
「私はドイツに功労があったわけではないが、
戦前、若いときに留学した国が、その後、
現在までの私の日本における仕事を見守っていてくれて、
その意義を認めてくれたことをありがたく思った」
ドイツもありがたく思う「緑のハイデルブルク」である。