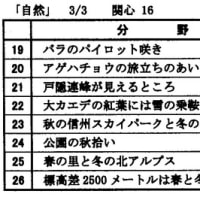「今度は、日本が100年前の恩返しをする番だ」
「日露戦争に勝つことができたのは、イギリスのおかげだ」
と、イギリス人は言うのだ。
なんのことか、さっぱりわからなかった。
なんで、「日露戦争」の勝利がイギリスのおかげなんだ?
なんで、イギリスに「恩返し」をしなければならないんだ?
イギリス人が言うのは、こうだ。
100年前の日露戦争のときに、イギリスから買いつけた軍艦と、
学んだ戦術を使って、日本はロシアに勝つことができた。
東郷平八郎は、世界一の海軍国、イギリスに留学して、
軍艦や兵器、軍事作戦などの軍事力を学んだ。そして、日本は、
「海軍はイギリス方式」とする、を国策として、
イギリスから戦術を導入し、軍艦、近代兵器を購入した。
連合艦隊の司令長官、東郷平八郎の乗った、
旗艦「三笠」をはじめ、軍艦のほとんどはイギリス製だ。
「三笠」。横須賀の「三笠記念艦」で。

確かに、イギリスのバローにあるヴィッカース造船所製であった。
日露戦争の「日本海海戦」で、東郷平八郎が指揮をとった場所は、
マストの手前にある四角の指令室ではなく、その上の艦橋だった。
イギリス人は、さらに続ける。
日露戦争の勝利を決定づけた「日本海海戦」で、
連合艦隊は、ロシアのバルチック艦隊を殲滅(せんめつ)した(1905年)。
有名な「トーゴー・ターン」は、イギリスで学んだT字作戦そのものだ。
そして、日本はロシアに勝つことができたじゃないか。
2013年8月のロシア旅行では、
「日露戦争」の相手国へ行くわけだから、
ロシア人の反応や、何らかの痕跡があれば、
知りたいと思っていた。
サンクト・ペテルブルクで、
バルチック艦隊の巡洋艦「オーロラ号」を見た。

「これが、日露戦争で戦ったバルチック艦隊か!」
「バルチック艦隊は壊滅状態だったが、生き延びたんだ!」
と、移動中のバスの中からしげしげと見た。
団体旅行を案内するロシア人のツアー・コンダクターは、
「オーロラ号が係留されています」
と、バスから言って、
夕刻から始まる、バレー「白鳥の湖」を観るために、
「オーロラ号」のわきを通り過ぎて、劇場へ急いだ。
バルチック艦隊38隻のうち、19隻を撃沈、7隻を捕獲し、
主力の戦艦、装甲巡洋艦を全滅させた。
連合艦隊は水雷艇3隻が沈没した。
バルチック艦隊は、戦死者が5千名近く、捕虜が6千名以上、
連合艦隊は、戦死者が117名、戦傷者が600名近くだった。
海戦の歴史上、まれにみる一方的な勝利だった。
「日本海海戦」の結果は、世界が注目していた。
日本が勝利した打電が飛びこんできたときには、
何かの間違いで、ロシアの勝利ではないか、と疑った。
「オーロラ号」は、撃沈や捕獲からフィリピンに逃がれた。
「オーロラ号」は、その後、ロシア革命でも活躍した。
1917年10月25日にエルミタージュの冬宮を砲撃して、
10月革命の火蓋を切った。今は記念艦として、
ネヴァ川河畔に保存されていた。
イギリス人は、まだある。
絹しか売るものがなかった貧乏な日本が、
日露戦争の戦費をまかなうために、
イギリスとアメリカから借金をした。
その金で、イギリスから軍艦や大砲などの近代兵器を買った。
ロシアが、バルチック艦隊を日本に差し向けたときに、
大国ロシアを相手では、アジアの小国、日本の勝ち目はない、
これで日本は、ロシアの植民地になるものと、世界は考えていた。
それで、日本が負ければ、回収ができなくなるから、危険な投資だった。
ここで、日本がイギリスであったら、どうしただろうか? 考えてみた。
もし、立場が逆で、イギリスがロシアに征服されそうだったら、
日本は、みなさんは、イギリスをこれほど助けるだろうか?
投資した金は無になる! 知らん顔をしていた方がいい?
機密である軍事力をイギリスに授けただろうか?
イギリスには、歴史の方向を見定める力があって、
帝政ロシアは滅びると思っていた?
イギリスは、日本をロシアの植民地にしたくなかった?
イギリス人には、「ノーブル・オブリゲーション」という、
「高貴な者には、義務が伴う」という精神が宿っていて、
日本の将来をほうっておけずに、起ちあがった?
イギリス人は、まだまだある。
「日英同盟」という軍事同盟を結んで(1902年~1912年)、
日本の外交政策はイギリスを軸として進められた。
「日英同盟」は、ロシアのアジア進出を封じるためのもので、
イギリスは積極的に日本に協力した。
バルチック艦隊が日本に向かう時には、
イギリスが支配していたスエズ運河を通らせなかった。
このために、武器、弾薬を満載した大型戦艦は、
アフリカ大陸を回ったから、喜望峰ルートの遠回りになった。
小型艦だけは、スエズ運河を通させたから、先行した大型戦艦とは、
フランス領のマダガスカル島で、合流しなければならなかった。
このために、バルチック艦隊は、ロシア領であったラトビアを、
1904年10月に出発してから、日本海に到着する1905年5月まで、7か月もかかった。
それに蒸気船だから、航海中には石炭を、
ところどころで、補給しなければならない。
だが、イギリスの植民地では、石炭を補給させなかった。
それに、水や食料品の補給もしなければならないが、
イギリスの植民地には、寄港させなかった。
石炭や水、食料品の補給で不便を強いられ、
スエズ運河を通れば、3か月ですむところを7か月もかかった航海で、
バルチック艦隊の乗組員は疲労し、戦意は低下した。
それに、イギリスは、最新の無線機を日本に提供して、
バルチック艦隊の戦力、武器、進路を日本に伝えた。
「日露戦争に勝つことができたのは、イギリスのおかげだ」
「イギリスから最新技術の軍艦や戦術のほかに戦費も調達して、
日本は国の興亡をかけて、大国ロシアと戦って、勝った」
「この勝利を機に、日本は近代国家の仲間入りをしたじゃないか」
「日本の歴史の大転換となった奇跡の勝利に、
イギリスの貢献がなかったら、日本は負け、
ロシアの植民地になっていた。そして、こんにちの日本はなかった」
「今度は、日本がイギリスを助けて、100年前の恩返しをする番だ」
という、イギリス人の最初の話につながってくる。
「日露戦争から100年たって、日本はIT(情報機器)や、
バイオテクノロジーのハイテク産業にうまく転換できた」
「そして日本は、こんにちの繁栄の道を歩むことができた」
「だが、イギリスは造船や製鉄の重工業から、
ハイテク産業への転換が遅れた」
「それに、政府による国営企業の運営は立ち行かなくなり、
労働争議が頻発し、国から活力が失われた」
「名車ロールス・ロイスは経営危機に陥り、
ドイツのBMWとフォルクスワーゲンに身売りされてしまった」
と、陽が沈むことがないといわれたイギリスの凋落ぶりを嘆く。
イギリス人が、100年前の「日露戦争」の話を持ち出して、
イギリスの貢献を言い、日本に「助け」を求めることは、
イギリスのジェントルマンにとっては、やりたくないことだろう。
屈辱的だが、イギリスはそんなことを言っていられる状況ではなかった。
1990年代のことで、私はイギリスに赴任していた。
イギリスの経済を立ち直らせ、復興させるために?
そして、自動車産業を旗頭にイギリスの経済が立ち直った。
雇用の機会も増えた。技術先進国、日本の援助の「おかげ」じゃないか。
私も貢献してきた?
さて、「日露戦争」だが、
蔑視(べっし)されていた有色人種が、
初めて白色人種を打ち負かした。
この日本の勝利は、多くの国を勇気づけた。
インドでは、のちに初代首相になったネルーは、
「日本の勝利に血が逆流するほど歓喜し、
インド独立のため命を捧げる決意をした」
中国では、「建国の父」と言われた孫文は、
「アジア人の欧州人に対する最初の勝利であった。
この日本の勝利は全アジアに影響を及ぼし、
アジアの民族は極めて大きな希望を抱くに至った」
トルコは長い間、ロシアとは宿敵だった。
ロシアは冬でも凍らない港を求めて、
黒海から地中海に出る航路を確保したいが、
それには、トルコの「ボスポラス海峡」を通るから、

ロシアとは長い間の仇敵で、トルコ艦隊が敗れたことがあった。
左のヨーロッパと、右のアジアとの架け橋は、「第1ボスポラス大橋」。
奥には「第2ボスポラス大橋」があり、さらに奥は「黒海」に連なる。
手前は「地中海」に連なる。
サンクト・ペテルブルクには、
トルコ戦争の勝利を記念した、「凱旋門」がある。

サンクト・ペテルブルクのメイン・ストリート、モスコフスキー通り。
トルコ人は、つぎのように言っていた。
「日本はバルチック艦隊を破って、ロシアに勝ったから、
『大国ロシアに日本が勝った!』と、トルコ人は拍手喝采をし、
大いに勇気づけられたのです」
「『日露戦争』が単なる戦争の勝利だけではなく、
日本がロシアの植民地になることを防いだ歴史の転換であった。
あわせて、中国、韓国への侵出による植民地化をくい止めた」
「アドミラル・トーゴー(東郷平八郎)が有名になって、
多くの子どもに、トーゴーという名前がつけられました」
フィンランドは、ロシアと国境を接して、
戦争を繰り返して敗れ、長い間、支配されていた。
「ロシアに勝ち目のない蜂起を挑むのか、
それとも、このまま国が消滅するのを待つか?」
フィンランド人は、つぎのように言っていた。
「ロシアのバルチック艦隊が日本へ向かったときに、
これで、日本は敗れて、ロシアの植民地になるものと思っていた。
ところが、日本は勝ったから、フィンランド人は喜び、
大いに勇気づけられました」
そして、日露戦争で帝政ロシアが弱体化して倒れた、
1917年に、フィンランドは独立宣言をした。
東郷平八郎を敬って、「東郷ビール」を作った。

フィンランドで作られたものの復刻版。横須賀の「三笠記念艦」で。
フィンランド独立の喜びの味? がする。
さて、「日露戦争」に対するロシア人の反応は?
サンクト・ペテルブルクのロシア人のツアー・コンダクターは、
「オーロラ号が係留されています」
とは言う。が、
「日露戦争」で戦った、
とは、説明がなかった。
「日露戦争」は、日本とロシアは当事者であり、
帝政ロシアは弱体化して、革命が起こる、
歴史が大転換するできごとなのに。
それに、「オーロラ号」と、
「ロシア革命」との関わりにも触れなかった。
ロシア人にとっては、「日露戦争」も、「ロシア革命」も、
乗り越えてきた「傷」。その「傷」から立ち直った。
もう、振り返ることはしない。明日に向かう。
「日露戦争に勝つことができたのは、イギリスのおかげだ」
と、イギリス人は言うのだ。
なんのことか、さっぱりわからなかった。
なんで、「日露戦争」の勝利がイギリスのおかげなんだ?
なんで、イギリスに「恩返し」をしなければならないんだ?
イギリス人が言うのは、こうだ。
100年前の日露戦争のときに、イギリスから買いつけた軍艦と、
学んだ戦術を使って、日本はロシアに勝つことができた。
東郷平八郎は、世界一の海軍国、イギリスに留学して、
軍艦や兵器、軍事作戦などの軍事力を学んだ。そして、日本は、
「海軍はイギリス方式」とする、を国策として、
イギリスから戦術を導入し、軍艦、近代兵器を購入した。
連合艦隊の司令長官、東郷平八郎の乗った、
旗艦「三笠」をはじめ、軍艦のほとんどはイギリス製だ。
「三笠」。横須賀の「三笠記念艦」で。

確かに、イギリスのバローにあるヴィッカース造船所製であった。
日露戦争の「日本海海戦」で、東郷平八郎が指揮をとった場所は、
マストの手前にある四角の指令室ではなく、その上の艦橋だった。
イギリス人は、さらに続ける。
日露戦争の勝利を決定づけた「日本海海戦」で、
連合艦隊は、ロシアのバルチック艦隊を殲滅(せんめつ)した(1905年)。
有名な「トーゴー・ターン」は、イギリスで学んだT字作戦そのものだ。
そして、日本はロシアに勝つことができたじゃないか。
2013年8月のロシア旅行では、
「日露戦争」の相手国へ行くわけだから、
ロシア人の反応や、何らかの痕跡があれば、
知りたいと思っていた。
サンクト・ペテルブルクで、
バルチック艦隊の巡洋艦「オーロラ号」を見た。

「これが、日露戦争で戦ったバルチック艦隊か!」
「バルチック艦隊は壊滅状態だったが、生き延びたんだ!」
と、移動中のバスの中からしげしげと見た。
団体旅行を案内するロシア人のツアー・コンダクターは、
「オーロラ号が係留されています」
と、バスから言って、
夕刻から始まる、バレー「白鳥の湖」を観るために、
「オーロラ号」のわきを通り過ぎて、劇場へ急いだ。
バルチック艦隊38隻のうち、19隻を撃沈、7隻を捕獲し、
主力の戦艦、装甲巡洋艦を全滅させた。
連合艦隊は水雷艇3隻が沈没した。
バルチック艦隊は、戦死者が5千名近く、捕虜が6千名以上、
連合艦隊は、戦死者が117名、戦傷者が600名近くだった。
海戦の歴史上、まれにみる一方的な勝利だった。
「日本海海戦」の結果は、世界が注目していた。
日本が勝利した打電が飛びこんできたときには、
何かの間違いで、ロシアの勝利ではないか、と疑った。
「オーロラ号」は、撃沈や捕獲からフィリピンに逃がれた。
「オーロラ号」は、その後、ロシア革命でも活躍した。
1917年10月25日にエルミタージュの冬宮を砲撃して、
10月革命の火蓋を切った。今は記念艦として、
ネヴァ川河畔に保存されていた。
イギリス人は、まだある。
絹しか売るものがなかった貧乏な日本が、
日露戦争の戦費をまかなうために、
イギリスとアメリカから借金をした。
その金で、イギリスから軍艦や大砲などの近代兵器を買った。
ロシアが、バルチック艦隊を日本に差し向けたときに、
大国ロシアを相手では、アジアの小国、日本の勝ち目はない、
これで日本は、ロシアの植民地になるものと、世界は考えていた。
それで、日本が負ければ、回収ができなくなるから、危険な投資だった。
ここで、日本がイギリスであったら、どうしただろうか? 考えてみた。
もし、立場が逆で、イギリスがロシアに征服されそうだったら、
日本は、みなさんは、イギリスをこれほど助けるだろうか?
投資した金は無になる! 知らん顔をしていた方がいい?
機密である軍事力をイギリスに授けただろうか?
イギリスには、歴史の方向を見定める力があって、
帝政ロシアは滅びると思っていた?
イギリスは、日本をロシアの植民地にしたくなかった?
イギリス人には、「ノーブル・オブリゲーション」という、
「高貴な者には、義務が伴う」という精神が宿っていて、
日本の将来をほうっておけずに、起ちあがった?
イギリス人は、まだまだある。
「日英同盟」という軍事同盟を結んで(1902年~1912年)、
日本の外交政策はイギリスを軸として進められた。
「日英同盟」は、ロシアのアジア進出を封じるためのもので、
イギリスは積極的に日本に協力した。
バルチック艦隊が日本に向かう時には、
イギリスが支配していたスエズ運河を通らせなかった。
このために、武器、弾薬を満載した大型戦艦は、
アフリカ大陸を回ったから、喜望峰ルートの遠回りになった。
小型艦だけは、スエズ運河を通させたから、先行した大型戦艦とは、
フランス領のマダガスカル島で、合流しなければならなかった。
このために、バルチック艦隊は、ロシア領であったラトビアを、
1904年10月に出発してから、日本海に到着する1905年5月まで、7か月もかかった。
それに蒸気船だから、航海中には石炭を、
ところどころで、補給しなければならない。
だが、イギリスの植民地では、石炭を補給させなかった。
それに、水や食料品の補給もしなければならないが、
イギリスの植民地には、寄港させなかった。
石炭や水、食料品の補給で不便を強いられ、
スエズ運河を通れば、3か月ですむところを7か月もかかった航海で、
バルチック艦隊の乗組員は疲労し、戦意は低下した。
それに、イギリスは、最新の無線機を日本に提供して、
バルチック艦隊の戦力、武器、進路を日本に伝えた。
「日露戦争に勝つことができたのは、イギリスのおかげだ」
「イギリスから最新技術の軍艦や戦術のほかに戦費も調達して、
日本は国の興亡をかけて、大国ロシアと戦って、勝った」
「この勝利を機に、日本は近代国家の仲間入りをしたじゃないか」
「日本の歴史の大転換となった奇跡の勝利に、
イギリスの貢献がなかったら、日本は負け、
ロシアの植民地になっていた。そして、こんにちの日本はなかった」
「今度は、日本がイギリスを助けて、100年前の恩返しをする番だ」
という、イギリス人の最初の話につながってくる。
「日露戦争から100年たって、日本はIT(情報機器)や、
バイオテクノロジーのハイテク産業にうまく転換できた」
「そして日本は、こんにちの繁栄の道を歩むことができた」
「だが、イギリスは造船や製鉄の重工業から、
ハイテク産業への転換が遅れた」
「それに、政府による国営企業の運営は立ち行かなくなり、
労働争議が頻発し、国から活力が失われた」
「名車ロールス・ロイスは経営危機に陥り、
ドイツのBMWとフォルクスワーゲンに身売りされてしまった」
と、陽が沈むことがないといわれたイギリスの凋落ぶりを嘆く。
イギリス人が、100年前の「日露戦争」の話を持ち出して、
イギリスの貢献を言い、日本に「助け」を求めることは、
イギリスのジェントルマンにとっては、やりたくないことだろう。
屈辱的だが、イギリスはそんなことを言っていられる状況ではなかった。
1990年代のことで、私はイギリスに赴任していた。
イギリスの経済を立ち直らせ、復興させるために?
そして、自動車産業を旗頭にイギリスの経済が立ち直った。
雇用の機会も増えた。技術先進国、日本の援助の「おかげ」じゃないか。
私も貢献してきた?
さて、「日露戦争」だが、
蔑視(べっし)されていた有色人種が、
初めて白色人種を打ち負かした。
この日本の勝利は、多くの国を勇気づけた。
インドでは、のちに初代首相になったネルーは、
「日本の勝利に血が逆流するほど歓喜し、
インド独立のため命を捧げる決意をした」
中国では、「建国の父」と言われた孫文は、
「アジア人の欧州人に対する最初の勝利であった。
この日本の勝利は全アジアに影響を及ぼし、
アジアの民族は極めて大きな希望を抱くに至った」
トルコは長い間、ロシアとは宿敵だった。
ロシアは冬でも凍らない港を求めて、
黒海から地中海に出る航路を確保したいが、
それには、トルコの「ボスポラス海峡」を通るから、

ロシアとは長い間の仇敵で、トルコ艦隊が敗れたことがあった。
左のヨーロッパと、右のアジアとの架け橋は、「第1ボスポラス大橋」。
奥には「第2ボスポラス大橋」があり、さらに奥は「黒海」に連なる。
手前は「地中海」に連なる。
サンクト・ペテルブルクには、
トルコ戦争の勝利を記念した、「凱旋門」がある。

サンクト・ペテルブルクのメイン・ストリート、モスコフスキー通り。
トルコ人は、つぎのように言っていた。
「日本はバルチック艦隊を破って、ロシアに勝ったから、
『大国ロシアに日本が勝った!』と、トルコ人は拍手喝采をし、
大いに勇気づけられたのです」
「『日露戦争』が単なる戦争の勝利だけではなく、
日本がロシアの植民地になることを防いだ歴史の転換であった。
あわせて、中国、韓国への侵出による植民地化をくい止めた」
「アドミラル・トーゴー(東郷平八郎)が有名になって、
多くの子どもに、トーゴーという名前がつけられました」
フィンランドは、ロシアと国境を接して、
戦争を繰り返して敗れ、長い間、支配されていた。
「ロシアに勝ち目のない蜂起を挑むのか、
それとも、このまま国が消滅するのを待つか?」
フィンランド人は、つぎのように言っていた。
「ロシアのバルチック艦隊が日本へ向かったときに、
これで、日本は敗れて、ロシアの植民地になるものと思っていた。
ところが、日本は勝ったから、フィンランド人は喜び、
大いに勇気づけられました」
そして、日露戦争で帝政ロシアが弱体化して倒れた、
1917年に、フィンランドは独立宣言をした。
東郷平八郎を敬って、「東郷ビール」を作った。

フィンランドで作られたものの復刻版。横須賀の「三笠記念艦」で。
フィンランド独立の喜びの味? がする。
さて、「日露戦争」に対するロシア人の反応は?
サンクト・ペテルブルクのロシア人のツアー・コンダクターは、
「オーロラ号が係留されています」
とは言う。が、
「日露戦争」で戦った、
とは、説明がなかった。
「日露戦争」は、日本とロシアは当事者であり、
帝政ロシアは弱体化して、革命が起こる、
歴史が大転換するできごとなのに。
それに、「オーロラ号」と、
「ロシア革命」との関わりにも触れなかった。
ロシア人にとっては、「日露戦争」も、「ロシア革命」も、
乗り越えてきた「傷」。その「傷」から立ち直った。
もう、振り返ることはしない。明日に向かう。