ときどき、注文した覚えのない「商品」の案内がFAXで来ます。
そのなかで多いのが「設計ソフト」の売込み。
先日届いたのは、「長期優良住宅制度」と「省エネエコポイント制度」対応の「設計ソフト」の発売案内。
下はそのキャッチコピー。商品名は消してあります。

いったい、こういうソフトを買って、設計者は「何をする」のだろうか、と考えてしまいます。いったい、設計者の職分とは何か、ということです。
そしてまた、ここにはいくつも問題があります。
まず、申請用の書類が審査され、「お墨付き」をもらえれば、「長期優良住宅」が本当にできあがるのか?本当に「省エネ」になるのか?
「制度の規定する条件」をクリアすれば「長期優良住宅」、つまり、寿命の長い建物になる、という保証はどこにあるのでしょうか?
そもそも、「制度の規定している長期優良住宅の条件」自体の信憑性も、問われたことがありません。
簡単に言えば、なぜ最近の住居が短命になったか、なぜ、かつての住居が長命であったか、その分析は行なわれた形跡がないにもかかわらず「条件」が設定されているのです。
そしてさらに、「長期優良住宅」として認定された建物が、もしも「長期優良」でない事態に至ったとき、つまり寿命が短かったり地震で損壊したりしたならば、その「責任」はどうなるのでしょう?例の倒壊した長期優良住宅の実物大実験のようなことは、現実にも十分に起き得るのです。
この後者の問題は、「長期優良住宅」だけの問題ではなく、現行の法令規定そのものの根本的に孕む「問題」にほかなりません。
何度も書いてきたように、そのような事態が生じると、これまでは、それは想定外であったとして「規定条項」を改変すること:これを「法の改訂」と称しています:で過ごしてきて、その「責任」は一切とっていません。
これが一般人のしたことならば、かならずその責が問われます。責任を問われないで済んでいるのは、「法令は何よりも上位に立つ」と(勝手に)見なしているからに過ぎないのです。
しかし、法令の内容もまた「人為」であることに変りはない。それゆえ、「法令は何よりも上位に立つ」とする以上、その「人為」は、より厳しく問われなければならないのですが、そうではない。
最近のこのような「動き」は、「耐震診断⇒耐震補強」と同様の「霊感商法の奨め」のように、私には見えます*。
* http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/da1ac6204ccfee6d9671035bab31678a
簡単に言えば、数字に弱い一般の人びとを、数字を弄して欺くのです。それに「協力する」ことで「経済」が繁栄する、などと喜んでいてよいのでしょうか。
こういう「動き」の背後にあるのは、「建物づくりの現場」を離れて机上でご都合主義的、便宜的発想でつくられてしまった現行「建築基準法」の諸規定にほかなりません。
簡単に言えば、「建物づくりの現場の発想」からはまったく乖離した《理論・考え方》が、「実作の思考」を押し潰してしまっているのです。
これは、普通の人びとの生活にとって「最大の禍」なのであり、それはすなわち、社会に対しての「最大の禍」にもなっているのです。
ところで、こういった類の設計ソフトが巷に溢れているようです。そしてそれをつかって設計することを称してCADと言う。
CADとは、Computer Aided Design の略のはずです。
しかし、上記のようなソフトは、ソフトが設計者に指示しているようなもの。設計者は、無思慮にソフトの指示に従うだけ。
CADが流行りだしたころ、ある設計者が、もう製図板も製図者も要らない、オペレーターが居ればいい、と語っていたことを思い出します。
註 昔聞いた話。
自動車製造工場で、塗装ロボットが導入されたとき、二つの相反する反応があった。
一つは、もう塗装の熟練工は不要だ、という判断。
もう一つは、熟練工の塗装工程を相変わらず維持するという判断。
前者は、日本の自動車工場。
後者はドイツ。熟練工の養成まで行なった。
なぜドイツはそうしたか。
塗装ロボットは、熟練工の「作業工程」を倣ってつくられるからです。
日本がその「事実」に気付いたのは、大分経ってからだった・・・。
「設計ソフト」が普及した結果、若い人たちを悩ましているのは、建築士試験です。
なぜなら、建築士試験は相変わらず手描きの「設計製図」が必修だからです。
日ごろ、ソフトによって設計図を作成しているため、自分の手で描いたことがない。
たとえば、駐車スペース。ソフトは縮尺に応じて車まで描いてくれる。
手で描くとなれば、車の一般的大きさを知っていなければならないのですが、いつも、ソフトが「適切に」描いてくれているため、大きさについての「認識」がまったくない。
樹木なども同じ。適当に描いてくれるから、自ら針葉樹、広葉樹・・・など樹木をまともに観察する習慣もない。
まして、建物が存在する基本:人や社会:についての「観察」など、問題外。
要するに、建物の設計にかかわる「知識」、知っていなければならない「素養」、そのすべてが、ソフト任せになっているということ。
このような建築界の状況もまた、人びとが暮す環境にとって「最大の禍」である、と私は思います。
これほどまでにソフトが「主導権」を握ってしまうと、ソフトに組込まれているもの以外、今後つくられない、と言っても過言ではないからです。先に「文化財」の「耐震診断・耐震補強」について触れたのと同じことが、どこでも起きているのです*。
* http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f
昨3月15日付の毎日新聞朝刊のコラムに、注目すべき、そして参考にすべき記事が載っていました。
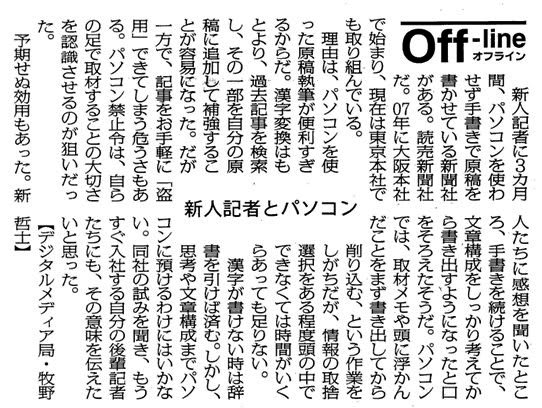
私は、CADソフトを使うことを全否定しているわけではありません。
ソフトに頼るまえに、「素養」の培養・育成が必要だと思うのです。自分の頭脳で観て考える訓練です。
第一、作業を簡易化・簡略化して、生まれた時間を何に使っているのでしょう?
先の記事に応じれば、私は、設計に係わる者は、パソコンに拠る前に、手描きの期間がかなり必要のように思います。
そのなかで多いのが「設計ソフト」の売込み。
先日届いたのは、「長期優良住宅制度」と「省エネエコポイント制度」対応の「設計ソフト」の発売案内。
下はそのキャッチコピー。商品名は消してあります。

いったい、こういうソフトを買って、設計者は「何をする」のだろうか、と考えてしまいます。いったい、設計者の職分とは何か、ということです。
そしてまた、ここにはいくつも問題があります。
まず、申請用の書類が審査され、「お墨付き」をもらえれば、「長期優良住宅」が本当にできあがるのか?本当に「省エネ」になるのか?
「制度の規定する条件」をクリアすれば「長期優良住宅」、つまり、寿命の長い建物になる、という保証はどこにあるのでしょうか?
そもそも、「制度の規定している長期優良住宅の条件」自体の信憑性も、問われたことがありません。
簡単に言えば、なぜ最近の住居が短命になったか、なぜ、かつての住居が長命であったか、その分析は行なわれた形跡がないにもかかわらず「条件」が設定されているのです。
そしてさらに、「長期優良住宅」として認定された建物が、もしも「長期優良」でない事態に至ったとき、つまり寿命が短かったり地震で損壊したりしたならば、その「責任」はどうなるのでしょう?例の倒壊した長期優良住宅の実物大実験のようなことは、現実にも十分に起き得るのです。
この後者の問題は、「長期優良住宅」だけの問題ではなく、現行の法令規定そのものの根本的に孕む「問題」にほかなりません。
何度も書いてきたように、そのような事態が生じると、これまでは、それは想定外であったとして「規定条項」を改変すること:これを「法の改訂」と称しています:で過ごしてきて、その「責任」は一切とっていません。
これが一般人のしたことならば、かならずその責が問われます。責任を問われないで済んでいるのは、「法令は何よりも上位に立つ」と(勝手に)見なしているからに過ぎないのです。
しかし、法令の内容もまた「人為」であることに変りはない。それゆえ、「法令は何よりも上位に立つ」とする以上、その「人為」は、より厳しく問われなければならないのですが、そうではない。
最近のこのような「動き」は、「耐震診断⇒耐震補強」と同様の「霊感商法の奨め」のように、私には見えます*。
* http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/da1ac6204ccfee6d9671035bab31678a
簡単に言えば、数字に弱い一般の人びとを、数字を弄して欺くのです。それに「協力する」ことで「経済」が繁栄する、などと喜んでいてよいのでしょうか。
こういう「動き」の背後にあるのは、「建物づくりの現場」を離れて机上でご都合主義的、便宜的発想でつくられてしまった現行「建築基準法」の諸規定にほかなりません。
簡単に言えば、「建物づくりの現場の発想」からはまったく乖離した《理論・考え方》が、「実作の思考」を押し潰してしまっているのです。
これは、普通の人びとの生活にとって「最大の禍」なのであり、それはすなわち、社会に対しての「最大の禍」にもなっているのです。
ところで、こういった類の設計ソフトが巷に溢れているようです。そしてそれをつかって設計することを称してCADと言う。
CADとは、Computer Aided Design の略のはずです。
しかし、上記のようなソフトは、ソフトが設計者に指示しているようなもの。設計者は、無思慮にソフトの指示に従うだけ。
CADが流行りだしたころ、ある設計者が、もう製図板も製図者も要らない、オペレーターが居ればいい、と語っていたことを思い出します。
註 昔聞いた話。
自動車製造工場で、塗装ロボットが導入されたとき、二つの相反する反応があった。
一つは、もう塗装の熟練工は不要だ、という判断。
もう一つは、熟練工の塗装工程を相変わらず維持するという判断。
前者は、日本の自動車工場。
後者はドイツ。熟練工の養成まで行なった。
なぜドイツはそうしたか。
塗装ロボットは、熟練工の「作業工程」を倣ってつくられるからです。
日本がその「事実」に気付いたのは、大分経ってからだった・・・。
「設計ソフト」が普及した結果、若い人たちを悩ましているのは、建築士試験です。
なぜなら、建築士試験は相変わらず手描きの「設計製図」が必修だからです。
日ごろ、ソフトによって設計図を作成しているため、自分の手で描いたことがない。
たとえば、駐車スペース。ソフトは縮尺に応じて車まで描いてくれる。
手で描くとなれば、車の一般的大きさを知っていなければならないのですが、いつも、ソフトが「適切に」描いてくれているため、大きさについての「認識」がまったくない。
樹木なども同じ。適当に描いてくれるから、自ら針葉樹、広葉樹・・・など樹木をまともに観察する習慣もない。
まして、建物が存在する基本:人や社会:についての「観察」など、問題外。
要するに、建物の設計にかかわる「知識」、知っていなければならない「素養」、そのすべてが、ソフト任せになっているということ。
このような建築界の状況もまた、人びとが暮す環境にとって「最大の禍」である、と私は思います。
これほどまでにソフトが「主導権」を握ってしまうと、ソフトに組込まれているもの以外、今後つくられない、と言っても過言ではないからです。先に「文化財」の「耐震診断・耐震補強」について触れたのと同じことが、どこでも起きているのです*。
* http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f
昨3月15日付の毎日新聞朝刊のコラムに、注目すべき、そして参考にすべき記事が載っていました。
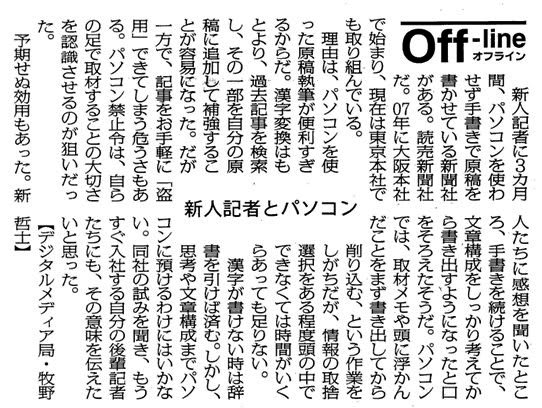
私は、CADソフトを使うことを全否定しているわけではありません。
ソフトに頼るまえに、「素養」の培養・育成が必要だと思うのです。自分の頭脳で観て考える訓練です。
第一、作業を簡易化・簡略化して、生まれた時間を何に使っているのでしょう?
先の記事に応じれば、私は、設計に係わる者は、パソコンに拠る前に、手描きの期間がかなり必要のように思います。















