役付取締役を定款に定めるのは、ある意味形式的な理由があるのではないか? とワタシは考えています。
定款には、株主総会や取締役会の招集権者、議長を定めます。会社法の原則だと、議長や取締役会の招集権者はだれか一人に決まるワケではないし、株主総会の招集権者も代表取締役が複数人いれば同じです。
そこで、通常、定款にはこれらを行うヒトを社長と決めています。そして、社長が不在等の場合には、その代行順位を取締役会で予め決めることにするわけです。こうすると、議長とか招集権者が一人のヒトに決まるので、わざわざ議長を選出する。。。などどいう手間が省けてベンリなんです。
でも、そこに突然法律上の資格ではない「社長」が登場すると、「社長ってダレッ!?」ってことになりますよね。そこで、「社長というのは取締役の中から取締役会で選ばれたヒトをいうんだよ」と定義を置いておくと、「ナルホド~、そういうヒトね♪」と納得できると思うんです。
さらに、任意的な資格である「社長」の選定について規定を置くのなら、他の役付取締役についてだって定款に規定しなくちゃオカシイ(整合性が取れない)ということで、役付取締役全般について定款に定めているのでは? とワタシは思ってマス。
異論もあるところだと思いますので、「それはチガウ」というご意見もお寄せくださいね(笑)。
さて、そこで社長に絞って、定款規定のしかたを考えてみましょう!
パターン①「取締役会の決議によって社長1名を選定する。社長は当会社を代表する。」
パターン②「取締役会の決議によって代表取締役1名を選定する。代表取締役は社長とする。」
パターン③「取締役会の決議によって代表取締役を選定し、うち1名を社長と定める。」
パターン④「①取締役会の決議によって代表取締役を選定する。②取締役会の決議によって社長1名を定める。」
大きく分けると、定款での定め方はダイタイこんな↑感じです。
パターン①と②は、社長=代表取締役で、代表取締役を選ぶのか、社長を選ぶのかの違い。パターン③は、社長に選定されるためには代表取締役の前提資格が必要というもの。パターン④は、社長と代表取締役はそれぞれ別々に決める、つまり、代表取締役じゃないヒトを社長にすることもできる、という内容デス。
取締役が改選されますと、その定時株主総会の直後に取締役会を開いて代表取締役を選定しなおすので、株式会社であれば定期的にその決議をすることになります。が、定款の定め方によって、決議の内容も若干異なってくるんです。
どんな違いなのか? については、また来週~ >^_^<
定款には、株主総会や取締役会の招集権者、議長を定めます。会社法の原則だと、議長や取締役会の招集権者はだれか一人に決まるワケではないし、株主総会の招集権者も代表取締役が複数人いれば同じです。
そこで、通常、定款にはこれらを行うヒトを社長と決めています。そして、社長が不在等の場合には、その代行順位を取締役会で予め決めることにするわけです。こうすると、議長とか招集権者が一人のヒトに決まるので、わざわざ議長を選出する。。。などどいう手間が省けてベンリなんです。
でも、そこに突然法律上の資格ではない「社長」が登場すると、「社長ってダレッ!?」ってことになりますよね。そこで、「社長というのは取締役の中から取締役会で選ばれたヒトをいうんだよ」と定義を置いておくと、「ナルホド~、そういうヒトね♪」と納得できると思うんです。
さらに、任意的な資格である「社長」の選定について規定を置くのなら、他の役付取締役についてだって定款に規定しなくちゃオカシイ(整合性が取れない)ということで、役付取締役全般について定款に定めているのでは? とワタシは思ってマス。
異論もあるところだと思いますので、「それはチガウ」というご意見もお寄せくださいね(笑)。
さて、そこで社長に絞って、定款規定のしかたを考えてみましょう!
パターン①「取締役会の決議によって社長1名を選定する。社長は当会社を代表する。」
パターン②「取締役会の決議によって代表取締役1名を選定する。代表取締役は社長とする。」
パターン③「取締役会の決議によって代表取締役を選定し、うち1名を社長と定める。」
パターン④「①取締役会の決議によって代表取締役を選定する。②取締役会の決議によって社長1名を定める。」
大きく分けると、定款での定め方はダイタイこんな↑感じです。
パターン①と②は、社長=代表取締役で、代表取締役を選ぶのか、社長を選ぶのかの違い。パターン③は、社長に選定されるためには代表取締役の前提資格が必要というもの。パターン④は、社長と代表取締役はそれぞれ別々に決める、つまり、代表取締役じゃないヒトを社長にすることもできる、という内容デス。
取締役が改選されますと、その定時株主総会の直後に取締役会を開いて代表取締役を選定しなおすので、株式会社であれば定期的にその決議をすることになります。が、定款の定め方によって、決議の内容も若干異なってくるんです。
どんな違いなのか? については、また来週~ >^_^<










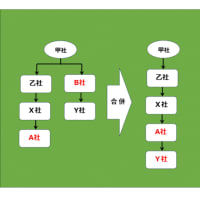
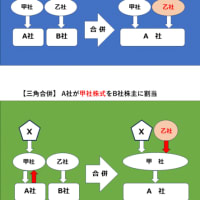
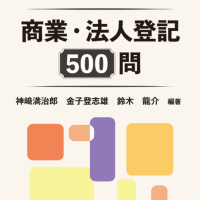
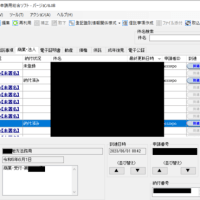
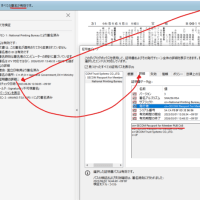
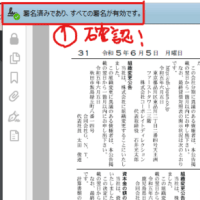










ある有名な予備校講師の先生が書いた司法書士試験の記述式問題の解答では、定款に補欠規定に関する定めがないにもかかわらず、「選任後2年以内に終了する最終事業年度の株主総会終了まで」となっています。
司法書士でもある作者がこんな重大な誤りをするのはおかしいと思うのですが、私の理解不足なのでしょうか。ご教示頂きたくお願い申し上げます。
ご質問の件、申し訳ないのですが、イマイチ事例が把握できておりません。ですので、補欠役員の任期に関する一般的なお話しをしますね。
まず、補欠役員の任期は、株主総会で補欠として選任された時点から起算されることになっています。
例えば、法定任期を採用している会社の場合、平成20年6月の定時総会で選任された補欠取締役が実際に補欠として就任した場合は、平成21年3月に就任しようが、平成22年3月に就任しようが、結果は同じで平成22年6月の定時総会で任期満了します。
ただし、補欠取締役の任期は前任者の任期満了までとする旨の定款規定がある場合は、被補欠者の任期が平成22年6月の定時総会より前に満了するときは、補欠取締役の任期も前任者の任期と同じになります。
。。。と、こんなカンジなんですが、どうでしょうか?
実際は、選任決議の有効期間とも絡みますので、整理して考えてみると良いと思います。
会社法施行規則96条3項の読み方ですが、補欠取締役についての定款で別段の定めがない以上、平成20年6月選任の補欠取締役は、実際の就任の有無にかかわらず、平成21年6月の定時株主総会の開始時で任期満了するということではないのですか。根本的に私の条文の読み方が間違っているのでしょうか。
お手数をおかけして申し訳ありません。
ご質問の趣旨が分かりました(^_^.)
選任決議の有効期間と任期を混同されているのではないでしょうかね?
平成20年6月の定時総会で補欠監査役を選任した場合、その決議が効力を有する期間は平成21年6月の定時総会開始の時まで、というのが施行規則第93条第3項の規定です。
例えば、法定任期の取締役Aが平成20年6月の定時総会で選任され、その総会でAの補欠取締役甲も選任されたとしましょうか。
この場合、Aが平成21年3月に辞任すると、補欠取締役甲はその時点で取締役に就任しますが、任期は通常の法定任期、つまり、平成22年6月の定時総会で任期満了します(選任時から起算)。
一方、Aが平成21年7月に辞任した場合は、補欠選任の効力が平成21年6月の定時総会開始時に失効していますから、甲はAの補欠として取締役に就任できないという結果になります。
施行規則でいう定款の別段の定めとは、選任の効力をもっと長くする、あるいは短くするという意味で、補欠就任した場合の任期とは別物ですね。
選任の効力を法定どおりとした場合、毎年補欠取締役を選任しなければならず面倒なので、取締役の改選と合わせられるよう、定款に別段の定めができる、ということだと思います。
近々、このヘンのことを記事にしようと思っていますので、よろしければまた覗いてみてください。
今後ともよろしくお願いいたします♪
またこれで勉強を続けられそうです。ありがとうございました。お手を煩わせて申し訳ありませんでした。