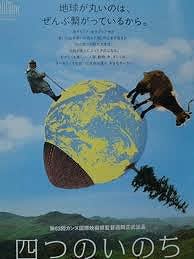『四つのいのち』を渋谷のイメージ・シアターで見てきました。
(1)この映画の冒頭は、黒くて丸い塚のようなものに人が登って、スコップの形をしたものでペタペタ叩いている場面です。何をしているのかさっぱり分からないのですが、その塚のようなものから盛んに煙が噴き出しているので、あるいは陶器を製作しているのかなと思っていると、場面が変わって、年老いた牧夫が山羊を放牧させているシーンとなります。
山の斜面の草地ではたくさんの山羊が草を食べていますが、その間も、上のペタペタという音が聞こえますから、冒頭の場面は何かしら意味があって、あとで再度登場するのではと思わせます。
この山羊の放牧については、よく見ると、牧夫がコントロールするというよりも、数頭の犬が山羊の動きを監視していて、群れ全体を統率しているようです。
老人の方は絶えず咳き込んでいて、放牧が終わると教会に行っては、山羊の乳と引き換えに、そこの掃除人から煎じ薬をもらっています(といっても、教会にたまっているチリ・ホコリをかき集めたもののようで、にもかかわらずそれを飲むと牧夫の咳が治まるのです)。
ある時、老人はその薬を草地に落としてしまい、飲まずにいたところ、咳が酷くなってついには亡くなってしまうのです。

その一方で、山羊の小屋では子山羊が生まれます(この子山羊も、仲間の群れから一匹だけ逸れてしまい、探し回った挙句、大きな樅の木の根元で力尽きてしまうのですが)。
といったところまで進んでくると、この映画は一体何なのか、という疑問が生まれざるを得ません。
どうして牧夫の老人以外の人間が明示的に登場しないのか、いったい時代設定はいつなのか、このあと物語はどんなふうに展開するのか、そもそも「四つのいのち」とは何を指しているのか、などなど。
そして、この映画は、こんな風に台詞なしで最後まで進行するのだろうし、「四つのいのち」のうちの少なくとも二つは牧夫と山羊だろうが(犬の可能性も排除できないものの、大写しにならないので違うのではなかろうか)、他の二つはこれから登場するのだろう、などと自分で自分に言い聞かせつつ見続けることになります。
結局、後の二つは、大きな樅の木と、冒頭の塚(ここで炭を焼いていたのです)であることがわかってきます。「人間、動物、木、木炭という四つの命」の移ろいが描かれているといえるのかもしれません。
ですが、4番目の炭は無機物ではないでしょうか、となると「四つのいのち」といえるのでしょうか?原題は「Le Quattro Volte」(英語タイトルが「The Four Times」)ですから、「いのち」というよりも、むしろ、4つの「時」の移ろいというべきではないのか、などと思えてきます。
それはともかく、本作品において興味をひかれるのは次のような点です。
イ)まったく台詞がないままに最後まで進むものの(あるいはだからこそ)、かえって次はどうなるのだろうという興味から、退屈することなく見終わることができます。
ロ)劇場用パンフレットの解説からすると、時代は現代であり、舞台は南イタリアのカラブリア州の田舎にある小さな村とのことですが、よくもまあこんな現代文明から見放されたような場所があったものだと驚いてしまいます。
アンデスのマチュピチュのように、山の上に設けられた村であり、電気は通っているものの、夜になると数本の街灯しか点いておらず、また下からかけ上がってくる軽トラックも酷く時代がかっていますし、カトリックの古い祭礼が律儀に執り行われているようでもあります(イスラエルのエルサレム市のヴィア・ドロローサで行われるような行事が行われたりします)。
ハ)「四つのいのち」のうちの大きな樅の木は切り倒されて、村に運ばれてお祭りに使われますが、村まで運ぶ様子は、まるで諏訪大社の御柱祭を見ているような印象です。

ニ)最後のシーンで生産される炭は、実際にもこの村の各家に配られているのですが、今時このような燃料を使っている場所が他にもあるのでしょうか?
(2)この映画を見ていたら、なんとなく昨年末に見た『うつし世の静寂(しじま)に』が思い出されました。
本作品が台詞が一言もないところから、『うつし世の静寂に』のようなドキュメンタリー風の作品と感じられたのかもしれません。
あるいは、本作品が、文明の発達したヨーロッパの中に見出される非現代的なものを大きく取り上げているのと同じように、『うつし世の静寂に』は、頗る現代的な首都圏の中に取り残されて存続する前時代的なものを取り上げているためなのでしょう。
そんなところから、『ブンミおじさんの森』とのつながりも見えてくるかもしれません。というのも、ブンミおじさんの息子は、9年ほど前に失踪してしまうのですが、ブンミおじさんが自分の死期を悟ると、猿の精霊の姿になって表れるのですが、あるいは本作品において、老いた牧夫が死ぬとその代わりのように子山羊が生まれてくるのとパラレルに思えてきます。
全体として、本作品は、この『ブンミおじさんの森』と同じように、自然と随分親和的なのです。
(3)福本次郎氏は、「一切の説明やセリフ、音楽を排し長まわしを多用したドキュメンタリーのような手法は、時に退屈を覚えるほど変化に乏しい。しかし、映像と自然の音のみで表現しようとする試みはイマジネーションを刺激する」、「特殊効果でもCGでもないが、「そこにある何気ない風景」を装ったすさまじいまでの作り込みは、まさに“今までに見たことがない映像”。新鮮な驚きと強烈なインパクトに瞬きするのを忘れてしまった」として70点もの高得点を付けています。
★★★☆☆
(1)この映画の冒頭は、黒くて丸い塚のようなものに人が登って、スコップの形をしたものでペタペタ叩いている場面です。何をしているのかさっぱり分からないのですが、その塚のようなものから盛んに煙が噴き出しているので、あるいは陶器を製作しているのかなと思っていると、場面が変わって、年老いた牧夫が山羊を放牧させているシーンとなります。
山の斜面の草地ではたくさんの山羊が草を食べていますが、その間も、上のペタペタという音が聞こえますから、冒頭の場面は何かしら意味があって、あとで再度登場するのではと思わせます。
この山羊の放牧については、よく見ると、牧夫がコントロールするというよりも、数頭の犬が山羊の動きを監視していて、群れ全体を統率しているようです。
老人の方は絶えず咳き込んでいて、放牧が終わると教会に行っては、山羊の乳と引き換えに、そこの掃除人から煎じ薬をもらっています(といっても、教会にたまっているチリ・ホコリをかき集めたもののようで、にもかかわらずそれを飲むと牧夫の咳が治まるのです)。
ある時、老人はその薬を草地に落としてしまい、飲まずにいたところ、咳が酷くなってついには亡くなってしまうのです。

その一方で、山羊の小屋では子山羊が生まれます(この子山羊も、仲間の群れから一匹だけ逸れてしまい、探し回った挙句、大きな樅の木の根元で力尽きてしまうのですが)。
といったところまで進んでくると、この映画は一体何なのか、という疑問が生まれざるを得ません。
どうして牧夫の老人以外の人間が明示的に登場しないのか、いったい時代設定はいつなのか、このあと物語はどんなふうに展開するのか、そもそも「四つのいのち」とは何を指しているのか、などなど。
そして、この映画は、こんな風に台詞なしで最後まで進行するのだろうし、「四つのいのち」のうちの少なくとも二つは牧夫と山羊だろうが(犬の可能性も排除できないものの、大写しにならないので違うのではなかろうか)、他の二つはこれから登場するのだろう、などと自分で自分に言い聞かせつつ見続けることになります。
結局、後の二つは、大きな樅の木と、冒頭の塚(ここで炭を焼いていたのです)であることがわかってきます。「人間、動物、木、木炭という四つの命」の移ろいが描かれているといえるのかもしれません。
ですが、4番目の炭は無機物ではないでしょうか、となると「四つのいのち」といえるのでしょうか?原題は「Le Quattro Volte」(英語タイトルが「The Four Times」)ですから、「いのち」というよりも、むしろ、4つの「時」の移ろいというべきではないのか、などと思えてきます。
それはともかく、本作品において興味をひかれるのは次のような点です。
イ)まったく台詞がないままに最後まで進むものの(あるいはだからこそ)、かえって次はどうなるのだろうという興味から、退屈することなく見終わることができます。
ロ)劇場用パンフレットの解説からすると、時代は現代であり、舞台は南イタリアのカラブリア州の田舎にある小さな村とのことですが、よくもまあこんな現代文明から見放されたような場所があったものだと驚いてしまいます。
アンデスのマチュピチュのように、山の上に設けられた村であり、電気は通っているものの、夜になると数本の街灯しか点いておらず、また下からかけ上がってくる軽トラックも酷く時代がかっていますし、カトリックの古い祭礼が律儀に執り行われているようでもあります(イスラエルのエルサレム市のヴィア・ドロローサで行われるような行事が行われたりします)。
ハ)「四つのいのち」のうちの大きな樅の木は切り倒されて、村に運ばれてお祭りに使われますが、村まで運ぶ様子は、まるで諏訪大社の御柱祭を見ているような印象です。

ニ)最後のシーンで生産される炭は、実際にもこの村の各家に配られているのですが、今時このような燃料を使っている場所が他にもあるのでしょうか?
(2)この映画を見ていたら、なんとなく昨年末に見た『うつし世の静寂(しじま)に』が思い出されました。
本作品が台詞が一言もないところから、『うつし世の静寂に』のようなドキュメンタリー風の作品と感じられたのかもしれません。
あるいは、本作品が、文明の発達したヨーロッパの中に見出される非現代的なものを大きく取り上げているのと同じように、『うつし世の静寂に』は、頗る現代的な首都圏の中に取り残されて存続する前時代的なものを取り上げているためなのでしょう。
そんなところから、『ブンミおじさんの森』とのつながりも見えてくるかもしれません。というのも、ブンミおじさんの息子は、9年ほど前に失踪してしまうのですが、ブンミおじさんが自分の死期を悟ると、猿の精霊の姿になって表れるのですが、あるいは本作品において、老いた牧夫が死ぬとその代わりのように子山羊が生まれてくるのとパラレルに思えてきます。
全体として、本作品は、この『ブンミおじさんの森』と同じように、自然と随分親和的なのです。
(3)福本次郎氏は、「一切の説明やセリフ、音楽を排し長まわしを多用したドキュメンタリーのような手法は、時に退屈を覚えるほど変化に乏しい。しかし、映像と自然の音のみで表現しようとする試みはイマジネーションを刺激する」、「特殊効果でもCGでもないが、「そこにある何気ない風景」を装ったすさまじいまでの作り込みは、まさに“今までに見たことがない映像”。新鮮な驚きと強烈なインパクトに瞬きするのを忘れてしまった」として70点もの高得点を付けています。
★★★☆☆