先の「EU、土壇場のエンジン車容認 無理筋はEVか合成燃料か」の論考で、
「欧州連合(EU)は2035年に内燃機関(エンジン)車の新車販売を禁止する方針だったが、3月28日のエネルギー相理事会で合成燃料を利用するクルマに限り販売を認めることで合意した。」
と言う記事では、2023年3月28日にICEでe-fuelに限り使用を認めることにすると発表されているが、この上記の「ゴルフ」のエンジン車は開発しないと言う発表は、4月3日であった。
と言うことは、何はともあれ発表日だけで考察すると、VWは合成燃料(e-fuel)の使用が認められた後に、ゴルフのICE(内燃機関のクルマ)の開発はしないと宣言したことになる。e-fuelを使えば、ゴルフのエンジン車は販売できるのに、何を血迷ったのかとも小生は勘繰らざるを得なかった。まあ、VWとしては、ゴルフにはコストが合わない、と見ていたのであろう。
e-fuelはその製造過程でかなりの熱(電気)を使わざるを得ないので、火力発電であればCO2を排出していることになるが、Batt.の製造過程での電気の使用量程ではないのではないのか、だから、合成燃料(e-fuel)はBatt.よりも環境にやさしいと言うことになろう。
だが合成燃料を作るにはH2が必要となるわけだが、水素を直接燃やしてエンジンを動かす方法もあるのに、EUはなぜ水素に言及していないのか、はなはだ疑問である。
H2を燃やせばICEが使えるのに、VWは(ゴルフのエンジン車開発断念に)先走ってしまったと勘繰ったわけだが、それ相応の深謀遠慮(コスト的に許容出来ればゴルフを再販するなど)があるのであろう。とはいえ、EVシフトと言う世の流れには逆らえなかった、と言うことか。
何はともあれ、「e-fuelが認められてもEV戦略は変わりない」と言うことで、EV化が世の流れになってしまっているので、どうあがいても抗しようがない、と言うことか。
EUはそれでも良いのかもしれないが、世界(トヨタ)はそうはいかない。BEVに固執することなくH2も含めて「全方位」が必要なのだ、HEV、PHEV、FCV、 H2、ICE(e-fuel)も。
差し当たって(でなくても)合成燃料(e-fuelなど)は(高級車などには)必須となる。
VW(グループ)の80%がBEVで、残りの20%がICEと言うことでも、その20%での合成燃料の使用は重要な選択肢なのである。いくらカーボンゼロ社会であっても、ICEはカーボンフリーの燃料で生き残るし、生き残らなければならないのである。
新生VW、執念の合成燃料でエンジン延命も トヨタとの類似性
沸騰・欧州EV(41)
2023.4.6
14件のコメント
 大西 孝弘 ロンドン支局長
大西 孝弘 ロンドン支局長 
写真の奥に4本の煙突が印象的なフォルクスワーゲンの本社工場がある
フォルクスワーゲン(VW)グループとトヨタ自動車というドイツと日本を代表する2つの巨大企業が、世界的な電動化という歴史の大きな転換点に立っている。EVシフトで先行するVWは、どのように事業構造改革を進めているのか。シリーズ「沸騰・欧州EV」では複数回にわたり、VWの改革に迫る。
3月12日、日曜日。筆者はドイツ北部のウォルフスブルクにあるフォルクスワーゲン(VW)本社を訪れた。ハノーバー空港からクルマで向かうと、遠くに本社工場の象徴である4本の大きな煙突が見えてくる。
5回目のVW本社訪問になるが、その中でも2015年10月に訪れた本社周辺の様子は異様だった。同年9月に米国でディーゼル車に排ガス性能を偽るための不正なソフトを搭載していたことが発覚し、VWブランドへの信頼は失墜。巨額の賠償金の支払いも予想されていたことから、城下町の雰囲気は陰鬱そのものだった。それでも本社敷地内の巨大な納車施設で顧客向けの納車が行われていたのは、印象的だった。

VW本社近くの巨大納車施設には充電設備が整備されている
何回訪れても、納車施設で繰り広げられるシーンに心を動かされる。多くの人々にとって自動車は高価な商品であり、購入は一大決心が必要になる。納車施設では待機のためのレストランや待合スペースまで、納車を盛り上げるための配慮がなされている。今回はその納車スペースが、新型コロナウイルス感染拡大前の19年の訪問時と大きく変わっており、充電設備が増えていた。もちろん、増加する電気自動車(EV)への対応だ。
今回の訪問では、メディア向けにEVの試乗会があった。VWグループのVW、アウディ、ポルシェ、シュコダ、クプラの5ブランドの合計22種類のEVがずらりと並ぶ。本社から片道10キロほどの場所を往復するルートで、途中に一般道を時速100キロで走れる場所もあり、性能を比較できる。VWのID.4とアウディのQ4 e-tron、ポルシェのタイカンを試乗した。特にタイカンの走りは圧倒的で、あっという間に時速100キロまで達する。
(続く)










 2022年夏に日経ビジネスのインタビューに応じたフェラーリのベネデット・ビーニャCEO
2022年夏に日経ビジネスのインタビューに応じたフェラーリのベネデット・ビーニャCEO 大西 孝弘 ロンドン支局長
大西 孝弘 ロンドン支局長 
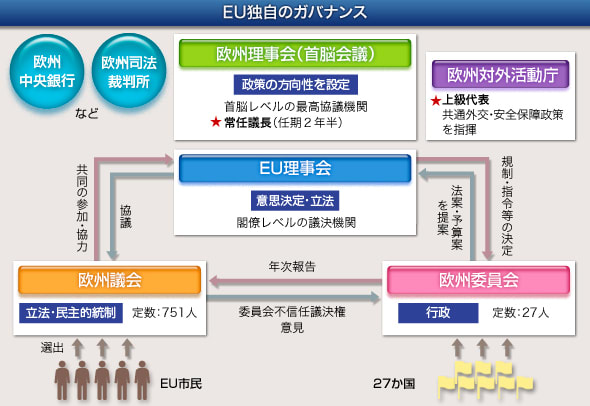





 トヨタ自動車のFCV「新型MIRAI」(出典:トヨタ自動車)
トヨタ自動車のFCV「新型MIRAI」(出典:トヨタ自動車)







