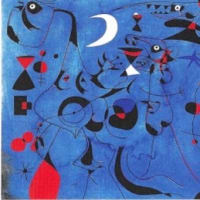東日本大震災の死者を上回る死者を出しているトルコ・シリアの地震は、「阪神淡路」や「熊本」ほどの都市直下型ではないが、内陸の活断層によるものなので、震度(揺れの強さ)が高かったはず。
しかも「熊本」と同じく、本震が2度あった。
このように、ただでさえ被害をもたらす地震だったが、被害をさらに大きくしたのは、人為的要因で、建物の耐震性の問題。
少なくともトルコは地震国の自覚があるので、耐震基準は厳しかったが、如何せん、運用が甘かった。
日本で言えば、耐震基準を満たさない”姉歯物件”が野放し状態(お金を払えばokらしい)で、昨年建てた新築のビルさえもあっという間に崩壊した。
これは日本ではあり得ない。
ビルでなくてもあちらは石造りの家なので、家が崩壊すれば、中の住民は瓦礫に押し潰される。
江戸時代の日本で藩によっては瓦屋根が禁止されたのも、明治に入ってきた西洋のレンガ建築がその後廃れたのもこの理由(紙と木でできて屋根が茅葺の日本家屋は、地震で崩壊しても人が潰されなかった)。
ただ、瓦礫の崩れ具合によっては、空間が形成されるため、うまくその空間に収まれば生き延びられる可能性がある(雪崩に襲われた場合も、こういう可能性がある)。
また木造建築と違って、火災が延焼しないのも救い(「阪神淡路」では、倒壊した建物に身動きが取れない状態で火災に見舞われて死者が増えた)。
現在の救助活動にはそれを期待するしかない。
日本の地震防災でも、自宅の耐震性の確認がその第一歩。