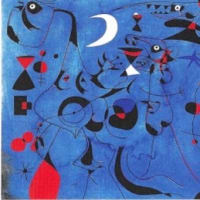昨日、4月なのに奈良で落雷事故が起きた。
実は昨年の4月にも宮崎で落雷事故が起きていた→記事
起きた現場は同じく学校のグラウンドで、サッカー部の練習(広場の真ん中で直立していると雷の標的となる)。
そしてあっという間に雨が降って雷が落ちたというのも同じ。
いわゆる”春雷”というやつで、夏の夕立のように、昼過ぎから時間をかけて成長する入道雲ではなく、典型的には温帯低気圧の寒冷前線に伴う積乱雲、すなわち移動してくる積乱雲による。
ただし、昨日は寒冷前線は通過しておらず、より規模の小さい擾乱によるもののようだ。
現地を管轄する気象台はそれを把握していて、当日は朝から「雷注意報」が発令されていた。
すなわち、この地の大気は朝から不安定(上空に寒気、下層に暖気)で、積乱雲が発生してもおかしくない状態だった(それが雷注意報の根拠)。
積乱雲は30分あれば10000mに成長するので、まさに「あっという間」に襲われる。
雷光や雷鳴が発生したら、もう落雷域に入っているので、第1撃をくらってもおかしくない。
すなわち雷光や雷鳴は落雷の”予兆”にはならない。
困るのは、夏の雷のように、青空の中に巨大な入道雲(雄大積雲)がどんどん成長している姿が目視できないこと(入道雲が発雷したら「積乱雲」となる)。
目視できるのは、厚い雲の雲底すなわち暗い雲の塊が接近しているくらい。
これは雲の観察眼がないと難しく、素人では無理かもしれない※。
※:静電位計(ロケーター)による空気中の電位の上昇が予兆となるかもしれない。自然落雷の可能性がある地表電界は15kV/m以上になるという(野長治『雲と雷の科学』)。ただ電位が急上昇した瞬間、落雷となるから、間に合わないか。
積乱雲を見つける自信がないなら、「雷注意報」発令時はグラウンドでの練習は避けたほうがいい。