『解』は秋葉原連続殺人事件を起こした加藤智大が、事件について書いた本で、
いわば本人直々による事件についての「解」という訳だ。
私が彼(以後、加藤智大を指す)に関心をもっているのは、
彼がもともと凶悪殺人を起こすタイプではないからだ。
すなわち、反社会的カルトに支配されていたりとか、殺す事や遺体に異常に興味を示すタイプではなく、
仕事に苦労しながらも普通にネットを楽しんでいた青年だから。
彼自身、自分を人殺しをするタイプではなく、大量殺人を犯す人を理解できないと言っている。
社会に恨みをもっているわけでもなく、むしゃくしゃして誰でもいいから殺したい衝動に襲われていたわけでもないという。
では、なぜ大量殺人事件を起こしたのか。
このへんの経緯は、本書で詳しく述べられているので、ここで下手にまとめることは控えるが、
一言でいえば、ネットでの「成りすまし」に対する警告の実行であった。
心理学用語を使うと、彼の不満の表現法である「受動攻撃性」が相手に伝わらないことによる、
攻撃の可視化であった。
彼の攻撃対象は、当時の彼にとって唯一の他者である「成りすまし」である。
実際の被害者はその攻撃を可視化するための「物」でしかなかった。
原因論的には、彼の記述からも”悪い母親”像が浮かんでくるので、
まずは伝統的な精神分析的解釈が可能だが、
本人は今流行りの認知行動療法的解釈に立っている(たぶん精神科医からの助言によるのだろう)。
すなわち、母親との関係で不適切な思考・行動パターンを学習してしまい、
そしてのそのパターンが、スムースな対人コミュニケーションを阻害することで、
リアルな対人関係だけでなく、文字だけに頼るネットでの対人関係においても孤立することになってしまった。
そして最終的に「成りすまし」によって、彼に唯一残されたネット上の”自己”が乗取られた。
これが事件直前までの流れである。
本書を読むまで、私は正しい情報に接していなかったことに気づいた。
まず、マスコミで「供述した」という引用元は、本人の口述記録ではなく、
取り調べ官が作成した「供述調書」であって、本人の口述とはまったく関係ないということ。
これは、彼だけでなく、すでにさんざん被疑者たちによって指摘されているので、
いまやわれわれは、マスコミで流される”供述”を鵜呑みにしてはならないことを改めて痛感した。
ただ、これが大抵第一報となるので、強い関心をもって能動的に他の情報にあたらない限り、
われわれはいつのまにかこの”供述”だけで事件を解釈してしまう。
タレ流される”供述”を盲信せず、われわれに代って真偽を探ってくれるのが本来のジャーナリズムである。
それはテレビや新聞などのマスコミではなく、フリーのジャーナリストの個人的努力に期待するしかない
(私はマスコミとジャーナリズムを分けている)。
その一つ(本件に関しては唯一例?)が、
中島岳志の『秋葉原事件』(朝日新聞出版)である(著者は大学准教授)。
この本はネットでのログを詳細に記載し、そこから事件に至る過程を分析していく。
これは第3者的立場からのアプローチとして、至極当然の方法であるが、また限界でもあった。
彼(加藤)自身、ネット上の自己のログを字義通りに解釈することの誤りを指摘している。
それはあくまで「ブサイク」キャラの演技であって、自分の内面を吐露したものではない。
彼は、リアルでもネットでもウケねらいの演技しているのだ。
孤立を恐れているから。
彼はなぜこの本を書いたか。
以上(マスコミで作られた人物像、ネットで演じたキャラ)の誤解を解きたかったからだ。
そして、今後このような事件が起きないための資料を提出したかったから。
彼によれば、そこまで考えるのが、本当の「反省」だという。
つまり、反省の姿勢を示すのがこの本ということ。
地裁で死刑判決を受けた彼は、判決を受入れず、減刑を求めて控訴した。
その理由は、心神喪失ではなく、「殺意はなかった」という点。
本書の真の出版意図は、殺意はなかったということの主張ともいえる。
事件中の彼の意識状態の短い記述(p100-108)がその部分にあたる。
確かに自覚的意識においては、個々の被害者に対して、個別の殺意をもっていなかったろう。
だが、彼がやろうとしていた事は、秋葉で”人を殺す”という行為を意図していた事は疑いえない。
突入直前、彼は自分のやることが「死刑」にあたることを自覚していた(p102)。
日本国民にとって「死刑」とは「殺人」の刑以外にない。
彼は、個々の人を殺すことは意識していなかった。
なぜなら、単に”事件”を起こすのが目的であるから。
それは、地下的サリン事件の犯人が、サリンを撒くことを目的としており、
居合わせている個々の乗客への殺意を抱いていないのと同じだ。
本書で彼が実行している「反省」、すなわち自己のメンタリティを解説し客観視することで、
事件の再発を防ぐ一助にするという、一見殊勝な態度が、
控訴中の被告の態度としては共感できない部分でもある。
彼のやっている反省は知的作業にすぎないからだ。
自己の行為を自己批判してはいるが、それはまずい事やってしまったという”失敗”への反省であって、
何の罪もなく生命を奪われた被害者に対する懺悔ではない。
彼にとって被害者はいまだ「人」になっていないのではないか。
自分自身における再発の懸念の無さを、
認知行動療法的な、認知の切り替え策の再学習によって、簡単になしとげられたと主張している。
この「反省」は加害者当人が今・やるべき事ではない。
心からの懺悔をして情状酌量を求めるのではなく、
事実関係としての殺意の無さを主張しているのも、
彼の被害者に対する態度を示している。
本書は、彼にとっての弁明であり、確かに本人でしか知りえない内面についての理解は深まった。
最新の画像[もっと見る]
-
 川の水位はネットで確認
1週間前
川の水位はネットで確認
1週間前
-
 臨死体験はあの世を見ているか
2週間前
臨死体験はあの世を見ているか
2週間前
-
 カエル館でゴースト・ハンティング
1ヶ月前
カエル館でゴースト・ハンティング
1ヶ月前
-
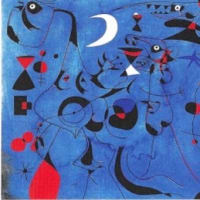 ミロTを着てミロ展に行く
2ヶ月前
ミロTを着てミロ展に行く
2ヶ月前
-
 元三大師を観に深大寺に行く
3ヶ月前
元三大師を観に深大寺に行く
3ヶ月前
-
 元三大師を観に深大寺に行く
3ヶ月前
元三大師を観に深大寺に行く
3ヶ月前
-
 志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
-
 志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
-
 志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
志段味古墳群と東谷山
5ヶ月前
-
 加曽利貝塚を見学
5ヶ月前
加曽利貝塚を見学
5ヶ月前









