2014 06 21(土)
栃木県栃木市郊外の桜とアジサイで有名な“太平山神社”を観光参拝。
県道269号線を跨ぐ様に建てられた太平山(おおひらやま)神社の第一鳥居(神明鳥居)。
途中の国学院大学栃木高校を過ぎると、直ぐに名所「あじさい坂」。(あじさい坂下に市営の有料P場有り、300円)
太平山神社の参道を兼ねていますので、紫陽花の道筋に幾つもの鳥居が建っています。


あじさい坂を少し上った左側に「奉納 虚空蔵菩薩」と染められた赤い幟が目に付く“六角堂”(天台宗 太平山連祥院)の堂宇。
廃仏毀釈が吹き荒れた明治期までは、神仏習合で太平山神社と同じ境内に建っていたそうです。
神仏分離令で神社と分離された連祥院は太平山中腹に移され、現在の地に建てられました。


ご本尊様は本堂奥に祀られている“虚空蔵菩薩像”。
京都の六角堂を模して建てられた六角形の連祥院本堂、通称“六角堂”と呼ばれ親しまれています。(明治38年建立)
連祥院六角堂境内に咲いていた可愛らしい紫陽花。
坂道も石階段になり、ここからが紫陽花の名所「あじさい坂」になります。
1000石段の両側に2500株の紫陽花が咲く「あじさい坂」。
「あじさい坂」に咲く色鮮やかな紫陽花が眼に優しく映ります。

「あじさい坂」の下方向。あさの9時30分頃なので観光客はまだちらほら・・・。
10時過ぎ頃から混雑、駐車場には長い車の列。
登る途中の右奥に「窟神社」が在ります。 投げた小石が石鳥居にのると幸運が訪れるかも・・・。

石鳥居から少し下がった場所に清水を湛えた大きな洞窟は“窟神社”の御神体。
太平山弁財天を祀り、財運・芸事・教養に霊験があります。

脇に流れる清水は冷たくて美味!
参道「あじさい坂」の紫陽花を愛でながら進むと立派な石碑が建てられています。
太平山と「あじさい坂」などの開発・整備に尽力した鈴木宗四郎翁顕彰碑。

あじさい坂途中の御茶屋の赤い和傘が印象的。 傘をモチーフに撮影していた人の横から一枚。(傘は六角堂で無料貸出)

1000石段ですから紫陽花参道はまだ続きます。 参道の右横に田村律之助翁の石像。

あじさい坂を8割ほど登った場所に銅作りの明神鳥居、掲げられた「太平宮」の扁額(松平定信の筆?)。
これまでは全て神明鳥居でしたが、急に明神鳥居になり違和感が・・・。

銅製明神鳥居の脇に高札場の様な建屋あり。 老中・松平定信の直筆の書板が掲げられています。
記されているのは太平山神社の由来のように見えます。

あじさい坂の最終地はきつい急角度の石段、頭上の朱塗り建物は太平山神社の随身門です。

「太平山のあじさい祭り」は6月13日(金)~6月30日(月)まで。
次回は太平山神社を参拝。
2014 06 27(金)記。 前橋市 薄 最高気温 29.7℃ 最低気温 21.3℃
最高気温 29.7℃ 最低気温 21.3℃
おまけコーナー。
赤ちゃんにハイハイを教える犬。
Buddy's Baby Crawling School
エサを必死で守る子犬。Tiny dog vs big dog - who's the boss?





























































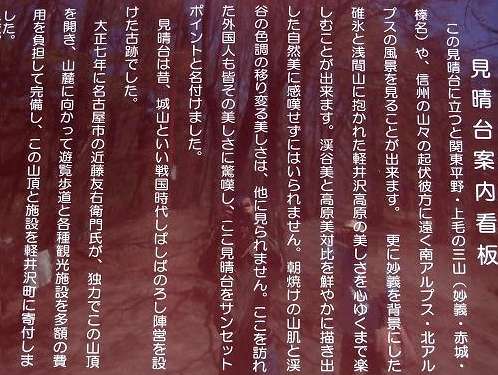





















































































 昨日関東梅雨入り。 最高気温 19.1℃ 最低気温 17.6℃
昨日関東梅雨入り。 最高気温 19.1℃ 最低気温 17.6℃















