2016 06 10(金)
“江戸三大祭り”の一つに数えられる山王日枝神社の例大祭“山王祭”。(江戸三大祭=山王祭・神田祭・深川八幡祭)
新装なった東京駅(駅前は工事中)から丸の内界隈を散策しながら皇居方面へ・・・。
正面に坂下門を臨む皇居前広場には山王祭を見物する人々が集まり始めています。(11時頃)
山王祭ポスター。 山王祭は2年に1度の開催、正式名称は“日枝神社大祭”。
山王祭パンフレット。 本日10日の渡御祭列は山王祭の中の一つで“神幸祭”と云います。
予定時刻より20分遅れて(11時45分)西の祝田橋方向から山王祭の渡御行列が内堀通りに入ってきました。

聞こえるのは太鼓の音くらい、わりと静かな祭列、鳳輦(ほうれん・神輿)も干支(猿)山車も車輪付きの輿に乗せられ氏子は担ぐ真似だけで気勢が挙がりません。

江戸三大祭りの筆頭に挙げられているとは思えない程のんびりした優雅な山王祭神幸祭。
因みに、山王祭は京都の祇園祭・大阪の天満祭と共に日本三大祭にも数えられているそうです。

花山車。 御幣猿山車。
内堀通りを渡御する山王祭の祭列動画。
山王祭 内堀通り 2016 06 10(金)
渡御祭列は皇居坂下門前の広場に集まり、皇居を拝礼してから約20分ほど小休止。暑い日差しの下、水分補給しながら鋭気を養います。
出立までの間、カメラサービス。 来日した外人さんも珍しい風俗にワンダフル!!

休憩時間は撮影タイム。 黒獅子頭。 諫鼓鳥。 「聖寿無窮 万民豊楽」「天下泰平 国土安穏」


山王祭で唯一の宮形山車に乗る人形は“随身像”。

坂下門前広場から12時15分頃出立、山王祭の渡御列は東京駅方面に向かいます。 白い神馬の鞍に据えられた宝珠がキラキラ輝き美しい。

山王日枝神社の宮司様も馬車でお出まし。 山王日枝神社の神様のお使いは猿なのです。

厳しい日差しの下、山王祭の祭列は東京駅方面へ静々と渡御して行きました。(12時30分頃)
坂下門前広場から東京駅方面に渡御する山王祭の祭列。
山王祭 和田倉門~東京駅 2016 06 10(金)
山王祭HP。
http://www.tenkamatsuri.jp/index.html
今年の山王祭は6月7日(火)~17日(金)まで、威勢が良く賑やかに行われるのは11日の日枝神社石段を駆け上がる連合宮入だそうです。
2016 06 30(木)記。 前橋市  最高気温 27.0℃ 最低気温 19.7℃
最高気温 27.0℃ 最低気温 19.7℃
日本にデフレを招いた「真犯人」 トヨタの大罪。
http://www.mag2.com/p/news/208211?utm_medium=email&utm_source=mag_W000000204_thu&utm_campaign=mag_9999_0630
おまけコーナー。
二足歩行するツキノワグマ。(アメリカ)
Pedals bipedal bear sighting
ドローンで犬の散歩をやってみた。
Walking Dog with Drone. FAIL!





















































































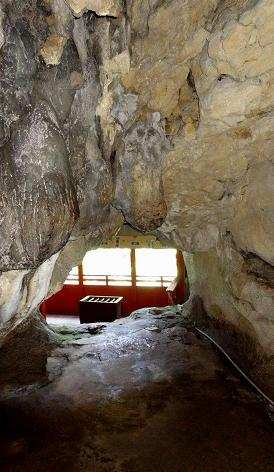



 最高気温 22.5℃ 最低気温 18.4℃
最高気温 22.5℃ 最低気温 18.4℃
























































 最高気温 26.6℃ 最低気温 10.9℃
最高気温 26.6℃ 最低気温 10.9℃