2012 11 03(土・文化の日)
秋の陽が暮れようとする午後4時15分頃に出雲大社に到着。
島根県大社市にある出雲大社が笠間市に分社を創建し、名は出雲大社常陸教会。
参拝客は殆んどいませんので大石鳥居まで車で上がります。
高さ10m46cm大きな石造鳥居は「稲田御影石」製で日本最大の明神形鳥居。 近くに「交通安全祈願塔」、模様は横断歩道?


大石鳥居から2分で“出雲大社常陸分社”に着きます。
社殿を飾る注連縄の大きさにビックリ!! 長さ16m、重量6トンという圧倒的な巨大さ!


拝殿の右に鎮座していたのは大国主命、右手の上に少名彦那命が乗った世界最大の大国主命像、
出雲一刀彫師・藤井孝三の名作です。



「神光満殿」額の下は本殿に連なる本拝殿。 左隅に立つ巨木杉は御神木でしょうか?
拝殿の上には6畳ほどの大きさの天井画、奥田コウドウ画伯が描いた「常陸の雲」と名づけられた金銀箔を用いて煌びやかな大作。

注連縄に投げたコイン(硬貨)が突き刺さると願いが成就するとか・・・?
奉納された絵馬を拝見。出雲大社は大黒様が御祭神、良縁を求めるなら縁結びの神・出雲大社で祈願ですね・・・。

出雲大社常陸教会本殿。
高さ13m、階15段の高床形式、総檜造りで日本一の大きさを誇る大社造りの本殿。
祭神は島根県の国宝“出雲大社”から分霊した大国主命が祀られています。
出雲大社常陸分社から日暮れの稲田地区を遠望します。
出雲大社常陸教会の社殿の参拝を終え、下る途中に参拝した「龍蛇神社」。
龍蛇神は大国主命の御使神で防火・水難の守護神、家内安全・商売繁盛にも霊験があると言います。

様々な見所・名所が点在する笠間市は興味尽きない地区、皆様も観光されては如何でしょうか・・・。
2012 11 30(金)記。 前橋市  最高気温9.5℃ 最低気温5.7℃
最高気温9.5℃ 最低気温5.7℃
おまけこーなー。
ゆるキャラがひたすら死んでいくオーストラリア鉄道会社の「安全啓発ビデオ」。
安全を訴える動画を翻訳してみた (・д・)
2012 11 03(土)
前回掲載の西念寺から約1kmほど東の場所にひっそりと佇む御廟が親鸞聖人の内室(妻)・玉日姫(恵信尼)の廟墓「玉日君御本廟」。
綺麗に刈込まれた植栽が囲む参道をすすむと正面に御廟山門が建っています。


両袖の透かし彫りが美しい廟門の奥が玉日姫の墓所「玉日廟」。

親鸞聖人の妻・恵信尼の「玉日廟」は親鸞の頂骨を収めた「御頂骨堂」がある稲田御坊西念寺と向い合う様にして建てられています。
境内の御堂に掲げられた「法然聖人」画額、「親鸞聖人玉日姫仲人役」と記されています。
法然は弟子・親鸞と恵信尼との縁を取り持ち、結婚仲人も引き受けたのですね・・・。

当時としては驚異的な長寿だったのですね~没年89歳(西暦1272年)とは・・・。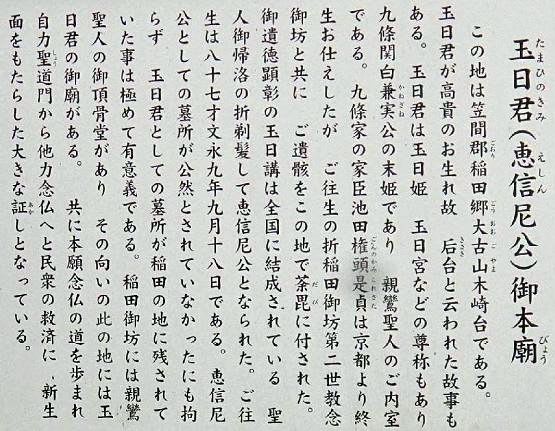
夕暮れ時で誰もいない「玉日廟」に弔意を表し、急いで「出雲大社」へ車を走らせます。
2012 1127(火)記。 前橋市  最高気温11.4℃ 最低気温7.1℃
最高気温11.4℃ 最低気温7.1℃
おまけコーナー。
ブタにダイビングさせると肉質がよくなる・・・?(中国)
Chinese Farmer trains pigs to jump from height into water
卵の割れる瞬間。
Egg Destruction! - Slo-As-A-Mofo-Sho
2012 11 23(金・勤労感謝の日)
笠間市周辺のの名所をいくつか御案内。
前橋市と水戸市を結ぶ国道50号線北側に位置する笠間市稲田469にある名刹“西念寺”を参詣。
国道50号線脇立つ「稲田御坊」の看板横に立派な石造りの太鼓橋、たぶん新しく架け替られた橋と思われますが、「聖橋」と記されていました。(大地震でも全く損傷の無い施工の良さに感心!)


「聖橋」を渡り、巨木が茂る参道を進むと親鸞聖人ゆかりの古刹“西念寺”の山門に到着。
山門脇に「親鸞聖人 教行信證 御製作地 浄土真宗別格本山」の大石柱、格式が感じられる古寺です。
この寺に20年間居た親鸞は浄土真宗の経典となる「教行信証」を書き上げました。
山門から続く土塀は昨年の3.11地震ので一部が倒壊したまま・・・修復には時間と浄財が必要。

境内の片隅に建っていたのは「稲田(西念寺)御幽楼」。
都から追放された親鸞聖人がこの楼屋で世俗と離れて隠棲していたそうです。
「浄土真宗開闢之霊地」と刻まれた大石碑と西念寺本堂。
左には名物の銀杏の大木が実もたわわに生い茂り、本堂では法要中で撮影は不可でした。
都を追われ、北陸路・越後を経て坂東は常陸の国の笠間に着いた親鸞は、ここ稲田の西念寺に居を構え浄土真宗の教えを広めてます。
西念寺の正式名は「別格本山稲田御坊西念寺」、本尊様は「阿弥陀如来」。
創建は嘉元2年(1304年)頼重房教養上人の開基。宗派は浄土真宗。 現在の本堂は1995年建立。
境内を拝見。 鐘楼と梵鐘。 古い桜の木の切り株は「弁円回心の桜」(べんねんえしん)。明治6年に強風で倒木。

西念寺本堂前に見られる銀杏の巨樹は親鸞聖人が実を蒔いて育てた「葉つき銀杏」よ呼ばれる世界的にも貴重な天然記念物の樹です。
今の季節が銀杏の落ちる時、運よく「葉つき銀杏」が拾えました。
中央画像の上の実は普通の銀杏の実、下が珍しい「葉つき銀杏」、銀杏の葉の一部から実が成っていますね。


右画像は境内の大岩に立つ親鸞聖人、浄土真宗布教の旅姿でしょうか・・・。
本堂の右手から小高い岡に整備された石段を上ると親鸞聖人の御骨を納めた「御頂骨堂」があります。

「御頂骨堂」は風格ある立派な御廟、京都に戻り押小路南万里の善法院で入滅した親鸞の遺骨は恵信尼(妻)の望みで分骨しここに祀りました。
「御頂骨堂」から少し下がった地に建っていたのは「太子堂」、もちろん聖徳太子をお祀りしていますが内部の厨子は空でした。。

西念寺にはとにかく切り株が多く保存されていました。
左は笠間稲田地方を領地としていた宇都宮頼重が浄土真宗に帰依し、高僧となり尊崇された教養上人の墓標樹。(墓石の代わり木)

右画像は戦国桃山時代に荒廃した西念寺の復興に多大な尽力した笠間城家老・石川信昌公の墓標樹。
まだまだ見所尽きない西念寺でしたが、親鸞聖人ゆかりの次なる見所に向かいました。
西念寺から200m程の田畑の中に石碑と石の太鼓橋が見られました。
上洛する親鸞が西念寺から見送りに出た妻(恵信尼)と子をこの石太鼓橋から振り返ったと伝えられる「見返り橋」。
橋も石碑も真新しく、昔の橋は地震で壊れたのでしょうか??
西念寺の詳細は ⇒ http://www.asahi-net.or.jp/~de3m-ozw/0toukai/toukai/shinran/shin02.html
笠間市周辺は親鸞聖人と縁の深い土地、西念寺が浄土真宗発祥の地だったのには驚きました。
次回は親鸞聖人の妻(恵信尼)の玉日御廟。
2012 11 23(金・勤労感謝の日)記。 前橋市  最高気温14.0℃ 最低気温5.6℃
最高気温14.0℃ 最低気温5.6℃
おまけーコーナ。
地下鉄ポスターが海外で評判。 下画像クリック。
ゆるキャラ鉄塔。 おもしろ画像は下クリック。
2012 11 03(土・文化の日)
笠間稲荷の参拝と菊人形・流鏑馬を見物した後、JR笠間駅から1.5kmほど離れた場所に建つ“春風萬里荘”を訪問。
正門前の無料P場に駐車し、入場料600円を支払います。
マルチ芸術家で料理人・美食家としても名高い北大路魯山人が居住した江戸時代中期の古民家を、昭和40年に北鎌倉からこの地へ移築し“春風萬里荘”と名付けました。(李白の詩にある言葉)
茅葺屋根の入母屋造りの家屋は約90坪、現在は笠間日動美術館分室として、屋内外に美術品を展示しています。
、
先ずは春風萬里の屋内から見物です。
少し雑然とした三和土土間の入口。 魯山人が居住していた和室。

幾つかの部屋を過ぎると明るい雰囲気の裏庭園が見られます。
京都の竜安寺の石庭を模した枯山水の石庭が裏庭となり、京都古寺見物の雰囲気に浸れます。
屋内は主に陶芸作品を集めた展示室。 陶芸家・画家・作家・料理家で万能の異才と呼ばれた北大路魯山人と陶芸皿。


入口左には馬屋だった場所を暖炉付き洋間に改造し、内部に彫刻作品など展示。

魯山人自作のタイルが貼られた10畳程の「長州風呂」。(五右衛門風呂)
魯山人が自ら設計した瀟洒な茶室「夢境庵」は落ち着いた佇まいを見せていました。。
春風萬里荘の表庭園を散策してみました。
広々とした庭園には現代彫刻が置かれ、回遊する見物客の眼を楽しませる彫刻庭園。


ブタ。 フクロウ。 おんな。
池泉回遊式庭園の中心部に大きな睡蓮池があり、初夏の蓮花が素晴しいとか・・・。
睡蓮池の奥方面に江戸時代風豪農屋敷の立派な長屋門が木立に囲まれ、重厚な趣で建っていました。
時代劇映画に使えそうな格式ある門構えです。
長屋門の内部は綺麗に整備され、囲炉裏など切られた小部屋が見られます。 脇にはあどけない少女の石刻像。


北大路魯山人の息吹きが薫る“春風萬里荘”で、文化の日の午後を芸術に触れ楽しんだひと時でした。
2012 11 20(火)記。 前橋市  最高気温16.4℃ 最低気温4.1℃
最高気温16.4℃ 最低気温4.1℃
おまけコーナー。
ヨーヨー世界チャンピオンの神技! 鈴木裕之氏
amazing!! 2012 yoyo Japan National 1A Champion .mp4
100m四足走行のギネスレコードは日本人のイトウケンイチ氏。
The Fastest 100m on All Fours! - Guinness World Records Day 2012
2012 11 03(土・文化の日)
毎年11月3日に笠間稲荷神社では「流鏑馬」(やぶさめ)が奉納されます。
10時15分から鎧姿の武者達が居並ぶ拝殿前で奉納流鏑馬の神事が神官たちにより厳かに挙行されました。
流鏑馬装束で威儀を正した「小笠原流弓馬術」の射手も拍手を打ち流鏑馬神事の成功を祈ります。

社殿に奉納され清められた弓・矢を神官から恭しく拝領した後、射手たちは御神酒を頂き邪気を祓い「流鏑馬」の安全を祈念します。


観客も交えた出席者全員で拍手を打ち、笠間稲荷神社での流鏑馬神事は滞りなく終了。
笠間稲荷の社殿を後に、流鏑馬武者行列は馬場に向かって、いざ出陣!!
凛々しい武者姿で次々に出陣! 後ろに続く四角い板は矢的でしょうか・・・。

武者行列は境内から楼門を経て門前町通りに向かいます。
古い家屋が立ち並ぶ門前町通りを威儀を正して行進。

流鏑馬武者行列は門前町通りから公園通り入り馬場のある笠間小学校方面へ・・・。
笠間稲荷 流鏑馬行列(境内・門前町通り・公園通り) ムービー.wmv
流鏑馬武者行列一行は笠間小学校西側の道路に作られた特設馬場に無事到着。(道路半分に土が敷き詰められています)
流鏑馬本番に先立ち、馬をゆっくり歩ませ馬場の下見を兼ねたお披露目パレードを行います。 矢場では的板の取り付けも完了。

11時から馬を駆けらせ、的に矢を射る豪壮華麗な「流鏑馬」神事が開始。
笠間稲荷奉納流鏑馬を行うのは「小笠原流流弓馬術」、的中率と割れ方で来年の農作物の豊凶を占う神事です。
馬場に矢的が三箇所置かれ、その全てを射抜くことを皆中る(みなあたる)として「皆中」(かいちゅう)と呼び吉となります。

昔は馬を駆せらせながら矢を射た事から「矢駆せ馬」(やばせめ)と云われ、江戸時代になり「流鏑馬」と呼ばれる様になったとか・・。
笠間稲荷神社「奉納 流鏑馬」の素晴らしい演武を動画でご覧ください。
笠間稲荷 流鏑馬 ムービー
笠間稲荷神社の「流鏑馬」は“日本三大流鏑馬”の一つ、他は二ヶ所は鎌倉の鶴岡八幡宮と日光東照宮。
的板の最上部を砕き、後ろの板に突き刺さった矢(鉄雁股付き鏑矢)、弓矢の凄いパワーに驚かされました。
流鏑馬会場での説明アナウンスでは「流鏑馬」とは、社殿での神事+武者行列+馬場での騎射行事の三位を総称して行う事だそうです。
霊験新たかな"笠間稲荷神社”と菊人形・奉納流鏑馬、文化の日の笠間市は楽しめます。
2012 11 16(金)記。 前橋市  最高気温16.4℃ 最低気温4.1℃
最高気温16.4℃ 最低気温4.1℃
おまけコーナー。
子猫を肩にのせ自転車で走る配達人。
My cat can ride a bike better than you can
2012 11 03(土・文化の日)
日本三大稲荷の一つに数えられる笠間稲荷神社の堂々とした楼門から参拝いたします。

鉄筋コンクリート造りの楼門は昨年の3.11地震にも耐え、晴れやかに参拝客を出迎えます。
掲げられた扁額には「稲荷宮」の文字。
お寺の山門にある仁王像の代わりに楼門には弓矢を携えた随身様の尊像が神をお守り致します。
楼門の裏側の左右には御神馬像。


楼門の左側には真新しい木造の御社「交通安全祈願所」が造営されていました。
帰路の安全を懇ろに祈ります。
楼門から左右の菊花展を鑑賞しながら進むと、正面に笠間稲荷神社の拝殿があります。
こちらも頑丈な鉄筋コンクリート造りですので昨年の3.11地震による倒壊を免れたようです。
境内に飾られた「菊花展」や露店を通り裏側の本殿を参拝。
本殿に祀られている神は“宇迦之御魂命”。(ウカノミタマノミコト)
食糧と五穀豊穣を司る、生命の根源に密接な有り難い神様で、商売繁盛の神でもあります。
本堂は江戸時代末期(万延元年1860年)に建築され、昭和63年に国の重要文化財に指定されました。
本殿壁面には素晴しい彫刻が施されています。
本殿を飾る彫刻「三頭八方睨みの龍」・「蘭亭曲水図」や「唐獅子牡丹」などは必見の名作。
笠間稲荷神社境内には縁り深い摂社・末社など沢山祀られ、信仰の深さを感じられます。

大きな一枚岩の石碑が倒れたまま、平23年3月11日の地震揺れの凄さが実感できました。(この地区は震度6強)
見応えある本殿の裏側には木造の瑞鳳殿(大正6年築)、内部では小学生による図画コンクール「私の好きな笠間」が開催中。
入口から数多くの子供たちが描いた可愛らしい絵画が沢山展示されていました。

笠間稲荷神社境内裏で開催中の「第105回 笠間菊人形まつり」を見物。(入場料800円)
日本で最初に菊人形展を開催したのは笠間稲荷の菊人形だそうです。確かに105回ですから・・・。
日露戦争で荒廃した人心を癒すため明治41年(1908年)に鮮やかな菊花で制作したのが始まりといいます。

入場口から菊人形館までの広場では大菊花壇展。色鮮やかな素晴しい菊花作品を見物することが出来ます。

「古都の華」「復興錦」「富士・・・」など題名が付けられた大菊花壇。

茨城県と言えば水戸黄門様、御老公に助さん角さんなど小菊を纏って出迎えます。
今年の菊人形はNHK大河ドラマ「平 清盛」。
菊人形は第1景「清盛誕生」から第10景「厳島神社」まで。
平清盛の視聴率が悪いのか? 入場料が高いのか? 見物客はガラガラの閑古鳥が鳴きっぱなし状態!

寂しい菊人形「平 清盛」を見て廻りますが、NHKの平清盛を全く見ていないので登場人物が判りません。
説明では左上は第2景の「海賊討伐」、三女性は第4景「清盛をめぐる女たち」とか・・・。平 明子 平 時子 平 宗子。
保元の乱で協力した源義朝(左)と平清盛(右)は平治の乱では敵対することになります。(6景 「平治の乱」)

平家一門の財政を潤した日宋貿易のシーン、後白河法皇(左)と平清盛(中央)と宋の商人でしょうか?(第8景「日宋貿易)
厳島神社で平家納経を行う平清盛(左)と建礼門院と高倉上皇の場面。(第10景「厳島神社」)
見所多く霊験新たかな笠間稲荷神社でした。
笠間稲荷神社HP。
http://www.kasama.or.jp/
次回は勇壮な「笠間稲荷 奉納流鏑馬」です。
2012 11 13(火)記。 前橋市 薄 最高気温16.5℃ 最低気温8.2℃
最高気温16.5℃ 最低気温8.2℃
おまけコーナー。
棺桶会社のカレンダー制作風景。
Kalendarz Lindner 2013 Backstage ( www.kalendarzlindner.pl)
御興味ある方はLINDNER社HPをご覧下さい。
http://calendarlindner.com/2013.php
2012 11 03(土・文化の日)
「天高く馬肥ゆる秋」快晴の文化の日、日本三大稲荷の一つ、茨城県笠間市の笠間稲荷神社を参拝。
一般には笠間稲荷と呼んでいますが、本名称は「胡桃下稲荷神社」と言うらしいです。
秋のこの時期、境内には菊花が展示され見物人で朝から賑わっていましたが、以前立っていた2本の石造大居が有りません。
胡桃下稲荷神社の石柱の右に細い注連縄が張られているのが一の鳥居のあった場所です。
もしかして、昨年(2011年)の3月11日の東日本大震災で倒壊したのかも・・・。(この地区は震度6強でした。)
社殿・楼門まで立ち並ぶ仲見世商店街前の参道のも沢山の菊花が・・・。

地元の小中学校の生徒さんたちが丹精込めて育てた鉢植え菊が鮮やかに満開!!
笠間稲荷神社楼門前の菊花壇の中、「大菊花展」「菊人形展」の幟旗。 菊に囲まれたおキツネ様も嬉しそうにコ~ン。

楼門前に立っていた朱塗りの三の鳥居も撤去され少し寂しい感もします。
朱塗り楼門をくぐる前に手水舎で身を清めます。 手水舎の欄間を飾る彫刻(手力雄命が天岩戸を開け、光が差してきた図)が素晴しい!

手水舎の合い向かいに建つ格式ある額殿(1899年明治32年築・絵馬殿)も拝見。
額殿の内外全て絵馬や奉納額が飾られ笠間稲荷への信仰心の篤さを物語っています。

天孫降臨絵馬でしょうか・・・。 こちらの大きな絵馬も古代神話からなのでしょう。

楼門に向かって右側に江戸時代の文化3年(1819年)に建てられた重厚な東門がありました。

歴史ある東門を抜けた境内に大きな“さざれ石”が鎮座。君が代に歌われている目出度い石。
東門の彫刻を拝見。 出雲風土記の国造りや大国主命を題材にした透かし彫りは見事な出来栄えです。

東門に奉納されていたのは非常に珍しい真っ黒な綱(縄?)。
説明では「毛綱」とか・・・大きな木材など運搬するさい通常の綱では切れてしまうので女性信者の長い毛髪と麻縄を撚り合わせ超強度に作り上げた綱だそうで、社殿造営の大柱などの搬入時に使用するそうです。

胡桃下稲荷神社の謂われの御神木である胡桃木(オニグルミ)の大きな古木。
胡桃樹の下に稲荷が祀られていた事から「胡桃下稲荷神社」の名が付けられました。
笠間稲荷神社の貴重品を拝見した後、楼門から社殿に向かいました。
次回は笠間稲荷社殿と菊人形展。
2012 11 09(金)記。 前橋市  最高気温19.0度 最低気温8.6℃
最高気温19.0度 最低気温8.6℃
おまけコーナー。
深い穴の落ちたコアラ。
Koala falls whilst being rescued from Australian mineshaft
可愛いアカエイの赤ちゃん。
Dancing baby stingray
2009 10 31(土)
錦秋薫る奥只見湖観光を終えた午後4時近く、帰路の途中で小出IC傍のの西福寺を訪れました。
西福寺は幕末の名匠“石川雲蝶”の彫刻作品のある寺として有名です。
赤トタン葺きで朱塗りがすっかり剥げ落ちてしまった赤門(山門)と白山神社の石鳥居。
並んでいますから神仏混交の寺社なのでしょうか・・・。
赤門前に立つ「禁葷酒」戒壇石と「火除け地蔵」は共に石川雲蝶作。 赤門には粗削りな石造り仁王像。


禁葷酒(きんくんしゅ)とは寺に入山する時にはネギ・ニンニク類と酒などを食してはいけないと言う意味。
餃子も酒も口に入れてませんから気軽に境内へ・・・。
巨大な覆屋で保護されている茅葺屋根の建物が目指す西福寺開山堂。

開山堂脇に建つ鐘楼には、新潟の鋳物師“土屋忠左衛門”作で「勅許」文字が彫り込まれ、重要美術品として戦時供出を免れた名鐘。
梵鐘には三十三体の観音像が模られています。(1850年建立)
先ずは、西福寺本堂の横に建つ開山堂正面の彫刻を拝見。
秋の夕刻、訪れる人は少なくひっそりとした開山堂。
開山堂は1857年(安政4年)蟠谷大龍(ばんおくだいりゅう)大和尚によって建立された茅葺二重層の鎌倉禅宗仏殿様式。
西福寺開山堂唐破風向拝上部の虹梁には眼を引き付ける細密彫刻。
左甚五郎をも凌ぐと云われる“石川雲蝶”の透かし彫り木彫芸術をご覧下さい。
柱上部の木鼻を飾るのは子供と戯れる獏(バク)のユニークな彫り物。

海老虹梁に施された深彫り彫刻の繊細さには感嘆!!

欄間には物語風の左右に細長い彫刻、仏教説話の大切な場面なのでしょうか・・・?

西福寺の山号は赤城山(せきじょうざん)、1534年芳室祖春大和尚により開創された曹洞宗の名刹。
中央が本堂、右建物(庫裏)から本堂と開山堂に入館です。(拝観料300円)
本堂内に掲げられた「赤城山」の扁額。 本堂須弥壇に安置されている御本尊は鎌倉時代の作“阿弥陀如来三尊像”。

本堂を過ぎると直ぐに「開山堂」。
堂内に入ると迫力ある尊像(仁王像?)が左右からお出迎えします。天邪鬼を懲らしめている姿か・・・?


6段ほどの階段を上がると、そこは極彩色に彩られた摩訶不思議な異空間!!

開山堂の最奥壇に祀られているのは開山の芳室祖春大和尚と曹洞宗開祖“道元禅師”と。
前後左右上部、足元の板の間以外は全て石川雲蝶の彫刻群。

圧巻は天井(三軒四方の吊り天井)を覆いつくす極彩色に彩色された巨大な彫刻、正に「越後のミケランジェロ」と呼ばれた石川雲蝶生涯掛けての力作!
巨匠“石川雲蝶”が彫り込んだのは「道元禅師 猛虎調伏之図」。
中国で修行中の道元が天童山への行脚の途中、大きな虎に襲われそうになった時、杖を投げつけ座禅を組むと杖が龍となって虎を追い払ったという逸話。
右上の崖上で座禅を組んでいる僧が道元禅師。龍虎争う場面をモチーフとしています。
虎と龍の他に、亀・鯉・鷲・猿・岩ツバメ・雀なども動くが如く活き生きと彫られていました。
西福寺開山堂パノラマビューをご覧下さい。
http://www.saifukuji-k.com/kaisandou_tour/index.html
西福寺HP.
http://www.saifukuji-k.com/
これほど素晴しい彫刻が越後の片田舎の寺にあるなんて・・・驚きです!
西福寺開山堂はその彫刻の素晴しさから「越後日光開山堂」とも呼ばれています。
奥只見湖紅葉狩りを兼ねて、西福寺を訪れ石川雲蝶の名作品を鑑賞しては如何でしょうか・・・。
2012 11 06(火)記。 前橋市 小 最高気温14.4℃ 最低気温12.2℃
最高気温14.4℃ 最低気温12.2℃
おまけコーナー。
2012 鹿児島実業高校文化祭 新体操部 ももクロ跳んでみた.
2009 10 31(土)
紅葉まぶしい奥只見湖遊覧を終えた後、奥只見ダム上部に建てられた“奥只見電力館”を見学。
ダムサイトの案内板に従って舗装された坂道を上がります。

100mほど上がった坂の左手の木立の中に「岡田正平翁」の銅像。(1959年建立)
昭和22年新潟県知事となり只見川流域の電源開発に尽力した人物。
坂道の途中のダムを見下ろす高台には電力神社、小さな社殿が落ち葉の中に祭られていました。

電力神社から見下ろした奥只見湖のパノラマ風景は正に絶景かな~~!
ほどなく電力館(2階に喫茶コーナー有り)に到着、電力館の前庭に建てられていたのは「慰 霊」の二文字が刻まれた石碑。

眼下に見える奥只見ダムの過酷な工事で犠牲になられた方々を祀った慰霊碑です。(合掌)
慰霊碑横の地肌にへばり付く様に生えていたのは“荘田エーデルワイス”。
ダム開発の障害となる雪害対策に貢献した“荘田幹夫博士”がスイスから種子を持ち帰りこの地に植えたものです。

可憐な花が咲くのが楽しみです。 (右上は拝借したエーデルワイス画像、荘田エーデルではありません)
電力館前に置かれていた円盤型金属は水のエネルギー(横水流)を回転エネルギーに変換する水車ランナ。(立軸フランシス水車・30トン)
「奥只見電力館」は入場無料、マスコットのモモンガー「モモ太」君がお出迎えです。

館内は奥只見ダムなど水力発電所についての説明板・ジオラマ・小型模型など理解しやすく展示されていました。
人形と比べると巨大さが判る「縦軸渦巻型カプラアン水車の水車ランナ」の模型。(縦水流用)

近頃の節電で一躍脚光を浴びている“揚水発電”の解説もありました。
夜間の余剰電力で下ダムから上ダムへ水を吸い上げ、昼間の電力逼迫時に下ダムへ落として発電します。
様々な発電設備が解説され一通り見ると電力通になった気分、水車タービンを下から見るとUFOに遭遇したみたい・・・・。

釣瓶落としと云われる秋の陽、ダムサイトからの下りはスロープカーの真下を歩いて下ります。
日陰に入ると少し寒さを感じつつ、楽しかった奥只見湖遊覧から大駐車場の戻りました。

次回は豪華な彫刻で有名な「西福寺 開山堂」です。
2012 11 02(金)記。 前橋市 最高気温16.3℃ 最低気温7.8℃
最高気温16.3℃ 最低気温7.8℃
「反日国家に工場を出すな」(中韓への技術流出を防げ)。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20121030/238785/?mlp
おまけコーナー。
ギネス認定世界一の「人間空気椅子」(10月28日 福岡県大野城市、参加数1318人)
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/shisei/seisaku/cityonojo40anniversary/_10945.html
「人間空気イス」福岡で世界記録を達成 大野城市
突然エレベーターの床が抜けたら・・・!
So Real it's Scary
史上最低高度からの落下に挑戦したら・・・。
CONAN Exclusive: World's Shortest Freefall! - CONAN on TBS









