
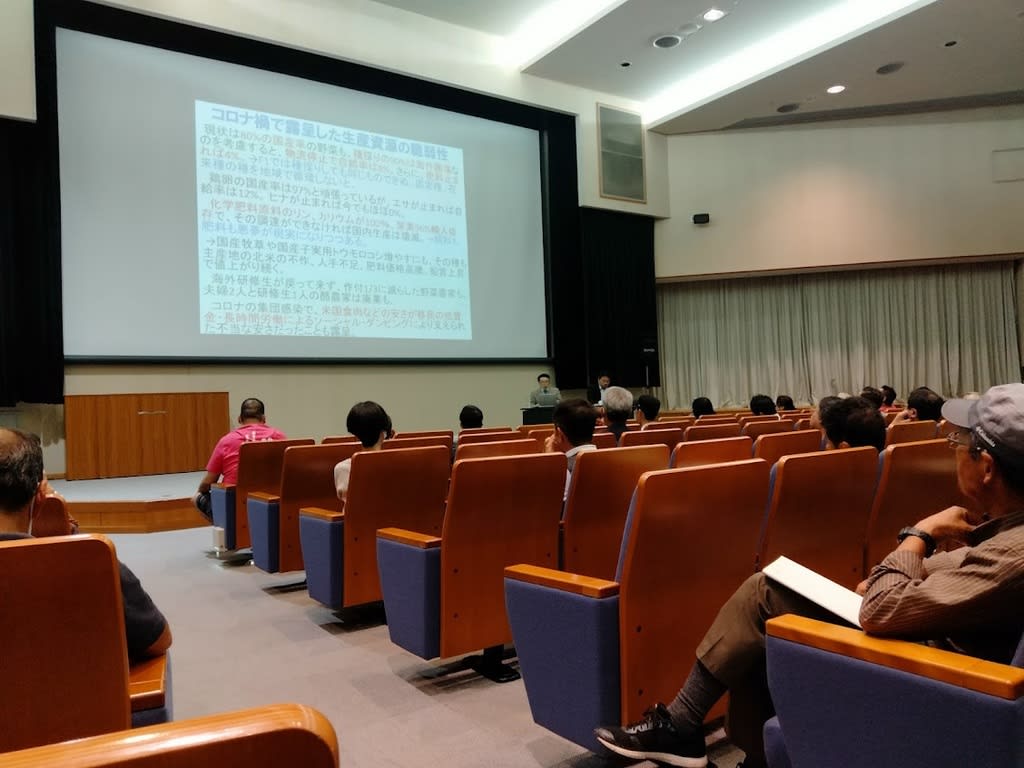

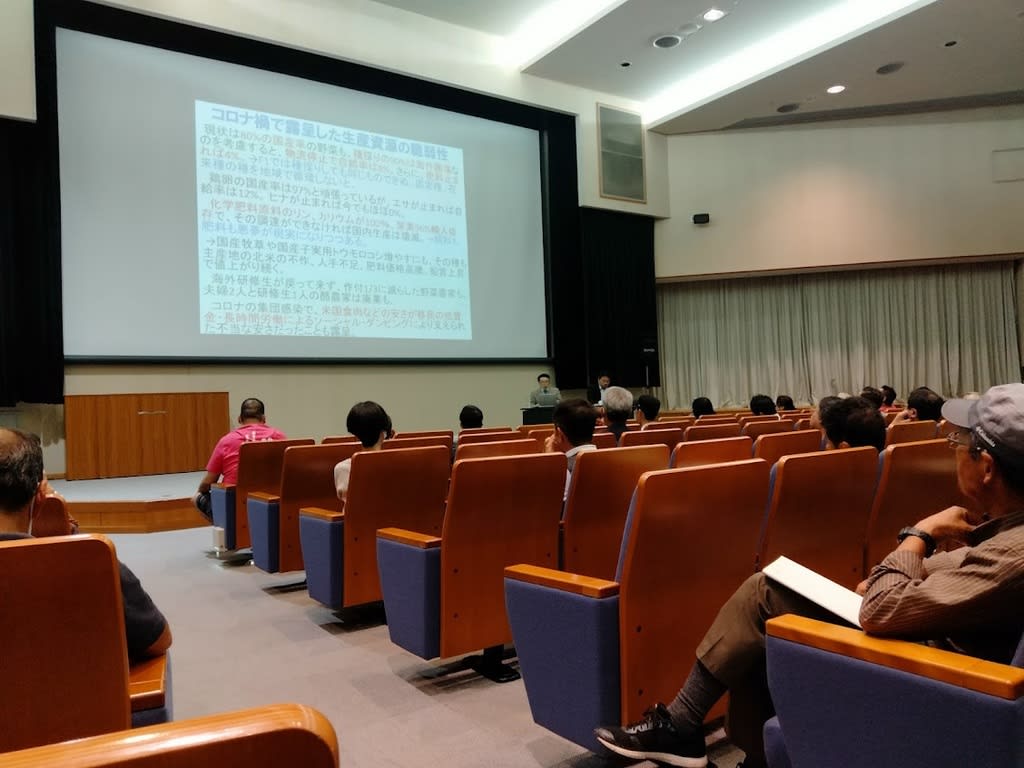





種まきから3週間、育苗イネは順調そのものだぜ。やっぱホワイトシルバーの威力だな。ヒトメボレなんて、びっしり緑の芝生だ。シートはぐるのが遅れたコシヒカリはまだ黄色っぽいが、徐々に色が上がって来てる。そう、今年は苗床土、ボカシの割合増やしたからな、追肥の心配必要なし、病気の兆候もなく正解だったな。

ただ、プール張るのに古いビニール使ったのは、分かっちゃいたけど、失敗だった。7つのプールのうち、3っつは水が駄々洩れ、朝夕時間をかけて注水せにゃならん。プール1枚に10分近く!とても見守っちゃいられないから、近くで小屋作り作業なんかしながら、時間見計らって次のプールへホース移動、なんてせわしない思いをしている。
でも雨で外仕事が無理となると、どうしよう?そうか、ハウス内でSNSとかネットニュースのチェックで時間をつぶすか。コンテナひっくり返した椅子に座って、ネットタイム。
そうだ、野菜苗にも水をやらなくっちゃ。まず、トマト、元気溌剌、花なんかも着き始めて、もう山盛りの大盛況だぜ。

芽が出ねえぞ、って文句言ってたサターンとか桃太郎も出遅れながら、精いっぱい追走してるしな。
スイートコーンは1回目畑に移し終えた。残り8本は新たに芽が出て来たものと一緒に植える予定だ。全部植え切ると60本以上になる。凄い、収穫時は保存作業に追われるぞ。

プリンスメロンは、イネ育苗後、このハウス内で育てるんでそれほど本数はいらないんだが、これ、よく生るし、甘み香り絶品なんで、欲しい人にはおすそ分けしようってことで、株分けしたから、ほれ、20本以上だぜ。

早生の栗カボチャ他、中生、晩生は伯爵、紅爵、雪化粧の3種、伯爵の発芽がいまいちで残念だったが、まっ、たっぷり半年分とれるだろう。

今年初挑戦の丸ナス育苗も思いの外、簡単かつ順調。こっちはすでに買ってしまった人が多いらしいので、1ポット2~3本出た芽は株分けせず間引きした。ごめん。

そして、里芋。順調に発芽した後、ちょっと生育は停滞気味かな?

まっ、暖かさが大好きなやつだから、夏に近づけば勢い盛り返してくるだろう。
イネや野菜たちの元気に育つ姿見て今日も1日気分爽快で過ごせるぜ。
ほれ、水もたまったようだしな。