21日のマーキュリーカップを勝ったマスターフェンサーの父はジャスタウェイです。父はハーツクライ。

2011年7月に2歳でデビュー。新馬を勝ち,新潟2歳ステークスで2着。東京スポーツ杯2歳ステークスでディープブリランテの4着に入り,2歳戦を終了。
3歳初戦はきさらぎ賞で4着。続くアーリントンカップで重賞初制覇。NHKマイルカップで6着になった後,日本ダービーにも出走しましたがこれはディープブリランテの11着と大敗。秋は古馬相手の毎日王冠で復帰し2着。天皇賞(秋)の6着で3歳戦を終了。
4歳初戦の中山金杯は1番人気に推されたものの3着。京都記念も1番人気で5着。中日新聞杯で8着に敗れた後,エプソムカップ,関屋記念,毎日王冠と3戦連続で2着。しかし天皇賞(秋)は2着馬に4馬身もの差をつける圧勝で大レース制覇を達成。
5歳初戦の中山記念で重賞3勝目をあげてドバイに遠征。ドバイデューティフリーも圧勝してみせました。帰国して出走した安田記念は不良馬場でしたがハナ差の接戦を制して大レース3勝目。秋は渡仏し凱旋門賞に挑戦。これは8着でしたが帰国初戦のジャパンカップでエピファネイアの2着に入り,引退レースとなった有馬記念は4着でした。JRA賞の最優秀4歳以上牡馬に選出されています。
2歳の時から走っていましたが,本格化したのは4歳秋になってから。マイラーに近い中距離馬だったと思いますが,本格化後の2400m級のレースでも大きく崩れなかったのは,能力の高さの証明といえるでしょう。
マスターフェンサーは種牡馬としての最初の世代。重賞勝ち馬はマスターフェンサーが5頭目で,ダートの重賞を勝ったのはこの馬が初めて。まだ重賞2勝馬というのは出ていませんが,ジャスタウェイ自身がそうであったように,産駒が本格化するのが4歳秋以降だとすれば,まだそれを迎えた馬がいないわけですから,種牡馬としての能力を正しく評価するには,もう少しの時間が必要でしょう。
実際のところは,力への意志Wille zur Machtが,現実的に存在する自分自身を超越することへと向かう意志voluntasであるとするなら,意志が知性intellectusを超越するか否かということ,あるいは同じことですが,意志作用volitioが観念ideaを超越するか否かということは,さほど重要ではありません。というのは意志と知性を,あるいは個々の意志作用と個々の観念を,同一であるとみなそうがみなすまいが,力への意志すなわち現実的に存在する自分自身を超越する意志が確保できるなら,そういったことはニーチェFriedrich Wilhelm Nietzscheにとってはどうでもいいといっても差し支えはないからです。力への意志が,コナトゥスconatusに対する対抗馬であるとは,そのようなことを意味していると解してください。すなわち,第三部定理六にあるように,自己の有に固執するsuo esse perseverare conaturのか,それとも力への意志によって自己の有を超越するのかということがニーチェにとってのすべてであり,意志が観念を超越するかどうかはあまり関係ないのです。意志作用が観念を超越するなら,力への意志は意志としてそのまま解せば問題ありません。しかし意志作用と観念あるいは意志と知性が同一のものであったとしても,観念なり知性なりが,現実的に存在する自身の知性なり知性を構成する観念なりを超越することができるのであれば,力への意志は成立することになります。それがどちらの形で成立するかということは,力への意志とニーチェがいうときには,どちらかでなければならないというものではありませんし,どちらであるべきだということでもないのです。
ここから分かるように,ニーチェにとっての力への意志は,現実的に存在する自分自身を超越するために,とても重要であったのです。したがって,ニーチェは一般的に意志という概念notioについては,特別視していたという可能性があるのです。このために,もし神Deusが自由意志voluntas liberaによって働いているときは,もちろんニーチェはそのような唯一神が存在するということは認めないのですが,なお神自身が蜘蛛となって巣を張っているのではないとみた可能性があります。意志によって働くagereものと,本性naturaの必然性necessitasによって働くものを,単に意志の概念によって区別する可能性が,ニーチェにはあったのです。

2011年7月に2歳でデビュー。新馬を勝ち,新潟2歳ステークスで2着。東京スポーツ杯2歳ステークスでディープブリランテの4着に入り,2歳戦を終了。
3歳初戦はきさらぎ賞で4着。続くアーリントンカップで重賞初制覇。NHKマイルカップで6着になった後,日本ダービーにも出走しましたがこれはディープブリランテの11着と大敗。秋は古馬相手の毎日王冠で復帰し2着。天皇賞(秋)の6着で3歳戦を終了。
4歳初戦の中山金杯は1番人気に推されたものの3着。京都記念も1番人気で5着。中日新聞杯で8着に敗れた後,エプソムカップ,関屋記念,毎日王冠と3戦連続で2着。しかし天皇賞(秋)は2着馬に4馬身もの差をつける圧勝で大レース制覇を達成。
5歳初戦の中山記念で重賞3勝目をあげてドバイに遠征。ドバイデューティフリーも圧勝してみせました。帰国して出走した安田記念は不良馬場でしたがハナ差の接戦を制して大レース3勝目。秋は渡仏し凱旋門賞に挑戦。これは8着でしたが帰国初戦のジャパンカップでエピファネイアの2着に入り,引退レースとなった有馬記念は4着でした。JRA賞の最優秀4歳以上牡馬に選出されています。
2歳の時から走っていましたが,本格化したのは4歳秋になってから。マイラーに近い中距離馬だったと思いますが,本格化後の2400m級のレースでも大きく崩れなかったのは,能力の高さの証明といえるでしょう。
マスターフェンサーは種牡馬としての最初の世代。重賞勝ち馬はマスターフェンサーが5頭目で,ダートの重賞を勝ったのはこの馬が初めて。まだ重賞2勝馬というのは出ていませんが,ジャスタウェイ自身がそうであったように,産駒が本格化するのが4歳秋以降だとすれば,まだそれを迎えた馬がいないわけですから,種牡馬としての能力を正しく評価するには,もう少しの時間が必要でしょう。
実際のところは,力への意志Wille zur Machtが,現実的に存在する自分自身を超越することへと向かう意志voluntasであるとするなら,意志が知性intellectusを超越するか否かということ,あるいは同じことですが,意志作用volitioが観念ideaを超越するか否かということは,さほど重要ではありません。というのは意志と知性を,あるいは個々の意志作用と個々の観念を,同一であるとみなそうがみなすまいが,力への意志すなわち現実的に存在する自分自身を超越する意志が確保できるなら,そういったことはニーチェFriedrich Wilhelm Nietzscheにとってはどうでもいいといっても差し支えはないからです。力への意志が,コナトゥスconatusに対する対抗馬であるとは,そのようなことを意味していると解してください。すなわち,第三部定理六にあるように,自己の有に固執するsuo esse perseverare conaturのか,それとも力への意志によって自己の有を超越するのかということがニーチェにとってのすべてであり,意志が観念を超越するかどうかはあまり関係ないのです。意志作用が観念を超越するなら,力への意志は意志としてそのまま解せば問題ありません。しかし意志作用と観念あるいは意志と知性が同一のものであったとしても,観念なり知性なりが,現実的に存在する自身の知性なり知性を構成する観念なりを超越することができるのであれば,力への意志は成立することになります。それがどちらの形で成立するかということは,力への意志とニーチェがいうときには,どちらかでなければならないというものではありませんし,どちらであるべきだということでもないのです。
ここから分かるように,ニーチェにとっての力への意志は,現実的に存在する自分自身を超越するために,とても重要であったのです。したがって,ニーチェは一般的に意志という概念notioについては,特別視していたという可能性があるのです。このために,もし神Deusが自由意志voluntas liberaによって働いているときは,もちろんニーチェはそのような唯一神が存在するということは認めないのですが,なお神自身が蜘蛛となって巣を張っているのではないとみた可能性があります。意志によって働くagereものと,本性naturaの必然性necessitasによって働くものを,単に意志の概念によって区別する可能性が,ニーチェにはあったのです。













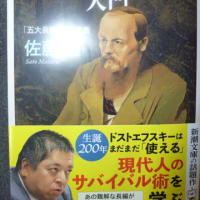
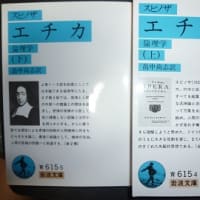






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます