スピノザと貿易の稿で触れたように,貿易に携わったことが,スピノザに経済的自由の重要さを身を持って体験させたと僕は考えています。そしてこの経験は,スピノザの哲学的思想にとっても,意味あることであったと理解しています。
スピノザと日本を並列的に扱ったストッパによるプロパガンダは,オランダ人全体を標的に据えたものでした。これはつまり,スピノザのようなマラーノといわれるユダヤ人だけが特別に貿易商を営んでいたわけではなく,オランダ人にも多くの商人が存在したことを示しています。当然ながらスピノザは,そういった同業者たちとも関係をもった筈です。『ある哲学者の人生』でナドラーは,その場所として,アムステルダム証券取引所を挙げています。
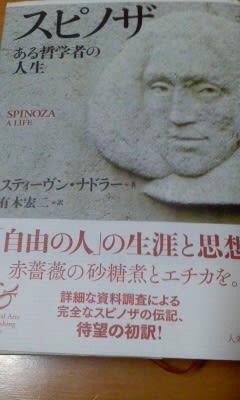
そうした商人仲間に,キリスト教のコレギアント派やメノー派に属する人びとがいました。カルヴィニストが頑迷な保守派であったのに対し,これらの宗派は進歩的でリベラルな改革派。デカルトの心酔者も多く存在しました。そのゆえにスピノザの哲学する自由という考え方も受け入れやすく,実際にそうした友人たちとスピノザは,秘密裡の勉強会のようなものを開いていました。それはむしろ,友人たちがスピノザから教えを請うような場であったかもしれませんし,またそうしたものが存在しなくても,スピノザは確固たる自身の思想というものを築き上げることができたかもしれません。しかしそうした場が,少なくともスピノザがその哲学を成熟させていく上で,一定の役割を果たしたと考えておくべきだと僕は思います。
ユダヤ教から破門された後,スピノザは貿易からも身を引きました。しかしこれらの友人との関係は,これ以降も続いています。望遠鏡に使用するレンズの研磨で清貧な暮らしを送っていたスピノザを,経済的に援助しようとする友人も存在したのです。たぶんスピノザとキリスト教改革派との関係を探求するだけで,一冊の本が完成するくらいの密度の濃さと重要性があるといえるくらいに僕は考えています。
第三の証明は第一部定義六だけを必要としています。これは逆にいうなら,第一部定義六の中に,神,すなわち絶対に無限な実体の存在が含まれているということです。いい換えれば神は自己原因であり,かつ知性のうちでの客観的な意味においても,知性の外での形相的な意味においても実在するということが,第一部定義六の中にはあるということです。そしてスピノザの哲学における定義のうちには,定義されるものの発生と本性が含まれています。つまり神の本性のうちに,神の実在が実在的な意味においても含まれているといえるのです。
このゆえに僕は,第一部定義六というのは,単に名目的な定義なのではなくて,実在的な定義であると理解しています。つまりもしも絶対に無限な実体が存在するならそれは神であるという意味に理解するのではなく,実在している絶対に無限な実体に関して,それを神というという意味で理解するのです。
もしもそうであるならば,少なくとも絶対に無限な実体が実在するということは,公理的性格を有する資格があるように僕には思えます。知性があるものを概念conceptusすることによって直ちにそのものの実在を認識するなら,そのあるもの自身とそのものの実在は不可分な関係にあるといえるからです。そして神の場合にはこれが妥当しているのですから,神の実在は,公理であるといってよいように思うのです。
したがって,強い意味を背後から支えるような条件は,公理的性格を有する資格があるといえると思うのです。そしてそうであるのならば,それによって支えられている第一部公理三も,公理的性格を有すると判断できる余地があると考えます。だから僕は現在は,必ずしも第一部公理三には公理的性格がない,公理として不成立であると断言しなければならないとは考えません。
とはいえ,第一部定理一一において神の実在をスピノザが証明しているのは事実です。そしてそれがなければ強い意味は成立しないと僕は理解します。したがってそれに固執はしませんが,第一部公理三は公理的性格を有し得ないというのが,結論ではあります。
スピノザと日本を並列的に扱ったストッパによるプロパガンダは,オランダ人全体を標的に据えたものでした。これはつまり,スピノザのようなマラーノといわれるユダヤ人だけが特別に貿易商を営んでいたわけではなく,オランダ人にも多くの商人が存在したことを示しています。当然ながらスピノザは,そういった同業者たちとも関係をもった筈です。『ある哲学者の人生』でナドラーは,その場所として,アムステルダム証券取引所を挙げています。
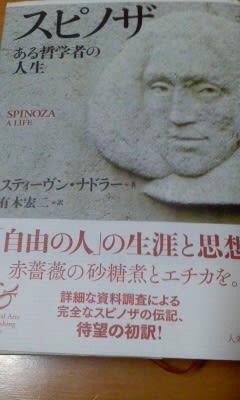
そうした商人仲間に,キリスト教のコレギアント派やメノー派に属する人びとがいました。カルヴィニストが頑迷な保守派であったのに対し,これらの宗派は進歩的でリベラルな改革派。デカルトの心酔者も多く存在しました。そのゆえにスピノザの哲学する自由という考え方も受け入れやすく,実際にそうした友人たちとスピノザは,秘密裡の勉強会のようなものを開いていました。それはむしろ,友人たちがスピノザから教えを請うような場であったかもしれませんし,またそうしたものが存在しなくても,スピノザは確固たる自身の思想というものを築き上げることができたかもしれません。しかしそうした場が,少なくともスピノザがその哲学を成熟させていく上で,一定の役割を果たしたと考えておくべきだと僕は思います。
ユダヤ教から破門された後,スピノザは貿易からも身を引きました。しかしこれらの友人との関係は,これ以降も続いています。望遠鏡に使用するレンズの研磨で清貧な暮らしを送っていたスピノザを,経済的に援助しようとする友人も存在したのです。たぶんスピノザとキリスト教改革派との関係を探求するだけで,一冊の本が完成するくらいの密度の濃さと重要性があるといえるくらいに僕は考えています。
第三の証明は第一部定義六だけを必要としています。これは逆にいうなら,第一部定義六の中に,神,すなわち絶対に無限な実体の存在が含まれているということです。いい換えれば神は自己原因であり,かつ知性のうちでの客観的な意味においても,知性の外での形相的な意味においても実在するということが,第一部定義六の中にはあるということです。そしてスピノザの哲学における定義のうちには,定義されるものの発生と本性が含まれています。つまり神の本性のうちに,神の実在が実在的な意味においても含まれているといえるのです。
このゆえに僕は,第一部定義六というのは,単に名目的な定義なのではなくて,実在的な定義であると理解しています。つまりもしも絶対に無限な実体が存在するならそれは神であるという意味に理解するのではなく,実在している絶対に無限な実体に関して,それを神というという意味で理解するのです。
もしもそうであるならば,少なくとも絶対に無限な実体が実在するということは,公理的性格を有する資格があるように僕には思えます。知性があるものを概念conceptusすることによって直ちにそのものの実在を認識するなら,そのあるもの自身とそのものの実在は不可分な関係にあるといえるからです。そして神の場合にはこれが妥当しているのですから,神の実在は,公理であるといってよいように思うのです。
したがって,強い意味を背後から支えるような条件は,公理的性格を有する資格があるといえると思うのです。そしてそうであるのならば,それによって支えられている第一部公理三も,公理的性格を有すると判断できる余地があると考えます。だから僕は現在は,必ずしも第一部公理三には公理的性格がない,公理として不成立であると断言しなければならないとは考えません。
とはいえ,第一部定理一一において神の実在をスピノザが証明しているのは事実です。そしてそれがなければ強い意味は成立しないと僕は理解します。したがってそれに固執はしませんが,第一部公理三は公理的性格を有し得ないというのが,結論ではあります。













