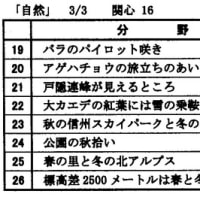日本で氷河地形として残る、涸沢カール。
残雪の涸沢(からさわ)カールのツアーに参加した。

涸沢カールの雪渓を登る仲間。
ツアーは2015年5月30日~6月2日。
奥は前穂高岳側、右上は奥穂高岳側。
涸沢カール。

スプーンでえぐり取ったようなくぼみ、カール地形。
中央の吊尾根の左が前穂高岳、右が奥穂高岳。
涸沢カールは、夏でも雪渓が残る。
涸沢カールへは、松本から上高地へ行く。

河童橋は、観光客と登山者でにぎわっている。下は梓川。2015年5月30日。
河童橋から穂高連峰が見える。
O奥穂高岳3,190メートルと、
M前穂高岳3,090メートルは、
T吊尾根でつながっている。
M前穂高岳の右は、明神岳2,931メートル。
O奥穂高岳の左は、Gジャンダルム3,163メートル、
A間ノ岳2,907メートル。さらに左は西穂高岳に連なる。
目指す涸沢カールは、O奥穂高岳、T吊尾根、M前穂高岳の裏側(北)になる。
ルートは、上高地 ⇒ 明神 ⇒ 徳沢 ⇒ 横尾(1泊) ⇒ 涸沢カール(2泊)。
1時間 1時間 1時間 4時間
参加者10人。遠くは京都、大阪から。群馬の人はリピーター。
リピーターは、ご夫妻も。女性は3人。
ゆったりとした行程になっている。
3日前の2015年5月27日に、美ヶ原から穂高連峰を見た。

標高2,000メートルの思い出の丘から。朝5時過ぎ。
N西穂高岳、M前穂高岳、O奥穂高岳、K涸沢岳、H北穂高岳。K涸沢岳の前山は蝶ヶ岳。
いよいよ、穂高連峰に囲まれた涸沢カールへ行くのか!
穂高連峰には、まだ雪がある。ワクワクする。
穂高連峰と残雪の涸沢カールを見たい!
ケガのないように、当日を迎えよう。
それに、晴れてほしい。
そしてツアーの当日、2015年5月30日。上高地から先は徒歩になり、
明神岳を迂回するように、梓川に沿って、横尾まで北上する。
明神岳2,931メートル。

明神岳の左にM前穂高岳が頭を出し、T吊尾根が連なる。
明神岳の下は梓川、右手前には、小梨が咲いている。
上高地には雪と新緑と花がある。
横尾からは、梓川を渡って西に入り、
それから、南へ回り込んで涸沢カールへ。
上高地 ⇒ 横尾は、梓川に沿った平坦な林の道を3時間。横尾山荘泊り。
翌朝、横尾から、梓川を横切って、本谷橋でアイゼンを着けて、
雪渓を上がり、涸沢カールの山小屋まで4時間。
横尾 ⇒ 涸沢カールまでを写真で追ってみる。
雨が上がった新緑。横尾の朝7時6分。

夜来の雨は上がってきた。
涸沢カールに登るこの日だけは雨の予測だった。が、
前線が南にとどまり、北に上がらななかった。
ありがたい! 涸沢カールを目指して出発。
このあとツアー中、天気に恵まれた。
横尾出発、7時10分。梓川にかかる横尾大橋を渡ると、
屏風岩。2,595メートル。

数分で屏風岩が現れて続く。この写真は、横尾から40分ほど経ったところ。
横尾谷にかかる本谷橋。

横尾から1時間20分。
夏道は、本谷橋を渡って、横尾谷の右岸を登るが、本谷橋は通行禁止。
今回は、ここで、アイゼンを着けて、横尾谷の左岸の雪上を登る。
奥は北穂高岳3,106メートル。

右の登山者は、雪の裂け目をのぞき込んでいる。激流が見える。
雪を踏み外して、横尾谷に落ちないように登る。
そして、→突き当たりを左に上がる。
この辺から、上りになる。
涸沢カールを目指して登っていく。
そして、奥穂高岳が右に見えてきた。

横尾から3時間15分。
左は前穂高岳。その右は吊尾根。
足元には落石がある。注意しながら抜けたい。
振り返ると、涸沢カールを、2人の→登山者が上がってくる。

奥の▽は、左が大天井岳、右が東天井岳。右手前は屏風岩。
奥穂高岳の下に涸沢ヒュッテが見えてきた。

奥は奥穂高岳。左は吊尾根。
涸沢ヒュッテはカール地形の中にあって、
モレーンといわれる堆積した土石の上にある。
涸沢ヒュッテの先には、雪が融けると現れる池の平がある。
横尾から4時間で涸沢ヒュッテへ。
夏道はジグザグだが、雪の上は直線だから、
途中、眺めながら、写真を撮りながらでも早い。
涸沢ヒュッテに2泊して、残雪の涸沢カールを楽しむ。
涸沢カールは、夏は穂高連峰の登山、
秋は紅葉で大にぎわいするところ。最盛期、
山小屋は、1枚の布団に3人が寝ることを覚悟するという。
春は、残雪の涸沢カールと穂高連峰を見ながら、
涸沢ヒュッテのテラスで生ビールを飲む。が、
標高2,310メートルの生ビールは格別だ!
そして、朝焼けや夕焼けを楽しむ。
布団は、1人に1枚、ちゃんとあった。
奥穂高岳には登らない。
装備、経験、技術から冬山は無理。
涸沢岳のザイテングラートの横で発生した滑落死を見ている。
北アルプス 穂高岳・涸沢。

涸沢ヒュッテのリーフレットから。
右下は本谷橋、ここから上がってきた。
涸沢ヒュッテからの眺望は素晴らしい。
前穂高岳、吊尾根、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳がそそり立ち、
涸沢岳の左下には、ザイテングラート、あずき沢と、
奥穂高岳へ登り降りする時の難所が見える。
穂高連峰を見回す。
涸沢ヒュッテと奥穂高岳。

奥穂高岳の左は吊尾根が続き、
奥穂高岳の右は涸沢岳に連なる。
涸沢ヒュッテの標高は2,310メートル。
前穂高岳3,090メートル。

右は吊尾根で奥穂高岳に連なる。
涸沢ヒュッテから登ってきた仲間。標高2,500メートル付近。
前穂高岳の豪快な岩尾根。

右のT吊尾根から左に、前穂高岳のⅠ峰~Ⅵ峰が続く。
Ⅵ峰には、→たぬき岩が見える。

耳があり、鼻がある。そして、ポンポコ腹が出ている。
涸沢岳3,110メートル。

左端の縦に並ぶ岩稜はザイテングラート。右端の三角錐は涸沢槍。
北穂高岳3,106メートル。

朝5時、陽が刺してきた。
北穂高岳の威容もいいもんだ。
たなびく雲が北穂高岳を引き立てる。
東を見ると、大天井岳(左端)、東天井岳(中)、横通岳(右)。夕方7時。

やがて、雲が焼けてきた。東天井岳(左)と横通岳(右)。

涸沢カールの北寄りから、常念岳が見える。

常念岳からの眺望は素晴らしい。槍ヶ岳が目の前に見える。
涸沢カールの上部から、蝶ヶ岳が見える。

手前は屏風岩。
蝶ヶ岳からは、穂高連峰~槍ヶ岳にかけて、北アルプスの眺望が素晴らしい。
これで、涸沢カールから、360度を見回した。
昼に、北穂高岳を眺めていると、沢を降りてくる人がいる。
北穂高岳の下にある⇒涸沢小屋の右を通って、涸沢ヒュッテにきた。

若い男性だった。テラスでカップ・ラーメンを食べ始めた。
食べ終わると、ホッとしているようだ。落ち着いてきて、
登ってきた北穂高岳の写真を撮っている。
話しかけた。
「北穂高岳へ登ったんですか?」
「そうです」
「やりましたね! いい思い出になりますよ」
喜んでいた。
そして、「怖くなかったですか?」
「怖かった! 北穂沢を下りたが、足がすくんだ」
と、本音を話してくれた。
山慣れした屈強な若者が怖かったから、私には無理だ。
2015年5月31日、夕方5時ころのこと。
涸沢ヒュッテから、360度の眺望を楽しんでいた。
「そろそろ陽が傾くころだ、あの雲が焼けてくれないかな!」
と、陽が沈む方向の涸沢岳を眺めていた。

ヘリコプターが、涸沢カールの静寂を破った。
涸沢槍の上を飛ぶ。
涸沢槍の下の三角は獅子岩。
涸沢岳の左の鞍部は白出のコル。
下にある岩稜はザイテングラート。
ザイテングラートは、奥穂高岳への夏のルート。
岩場の急登で、登り切ると、鞍部に出る。
鞍部には、穂高岳山荘があって、夜に灯りがあることでわかる。
ザイテングラートの左はあずき沢で、奥穂高岳への冬のルート。
雪渓を直登して、白出のコルに出る。
急傾斜で、滑落事故が多い難所。
ザイテングラートの左に、長野県警のヘリコプターが向かって来た。

ザイテングラートの飛び出た岩を目指している。
すでに扉を開けて、隊員が下を見ている。
報道によると、標高2,700メートル付近の岩場で、男性が倒れているのを、
別の登山者が発見し、山小屋を通じて松本署に連絡をした。
単独登山中に、数百メートル滑落したとみられる。
男性(59歳)は収容されたが、死亡が確認された。
奥穂高岳から、下山の途中だったんだろう。
この時間、あずき沢を登る人はいなかったから。
涸沢ヒュッテまで、標高差で、あと400メートルだった。
無念だっただろうな!
滑落事故に遭遇したのは初めてだ。
奥穂高岳は、装備、経験、技術、体力、集中力、判断力と、
全てを備えた人だけを受け入れるのだろう。冬は、とりわけ厳しい。
夕闇が訪れた。午後7時。

涸沢岳は、ピンクのグラデーションの中に浮かび上がった。
そして、星が出た。午後7時半。

涸沢カールは、何ごともなかったかのように、1日が暮れていく。
翌日、穂高岳に挑戦する登山者がいる。2015年6月1日、10時。

大きなリュックが、一歩一歩あずき沢を登っていく。
穂高岳は、急斜面、雪崩、落石、天候の急変で身を守っている。
未知への挑戦、人の飽くなき挑戦を見る。
残雪の涸沢カールは、
人を寄せ付けない峻厳な穂高岳と、
征服しようと挑戦する人間が、格闘するところ。
残雪の涸沢(からさわ)カールのツアーに参加した。

涸沢カールの雪渓を登る仲間。
ツアーは2015年5月30日~6月2日。
奥は前穂高岳側、右上は奥穂高岳側。
涸沢カール。

スプーンでえぐり取ったようなくぼみ、カール地形。
中央の吊尾根の左が前穂高岳、右が奥穂高岳。
涸沢カールは、夏でも雪渓が残る。
涸沢カールへは、松本から上高地へ行く。

河童橋は、観光客と登山者でにぎわっている。下は梓川。2015年5月30日。
河童橋から穂高連峰が見える。
O奥穂高岳3,190メートルと、
M前穂高岳3,090メートルは、
T吊尾根でつながっている。
M前穂高岳の右は、明神岳2,931メートル。
O奥穂高岳の左は、Gジャンダルム3,163メートル、
A間ノ岳2,907メートル。さらに左は西穂高岳に連なる。
目指す涸沢カールは、O奥穂高岳、T吊尾根、M前穂高岳の裏側(北)になる。
ルートは、上高地 ⇒ 明神 ⇒ 徳沢 ⇒ 横尾(1泊) ⇒ 涸沢カール(2泊)。
1時間 1時間 1時間 4時間
参加者10人。遠くは京都、大阪から。群馬の人はリピーター。
リピーターは、ご夫妻も。女性は3人。
ゆったりとした行程になっている。
3日前の2015年5月27日に、美ヶ原から穂高連峰を見た。

標高2,000メートルの思い出の丘から。朝5時過ぎ。
N西穂高岳、M前穂高岳、O奥穂高岳、K涸沢岳、H北穂高岳。K涸沢岳の前山は蝶ヶ岳。
いよいよ、穂高連峰に囲まれた涸沢カールへ行くのか!
穂高連峰には、まだ雪がある。ワクワクする。
穂高連峰と残雪の涸沢カールを見たい!
ケガのないように、当日を迎えよう。
それに、晴れてほしい。
そしてツアーの当日、2015年5月30日。上高地から先は徒歩になり、
明神岳を迂回するように、梓川に沿って、横尾まで北上する。
明神岳2,931メートル。

明神岳の左にM前穂高岳が頭を出し、T吊尾根が連なる。
明神岳の下は梓川、右手前には、小梨が咲いている。
上高地には雪と新緑と花がある。
横尾からは、梓川を渡って西に入り、
それから、南へ回り込んで涸沢カールへ。
上高地 ⇒ 横尾は、梓川に沿った平坦な林の道を3時間。横尾山荘泊り。
翌朝、横尾から、梓川を横切って、本谷橋でアイゼンを着けて、
雪渓を上がり、涸沢カールの山小屋まで4時間。
横尾 ⇒ 涸沢カールまでを写真で追ってみる。
雨が上がった新緑。横尾の朝7時6分。

夜来の雨は上がってきた。
涸沢カールに登るこの日だけは雨の予測だった。が、
前線が南にとどまり、北に上がらななかった。
ありがたい! 涸沢カールを目指して出発。
このあとツアー中、天気に恵まれた。
横尾出発、7時10分。梓川にかかる横尾大橋を渡ると、
屏風岩。2,595メートル。

数分で屏風岩が現れて続く。この写真は、横尾から40分ほど経ったところ。
横尾谷にかかる本谷橋。

横尾から1時間20分。
夏道は、本谷橋を渡って、横尾谷の右岸を登るが、本谷橋は通行禁止。
今回は、ここで、アイゼンを着けて、横尾谷の左岸の雪上を登る。
奥は北穂高岳3,106メートル。

右の登山者は、雪の裂け目をのぞき込んでいる。激流が見える。
雪を踏み外して、横尾谷に落ちないように登る。
そして、→突き当たりを左に上がる。
この辺から、上りになる。
涸沢カールを目指して登っていく。
そして、奥穂高岳が右に見えてきた。

横尾から3時間15分。
左は前穂高岳。その右は吊尾根。
足元には落石がある。注意しながら抜けたい。
振り返ると、涸沢カールを、2人の→登山者が上がってくる。

奥の▽は、左が大天井岳、右が東天井岳。右手前は屏風岩。
奥穂高岳の下に涸沢ヒュッテが見えてきた。

奥は奥穂高岳。左は吊尾根。
涸沢ヒュッテはカール地形の中にあって、
モレーンといわれる堆積した土石の上にある。
涸沢ヒュッテの先には、雪が融けると現れる池の平がある。
横尾から4時間で涸沢ヒュッテへ。
夏道はジグザグだが、雪の上は直線だから、
途中、眺めながら、写真を撮りながらでも早い。
涸沢ヒュッテに2泊して、残雪の涸沢カールを楽しむ。
涸沢カールは、夏は穂高連峰の登山、
秋は紅葉で大にぎわいするところ。最盛期、
山小屋は、1枚の布団に3人が寝ることを覚悟するという。
春は、残雪の涸沢カールと穂高連峰を見ながら、
涸沢ヒュッテのテラスで生ビールを飲む。が、
標高2,310メートルの生ビールは格別だ!
そして、朝焼けや夕焼けを楽しむ。
布団は、1人に1枚、ちゃんとあった。
奥穂高岳には登らない。
装備、経験、技術から冬山は無理。
涸沢岳のザイテングラートの横で発生した滑落死を見ている。
北アルプス 穂高岳・涸沢。

涸沢ヒュッテのリーフレットから。
右下は本谷橋、ここから上がってきた。
涸沢ヒュッテからの眺望は素晴らしい。
前穂高岳、吊尾根、奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳がそそり立ち、
涸沢岳の左下には、ザイテングラート、あずき沢と、
奥穂高岳へ登り降りする時の難所が見える。
穂高連峰を見回す。
涸沢ヒュッテと奥穂高岳。

奥穂高岳の左は吊尾根が続き、
奥穂高岳の右は涸沢岳に連なる。
涸沢ヒュッテの標高は2,310メートル。
前穂高岳3,090メートル。

右は吊尾根で奥穂高岳に連なる。
涸沢ヒュッテから登ってきた仲間。標高2,500メートル付近。
前穂高岳の豪快な岩尾根。

右のT吊尾根から左に、前穂高岳のⅠ峰~Ⅵ峰が続く。
Ⅵ峰には、→たぬき岩が見える。

耳があり、鼻がある。そして、ポンポコ腹が出ている。
涸沢岳3,110メートル。

左端の縦に並ぶ岩稜はザイテングラート。右端の三角錐は涸沢槍。
北穂高岳3,106メートル。

朝5時、陽が刺してきた。
北穂高岳の威容もいいもんだ。
たなびく雲が北穂高岳を引き立てる。
東を見ると、大天井岳(左端)、東天井岳(中)、横通岳(右)。夕方7時。

やがて、雲が焼けてきた。東天井岳(左)と横通岳(右)。

涸沢カールの北寄りから、常念岳が見える。

常念岳からの眺望は素晴らしい。槍ヶ岳が目の前に見える。
涸沢カールの上部から、蝶ヶ岳が見える。

手前は屏風岩。
蝶ヶ岳からは、穂高連峰~槍ヶ岳にかけて、北アルプスの眺望が素晴らしい。
これで、涸沢カールから、360度を見回した。
昼に、北穂高岳を眺めていると、沢を降りてくる人がいる。
北穂高岳の下にある⇒涸沢小屋の右を通って、涸沢ヒュッテにきた。

若い男性だった。テラスでカップ・ラーメンを食べ始めた。
食べ終わると、ホッとしているようだ。落ち着いてきて、
登ってきた北穂高岳の写真を撮っている。
話しかけた。
「北穂高岳へ登ったんですか?」
「そうです」
「やりましたね! いい思い出になりますよ」
喜んでいた。
そして、「怖くなかったですか?」
「怖かった! 北穂沢を下りたが、足がすくんだ」
と、本音を話してくれた。
山慣れした屈強な若者が怖かったから、私には無理だ。
2015年5月31日、夕方5時ころのこと。
涸沢ヒュッテから、360度の眺望を楽しんでいた。
「そろそろ陽が傾くころだ、あの雲が焼けてくれないかな!」
と、陽が沈む方向の涸沢岳を眺めていた。

ヘリコプターが、涸沢カールの静寂を破った。
涸沢槍の上を飛ぶ。
涸沢槍の下の三角は獅子岩。
涸沢岳の左の鞍部は白出のコル。
下にある岩稜はザイテングラート。
ザイテングラートは、奥穂高岳への夏のルート。
岩場の急登で、登り切ると、鞍部に出る。
鞍部には、穂高岳山荘があって、夜に灯りがあることでわかる。
ザイテングラートの左はあずき沢で、奥穂高岳への冬のルート。
雪渓を直登して、白出のコルに出る。
急傾斜で、滑落事故が多い難所。
ザイテングラートの左に、長野県警のヘリコプターが向かって来た。

ザイテングラートの飛び出た岩を目指している。
すでに扉を開けて、隊員が下を見ている。
報道によると、標高2,700メートル付近の岩場で、男性が倒れているのを、
別の登山者が発見し、山小屋を通じて松本署に連絡をした。
単独登山中に、数百メートル滑落したとみられる。
男性(59歳)は収容されたが、死亡が確認された。
奥穂高岳から、下山の途中だったんだろう。
この時間、あずき沢を登る人はいなかったから。
涸沢ヒュッテまで、標高差で、あと400メートルだった。
無念だっただろうな!
滑落事故に遭遇したのは初めてだ。
奥穂高岳は、装備、経験、技術、体力、集中力、判断力と、
全てを備えた人だけを受け入れるのだろう。冬は、とりわけ厳しい。
夕闇が訪れた。午後7時。

涸沢岳は、ピンクのグラデーションの中に浮かび上がった。
そして、星が出た。午後7時半。

涸沢カールは、何ごともなかったかのように、1日が暮れていく。
翌日、穂高岳に挑戦する登山者がいる。2015年6月1日、10時。

大きなリュックが、一歩一歩あずき沢を登っていく。
穂高岳は、急斜面、雪崩、落石、天候の急変で身を守っている。
未知への挑戦、人の飽くなき挑戦を見る。
残雪の涸沢カールは、
人を寄せ付けない峻厳な穂高岳と、
征服しようと挑戦する人間が、格闘するところ。