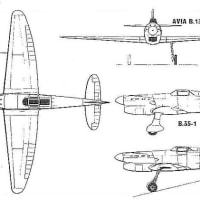タイトルの西暦からわかるように、清朝末から中共成立までの中国史である。過去の通説を否定することから始めているが、元の時代から中国が世界史に組み込まれた(P68)というのは西尾幹二氏も似たようなことを言っていたと思う。すなわち、それまではバラバラだった世界が元の統一帝国によって世界史が始まったというのである。明は漢民族の歴史に戻った、と言うのだが、それまでに入ってきた異民族は中国に居残った(P69)から日本人には訳が分からず明朝の研究は疎かになったというのである。
清末の洋務運動は、中国自身が何かしたというものではなく、英仏などの外国資本が金儲けのために入ってきて工場を運営したのに過ぎず、結局、現代中国と同じことをしているのに過ぎない、という指摘(P98)は、結局漢民族と称する連中は自分たちで地道に技術開発や西洋の勉強をする気はなく、外国を利用してその上に乗っかっているだけ、という体質を表わしている。
清朝の正規軍である。八旗軍やモンゴル軍は太平天国の乱などの討伐には役に立たず、結局自衛のために各地に軍閥が発生した。李鴻章の北洋軍閥などはその典型で、清朝の軍隊ではない。「李鴻章は全権大使や欽差大臣を歴任しますが、清国として工場を建設したわけではありません。そうではなくて、逆に一番強く、大きな軍隊を持っているから大臣をやらせて、外国と交渉させたというのが正解です。日清戦争では日本は国民軍ですが、清国側は李鴻章の私兵が戦ったと考えればいいのです。」(P98)というのであるが、このことは、清朝崩壊以後現代中国に至るまで、その体質を残していることを忘れてはならない。現代中国行けば、地方では軍隊が通行税を取ったり、工場を経営したりして、半自給自足の経営をしている。そのことと同じなのである。
十三世紀に元朝になると、朝鮮半島はモンゴルの支配下に入った。代々の高麗王はモンゴル人を母としている。それどころか、李氏朝鮮の始祖は女真人であるというのだ(P119)モンゴル時代の朝鮮には世界の文物が入って豊かになっていったのに、李氏朝鮮になったら、中国にのみこまれないために自給自足の経済としたため、進歩が止まり退化し、車も足るも作れなくなり、文明が退化した、というのは現代北朝鮮と同じだというのである。中国も朝鮮も体質は変わらないのである。韓国も高度成長期は日本の保守政治家はほめていたが、現在は様変わりである。これは、日本時代に育ったまともな人たちがいなくなって、先祖帰りしたのである。
日清戦争の際の英国対応は意外であった。英国は中立を宣言するが、実は英国は日本艦隊の動きを清国艦隊に連絡したり、英国商船が清国陸軍を輸送するなどの中立違反をしていた(P159)。この商船を東郷平八郎が砲撃したと一時英国内で紛糾して、結局東郷の行為は合法であると認められたというエピソードは有名であるが、それ以前に英国が国際法違反をしていたのだ、という指摘は初めてである。
案外有名なのが、辛亥革命当時の中国には共通語がなかったので、日本留学組だった革命を起こした地方軍の長官たちは、お互いに日本語で連絡を取り合っていた(P204)ということである。二十一カ条の要求についての正当性の宮脇氏の説明は簡単明瞭である。満洲や関東州において日本が清国と結んだ条約について、清を滅ぼして成立したはずの中華民国は、条約を認めないと言いだしたから、それを認めさせるための交渉だというのである(P218)。孫文のインチキさについては、他の本より具体的に書かれているが、省略する。日本の共産党もそうだが、創立期の中国共産党はコミンテルンの中国支部である(P261)。いうなればソ連の傀儡である。
中国で最初に外国と対等な条約を結んだのは、阿片戦争後の南京条約である、と言うことになっている。しかし事実はそれ以前にロシアとネルチンスク条約を結んでいる。ところがネルチンスク条約は満洲語とラテン語で書かれており、南京条約は漢文で書かれているから、最初の条約だというのだそうである(P208)。どちらも清朝だからいい加減な話である。清朝の支配者の満洲人は、漢字の使い方を知っていてわざと書かなかった(P209)というのも康熙帝や乾隆帝のエピソードで理解できる。しかし康熙帝も乾隆帝も漢文は理解したが、話し言葉としての漢語はできなかったはずである。なぜなら宮廷では漢人も、北京官話と呼ばれる宮廷用の満洲語を使ったのである。
国民党は、多くの軍閥を束ねて大きくなっていったというのは間違いである、という(P293)。蒋介石自体が一軍閥に過ぎず、他の軍閥との合従連衡であったという。各地の軍閥はけっして国民党の傘下に入ったわけではない、というのである。そもそも中国共産党からしてが、秘密結社である、というのだ。「中華ソビエト政府というのは・・・やくざの根城が各所にあったと考えるのが正しそうです。やはり『水滸伝』の世界で一旗あげたい乱暴な連中がネットワークを作り、力のある連中が山々に根城を作っていった感じなのです(P203)。」
そして有名な毛沢東の長征とはライバルを殺す旅だった(P306)というのは刺激的である。通説では、延安に行きつくまでに、色々な戦いがあり、当初の10万人が3万人にまで減ってしまった、というものである。実は、ライバルの部隊が死ぬように遠回りしたというのである。ソ連帰りのエリートの指導する部隊はゲリラ戦に向いていなかったこともあるが、彼らを毛沢東が助けなかったという。当初は下っ端でモスクワ帰りのエリートではなかった毛沢東が、ライバルを抹殺した結果長征の終わりにはトップにのし上がっていたのである。
日本の識者同士が集まって話をしたとき、高山正之氏がなぜいい加減なロシア人がコミンテルンの謀略は巧妙で成功したという疑問を出した(P316)。宮脇氏の曰くは、コミンテルンの指導者は皆ロシア人ではないというのである。マーリンはオランダ人、張作霖の暗殺に関係したのはブルガリア人である。そしてロシア以外の外国のコミンテルンの人間が活躍したというのである。
蒋介石は日本軍の矢面に立たされて闘わされた。ところが毛沢東は、共産軍で真面目に日本軍と戦った将軍がいると、激怒して止めさせたというのである。そして、共産党はアヘン貿易をして金を貯めて、裏で遊んでいた。共産党本部の延安でもアヘンを作っていた。アヘンが必要なのは金儲けばかりではない。当時まともに流通する通貨がないから、阿片が通貨として一番信用があった(P326)のだそうである。
この本は、孫文や中共成立までの毛沢東の正体を余すところなく描き、蒋介石などの軍閥や中国共産党の出自などがうまく描かれていて、いかにも中国らしいと納得させてくれる好著である。現代中国の実相を理解するのにもよい。