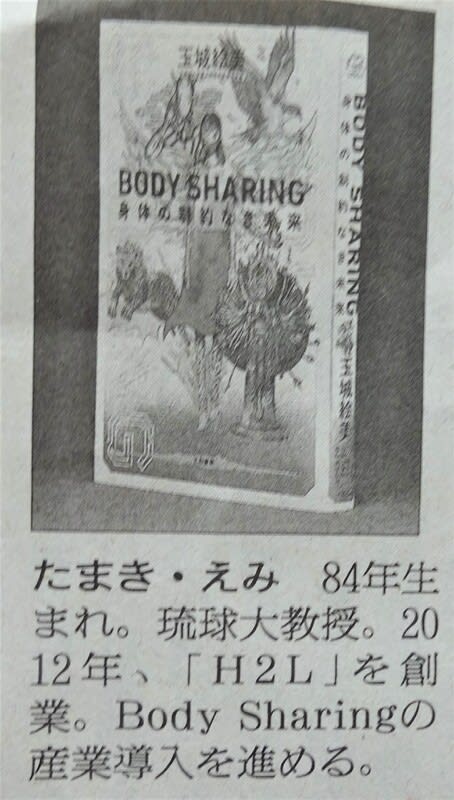いやあ、見ましたよ。
このサッカー嫌いな原左都子も、日本時間の27日(日)19時よりテレビ中継されたワールドカップ・カタール大会の “日本v.s.コスタリカ戦” を。
申し訳ないことに そもそもサッカー嫌いの身のためどちらを応援する等の偏りが一切無い立場で、冷静にテレビ中継を観戦した。
サッカー素人らしく試合開始からずっとダレたのだが。
その理由とは、両チームに特段の動きが全く無い故だった。
途中テレビのチャンネルを変えたりしつつ、後半戦に入ってもその動きの無さが続き。
正直言って、(サッカー観戦て、やっぱりつまらないなあ)などと勝手にボヤきつつまたチャンネルを変えようとしたところ、コスタリカが1点を先取した。
その場面はあっという間の出来事だったのだが、一体日本選手は何をボヤっとしてるんだ!!との腹立たしさのみは抱かされた。
そうこうして日本選手の何らの活躍も見られないままに、試合はコスタリカ勝利にて簡単に終了した。
この試合を原左都子の勝手な評価でまとめるならば、「コスタリカチームの“防衛力”」が勝った、との結論なのだが。
そうこう考えていたところ、本日のネット情報にて当該試合に関する興味深い解説を発見した。 以下に紹介しよう。
FIFAワールドカップ(W杯)カタール大会第2戦で日本がコスタリカに0-1で敗れたことを受け、10年南アフリカ大会日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、「おかしすぎる、どうした日本代表」「森保監督の采配が裏目に出た」「ドイツ戦の金星が台無しになった」と怒りをにじませた。
「 申し訳ないけど、森保監督の采配が良くなかった。途中から選手を変えていけば流れは変わると思っているのか。そうじゃない。最初からベストの選手を出していけばいい。なぜ上田綺世選手を出してきたのか。浅野拓磨選手が点を取ってくれたのだから、その勢いのままで出していればいい。なぜそれをしないのか。正直、いただけないな。コスタリカをどう崩していくかが問題だった。最初から三笘薫、浅野拓磨、伊東純也を出していればどうだったか。 後半から勝負という考えは、僕には通用しない。最初から状態がいいメンバーを出して行かなければいけない。能力がある選手を出していかなければいけない。」
また、3バックにも言及。 ドイツ戦で3バックがハマったのは「たまたま」とし、「3バックだと三笘の位置が低くなる。4バックで高い位置を取り、三笘はゴールに近い位置でプレーさせないと怖くない」。明確に日本の課題は得点力だとした。
そして「今までの盛り上がり、俺らの期待感を台無しににした。悔しくて、悔しくて。ドイツ戦の大金星を生かせないまま、スペイン戦に行ってしまった。厳しい状況になった」と表情を曇らせた。
(以上、ネット情報より引用したもの。)
原左都子の感想に入ろう。
申し訳ないことに田中マルクス闘莉王氏とやらを全く存じていない立場ではあるが、氏の発言には同意したくもなる。
以下にその発言を繰り返すが、「 森保監督の采配が良くなかった。途中から選手を変えていけば流れは変わると思っているのか。そうじゃない。最初からベストの選手を出していけばいい。なぜ上田綺世選手を出してきたのか。浅野拓磨選手が点を取ってくれたのだから、その勢いのままで出していればいい。なぜそれをしないのか。正直、いただけないな。コスタリカをどう崩していくかが問題だった。最初から三笘薫、浅野拓磨、伊東純也を出していればどうだったか。 後半から勝負という考えは、僕には通用しない。最初から状態がいいメンバーを出して行かなければいけない。能力がある選手を出していかなければいけない。」
これ、サッカーど素人の原左都子も全く同感だ!
最初から今ベストの選手を出すべきだし、前回の勝利を再現するためにもその勢いを残しておくべきだったのではあるまいか?
そんな意味で、もしも森安監督が“後半からが勝負”と考えていたとしたら、大いなる考え違いであろうと指摘したい。
全くもって、ドイツ戦勝利とは日本チームに取っては「大金星」だったはずだ。
そのラッキーを次にも何とかして持ち越せばよかったものを、何故方針を大幅に変えてしまったのか残念でならない。
そんな意味でも、監督(統率者・リーダー)の果たす役割とは多大であることを思い知らされる。
それはサッカーのみならず、いずれの分野においてもそういうことであろう。