あけましておめでとうございます。新年一回目の更新です。
 漢の武帝 (CenturyBooks―人と思想)の感想
漢の武帝 (CenturyBooks―人と思想)の感想
漢代史研究の泰斗による漢の武帝の評伝。吉川幸次郎の同名書と比べると対匈奴戦、経済政策に関してやや詳しい。また武帝が始皇帝を範としていたことを強調。新しい研究成果は儒学の官学化に関する近年の議論を取り入れている程度か。文章は吉川書と同様に読みやすい。
読了日:12月3日 著者:永田英正
 古典注釈入門――歴史と技法 (岩波現代全書)の感想
古典注釈入門――歴史と技法 (岩波現代全書)の感想
古代から近現代までの注釈の歴史をメインに、古典を読むことと注釈の意義についてと注釈の技法の話で脇を固めるが、メインより脇の話の方に啓発される部分が多かった。現代の注釈に関する節で岩波や小学館など各社の古典文学全集の特色をまとめている部分は参考になりそう。
読了日:12月8日 著者:鈴木健一
 天の血脈(4) (アフタヌーンKC)の感想
天の血脈(4) (アフタヌーンKC)の感想
神功皇后の朝鮮遠征と日露戦争とを重ね合わせるように話が展開。今文庫版で読んでる『王道の狗』の14、5年後の話なんですよね。『狗』で出てきた孫文も(だいぶキャラ付けが変わってるようですが)今巻で登場。巻末に先頃亡くなられた松本健一氏との対談あり。
読了日:12月11日 著者:安彦良和
 江戸時代の医師修業: 学問・学統・遊学 (歴史文化ライブラリー)の感想
江戸時代の医師修業: 学問・学統・遊学 (歴史文化ライブラリー)の感想
現代のように国家試験なんて無いから、なろうと思えば誰でもなれたと言われることもある江戸時代の医師。しかし(当然ながら)実態はそんな簡単なものではなかったということで、京都への遊学を中心に江戸時代の医師教育についてまとめています。遊学の話は朝日選書の『剣術修行の旅日記』と合わせて読むと面白いかも。
読了日:12月15日 著者:海原亮
 最終戦争論・戦争史大観 (中公文庫)の感想
最終戦争論・戦争史大観 (中公文庫)の感想
青空文庫版で読む。(講演・著作の時点から見て)過去のことはともかく、未来のことになると途端に話が怪しくなる印象。当然ながら今となっては石原莞爾に関する史料として読むのが適切な態度だろう。原子力発電・原子爆弾に目を付けていたのはさすがだが、原発のもたらす災禍にまでは思い至らなかったのはやむを得ないか。『戦争史大観』の終盤の「柴大人」(柴五郎)の話はいずれソースを当たりたい。
読了日:12月17日 著者:石原莞爾
 増補 八月十五日の神話: 終戦記念日のメディア学 (ちくま学芸文庫)の感想
増補 八月十五日の神話: 終戦記念日のメディア学 (ちくま学芸文庫)の感想
日本がポツダム宣言の受諾を表明した8月14日でもなく、降伏文書の調印が行われた9月2日でもなく、玉音放送が行われた8月15日を終戦記念日とするのは、「降伏」の屈辱を忘れたい右派、「8月15日の革命」を強調したい左派、双方にとって都合の良い「記憶の55年体制」の産物であったとする。元来9月3日を終戦記念日としていた中国で、日本との「歴史問題」がおこると8月15日がクローズアップされるようになってきたとか、日本の小・中・高あるいは日本史・世界史の教科書で終戦記念日の扱いが異なるという指摘が面白い。
読了日:12月22日 著者:佐藤卓己
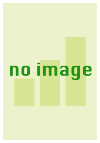 学問のかたち: -もう一つの中国思想史の感想
学問のかたち: -もう一つの中国思想史の感想
先秦から近代の中央研究院歴史語言研究所創設に至るまで、中国の各時代の学問のありかたを取り上げた論文集。個人的には水上雅晴「清代学術と幕府」で取り上げる所の地方官と幕友の関係が現代中国の各研究機関のボスとポスドクとの関係に似ている所があり、面白く読んだ。小南一郎「中国古代の学と校」は、『周礼』など礼文献の使用には慎重であらねばならないと断りつつ、その扱いがやや中途半端か。
読了日:12月23日 著者:
 王道の狗4 (中公文庫 コミック版 や 3-33)の感想
王道の狗4 (中公文庫 コミック版 や 3-33)の感想
若き日の内田良平、そして革命家となった孫文と宮崎滔天が登場し、現在連載中の『天の血脈』と話が繋がった。風間と陸奥宗光の対話を見てると、本作が安彦流の『坂の上の雲』なのかなと思った次第。その安彦版『坂の上の雲』と安彦版『古事記』が結びついた『天の血脈』がどうなっていくのか、期待半分不安半分です…
読了日:12月24日 著者:安彦良和
 織田信長 (ちくま新書)の感想
織田信長 (ちくま新書)の感想
信長は本当に「革命児」なのか?将軍義昭や天皇との関係、「天下布武」の意味、そして一向宗やキリスト教といった宗教への態度の3点から信長の実像を検討。信長は歴史学そのものよりも史学史というか人物像変遷史の対象として扱う方が面白いのではないかという印象を抱いた。
読了日:12月24日 著者:神田千里
 儒学殺人事件 堀田正俊と徳川綱吉の感想
儒学殺人事件 堀田正俊と徳川綱吉の感想
綱吉の時代の大老堀田正俊(幕末の堀田正睦の祖先と言った方が通りがよいかも)殺害事件は、儒学殺人事件と呼ぶべき性質のものだった… これを取っ掛かりにして、有名な「生類憐れみの令」の背景となった綱吉の儒学観と堀田正俊ら当時の大名・儒学者の儒学観との対立について論じる。『颺言録』に描かれるところの綱吉像を見てると、今でも北朝鮮あたりで金正恩のために同じような書が作られているのではないかという気がするが…
読了日:12月26日 著者:小川和也
 日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話 (中公新書)の感想
日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話 (中公新書)の感想
東大史料編纂所の関係者による、各自が関心を持つ史料をネタにしたエッセー集。取り上げる史料は文字史料のほか、地図あり、トコトンヤレ節のような歌あり、大砲のような実物あり、洞窟寺院のような建築もありとバラエティに富んでいる。一通り目を通せば歴史学研究がどういう営みかわかるのではないかと思う。
読了日:12月29日 著者:東京大学史料編纂所
 史料から考える 世界史二〇講の感想
史料から考える 世界史二〇講の感想
中公新書『日本史の森をゆく』の世界史版みたいなのかと思ったら、こちらは同じく岩波から出ている『世界史史料』(全12巻)のガイドというか販促本的な位置づけ。『世界史史料』での配分を反映して近現代史ネタが多い。第12講の「文書からどれだけの情報が引き出せるかは、それを当時の時代状況のなかで位置づけられるかどうかにかかっている。」という文章は史料読解の基本を示している。
読了日:12月31日 著者:
 漢の武帝 (CenturyBooks―人と思想)の感想
漢の武帝 (CenturyBooks―人と思想)の感想漢代史研究の泰斗による漢の武帝の評伝。吉川幸次郎の同名書と比べると対匈奴戦、経済政策に関してやや詳しい。また武帝が始皇帝を範としていたことを強調。新しい研究成果は儒学の官学化に関する近年の議論を取り入れている程度か。文章は吉川書と同様に読みやすい。
読了日:12月3日 著者:永田英正
 古典注釈入門――歴史と技法 (岩波現代全書)の感想
古典注釈入門――歴史と技法 (岩波現代全書)の感想古代から近現代までの注釈の歴史をメインに、古典を読むことと注釈の意義についてと注釈の技法の話で脇を固めるが、メインより脇の話の方に啓発される部分が多かった。現代の注釈に関する節で岩波や小学館など各社の古典文学全集の特色をまとめている部分は参考になりそう。
読了日:12月8日 著者:鈴木健一
 天の血脈(4) (アフタヌーンKC)の感想
天の血脈(4) (アフタヌーンKC)の感想神功皇后の朝鮮遠征と日露戦争とを重ね合わせるように話が展開。今文庫版で読んでる『王道の狗』の14、5年後の話なんですよね。『狗』で出てきた孫文も(だいぶキャラ付けが変わってるようですが)今巻で登場。巻末に先頃亡くなられた松本健一氏との対談あり。
読了日:12月11日 著者:安彦良和
 江戸時代の医師修業: 学問・学統・遊学 (歴史文化ライブラリー)の感想
江戸時代の医師修業: 学問・学統・遊学 (歴史文化ライブラリー)の感想現代のように国家試験なんて無いから、なろうと思えば誰でもなれたと言われることもある江戸時代の医師。しかし(当然ながら)実態はそんな簡単なものではなかったということで、京都への遊学を中心に江戸時代の医師教育についてまとめています。遊学の話は朝日選書の『剣術修行の旅日記』と合わせて読むと面白いかも。
読了日:12月15日 著者:海原亮
 最終戦争論・戦争史大観 (中公文庫)の感想
最終戦争論・戦争史大観 (中公文庫)の感想青空文庫版で読む。(講演・著作の時点から見て)過去のことはともかく、未来のことになると途端に話が怪しくなる印象。当然ながら今となっては石原莞爾に関する史料として読むのが適切な態度だろう。原子力発電・原子爆弾に目を付けていたのはさすがだが、原発のもたらす災禍にまでは思い至らなかったのはやむを得ないか。『戦争史大観』の終盤の「柴大人」(柴五郎)の話はいずれソースを当たりたい。
読了日:12月17日 著者:石原莞爾
 増補 八月十五日の神話: 終戦記念日のメディア学 (ちくま学芸文庫)の感想
増補 八月十五日の神話: 終戦記念日のメディア学 (ちくま学芸文庫)の感想日本がポツダム宣言の受諾を表明した8月14日でもなく、降伏文書の調印が行われた9月2日でもなく、玉音放送が行われた8月15日を終戦記念日とするのは、「降伏」の屈辱を忘れたい右派、「8月15日の革命」を強調したい左派、双方にとって都合の良い「記憶の55年体制」の産物であったとする。元来9月3日を終戦記念日としていた中国で、日本との「歴史問題」がおこると8月15日がクローズアップされるようになってきたとか、日本の小・中・高あるいは日本史・世界史の教科書で終戦記念日の扱いが異なるという指摘が面白い。
読了日:12月22日 著者:佐藤卓己
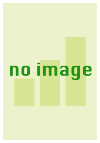 学問のかたち: -もう一つの中国思想史の感想
学問のかたち: -もう一つの中国思想史の感想先秦から近代の中央研究院歴史語言研究所創設に至るまで、中国の各時代の学問のありかたを取り上げた論文集。個人的には水上雅晴「清代学術と幕府」で取り上げる所の地方官と幕友の関係が現代中国の各研究機関のボスとポスドクとの関係に似ている所があり、面白く読んだ。小南一郎「中国古代の学と校」は、『周礼』など礼文献の使用には慎重であらねばならないと断りつつ、その扱いがやや中途半端か。
読了日:12月23日 著者:
 王道の狗4 (中公文庫 コミック版 や 3-33)の感想
王道の狗4 (中公文庫 コミック版 や 3-33)の感想若き日の内田良平、そして革命家となった孫文と宮崎滔天が登場し、現在連載中の『天の血脈』と話が繋がった。風間と陸奥宗光の対話を見てると、本作が安彦流の『坂の上の雲』なのかなと思った次第。その安彦版『坂の上の雲』と安彦版『古事記』が結びついた『天の血脈』がどうなっていくのか、期待半分不安半分です…
読了日:12月24日 著者:安彦良和
 織田信長 (ちくま新書)の感想
織田信長 (ちくま新書)の感想信長は本当に「革命児」なのか?将軍義昭や天皇との関係、「天下布武」の意味、そして一向宗やキリスト教といった宗教への態度の3点から信長の実像を検討。信長は歴史学そのものよりも史学史というか人物像変遷史の対象として扱う方が面白いのではないかという印象を抱いた。
読了日:12月24日 著者:神田千里
 儒学殺人事件 堀田正俊と徳川綱吉の感想
儒学殺人事件 堀田正俊と徳川綱吉の感想綱吉の時代の大老堀田正俊(幕末の堀田正睦の祖先と言った方が通りがよいかも)殺害事件は、儒学殺人事件と呼ぶべき性質のものだった… これを取っ掛かりにして、有名な「生類憐れみの令」の背景となった綱吉の儒学観と堀田正俊ら当時の大名・儒学者の儒学観との対立について論じる。『颺言録』に描かれるところの綱吉像を見てると、今でも北朝鮮あたりで金正恩のために同じような書が作られているのではないかという気がするが…
読了日:12月26日 著者:小川和也
 日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話 (中公新書)の感想
日本史の森をゆく - 史料が語るとっておきの42話 (中公新書)の感想東大史料編纂所の関係者による、各自が関心を持つ史料をネタにしたエッセー集。取り上げる史料は文字史料のほか、地図あり、トコトンヤレ節のような歌あり、大砲のような実物あり、洞窟寺院のような建築もありとバラエティに富んでいる。一通り目を通せば歴史学研究がどういう営みかわかるのではないかと思う。
読了日:12月29日 著者:東京大学史料編纂所
 史料から考える 世界史二〇講の感想
史料から考える 世界史二〇講の感想中公新書『日本史の森をゆく』の世界史版みたいなのかと思ったら、こちらは同じく岩波から出ている『世界史史料』(全12巻)のガイドというか販促本的な位置づけ。『世界史史料』での配分を反映して近現代史ネタが多い。第12講の「文書からどれだけの情報が引き出せるかは、それを当時の時代状況のなかで位置づけられるかどうかにかかっている。」という文章は史料読解の基本を示している。
読了日:12月31日 著者:









