『悪霊』の作品内作者である記者が,各々の登場人物について記述の上でどういう評価をしているかを簡潔にみておきます。
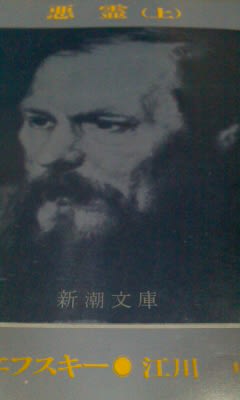
作品自体に特殊な目的があったと思われますが,それを除けば基本的に記者は登場事物を公平に評価しようとしていると僕は思います。記者も人間ですから好感を抱いている人物もいれば反感をもっている人物もいるに違いないのですが,自分自身のそういう視点はなるべく表に出ないようにしようとする意志を記者はもっていると考えてよいというのが僕の見解です。
ただし,ひとりだけ,記者が自身の好意を隠そうとしていない人物がいます。それはスタヴローギンの養育者のステパン・ヴェルホヴェンスキーです。ステパンの息子,物語上は実の親子であるかどうか疑わせる内容を含んでいますが,戸籍上は息子となっているピョートルは革命結社の首謀者で,スタヴローギンをその指導者にすることを企んだ人物ですから,物語の中ではそれなりに重要な位置を与えられているといえるでしょう。
とはいえ,ステパンに対して好意を表明することは,ピョートルら結社のメンバーを否定的に描くことに通じる面があります。僕はそうしたメンバーが記者によって悪意的に記述されているとは考えませんが,記者自身はそういう考えをもっているということを窺わせるようには思います。もっともそれは『悪霊』が政治的プロパガンダを内容に含んだ小説である必要があったということからみれば,記者の気持ちというより作者自身の必要性からそのように記述されなければならなかったという面があるでしょう。したがってこの部分を差し引くならば,基本的に記者は好意も悪意も覆い隠して記述していると判断してよいだろうと僕は思うのです。
このことは,記者がリーザに対してどういう想いを抱いていたのかは不明だということを意味します。リーザの撲殺が記者の欲望の代行であるとする仮説の弱みがここにはあるのです。
実際にジャレットが『知の教科書 スピノザ』で援用しているのは第四部定理一五ではなくその証明の最初の文です。ですがその一文は注意を要するものだと僕は考えています。そこでスピノザは確かに善bonumおよび悪malumの認識が感情affectusであるといっているのですが,ここでいわれている感情は実際には人間の身体の変状すなわち身体の刺激状態の観念に近いものなのです。なぜならスピノザはそれが感情であるならそこから必然的に欲望cupiditasが発生するということを第三部諸感情の定義一に訴えているのですが,そこに示されているのは与えられた感情についてではなく与えられた変状affectioについてであるからです。そしてまた,善および悪の認識が感情であるということについて訴求されている第四部定理八も,喜びlaetitiaおよび悲しみtristitiaそのものについて言及されているのではなく,その観念について言及されています。したがってこれは感情そのものというより感情の観念,とりわけ自分の身体がより小なる完全性perfectioからより大なる完全性へ移行する刺激状態の観念の観念,あるいはより大なる完全性からより小なる完全性へと移行する刺激状態の観念の観念と解することができるのです。なので僕はこの点について,ジャレットが言及している部分ではなく,定理そのものの方に言及しました。この定理は確かに善と悪の認識が欲望の原因であることを暗黙裡に前提しているといえるからです。
この場合のように,スピノザは感情といっていても,実際には身体の変状と解した方がよいと思われる場合は『エチカ』のほかの部分にもあります。岩波文庫版の冒頭の「『エチカ』について」の中で畠中は,スピノザには用語の使い方にルーズな面があると指摘しています。そしてその一例として変状と感情の用い方もあげられています。感情と解するべきなのか,変状と解した方がよいのかは,その用語が使われる各々の文脈から判断するほかありません。そしてジャレットが援用している部分に関しては,僕は変状と解しておいた方が安全だし理解しやすいと思うのです。もちろんそれは,ジャレットがこれを援用して善と悪の認識が欲望の原因であることを導くことの不当性を意味するのではありません。
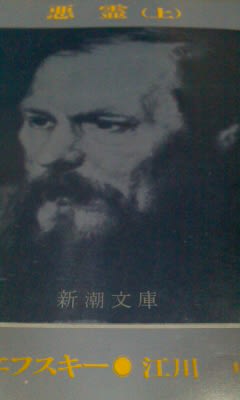
作品自体に特殊な目的があったと思われますが,それを除けば基本的に記者は登場事物を公平に評価しようとしていると僕は思います。記者も人間ですから好感を抱いている人物もいれば反感をもっている人物もいるに違いないのですが,自分自身のそういう視点はなるべく表に出ないようにしようとする意志を記者はもっていると考えてよいというのが僕の見解です。
ただし,ひとりだけ,記者が自身の好意を隠そうとしていない人物がいます。それはスタヴローギンの養育者のステパン・ヴェルホヴェンスキーです。ステパンの息子,物語上は実の親子であるかどうか疑わせる内容を含んでいますが,戸籍上は息子となっているピョートルは革命結社の首謀者で,スタヴローギンをその指導者にすることを企んだ人物ですから,物語の中ではそれなりに重要な位置を与えられているといえるでしょう。
とはいえ,ステパンに対して好意を表明することは,ピョートルら結社のメンバーを否定的に描くことに通じる面があります。僕はそうしたメンバーが記者によって悪意的に記述されているとは考えませんが,記者自身はそういう考えをもっているということを窺わせるようには思います。もっともそれは『悪霊』が政治的プロパガンダを内容に含んだ小説である必要があったということからみれば,記者の気持ちというより作者自身の必要性からそのように記述されなければならなかったという面があるでしょう。したがってこの部分を差し引くならば,基本的に記者は好意も悪意も覆い隠して記述していると判断してよいだろうと僕は思うのです。
このことは,記者がリーザに対してどういう想いを抱いていたのかは不明だということを意味します。リーザの撲殺が記者の欲望の代行であるとする仮説の弱みがここにはあるのです。
実際にジャレットが『知の教科書 スピノザ』で援用しているのは第四部定理一五ではなくその証明の最初の文です。ですがその一文は注意を要するものだと僕は考えています。そこでスピノザは確かに善bonumおよび悪malumの認識が感情affectusであるといっているのですが,ここでいわれている感情は実際には人間の身体の変状すなわち身体の刺激状態の観念に近いものなのです。なぜならスピノザはそれが感情であるならそこから必然的に欲望cupiditasが発生するということを第三部諸感情の定義一に訴えているのですが,そこに示されているのは与えられた感情についてではなく与えられた変状affectioについてであるからです。そしてまた,善および悪の認識が感情であるということについて訴求されている第四部定理八も,喜びlaetitiaおよび悲しみtristitiaそのものについて言及されているのではなく,その観念について言及されています。したがってこれは感情そのものというより感情の観念,とりわけ自分の身体がより小なる完全性perfectioからより大なる完全性へ移行する刺激状態の観念の観念,あるいはより大なる完全性からより小なる完全性へと移行する刺激状態の観念の観念と解することができるのです。なので僕はこの点について,ジャレットが言及している部分ではなく,定理そのものの方に言及しました。この定理は確かに善と悪の認識が欲望の原因であることを暗黙裡に前提しているといえるからです。
この場合のように,スピノザは感情といっていても,実際には身体の変状と解した方がよいと思われる場合は『エチカ』のほかの部分にもあります。岩波文庫版の冒頭の「『エチカ』について」の中で畠中は,スピノザには用語の使い方にルーズな面があると指摘しています。そしてその一例として変状と感情の用い方もあげられています。感情と解するべきなのか,変状と解した方がよいのかは,その用語が使われる各々の文脈から判断するほかありません。そしてジャレットが援用している部分に関しては,僕は変状と解しておいた方が安全だし理解しやすいと思うのです。もちろんそれは,ジャレットがこれを援用して善と悪の認識が欲望の原因であることを導くことの不当性を意味するのではありません。













